クルマネタなし、御免候へ、、、( ̄m ̄:)
最近、道端や空き地、庭などに勝手に生えて群落を形成している草が気になっていた。
その草は、春から初冬まで、薄紫の小花が球形に纏った花をあたり一面に咲かせ続ける。
12月も半ば入って、氷点下の冷え込みが数日続くと、いつの間にか枯れてしまうが、
また春が来ると宿根から新芽が吹いて再び花をつける。
 DSC04671
DSC04671 posted by
(C)どれみそくん
Carl Zeiss Makro-Planar 2.8/60 T*
何回かマクロ撮影の被写体にしてはいるが、名前がとんとわからない。
気にはなるが、わからないモノはわからない。
画像からググって調べることはできないのだ。
ちょうど、通学路で見染めた他所の女子高の美人の名前がわからないのと同じだ。
尾根遺産なら、意を決して突撃すれば名前を聞き出すことも出来るが、
花は聞いても何も語ってくれることはない。
 DSC_0453
DSC_0453 posted by
(C)どれみそくん
AF-S Nikkor 24-70mm F2.8G ED
V字型の斑紋のある丸い葉、地面を這うように伸びる茎、、、
球形に纏まった小花は其々先が割れるように開花して種子を作る。
 DSC_1351
DSC_1351 posted by
(C)どれみそくん
Carl Zeiss Distagon 1.4/35 ZF.2 T*
たまたま、みん友さんの
この方が他所のページにこの花の写真をアップされていたので、
突撃してお聞きしたところ、間髪いれずに「ヒメツルソバ」との御教示を頂いた。
それにしても尾根遺産の迸る知識と教養、、、流石である。
早速ウィキってみたところ、
下記の如く書いてあったので、
以下にコピーを載せておく。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ヒメツルソバとは、タデ科の植物の1種。学名はPersicaria capitata(シノニムはCephalophilon capitatum、Polygonum capitatum) 。別名はカンイタドリ、ポリゴナム。
ヒマラヤ原産で、花期は5月頃から秋にかけての時期であるが、真夏には花が途絶える。冬季には降霜すると地上部が枯死するが、地面が凍結しない限り翌年には新芽が成長する。花は小花が球形にまとまっており、内部には種子が成熟する。葉にはV字形の斑紋があり、茎はほふく性。
性質が丈夫であるためグラウンドカバーとしても用いられる。種子や株分け、挿し木などで容易に繁殖が可能なほとんど手のかからない植物であるため、空き地や道端などで雑草化もしている。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
そう言われてみれば、夏には花がなかったような気もする。
 DSC_1350
DSC_1350 posted by
(C)どれみそくん
Carl Zeiss Distagon 1.4/35 ZF.2 T*
12月になって氷点下の冷え込みが始まるとだんだん枯れてゆくのだが、
北風が吹き込まない暖かな日溜まりにはまだ花が残っていた。
 DSC_1346
DSC_1346 posted by
(C)どれみそくん
Carl Zeiss Distagon 1.4/35 ZF.2 T*
哀れシオシオノパーになったヒメツルソバ。
ところで、ディスタゴン、、、
凄いじょ~^^;
ナノクリちゃんに勝るとも劣らぬT*子ちゃん!
カール・ツァィス大三元が一、、、
神レンズの詳細レポートはまたいずれ♪
Posted at 2011/12/28 00:32:14 | |
トラックバック(0) |
日常 | 日記
 パソコンクラッシュ
パソコンクラッシュ  雑草化した花
雑草化した花 




 スノータイヤ装着他
スノータイヤ装着他 


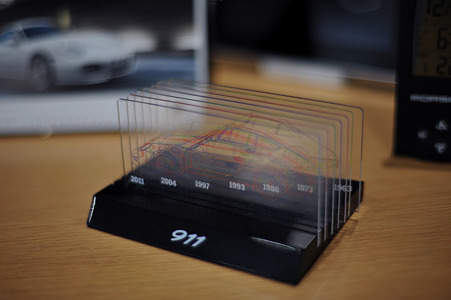
 冬の色
冬の色 










