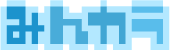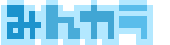生きろ!トンネルで死なない為に知っておくことがある。

-
クルマにしろ、鉄道にしろ繰り返される「トンネル」での災害。 「火災」 などが、その際たるものだが、実はそれ以外にも多くの災害が発生しているのだ。 そして 「トンネル」の災害 が多いのは、これから暑い時期だという事は意外にも知られていない。 これは長期の休暇、つまり夏休みなどで、一挙にサンデードライヴァーが増えて、事故が増えるという事と、さらに、それに伴う交通量の増大によって、火災以外の 「トンネル事故」 も多く起こっている。 その大きな要因としては 「渋滞」 がキーワードになる。連休時の通行量の増大による渋滞、真夏の気温上昇・・・・・ 一般国道や県道などの 500~1500mクラス の長さにトンネルで、渋滞に巻き込まれ、車内でエアコンなどをかけていると、突然に気分が悪くなって救急車の出動などというパターンが、暑い時期になると散見されるのだ。 つまり、渋滞でクルマがトンネルに滞り、一酸化炭素などの濃度が急激に上がり気分を害する人が増えるということなのだ。 「おいおい、そんなハズは無いんじゃないの?だってトンネルには、天井に筒状の換気装置が・・・」 とい ...出典:徳小寺 無恒さん
-
道路工学をかつてかじった一人として、今回の事故は衝撃的だった。 日本は、こうした土木工学の先進国と、正直思っていた。しかし、今回の事故は起きてしまった。 以前から僕は、ちっぽけな知識だけど、道路に関する危険への警鐘や、必要と思われる知識をブログに上げてきた。 隧道 繰り返される隧道(トンネル)の悲劇、対策対応は無いのだろうか? ⇒https://minkara.carview.co.jp/userid/124785/blog/338623/ 吹流 道路の吹流しをどれくらい理解していますか!? ⇒https://minkara.carview.co.jp/userid/124785/blog/4855292/ しかし、まさか構造物が、こうも脆くも崩れるとは。 考えてみれば、何年か前に新幹線のトンネルでも同じ様な崩落事故が有った。その時に、道路も・・・という発想が起きなかったのは痛切の至りだ。 おそらく、1970年代の構造物という事で、僕たちが一番恐れている 「ジャブコン」 なんていうことは無かったのか、砂に 「海砂」 を使っていなかったのか、 ...出典:徳小寺 無恒さん
-
今日から連休が始まり、16連休だの、9日から9連休だとかいう実に恵まれた環境の方も多いと聞く。まったくご同慶の至りだ。 GW、お盆休み、年末年始の長期休暇というと、行楽や帰省で日本中の道路が渋滞するのだが、日頃クルマに乗らずに、この時こそと言った感じでクルマに乗るサンデードライヴァーの方々には、最低限の点検をお願いしたいものだ。 特にタイアの空気圧くらいは、低いよりはちょいと高めの方が・・・・くらいの気合で見て欲しいモノだ。 誤認 タイアの空気圧の間違いに迫る! ⇒ https://minkara.carview.co.jp/userid/124785/blog/1178694/ こうなる前に、ちゃ~んと点検していれば防げたかも・・・・ さてさて、そんな民族大移動の時期、事故というモノには重々気を付けて欲しいモノなんだが、我々、小市民がどう頑張っても防げない、行政や企業の責任による事故も、こうした人の移動が激しい時期に起こりがちになる。 一人ひとりが気にするだけではなく、そうした行政や企業にも十二分以上に事故などが起きないように、さらに気を付けてメンテな ...出典:徳小寺 無恒さん
-
今回、不幸にして僕の故郷である東広島の山陽自動車道八本松トンネルで大きな事故が起きてしまいました。 事故の背景には、また、運送会社の不適切な管理が浮き彫りにされていますが、正直に言って、たまに帰省して山陽道を走行すると、良く事故が起きないようなァとも思えるマナーの悪さなどが目についてしまいます。 さらに道路工学の観点から見て、山陽自動車道の岡山から広島IC区間は、ちょっと危険だなと思う部分も多々あるのですが、残念ながら、そうしたマナーや道路工学の部分はなかなか改善されないのが事実です。 そうなれば、個人一人ひとりで、もしかの時にいかに適切に対応するかが大事になります。 今回の事故で、誰も指摘しませんでしたが、このトンネルの長さは「840m」。実は 500~1500 m クラスのトンネルは非常に危険なトンネルなんですね。 具体的に言えば「排煙装置」が無い場合が多いのです。 ジェットファンのあるなしで、随分と被害が変わる。 今回は幸運にも八本松トンネル下り線は、下り坂にトンネルを掘削したために、西条側が高くて志和側が低かったため、大多数の煙が西条側に排煙されましたが ...出典:徳小寺 無恒さん
-
広島県内の山陽自動車道、八本松トンネル事故がきっかけで、道路の設備に興味を持っていただけると幸いなのだが、不十分ながら現代の道路は、理論的に構築されている。 それが不幸にして、予算や人員という限られた資源によって制限がある事はいかんともしがたいモノだ。 その規格や基準を知っていると、ひとたび何かあった時に、自分を守る大切な知識になるとも思うのだ。 例えば以前紹介した、トンネルの排気設備の基準なんだが、 隧道 繰り返される隧道(トンネル)の悲劇、対策対応は無いのだろうか? → https://minkara.carview.co.jp/userid/124785/blog/338623/ トンネル長さ(Km)×交通量(台/毎時)> 600 これは僕が昔々、習った基準なんだが、この基準の根拠は、経験値で、この数字を超えると一酸化炭素の濃度が 100ppm を超えるので換気設備が必用というものだった。 (ちなみに一酸化炭素の濃度が 200ppm に達すると、ハッキリと頭痛等の症状が発症してしまう濃度だ。) 現代ではどうなっているか正直分からないのだが、僕が知 ...出典:徳小寺 無恒さん
オススメ関連まとめ
-
2020/08/14
-
2020/07/27
-
2020/08/30
-
2026/01/15