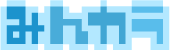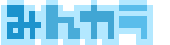真説 櫻井 眞一郎

-
皆さんからコメントを色々と頂いて、それが元になって話題が広がってゆきます。 自分のつたない知識の中から、こうして少しでもブログを読んで頂いて「楽しかった・・」って言われる事に本当に感謝しています。 さて、今回は市販車として世に出る前、デザインに関してスカイライン・・いえ、櫻井 眞一郎 氏ならではの秘話を公開しましょう・・・ 櫻井 眞一郎 氏と言えば、Mr.スカイラインとして有名ですが、スカイライン以外にも、ローレルや初代F30レパードの主管としてもクルマをまとめていました。 ご存知の方も多いかと思いますが、櫻井氏のクルマ造りは独特で、企画書などの文字でチームをまとめるのではなく、まずは櫻井氏がストーリーを作り、それを開発メンバー全員を集めて読み聞かせ、そこから開発を始めると言う独特の方法が取られていました。 そうやって開発に携わるメンバーのベクトルを統一するのですが、時に同時に開発される車種と、そのベクトルが交差する事もあったのです。 C110ケンメリの開発は、どんどん豊かになる購入者層のニーズと、公害対策に代表されるような 「もはや、クルマは汗を ...出典:徳小寺 無恒さん
-
240K GTの話題で盛り上がったところで、C110スカイライン、通称「ケンメリ」の白のクゥーペだけの秘密を今、明かしましょう・・・ 今では美しいとか、綺麗だと評価の高いC110クゥーペですが、実際に発売されるまでの評価は散々でした。 (こういう例は意外に多く、かのブル910も社内では最悪の評価でした。。) 最終的な生産の承認を得る為には、会社の上層部のOKが出なければいけなかったのですが・・・ そのセレモニーの前に、当時の社長へC110のクレイモデルを見せていたのだが、そこでの評価は芳しくなかったのだ・・ リヤが重々しい。。。ピラーからリヤフェンダーにかけての面が単調過ぎる・・・ピラーとリヤフェンダーの稜線の位置に、メッキモールを付けろ・・と、櫻井(敬称略)に内々にお達しが出ていたのだ。 勿論、櫻井は大反対をした、それまで苦労して作り上げたデザインが崩れてしまう・・・と。。しかし、会社という組織では、いち担当者のできる反論はたかが知れている。 最終プレゼンの日が来てしまった。。。場所は、荻窪の旧プリンスの工場だった。 プレゼンの直前まで、上層部の意見に反して、オリ ...出典:徳小寺 無恒さん
-
知性と理性のクルマ・・スカイラインを差してそういった評論家が居たが。 一見、冷たい機械であるクルマに魂を込めて、ドライバーと語り合えるクルマを目指したスカイラインだが、そこにはドライヴァーの利便性という事にも注力されていた。 必然的にアイディア装備と言えるような装備も数多く存在して、それが日本で始めて・・・といわれる装備も数多く存在する。 TOP画像は、初代スカイラインALSI-1がマイナーして登場したALSI-Ⅱ型だが、そこでも日本初の装備が装着されていた。 今ではまったく何のこと無い「4灯式ヘッドライト」がそうであった。 これでそれまで「暗い」と言われ続けていた国産車の中でもスカイラインは明るい・・と評判になった。 さらに・・・・このALSI-Ⅱ型からマイナーされて追加された「スカイライン・スーパー」では・・・ 国産車で初めて、グリルの中にヘッドライトを装着したモデルが登場した。 ちなみに、この「スカイライン・スーパー」が後に「グロリア」に発展した事は意外に知られていない事実である。 さてさてハナシを戻すが、時代は変わって「ケンメリ」にも国産車とか世界初 ...出典:徳小寺 無恒さん
-
先日も「プロジェクトX」で櫻井眞一郎氏が紹介されていたが、氏も直接、日産と言う会社を離れ、かつての様な氏にまつわるハナシも、時間と共に風化しつつある。。。 櫻井氏と言えば、スカイラインの開発主管として有名だが、もっと本質的に考えると、上司と部下、人と人との交わりが如何に大事かという多くの逸話がある。 現代の人間関係が希薄になってきた時だからこそ、氏にまつわる多くのエピソードを紹介する事によって、そこから何かを学ぶ事ができれば・・・と思い立ち、徒然となってしまうが、私の所蔵する文献や、かつてプリンス系のクルマを買うと定期的に送られて来た「プリンス誌」から、「狐狸庵山人」事「遠藤周作氏」との対談などを紐解き紹介したと思う。 今回は、R31やR32のスカイラインの主管となった「伊藤修令 氏」と櫻井氏とのエピソードを紹介したいと思う。 実は伊藤氏は、広島大学機械科卒業であり、私の郷土の大先輩である。 櫻井学校の一番弟子とも評される伊藤氏。僕と同じ広島出身の僕のヒーローだ。 意外に知られていないが、内燃機関の著名な研究人として、広島大学には「廣川氏」などがおり、私も学生時代 ...出典:徳小寺 無恒さん
-
ここに貴重な画像がある。 これはR30のレイアウトを描いた「櫻井眞一郎」自筆の図面と、ツゥール類だ。 細かく見ると手書きながらの、線の揺れと滲みが散見されるが、遠目に見れば現代のCADも恐れおののく緻密性とバランスの気迫が迫ってくる。 「図面は現場への設計者の唯一の意思表示だ」 とは櫻井の言葉である。 単純に正しく寸法に沿った図面を描いても、それが理解できない図面であれば、モノができないし、間違った解釈をして設計者の思いとは違ったモノができてしまう。。。 僕が図面を引き始めた頃、もちろんCADは存在していたが、最初の数ヶ月は一切の定規やシャーペンを使わせてもらえずに「フリーハンド」で図面を描かされていた。 頭に描いた物体の大きさ、寸法を、形状を定規などを使わなくとも図面を描く者の頭に叩き込む為であった。 現代は、すでにCADが主流でフリーハンドでなんて図面を描く事は皆無である。 これがかつては、 特殊な製図用のペンに、インクを吸わせ、力を均等にかけながら用途に合った線や文字数字を、それぞれの決った太さで描く事が、設計する以上に大切な技術者のテクニックだった ...出典:徳小寺 無恒さん
-
1969年の日本GPでの日産PITでの画像。。。 ゼッケン20の北野に、櫻井が話しかけている画像だが、僕は最初にこの画像を見た時に身体中に電気が走るような衝撃を受けた。 ちょうど、僕も生産技術の仕事を始めて数年が経って、ある程度のやってゆける自信みたいなものが出来始めた頃だったのだが、この画像を見て考えが変わった。。。 皆さんはお気づきだろうか? 僕は櫻井氏の右手のオイル汚れに心囚われてしまったのだ。 現代の設計者は、豊富なセンサーや設計のツゥールによって、段々と現場から遠ざかってしまった様に思えるのだ。 確かに現代のレースなどで、これほど手を汚してピットなどにいる設計者は見た事が無い。。といっても良いだろう。 櫻井は、自分が設計したマシンには真っ先に自分で乗るという。 それはGT-Rでも、R380から幻になってしまったR383まで全てそうだったという。 たしか「プリンス誌」か雑誌での岡崎宏司氏との対談だったと思うが、そんな櫻井のポリシーが伺えるエピソードが紹介されていた。 それを記憶を辿りながら再現してみたいと思う。。 昭和40年プリンスの念願だった本格的 ...出典:徳小寺 無恒さん
オススメ関連まとめ
-
2020/08/14
-
2026/01/15
-
2020/08/20
-
2020/07/27