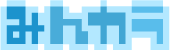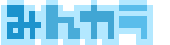#佐々氏のハッシュタグ
#佐々氏 の記事
-
佐々成政が切腹した寺・墓所もある法園寺/法園寺(尼崎市)
法園寺は浄土宗鎮西派の寺院です。開基は室町時代、勝誉恵光法園上人と伝えられています。佐々成政の終焉の地としても知られています。佐々成政は越中富山を居城とし、秀吉と戦ったが後に降伏し、後に赦され肥後国主
2024年6月4日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
越中三大山城の一つ・増山城/増山城(砺波市)
増山城は、和田川右岸の山上に築かれた山城です。松倉城、守山城と並び越中三大山城と称されています。築城時期は不明ですが、南北朝期の貞治2(1363)年の史料「二宮円阿軍忠状」に「和田城」として見え、足利
2022年8月11日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
秀吉に降伏した佐々成政が降伏した際剃髪した地・佐々成政剃髪址/佐々成政剃髪址(富山市)
天正13(1585)年、富山城主佐々成政が、豊臣秀吉の越中攻めで先鋒前田利家の軍に敗れ、その際に成政がこの地で髪を剃り僧衣を着けて服従の意思を示したとされています。当地の字名を道心山(仏道を信仰する)
2022年8月4日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
長尾為景により整備されたといわれる新庄城/新庄城(富山市)
新庄城は、太田新城・辰城とも呼ばれていました。東に常願寺川、西に荒川を望む要害の地にあり、北陸道に面する交通の要衝でもあったため、早くから軍事上の拠点として重要でした。永正17(1520)年、越後の長
2022年8月4日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
磯部の一本榎そばに建てられた早百合観音祠堂/早百合観音祠堂(富山市)
早百合観音祠堂は、早百合伝説の一本榎のそばに住んだ作家でジャーナリストであった翁久允(1888~1973)の手により昭和29(1954)年、建立されたものです。早百合は五福村の農家の娘で、織田信長の武
2022年8月4日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
「黒百合伝説」の残る一本榎/磯部の一本榎(富山市)
この地にはかつて榎の巨樹が茂り、神通川を行き交う人々の目印となっていました。富山城主佐々成政と愛妾早百合との「磯部の一本榎」の悲話が伝えれています。天正12(1584)年暮れ、成政は徳川家康に共に羽柴
2022年8月4日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
佐々成政ゆかりの神社・千歳神社/千歳神社(富山市)
千歳神社は天照大神、豊受大神を祭神とし、富山の土地神として最も古い神明社であり、相殿には誉田別之命を祀っています。天正9(1581)年、佐々成政公が、越中54万石を領して富山城主となった時、この神明社
2022年8月4日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
神保氏、佐々氏、富山前田氏の居城・富山城/富山城(富山市)
富山城は天文12(1543)年に越中守護代の神保長職が、家臣の水越勝重に命じて築城したとされています。別名を安住城といいます。戦国時代は、神保氏、椎名氏、越後上杉氏、一向一揆との間で激しい攻防戦が繰り
2022年8月1日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
佐々成政と前田利家の戦いで名高い末森城/末森城(宝達志水町・旧押水町)
末森城は末森山(標高138.8m)に築かれた山城です。末森城の築城時期などは不明ですが、畠山氏の家臣で地頭職であった土肥親真によって築城されたといわれています。土肥親真は上杉謙信の能登攻略で配下に加わ
2021年12月23日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
加越国境の城・一乗寺城/一乗寺城(小矢部市)
一乗寺城が史料に最初に現れるのは南北朝期の応安2(1369)年、南朝側桃井直常勢を幕府方の能登守護吉見氏頼方が追い落としたとあります(得田文書)。天正12(1584)年に佐々成政の加賀侵攻の際、成政の
2017年1月30日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
佐々氏の居城・比良城/比良城(名古屋市西区)
比良城は天文年間(1532年~1555年)に佐々成政の父成宗(盛政)が築いた城です。大きさは東西68m、南北72m、2重の堀に囲まれた城でした。成宗の死後は、次男の孫介が弘治2(1557)年稲生原の戦
2015年9月6日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
加藤清正以前の隈本城跡/隈本城〔古城〕(熊本市中央区)
加藤清正が今の熊本城を築く前に、隈本城がありました。鹿子木親員が茶臼山西山麓に隈本城を築きました。その後、城氏が居城としましたが、豊臣秀吉の九州征伐後は佐々成政が城主となりました。しかし、肥後国衆一揆
2012年10月5日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
木曽義仲が倶利伽羅峠の戦いの前に戦勝を祈願した埴生護国八幡宮/埴生護国八幡宮(小矢部市)
埴生護国八幡宮は、奈良時代の養老年間、宇佐八幡宮の御分霊を勧請したのに始まり、天平時代には越中国守大伴家持が国家安寧を祈願したと伝えられています。平安時代の末の寿永2(1183)年5月、木曽義仲は倶利
2012年5月18日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
能登、越中の境目の城・森寺城/森寺城(氷見市)
森寺城は、中世の史料には「湯山城」の名で登場していますが、廃城後は麓の村名から「森寺城」と呼ばれています。七尾城を居城とした能登守護畠山義統が越中への進出の拠点として16世紀の初頭に築いたと推定されて
2011年8月25日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
瑞泉寺を城として整備した井波城/井波城(南砺市・旧井波町)
井波城は、周囲土塁で囲んだ戦国末期の平山城です。瑞泉寺3代蓮乗の時代は、土豪や武士団との抗争が激しく、文明16(1484)年頃、本願寺は護法のため瑞泉寺を防衛の地とするべく塁濠を築き、越中一向一揆の拠
2010年12月21日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
椎名康胤の居城・松倉城/松倉城(魚津市)
松倉城は越中最大の山城といわれています。築城は南北朝時代に築かれたと言われていますが、明確ではないようです。戦国時代は椎名氏の居城で、越後の長尾氏(上杉氏)に属していましたが、永禄11(1568)年、
2010年5月5日 [おすすめスポット] ピズモさん