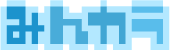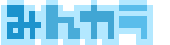#歴史的建造物のハッシュタグ
#歴史的建造物 の記事
-
旧平賀家住宅主屋、源内先生ゆかりの薬草園、平賀源内銅像などで構成されている平賀源内旧邸/平賀源内旧邸(さぬき市〔旧志度町〕)
平賀源内は高松藩の軽輩御蔵番の子として、ここ志度町新町に生まれました。幼名を伝次郎、四方吉といい元服して国倫(くにとも)と名乗り、通称を源内と呼ばれました。また、号を鳩渓、風来山人、天竺浪人とし、作家
2025年6月18日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
国指定文化財の旧矢掛本陣石井家/旧矢掛本陣石井家(矢掛町)
矢掛町は、旧山陽道の第18番目の宿場町として栄え、産業、交通、文化の中心として発展していました。全国唯一、本陣(石井家)、脇本陣(高草家)が共に国指定重要文化財となっています。国指定重要文化財の矢掛本
2025年6月9日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
本陣と共に国の重要文化財に指定されている旧矢掛脇本陣髙草家/旧矢掛脇本陣髙草家(矢掛町)
脇本陣は本陣を補佐する役目を持ち、矢掛宿の最後の脇本陣を務めた髙草家は本陣から東に400mの所にあります。高草家の祖は、国幡国(現在の鳥取県)の守護であった山名氏に由来すると伝えられており、戦国時代に
2025年6月9日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
旧山陽道矢掛宿のメイン通りにある古民家を再生した施設矢掛ビジターセンター問屋/矢掛ビジターセンター問屋(矢掛町)
矢掛ビジターセンター問屋は、旧山陽道矢掛宿のメイン通りにある古民家を再生した施設です。江戸時代には「因幡屋」という屋号で、宿場から宿場へ公用の貨客を運ぶ馬や人足などの輸送手配を行っていました。令和3(
2025年6月9日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
石田城(福江城)を偲ばせる名勝・石田城五島氏庭園隠殿屋敷・心字が池/石田城五島氏庭園隠殿屋敷・心字が池(五島市〔旧福江市〕)
石田城五島氏庭園隠殿屋敷・心字が池は、石田城(福江城)二の丸の一郭にあります。五島家第30代盛成公の隠居所として建てられた隠殿屋敷と、大名庭園である五島氏庭園からなります。嘉永2(1849)年、幕府の
2025年5月11日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
「福江武家屋敷跡」に遺構を活かして造られた観光拠点施設・福江武家屋敷通りふるさと館/福江武家屋敷通りふるさと館(五島市〔旧福江市〕)
五島市の福江地区は、五島藩の城下町として発展してきた寛永11(1634)年、第2代主五島盛利は、五島における中央集権体制を目指し、各地に散在していた五島藩士170余家を福江に定住させを福江城下に強制的
2025年5月11日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
尼崎紡績に関して唯一現存している歴史遺産・旧尼崎紡績本社事務所 〔前ユニチカ記念館〕/旧尼崎紡績本社事務所 〔前ユニチカ記念館〕(尼崎市)
尼崎市東本町に所在する旧尼崎紡績本社事務所(前ユニチカ記念館)は、明治33(1900)年に建築された尼崎市内現存最古の洋館であり、尼崎が工業都市として発展する契機となった尼崎紡績に関して唯一現存してい
2025年4月30日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
日野の観光案内の拠点・休憩スポットとなっている日野まちかど感応館〔旧正野玄三薬店〕/日野まちかど感応館〔旧正野玄三薬店〕(日野町)
日野まちかど感応館(旧正野玄三薬店)は、「万病感応丸」の大きな看板が掲げられ、日野の薬業や町並みのシンボルとして親しまれています。江戸時代日野椀に代わって行商の有力商品となり、日野商人の発展を導くもの
2025年4月29日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
日出藩の藩校・到道館/到道館(日出町)
到道館は安政5(1858)年、日出藩第15代藩主木下俊程の命により日出城二の丸に創立されました。明治4(1871)年に廃藩と共に廃校となりました。校舎は学校や図書館などに利用され、昭和26(1951)
2025年1月21日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
第二次世界大戦中の外務大臣重光葵の生家・重光家/重光家(杵築市)
重光家は杵築市の郊外にある第二次世界大戦中の外務大臣重光葵の生家です。重光家の先祖は、藤原貞周といわれ、五代目になり大友氏に従い豊後に来ました。その後、文禄2(1593)年の大友氏の滅亡により国東半島
2025年1月21日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
杵築藩の藩医を務めた佐野家/佐野家(杵築市)
佐野家は代々杵築藩の藩医をつとめた家です。佐野家の始祖徳安は伊賀国(三重県)名張郡の出身で元和元(1615)年、大阪夏の陣後の騒乱を避け、豊後岡(竹田市竹田)藩の藩医であった祖父の佐野卓節の許に身を寄
2025年1月19日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
くの字型の坂・飴屋の坂/飴屋の坂(杵築市)
飴屋の坂は、南台の武家屋敷と、商人の町を繋ぐ位置にある坂です。くの字型の曲線が、杵築では珍しい坂です。Photo Canon EOS 5D MarkⅡH22.7.19
2025年1月19日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
昭和初期の政治家で杵築市の初代名誉市民一松定吉氏の邸宅・一松邸/一松邸(杵築市)
一松邸(ひとつまつてい)は、昭和の前半、国会議員として国務、逓信、厚生、建設大臣を歴任し、杵築市の初代名誉市民となった一松定吉氏の邸宅です。昭和2(1927)年9月から2年間かけて建てられ、昭和4(1
2025年1月19日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
家老丁に残る唯一の家老屋敷・中根邸/中根邸(杵築市)
志保屋の坂を上がった一帯は家老丁といわれ、中根邸をはじめ家老の屋敷が数十軒ありました。中根邸は、文久2(1862)年に中根家九代家老中根源右衛門が建築したこの屋敷は、「家老丁」に残る唯一の家老屋敷です
2025年1月19日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
杵築を代表する歴史的建造物・大原邸/大原邸(杵築市)
大原邸は「居宅考」に、宝暦のころは相川東蔵(120石)が住み、東蔵が知行返上後、中根斎(家老新知350石)、岡三郎左衛門を経て、桂花楼となったとあり、御用屋敷桂花楼の場所であったと伝えられています。「
2025年1月19日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
杵築藩主松平氏の一族・能見邸/能見邸(杵築市)
能見邸は、北台武家屋敷群に立地する能見家は、杵築藩主松平氏の出身地である三河国能見を姓とし、五代藩主親盈の九男幸之丞が初代となります。「居宅考」によれば、寛政12(1800)年の寛政の大火以前は岡藤介
2025年1月19日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
杵築藩藩校・学習館の跡に現在も残る藩校の門/藩校の門〔藩校学習館跡〕(杵築市)
藩校の門は、杵築藩藩校・学習館の藩主御成りの門で、天明5(1785)年に七代藩主松平親賢が設立したもので、藩の定紋である雪笹の瓦を用い、現在市内に残る門の中で最も規模が大きく、格調高い門です。 内側に
2025年1月19日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
北台の武家屋敷・磯矢邸/磯矢邸(杵築市)
藩政時代、このあたりは「北台家老丁」と呼ばれていましたが、屋敷は、「居宅考」によると、宝暦(1751~1763)のころは、安西源兵衛が住んでいて、寛政の大火(1800年)の後、御用屋敷である「楽寿亭」
2025年1月19日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
広瀬淡窓を輩出した広瀬家を改築した資料館・廣瀬資料館/廣瀬資料館(日田市)
廣瀬資料館は、広瀬淡窓を輩出した日田の商家だった広瀬家の蔵の一部を改築した資料館です。広瀬家は、武田信玄の家臣だった広瀬郷左衛門の弟、広瀬将監正直であると伝えられ、五左衛門貞昌が18歳の延宝元(167
2025年1月19日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
広瀬淡窓の私塾・咸宜園跡/咸宜園(日田市)
咸宜園は、幕末の儒者広瀬淡窓の私塾です。高野長英や大村益次郎などもこの咸宜園で学びました。淡窓は、文化2(1805)年、24歳の時豆田町の長福寺を借りて開塾しましたが、その2年後に桂林荘を中城川の側に
2025年1月19日 [おすすめスポット] ピズモさん