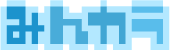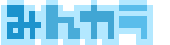#毛利氏のハッシュタグ
#毛利氏 の記事
-
土岐氏、織田氏、尾張徳川家に仕えた毛利氏の居城・八神城/八神城(羽島市)
八神城の城主は毛利氏でした。同氏は鎌倉時代より尾張国長岡庄石田郷司職として、この地方の地頭あるいは領主として幕末まで居住していました。明治維新後も、八神城跡の一角に居住していたとされています。その間、
2025年3月17日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
佐伯藩毛利氏の居城・佐伯城/佐伯城(佐伯市)
佐伯城(さいきじょう)は、慶長7(1602)〜慶長11(1606)年にかけて毛利高政が築城した城です。毛利高政は元々、森姓でしたが秀吉の中国大返しの際、毛利輝元に人質に出された際、輝元に気に入られ毛利
2025年1月17日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
豊前との境目の城・角牟礼城/角牟礼城(玖珠町)
角牟礼(つのむれ)城は、弘安年間(1278〜1288)に玖珠郡衆の森朝通により標高577mの角埋山(つのむれやま)に築かれたといわれています。古くから豊前側からの侵入を防ぐ豊後の境目の城として、 玖珠
2025年1月14日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
大内・尼子の衝突の舞台となった鏡山城/鏡山城(東広島市)
鏡山城は鏡城とも呼ばれ、山口の守護大名大内氏の安芸国支配の拠点として築かれました。古文書等に初めてその名が見えるのは寛正6(1465)年頃と考えられる小早川熙平宛細川勝元感状写(小早川家証文)ですが、
2024年10月2日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
上月合戦に使用されたとみられる仁位山城/仁位山城(佐用町〔旧上月町〕)
仁位山城は上月城に近接しており上月合戦に使用されたとみられます。別名仁位の陣山とも呼ばれ、標高233m、佐用川を挟んで上月城と対時する位置にあります。城についての記録はほとんどありませんが、「赤松家播
2024年4月8日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
毛利輝元の長男・毛利秀就公誕生の地/長州藩初代藩主毛利秀就公誕生の地(宇部市)
毛利秀就は毛利輝元の長男で、天正19(1591)年1月20日、この地長門国厚東郡小野村の領主財満就久の土居内、別名西御前で誕生しました。ここにはその時の産湯の池のほか、生まれた時建てた若宮神社や高良神
2024年2月21日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
毛利氏庭園/毛利氏庭園(防府市)
毛利氏庭園は、明治25(1892)年頃から旧長州藩主毛利家の新しい本邸の場として選ばれ、建設準備が始まりました。しかし、折からの日清・日露の役のために遅延し、大正元(1912)年になってやっと着工し、
2024年2月6日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
毛利元就教訓状発祥の地及び土塁が残る中世の城郭的寺院・勝栄寺/勝栄寺(周南市・旧新南陽市)
勝栄寺は、山号は出城山、浄土宗の寺院です。創建当初は時宗の寺院で、開山は基阿(ごあ)上人、開基は大内弘世の重臣陶弘政です。創建されたのは、陶氏が富田保へ移住して間もない南北朝時代の1350〜70年頃と
2024年1月31日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
阿賀氏、井上氏の居城・阿賀城/阿賀城(安芸高田市・旧八千代町)
阿賀城は、中世は阿賀氏の居城で、毛利元就の時代には井上越前守光貞、井上左馬之助就任の親子二代の居城だったと伝えられています。井戸跡、土塁、曲輪などが残っています。Photo Canon EOS 5D
2024年1月21日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
毛利氏、福島氏、浅野氏ゆかりの寺院・明星院/明星院(広島市東区)
明星院は、正式には月光山大日蜜寺明星院という真言宗御室派の寺院です。毛利輝元が母の位牌所として建立し、当時は妙寿寺(院号明星院)といいました。その後、福島正則は寺領200石を附して祈祷寺を命じました。
2024年1月21日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
藤原興藤、陶晴賢、桂元澄、毛利(穂井田)元清の墓がある洞雲寺/洞雲寺(廿日市市)
洞雲寺は、山号は応龍山、曹洞宗の寺院です。大内氏の重臣陶氏の菩提寺である山口県・龍文寺の僧金岡用兼(きんこうようけん)を開祖とし、桜尾城主であった厳島神主藤原教親・宗親父子により、長享元(1487)年
2024年1月21日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
城井谷合戦で戦死した毛利の将・勝間田彦六左衛門重晴の碑/勝間田彦六左衛門重晴の碑(築上町・旧椎田町)
天正15(1587)年10月、第一次城井谷合戦で、黒田勢は寒田攻めを開始しましたが、城井谷からではなく、東側の谷の入口、広幡城を攻略し、9日、黒田長政は宇都宮鎮房と岩丸山上で戦いました。尾根上が小山田
2023年8月27日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
小早川秀包、田中氏、有馬氏の居城となった久留米城/久留米城(久留米市)
久留米城は、永正年間(1504~1521)地元の土豪が城砦を築いたのが始まりといわれています。近世城郭の始まりは、天正15(1587)年、豊臣秀吉の九州平定後に毛利元就の子である小早川(後に毛利に復姓
2023年8月9日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
織田信長公が建立・毛利家の菩提寺の大徳寺黄梅院/大徳寺黄梅院(京都市北区)
永禄5(1562)年織田信長公が羽柴秀吉公を伴い上洛した際、秀吉公を京都所司代に任じ、併せて父信秀公の追善供養のために普請を命じ、小庵を建立させました。大徳寺98代住持・春林和尚を開祖に迎え、黄梅庵と
2022年3月20日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
長府藩の居城・櫛崎城/櫛崎城〔串崎城・雄山城〕(下関市)
櫛崎城〔串崎城〕は遠く天慶3(940)年、藤原純友の配下稲村平六景家がこの地に拠ったとも伝えられていますが、確かな記録が無く、大内氏の重臣内藤左衛門太夫隆春が築城し、配下の勝間田氏が城主となって長府の
2015年1月26日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
大内義隆の月山富田城攻めの本陣跡・京羅木山城/京羅木山城(松江市〔旧東出雲町〕・安来市〔旧広瀬町〕)
京羅木の語源については、「清木(きよらぎ)」「京萩(きょうはぎ)」など諸説あります。標高473m、実に中海をめぐる連山中の最高峰です天文12(1543)年、山口の大内義隆は、尼子攻めに宍道からこの京羅
2014年10月6日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
毛利元就を祀る神社・石見銀山にある豊栄神社/豊栄神社(大田市)
豊栄神社は、戦国の武将毛利元就を祀った神社で、毛利家ゆかりの社です。元就が生前、自分の木像を造り山吹城に安置させましたが、元就の孫の毛利輝元が、洞春山長安寺を建立し、木像を写しました。関ヶ原の戦いの後
2014年2月13日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
石見銀山支配の拠点・山吹城/山吹城(大田市)
山吹城は、鎌倉時代末期の延慶年間(1308~1311)に石見銀山が発見された際、その守備のために大内弘幸によって築かれたと伝えられています。戦国時代の中期、大内義興の代になると出雲国の尼子経久の間で両
2014年2月13日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
毛利元就の撤退戦で身代わりとなった渡辺通ら七人の武士の戦死の地と伝えられる七騎坂/七騎坂(大田市・旧温泉津町)
永禄2(1559)年、出雲の尼子晴久に奪われた石見銀山を取り戻すため、毛利元就は1万4千騎を率いて銀山と向かい合わせにそびえ立つ山吹城を攻めました。山吹城を守っていた本城越中守経光の激しい抵抗に遭い、
2014年2月11日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
毛利水軍の拠点として築城された鵜丸城/鵜丸城(大田市・旧温泉津町)
鵜丸城(うのまるじょう)は中世の港湾として繁栄した沖泊の南側の丘陵突端に位置する標高59m(比高55m)の海城です毛利氏によって元亀2(1571)年に毛利水軍の拠点として約1か月で築城されたことが「児
2014年2月11日 [おすすめスポット] ピズモさん