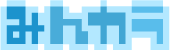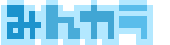#長野氏のハッシュタグ
#長野氏 の記事
-
「伊勢は津でもつ津は伊勢でもつ、尾張名古屋は城でもつ」・津城〔安濃津城〕/津城〔安濃津城〕(津市)
津城は長野氏の一族の細野藤敦が築城しました。その後織田氏の伊勢支配と共に織田掃部頭(津田一安)、織田信包が入城し天正5(1577)年には5重天守と小天守が完成しました。文禄4(1595)年富田知信が5
2020年4月5日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
伝、箕輪城主長野業盛の墓/伝、箕輪城主長野業盛の墓(高崎市・旧群馬町)
長野業盛は、戦国時代の西上州の要であった箕輪城の長野氏最後の城主です。永禄9(1566)年武田信玄の攻撃を受け落城し、自害しました。その遺骸は当地の僧法如らによってこの井出の地に葬ったとされています。
2016年9月10日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
細野氏が築き、長野氏が後に居館としたと考えられる長野氏城居館(細野城)/長野氏城居館(細野城)〔東の城・中の城・西の城〕(津市・旧美里村)
長野氏城居館は、細野城とも呼ばれ、築城年代は不明ですが、南北朝時代に細野氏によって築かれたといわれます。細野氏は長野氏の一族で弘治年間に安濃城を築いて移り、長野氏が南北朝時代の長野城から細野城へ居城を
2015年7月8日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
長野氏十六代のうち、三柱を御祭神に・長野神社/長野神社(津市・旧美里村)
長野神社は、長野家2代当主・祐藤が経ケ峰の中腹にあった安濃国造社を、正応2(1289)年にこの地に移したのが、長野神社の起源とされています。明治41(1908)年11月、南長野、北長野、平木、桂畑の四
2015年7月7日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
長野氏の居城だった長野城/長野城〔長野氏城〕(津市・旧美里村)
長野城は伊賀街道を見下ろす、桂畑の地の地元では「城の台」とも呼ばれている標高580mの山上に築かれています。長野氏はこの他にも北長野の標高230mの丘陵尾根に東の城・中の城・西の城を築いていました。長
2015年7月7日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
黒田官兵衛孝高が入国後仮の居館とした法然寺/法然寺(築上町・旧椎田町)
法然寺は、西山浄土宗の寺院です。鳥羽天皇の時代、天仁元(1108)年、西願法師の開基による寺院で、当時は天台宗の日峯山台蔵寺と称しました。永正年間(1504〜1520)に僧行信が入山し、荒廃した寺院を
2014年9月16日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
史跡/馬ヶ岳城跡
天慶4年に築城と伝わる。14世紀半ばから15世紀前半にかけて新田氏三代が居城したとされている。その後長野氏が城主となり、秀吉の九州征伐軍に降り秀吉はこの城に滞在している。九州平定後に黒田如水が中津に居
2013年12月31日 [おすすめスポット] うどん子@総統閣下さん
-
西上野の名城・箕輪城/箕輪城(高崎市・旧箕郷町)
箕輪城は永正9(1512)年長野業尚によって築かれました。長野氏は在原業平の子孫と言われ当主は「業」を名前の一字としています。武田・上杉・北条の攻防の舞台となりましたが、戦国期の当主長野業正は上杉氏に
2013年9月15日 [おすすめスポット] ピズモさん
-
織田信包、分部氏の居城・伊勢上野城/伊勢上野城(津市・旧河芸町)
上野城は、元亀元(1570)年、織田信長の弟信包が津の仮城として、この地に築城しました。織田信長は、永禄11(1568)年に伊勢国に侵攻し、長野氏は信包が跡を継ぐことになりました。信包は、それまで長野
2011年4月3日 [おすすめスポット] ピズモさん