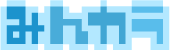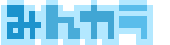ブレーキバランスチューニング

-
ブレーキの性能は、車の安全に関わる重要な部分なので、誤った扱いをすると事故に繋がりかねません。
が、
机の上で絵を描いて計算してシミュレーションする分には何だってできちゃう!自由だ!!
字と数式ばっかなので、読書アレルギー&数学苦手な方は要注意w -
ブレーキバランスチューンの考え方
-
どうもトライズです! ブレーキの話をしましょう!! 楽しいブレーキの話です。 時は少し戻って、ディレチャレエリアカップより前の話ですが、VEシルビアのブレーキは純正からいくらかのアップデートが行われました。 初期の仕様では、キャリパー側がS15スペックS純正そのまま。マスターシリンダは、S14シルビアのABS無し用を使っていました。 フロント片押し、リアもサイド兼用片押し。 ローター径はフロント280mm リア258mm。 マスターシリンダ径は、15/16インチ マスターバックは7+8インチ。 どちらもS14後期ターボABS無し用。 さーどう料理しましょう。 定番のフロント4potはもちろんやるとして、他にもいろいろ変えたいと思います。 時にみなさま、ブレーキバランスの計算とかはお好きでしょうか。ブレーキセッティングは重要かつ非常に面白いところなので、これから数回にわたりブレーキ関連の日記を書きたいと思います。 多分に、マッドメカニックの趣味趣向が色濃く反映される内容になると思いますが、「いやその考え方は気に入らない」って人 ...出典:トライズさん
-
こんばんは!トライズです。 先日に引き続きブレーキの話をば。 S15シルビアってブレーキバランスが前寄りな気がしませんか? サイドブレーキが利きにくいのはディスク式だから仕方ないとして、とゆーかサーキットタイムアタックでは、サイドはほぼ使わないので置いておくとしても。 たとえば、ヘアピンのターンインとかブレーキングドリフトをやろうとしてもなーんかどうも大人しくて物足りない気がします。 また、S15シルビアは全車ABS標準装備ですが、ABSをキャンセルすると、この無駄な安定感がより強くなります。いまいちバランスが悪い感じ、、 では、実際のところ、S15のブレーキ前後バランスはどんな感じなのでしょうか。 ざっくり試算してみます。 まず、ブレーキの前後バランスを決定する要件を列挙します。 1.ローター径 前後のローター径の比は、そのままブレーキバランスを決定する係数になります。 ただし、より正確に計算するならばローター外径ではなく、キャリパピストンの中央を通る弧の位置(有効ローター径)を用いて計算します。 2.キャリパピストン面積 これも前 ...出典:トライズさん
-
基礎編ばっかでつまんないと思いますがね。 続けますw ブレーキチューンを考慮するに当たって、もうひとつ重大なファクターがあります。 それは、荷重移動。 ブレーキング時にはかならず前後の荷重移動が起こります。 ブレーキの前後バランスを決定するに当たっては、この荷重移動分を必ず考慮しなければなりません。 今回は、制動時の荷重移動量の計算について説明したいと思います。 ちなみに、ブレーキング時の挙動は、サスペンションセッティングや、ロール剛性の影響をもろに受けます。 いくらアンダーが強い車でも、リアに極端に硬いバネを入れたり、リアタイヤをいわゆるドリケツタイヤにすれば、簡単にケツが出ますし、すーぱーテールハッピーな楽しい車が出来上がります。 しかし、タイムアタック車両として考えた場合、リアのハイレート化やタイヤの変更は思いっきりトラクションを下げる方向になってしまいます。 考え方としては、ブレーキを適正なバランスまで合わせ、それからサスセッティングを詰めることで、立ち上がりでのトラクションを犠牲にすることなく、進入(ブレーキング)で向きが変えられ ...出典:トライズさん
-
どーもー!トライズです! さあ!!ブレーキ前後配分の続きいきましょう! 前回、制動Gあたりの理想前後制動力をグラフにするところまでいきました。 これですね。 これを、横軸をフロントの制動力、縦軸をリアの制動力にしてグラフに書き直します。 すると、 こんな感じ! これが、理想制動配分曲線と呼ばれるもので、ブレーキを設計するには必ず必要になるデータです フロントの制動力に対して、リアをどのくらいの制動力に持っていけば一番効率が良いかが一目でわかるわけですね。 グラフの各点は0.1G刻みで、一番右が1.0Gです。 このグラフに、S13の実ブレーキ配分を重ねてみます。 S13のブレーキセットは次のとおり。 フロント:片押しシングル キャリパピストン径:57.20mm ピストン断面積:25.68cm2 ローター径:280mm 有効ローター半径:111.40mm リア:片押しシングル キャリパピストン径:33.96mm ピストン断面積:9.05cm2 ローター径:258mm 有効ローター半径:112.02mm 前後 ...出典:トライズさん
-
キャリパーについて
-
あっついっすねー。 どうも。トライズです。 前回は、ブレーキの前後比と軸重に注目しました。 その補足をもう少し。 ■まず、ブレーキ性能はパッド面積に左右されないのかと言う点。 なんとなく、パッド面積が広いほうがブレーキは良く効く気がしますね。 パッド面積を広げることは、ブレーキの安定性に貢献します。 パッド-ローター間の摩擦係数には温度依存性があり、ある特定の温度帯でのみ安定した性能を発揮します。 それで、パッドを大きくする、面圧が均一になるようにする、もしくはローターの冷却性能を上げることによって温度変化を抑えるなら、より広い範囲で安定した制動力を得られるようになります。 とはいえ、同じ温度帯であれば、パッド面積を大きくしたとしても制動力は変わりません。 このあたりはピンヒールで踏まれると痛い理論ですな。 大きいパッドでも、同じ力で押すなら面積が広がるぶん力も分散しますから。 専門用語では、しゅうどうするめんのめんせきはまさつりょくにはむかんけいとかなんとか言うあれ。 クーロン先生ありがとう。 そういうわけで! ブレーキの前後バラ ...出典:トライズさん
-
■S15シルビアに流用できそうな他車種ブレーキのスペック なお、車両名はできるだけブレーキが特定できるように書いていますが、年式、グレードによって一部異なる場合があります。 シングルピストン(もしくは対向2pot)の場合、ピストン中心=パッド中心位置になるので、パッド幅も調べておきました。 ---------- 車両/前後/ピストン(シリンダ内径)(mm)/シリンダ断面積(cm2)/パッド幅/ローター径/有効半径(mm)/トルク値(kgf・m) ---------- トルク値は、パッドμ係数=1.0、油圧=1.0kg/cm2とした時の軸トルクを現した値です。 データ内のローター有効半径、トルク値は、算出されたものなで実測とは異なる場合があります。出典:トライズさん
-
Pバルブについて
-
ふと我に返るマッドメカニック・・・ 大丈夫ですかね??このブログ。 段々と、頭の固い教授の自分語りようなつまらない内容になってきてませんかね? え、既になってる?(汗 いやえっとそうじゃないんですよ。カーチューニングはドリームなんですよ。ファンタジーですよ。 もし杖を振って炎を出せたりしたらなんかすごいかっこいいじゃないですか。 しかもその仕組みが分かっちゃったりしたらすごくワクワクするじゃないですか。 そういうワクワクをメカニカルな分野でも共有したいんですよ! ・・・ えー。Pバルブの解説いきます。 Pバルブ(プロポーショニングバルブ)って知っていますか? 辞書には、 制動時の車輪ロックを防止するために、ホイールシリンダーに作用させる液圧を減圧する液圧制御バルブの一種である。 となっていて、 ざっくり言えば、ブレーキの前後配分において絶妙なプロポーション(調和の取れた比率)を実現するための部品です。 Pバルブにはいくつか種類があります。種類というか用途別というか。 1.普通のPバルブ 最も多く ...出典:トライズさん
-
夏休み終わったー! あっとゆうまの夏・・・ あろはー。どうもトライズです。 今回はPバルブの動作と特性について書きます。 前回までのダイジェスト! 大抵の自動車のブレーキシステムにはPバルブ(プロポーショニングバルブ)というものが付いていて、これによっていかなる路面μやあらゆる動作によっても安全に制動ができるように、理想的な前後配分により近いブレーキバランスを実現することが可能になった。Pバルブのシステム自体は機械的なものでABSを初めとする電子制御的な先進技術には及ばないものの、ブレーキの基本構成を整える非常に重要なファクターである。 Pバルブの特性を理解するために、 Pバルブ搭載車両のブレーキバランスをグラフにします。 サンプルは、S13前期。エンジンが名機CA18のやつですな。 こんなかんじ。 Pバルブの作用によって、加速度(減速度)の高い領域でリアが弱くなるわけですね。 ちゃんとPバルブ付ける前提で設計されているようで、1G付近まで割と理想配分に近いです。 Pバルブの動作をより分かりやすくするため、マスターシリンダ発 ...出典:トライズさん
-
「ダッシュボードなんて」でググると、このブログにたどり着けるようですよ! というか既に自分でも過去の日記を検索するのに、「ダッシュボードなんて+"検索語句"」を多用していたりw どうも、マッドなメカニックです。 いつも文字やら数式やらばかりの日記でお疲れかと思いますので、今日は写真多めで行きますよ! やっぱたまには心癒される精密部品の写真でも眺めながらリラックスするのも良いと思うんですよねー。 Pバルブの構造について。 Pバルブの動作自体は大体どれも同じなのですが、内部構造はメーカーによってかなり種類があるようです。 基本は、マスターシリンダーからの油圧を入力、リア配管側を出力とした1入力1出力のものですが、フロント側の油圧を引っ張ってきて、2入力1(2)出力のものもあります。 日産のシルビア系のPバルブは大きく分けて2種類。 いずれもマスターシリンダーにくっついていて、 ABS付き車用のこんなやつと、 ABS無し車用のこれ、 この2種類。 内部構造は若干違いますし、どちらもマスターシリンダ一体(非分解)ですが、 ...出典:トライズさん
-
そういえば、このブログも立ち上げから1年が経ちました。 時が経つのは早いものです。 トライズです! 需要そっちのけな独り言ブログですが、まだまだがんばります! Pバルブ分解の続きいきます。 ABS無し用マスターシリンダのPバルブ(TOKICO製)。 これの、 中身を、 図解! たぶん初公開S14Pバルブの断面図。 注釈入れてみた。 左側がマスターシリンダ、右がリア配管のつながるところ。 ど真ん中の妙な形をした部品がPバルブのピストン(プランジャー)。 ピストンの真ん中に、直径1mm位の穴が貫通しています。 反対側から 左側の細いスプリングで押されているのが流路を遮断する弁です。 スプリング入ってます。 これ以上は分解するのが怖かったので、放置。 左のほうの赤斜線の部品は、 これなんですが、これ自体が何の働きをしているのかはイマイチ分からず。 裏面 なにかのトラブルの時にリアのブレーキを遮断するモノのようにも見えますが、イ ...出典:トライズさん
-
今年の夏は雨がひどいですねぇ、、 どうも!トライズです! Pバルブの中身がどのように動作しているのか解説したいと思います。 こちらがPバルブの断面図。 Pバルブの作動グラフ マスターシリンダ側が入力圧 リアキャリパ側が出力圧 Pバルブは、油圧制御弁の一つですが、その動作は不思議な感じがしませんか? 1ウェイバルブ(チェックバルブ)とかリリーフバルブとかなら、入力圧が一定以上になると油圧がスプリングの力に勝って弁が開く仕組み。油圧はその圧力以上あがらなくなります。 オリフィスなど流量を調整する絞り弁であれば、圧力変化の過渡期は入力側と出力側の圧力が違いますが、一定圧で保持していれば、入出力の油圧は同じになります。 ブレーキ用のPバルブの場合は、一定圧以上で弁が開きリア側の油圧が入力側よりも低くなります。そこまでは、リリーフバルブの動作と同じですが、一定圧(スプリットポイント圧)以降のリア油圧は、フロント側より低いものの比例して変化します。 ただし、オリフィスとは違いペダルを保持(入力油圧が一定)なら、時間経過によってリア油圧が変化 ...出典:トライズさん
オススメ関連まとめ
-
2018/01/26
-
2021/11/22
-
2024/08/06
-
2026/02/15