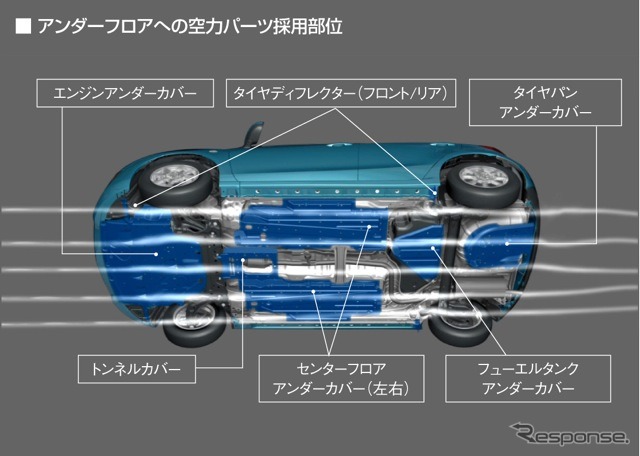色々な思考が錯綜して混乱しているATSUです。
たまには「速さ」の概念を捨てたことでも。今回は「マフラーの音」という趣向性の高い部分について考察してみました。調べ物の記録簿として。
それこそ趣向性によるものなので、人によって「良い音」というのは全然違います。
が、ATSU的にはF1音が好みです(*´∀`*)
こんなヤツ
もう最高です!
ただこの車たちはそもそも気筒数が違いますし、回転数も違うためこのような高音(高いHzの音)がでています。
しかしこの音に少しでも近づけたらという願望から、高音を獲得するために何かできることがないか考えてみました。いつかマフラーワンオフする時にも使えそうです。
一般的にマフラーの高音を鳴らす手法として
・直管にする
・径を細くする
などがあります。じゃあなぜこれらをすると高音が出るのか??
①なぜ直管は高音が鳴るのか?
まず一般的にスポーツマフラーというのはグラスウールと呼ばれる綿状の物に音を吸収させて消音させています。
 DIY道楽
DIY道楽様より
まとめるとグラスウールによって排気は減圧されるため音圧が抑えられて消音という結果がもたらされるみたいです。
ここで重要なのが、このような構造だと高音は簡単に吸収されてしまい、低音はなかなか吸収されないことです。
よく社外のスポーツマフラーをつけると「ボーボー」という音がするのは、消音しきれなかった低音が出てしまっているようです。
だから音圧が高いことももちろんですが、直管だと高音が吸収されずそのまま排出されるため高音が鳴るみたいです。
これに付随して低音を消すにはどうしたらいいかというと、径を絞れば消えていきます。よくマフラーに突っ込むサイレンサー(バッフル)がありますが、コレについて上記のHP様では
>バッフルといえば、ほとんどがサイレンサーの出口に取り付けるものですが、装着した時と非装着の時の音質の違いを聞いたことがある方にはわかるでしょうが ・・・ 音が抑えられるというよりは、低音だけが押さえつけられているような ・・・ もちっと言うと、すかしっ屁 のような ・・・ パスパス音になります。ビスビス音でもブスブス音でもいいですが。
と書かれています。その通りでそんな音がします(笑)
これを効率的に行っているのが純正マフラーなどでよく採用されている多段膨張式サイレンサー

 BADMOON
BADMOON様より
こんな構造にすると低音を消して狙った音域だけを残した夢のようなマフラーを作ることも夢じゃない!?
しかし一般的な社外マフラーでこんな構造しているのはなかなか無いのはコストもありますが、狙った音域をコントロールする音室容積計算ノウハウが無いからかもしれないですね。
ホンダS2000純正マフラーの製造会社さんの施設をチラッと調べてみましたがトンデモない研究施設だったと記憶してます(笑)
ちなみに現在つけているGPスポーツのEXAS EVO TUNEマフラーのアレ

画像ではパワーチャンバーとか呼ばれてますが、友達曰く「ヘルムホルツ共鳴器」と言うらしいです。F1ではアクセル開閉に合わせて圧を均衡化するために採用されてる場合もあるとか。
GPスポーツの場合はをれを消音にうまいこと利用しているみたいです?
②なぜ径を細くすると高音が出るのか?
よくドリフトでデュアルマフラーにしている人達のおとは少し甲高く聞こえますよね?
その他AE86のマフラーの音は凄く甲高いですが、マフラーを見ると凄く細いです。
これを解くために笛の構造をお勉強(笑)
高音が鳴るということは概ねHz(ヘルツ)が高いことを指すことが多いみたいです。
さらに笛の構造には開管型と閉管型があります。

これが開管型

これが閉管型
画像は
気柱の振動様より
上記HP様の中にも書いてありますが、音波長λは筒長よりも少し長いらしいです。
開口端補正値は管径の0.6倍ぐらいになる、ということは管径によって開口端補正は変わるということになります。
車のマフラーは開管型なので少し解いてみました。(実際のマフラーの条件とは異なりますが、基本振動での鳴り方として考えています)
用いる条件としてはマフラーを想定して3.5mの管、音速340mでの、異なる径によって出る基本振動(ヘルツ)はどう変化するかです。
・まずターボ車でありがちな80Φの管の場合
開口端補正 = (80/2)×0.6 = 24mm
波長 = (3500+2×24)×2 = 7096mm
Hz = 340/7.096 = 47.91(Hz)の音が鳴る
・NAにありがちな60Φの管の場合
開口端補正 = (60/2)×0.6 = 18mm
波長 = (3500+2×18)×2 = 7072mm
Hz = 340/7.072 = 48.07(Hz)の音が鳴る
となり、径が2cm変わったときの変化としては0.2Hzぐらいです(泣)
数字としては僅かですが、これはあくまで基本振動数であって、ここにエンジンの周波数が掛けられてくるので人間の耳にも音の変化が感じられるようです。
ちなみによくチタンにすると乾いた音がするとか言いますが、上記の式の音速の数字が
音速=√金属の弾性率(Pa)/密度(kg/m3)
によって変化するので変わるみたいです。ステン(SUS430)の縦弾性係数が204KN/㎜2、密度が7.7g/㎝3なのに対し、チタンはそれぞれ106と4.51になるので音速に若干変化が生じるようです。
上記のことから高音を獲得して良い音を出すためには
・直管(もしくはグラスウールを使わない構造) ⇒
実験してみました
・マフラー径を細くする
ついでに素材をSUS430のような音速確保できる素材で作るとよろしいみたいです。
しかし一般道を走るのに直管にするワケにはいかないですし、径を細めたり素材にこだわってもその違いはあるとは言え僅かな物の様です。
できたら多段膨張式サイレンサーにしたいですが、そんな緻密な計算できません(爆)
「じゃあそもそもの音の周波数を上げてしまえば良いのでは?」という発想になります。。。あ、エンジン載せ換えはナシですよ?(笑)
コストや排気効率度外視してコレをやると上記以上に高音を獲得することが出来ます?
直4のエンジン音を8気筒の音にするのも夢じゃない!?
コレを踏まえた上記のようなマフラーを作ると、なおよろしい感じです。
しかしそれについては
続きのブログにて。・・・ってこんなマニアックでメモ書きみたいな話を最後まで読んでる人はどれだけいるのでしょうか?(笑)
I wrote this article in English.If you
wanna read this, pls visit
this English ver.
※2018年8月4日追記
実際にグラスウールを取って管構造を変えるとどうなるか実験してみた
ブログはコチラ。
※2019年8月30日追記
マフラーサウンド、音質を良くするにはどうしたら良いのか。あるマフラーを例に
続きの考察をしてみました。