ちょっとお堅いネタは小休止するつもりだったのですが(^^ゞ
以前、
惰眠さんが取り上げられていた八代センセイが
NBオンラインで対談していて、本音が語られていたので感じたところをちょっと書き綴ってみたいと思います。
長くなると思うので、興味のない方はスルーしてください。
まず「戦後にできた労働法制は、主として高度成長期における終身雇用・年功賃金などの慣行を対象にしたもの」と言われていますが、この表現ってちょっと違和感があって、本当に戦後の混乱期に高度成長を見越して法制を定められたんでしょうか?
「盛んに言われている格差や貧困の多くは長期経済停滞の影響から生じているものであって、規制緩和をしたからではありません。」もおかしくて、今の政府の見解では戦後最長の好景気なんではなかったでしたっけね?
「管理職手当のように、残業手当に相当するものはあらかじめ一括してもらって、固定的な勤務時間に縛られずに自分の判断で働く。例えば大学教師やマスコミの人の大部分は、現にそういう働き方なのではないでしょうか。」こんな働き方が出来るホワイトカラーが全体のどれほどを占めているのでしょうか?
そもそも、大学教師やマスコミの人の大部分だけがそうであれば、年俸制の給与にすれば良いだけで、ホワイトカラー全体に当てはめるような法を新しく制定する必要はないはずです。
「本来は個人の責任と成果が極めて漠然としたままなのに、賃金はブルーカラーと同じように労働時間で決められる法制度になっています。そういう矛盾を抱えた制度が、自己申告通りに残業代が払われる一部の人たちにとっては既得権のようなものになっている。そういう人たちにとって、今回の改革は既得権を手放すことになりますから反発が起こるのは当然でしょう。反対のない改革なんてあり得ませんからね。」
出ましたコイズミ前政権以来の決まり文句!既得権、反対勢力とレッテル貼れば思考停止に陥ると思っているかのようです。
自己申告通りに残業代が払われてる人が今の日本でどれくらいいるのか、一度現状を把握されてみた方が良いのではないでしょうかね。
「逆に言うと、残業をしなければまともな給料がもらえない。法律が非効率な働き方を生み、長時間労働を助長しているような側面があるのです。」
本当にそうなんでしょうかね?残業しても割増賃金を払わない、法律にしたら、本当に残業しなくてもまともな給料がもらえる社会になるなんて能天気に期待しても良いんですか?
「ホワイトカラーの悪平等を解消して守るべき人たちを守るためには、きちんと成果主義を取っていくしかありません。求められた成果をきちんと出せば、どんなに労働時間が短くても文句をつけられない。正社員か否かに関わらず、成果を出すほど給料も上がる。成果を出せない人は給料が上がらないようにすることが、労働市場全体での「公平な働き方」です。」
結局、このセンセイは成果主義信奉者のようです。
僕もずっとソフトウェアの第一線で仕事してましたから、能力でコーディングの差がつく事は良く理解しています。また出来が悪く、残業しないと出来ない=結果的に残業代が嵩む図式も解ります。
でも、短期でその能力を給与に反映させるなんて空論に過ぎません。結局ロングレンジで、出来る人をより上のポジションにつけるような処遇で対処するしかないはずです。
「そういう不公平や非効率性を、もはや放置していられる時代ではありません。日本では既に1995年から生産年齢人口が減少に転じています。貴重な働き手にもっと効率良く働いてもらわなければいけない。」
このセンセイの本音がとうとう語られました(^^;)
効率良く働いてもらわないといけないんだそうです(苦笑)
「評価ができないなんていうのは甘え以外の何物でもありません。仕事の評価ができなくてどうしてマネジメントができるのですか。完璧でないにしても、それをするのが管理職の仕事でしょう。欧米の企業にできることが日本の会社になぜできないんですか。」
と言われてますが、
ウィキペディアに諸外国の例がまとめてありました。
アメリカでさえ、管理職・専門職か、ホワイトカラーかつ「重要事項に関する自由裁量・独立した判断」を出来るか、年収が10万ドル以上、だそうです。
独、仏、英いずれも管理職か、自由裁量権が要求されているそうです。
センセイのお話では、管理職が成果主義で管理せよ、と仰っているので、自由裁量権はかなり狭そうですし、以前は年収400万円が対象ても噂されてましたから、いやはや何とも、って感じですね…。
あと、成果主義ですが、
日本の企業はノルマでも上からの指示でもなく、勝手に下から提案を持ち上げていたと、それが成果主義で一掃されたと言われています。
これは僕もそのような仕事の進め方していましたから良く解ります。
アメリカのように、職務定義書を作ってその範囲内でしか仕事をしなければ成果主義は成り立つでしょうが、その成れの果てが
これで、今や米国企業の7割がBB以下(ジャンク債)の評価なんだそうです。
そして、オフショアとかアウトソーシングとかして一見競争力がつくように見えますが、実際は国内市場を空洞化させ、本来社内で持っておくべき技術力まで失わせているように思えてなりません。
そんな米国企業のする事なす事をことごとく盲従している日本企業って何だろうと、不思議でなりません。
マリー・アントワネットは
「パンがなければお菓子を食べればいい」と言ったそうですが(^^;)、成果主義や格差を是認する人達も五十歩百歩なのかも知れませんね。
あと、ずっと疑問視しているのが、このセンセイのようにかなり偏った人が規制緩和やら経済財政諮問会議の議長やら議員やらをお勤めになる。
そこになんら実情も民意も入らず、思い込みや机上の空論、そして一番怖いのは関係者の恣意で政策が決まってしまう事です。
例えばこの
お方、「格差は甘え」「過労死は自己責任」とかなり過激な主張の持ち主ですが、やはり規制改革会議委員をお勤めになられています。
が、
この方の会社は2005年度の人材派遣会社業界売上高ランキングでは総合105位程度であり、どうして選出されたのか、それについて疑問を唱えた野党議員に猛反発したり、取引のある会社の社外取締役に就任したり、オリックス社長や郵政公社総裁、村上ファンドなどともかなり親交が深いようです。
格差は当然、機会均等、再チャレンジなどと言われていますが、このようなお金持ちサークル内で規制緩和をしては仕事を回しあっているように見えて仕方ありません。
あれこれ指摘している内、すっかり長くなりました(^^ゞ
ついでに少しだけ触れておくと、規制緩和絡みのハゲタカ外資の絡んでいると言われる、
コレと
コレ、いずれも闇は深そうです。
Posted at 2007/02/07 01:46:54 | |
トラックバック(1) |
政経 | 日記
 久しぶりにカタいネタ3題
久しぶりにカタいネタ3題 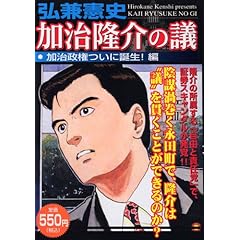
 ホワイトカラー・エグゼンプション少し調べてみました
ホワイトカラー・エグゼンプション少し調べてみました  闇は深い
闇は深い  不二家をあまり責めないで(^^;)
不二家をあまり責めないで(^^;) 
 ホワイトカラーエグゼンプションって
ホワイトカラーエグゼンプションって 


