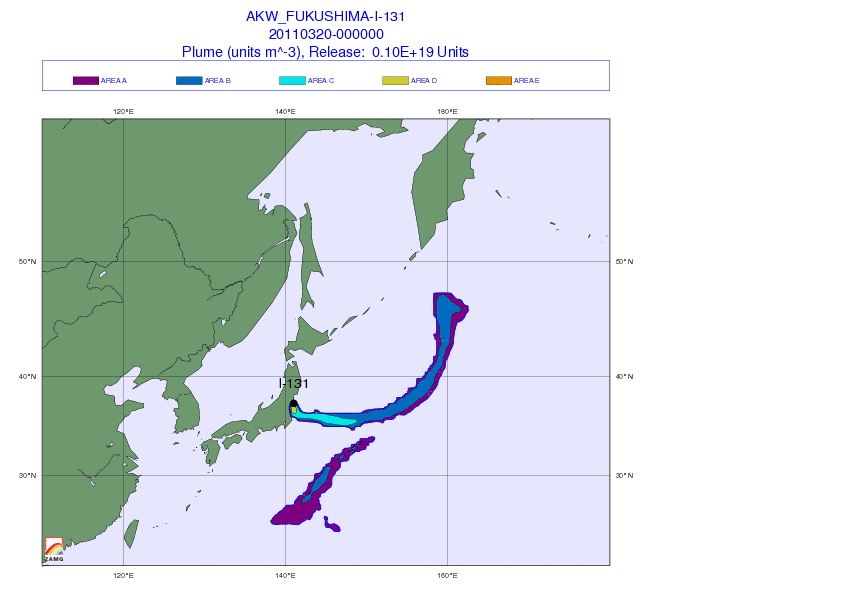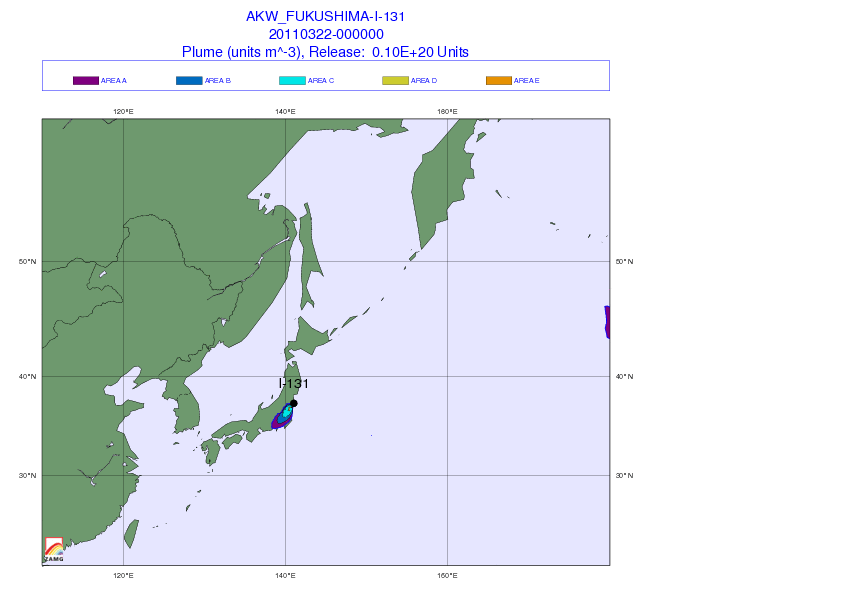飲料水の基準とは、一体どのように考えれば良いのか?
その根底には「基準」なるものが存在するが、原発問題の発生前後でその「基準」が変わっていたら、どのように理解すれば良いのだろうか?
世界保健機関(WHO)による飲料水基準は、「230ページ、表9-3」参照のこと。
詳細(PDF)については、↓の表紙をクリック


このWHOのガイドラインによれば、飲料水における「ヨウ素-131」「セシウム-137」の基準は、共に「10ベクレル(Bq/L)」である。
しかし、震災後の平成23年3月17日、厚生労働省から「放射能汚染された食品の取り扱いについて」という通知が出され、新たな飲料水の基準が示されている。
詳細(PDF)については、↓の表紙をクリック


この通知により、飲料水における「ヨウ素-131」「セシウム-137」の基準は、原子力安全委員会により示された指標値を暫定規制値として、それぞれの値は「300ベクレル(Bq/kg)」と「200ベクレル(Bq/kg)」に引き上げられている。
そして、23日には東京都から浄水場における放射能測定結果についての発表があり、「
190ベクレル(Bq/kg)」を示したが、24日には「
79ベクレル(Bq/kg)」まで低下したことにより都は乳児の摂取自粛要請を取りやめた。
ちなみに、23日に新宿区で採水された調査では「25.8ベクレル(Bq/kg)」であった。


おそらく混乱を避けるために新たな水質基準が示されたのであろうが、「水質基準」設定の根拠を含めて、水の摂取に当たりこの数値の判断は難しい。
半減期についても、「ヨウ素-131」は8日で「セシウム-137」は3年らしいが、この解釈に関する詳細な情報も示して欲しいものである。
また、政府と販売店には「母子手帳」の提示で優先的にミネラルウォーターを購入出来るような配慮を提言したい。乳児を抱えた母親の目前で、老人と団塊世代が我先に購入する姿は見苦しいものである。
※ このタイトルは数日で削除する予定であり、深刻な問題でもあるので「コメント」および「イイね!」は''不可''とさせて頂きます。
Posted at 2011/03/24 14:37:44 | |
トラックバック(0) |
etc | 日記






 ←は、3月12日から18日までにDigitalGlobeが撮影した衛星写真の一部。
←は、3月12日から18日までにDigitalGlobeが撮影した衛星写真の一部。