ではラストです。
一般公開はされませんでしたが、桟橋から護衛艦「くらま」と豪州のフリゲイト「スチュアート」が見えましたので何枚か写真を写してみました。

ヘリコプター搭載護衛艦DDH-144「くらま」(満載排水量7200トン)です。
「しらね」型DDHの2番艦として昭和56年に竣工した大ベテラン艦で、「はるな」「ひえい」「しらね」と4隻就役したヘリコプター3機搭載護衛艦の最後の1隻です。
「しらね」型は昭和56年開催の第15回観艦式から観閲艦を務め、実質的な海上自衛隊のシンボル的な護衛艦です。
艦載ヘリコプターとしては非常に大型になるHSS-2型ヘリコプターを3機、基準排水量5000トン程度(「はるな」型で4950トン、「しらね」型で5200トン)の比較的小型の艦艇に搭載するのは世界でも非常に珍しく、注目を浴びたようです。
また「しらね」型はウエポンシステムをコンピュータで統括した海上自衛隊で初めてのシステム艦でもあります。
艦首から艦尾にかけて「くらま」の流麗な艦影を写したかったのですが、桟橋の長さの関係で写せませんでした。。。

2門の速射砲を背負い式に設置された姿は戦艦を髣髴とさせる優美さを感じます。
マストに見える黒く四角い巨大な板はOPS-12対空レーダで、シースパロー短距離艦対空ミサイルシステム搭載のため三次元レーダを搭載するようになりました。
その手前に2つメッシュ状のパラボラアンテナが見えます。
これは72式射撃指揮装置1型(FCS-1)で、5インチ砲の射撃統制用です。
2門の5インチ砲に2つの射撃指揮装置があるということは別々の目標を同時に対処することが出来ることを意味します。

こちらは艦首に搭載された73式5インチ54口径単装速射砲です。
米海軍のMk42 5インチ速射砲を国産化したもので、「くらま」は2門搭載しています。
射界を確保するため前後の背負式の配置となりました。
艦首側を51番砲、艦橋側を52番砲と呼んでいます。
こちらは51番砲で、砲塔に短波用の空中線が設置されています。

こちらは52番砲。
「こんごう」型のOTOメララ127ミリ速射砲や、「あきづき」型のMk45-mod5 5インチ砲と比べるとやはり大型で、重量は67トンにもなります。
砲の操作、弾庫から砲身への装填は全自動電気油圧式ですが給弾方式は手動なんだそうです。
1分間に35発の射撃が可能でこれはMk45-mod5の20発よりも発射速度は速いことになります。
観艦式の訓練展示では祝砲として空包射撃を行いますが、Mk45-mod5やOTOメララ127ミリ速射砲、OTOメララ76ミリ速射砲といった自動砲は弾頭が未装着の場合エラーとして判断されるため、空包射撃ができないそうです。
現在この73式5インチ砲を搭載しているのは「くらま」、DDH「はたかぜ」「しまかぜ」の3隻のみとなっています。

「くらま」の艦橋構造物。
艦橋手前にあるパイプを組み合わせて設置されているものはハイラインポスト。
洋上補給はハイラインを使いますが人力作業用となっています。
トラスの先端にハイラインを通し、人力で引っ張って使います。
艦橋右舷側にサイレン(?)のようにみえる大型の円筒状のものはOE-82C衛星通信アンテナ。
見切れてしまっていますが艦首側に見える大型の四角いものはアスロックランチャMk112です。
8連装のアスロック発射機で米海軍が開発した装備です。
アスロックは対潜用の短魚雷をロケットの弾頭部に装着したもので、遠方にロケットを使って投射しパラシュートを使って着水すると魚雷の誘導装置で敵の潜水艦に突入していきます。
ちなみに隣に見えるマストは護衛艦「おおなみ」のもの。

マストを下から。
搭載艇の上側に見える白いドーム状のものはスーパーバード衛星通信アンテナ。
白い布が張られているのは「くらま」が観閲艦のため。
安倍晋三内閣総理大臣が乗り込み、観艦式では観閲を行いました。
警備の関係で一般公開されなかったのは残念でしたが、引退間近の「くらま」にとってハレ舞台となりました。

艦構造物中央付近です。
護衛艦の多くは艦橋構造物と後部艦構造物は煙突をはさんで分かれていますが、「くらま」は一体型となっています。
艦構造物の上部で黒く塗られているのが煙突で、前後に2基ありますが、第1煙突にマスト、第2煙突に射撃統制用レーダが設置してあるのが面白いですね。
マストと煙突が一体になっているのをマック方式というようです。
「くらま」の主機はガスタービンではありません。
海上自衛隊の護衛艦では唯一蒸気タービンを用いています。
後部艦構造物は巨大なヘリコプター格納庫につづきます。

艦構造物中央付近、搭載艇の下です。
3本の筒が俵状に積まれているのは3連装短魚雷発射管HOS-301です。
米海軍のMk32短魚雷発射管を国産化した68式短魚雷発射管で旋回操作は人力で行います。
接近した敵潜水艦に対して射撃するもので、73式短魚雷やMk46短魚雷を空気圧で発射します。

第2煙突横には高性能20ミリ機関砲が搭載されています。
ミサイル護衛艦の長射程艦対空ミサイルや個艦の速射砲や電波妨害、短SAMの迎撃をくぐりぬけてさらに突入してくる敵対艦ミサイルを打ち落とす最後の砦ですが、海上自衛隊で新造時から搭載したのはこの「くらま」からです。

艦尾です。
ヘリコプター搭載護衛艦と呼ばれるだけあって非常に広大なヘリコプター甲板と格納庫が目を引きます。
ヘリコプター甲板はSH-60ヘリコプターをタンデムに2機並べることが出来る長さをもっているそうです。
第2煙突が右側に偏って設置されているのがわかります。
その関係もあって搭載する3機のヘリコプターは右側に1機、左側に2機という形になるようです。

格納庫天蓋部。
第2煙突上部にみえる白いドームは81式射撃指揮装置2型(FCS-2)でシースパロー短距離艦対空ミサイルの射撃統制をします。
天蓋上部中央部に「x」型の形のカバーがついている4連装が2セットついたものがシースパロー発射機です。
この発射機の中にRIM-7シースパロー短距離艦対空ミサイルが装填されます。
シースパローはF-15戦闘機に搭載するAIM-7スパロー空対空ミサイルを艦艇用にしたもので、FCS-2から照射された誘導電波によって目標に突入します。
「しらね」型は初めてこのシースパローシステムを搭載した護衛艦で、個艦防空能力を得ることが出来ました。
その手前にはヘリコプター誘導指示用の水平灯などがみえます。

ヘリコプター格納庫を別アングルで。
格納庫の中も広く、汎用護衛艦がヘリコプターを1機(必要に応じて2機)搭載するのに対して、3機を搭載することが出来るだけの広さがあります。
格納庫が小さい汎用護衛艦にはない整備資材や部品などもここに置かれるようです。
格納庫外壁にはいくつもの膨張筏がおかれています。
これは右舷・左舷両側にありますが、基本的に片側だけで乗員全員分を確保されているようですね。

艦尾のヘリコプター甲板の下です。
「くらま」と書かれていますね。
飛行甲板の下は係留装置などが収納されています。

「くらま」を後ろから。
隣は「おおなみ」と「いかづち」ですが、「くらま」はそれとくらべるとずいぶん長く感じますね。
「むらさめ」型、「たかなみ」型の長さは151メートルに対して「くらま」は159メートルと、8メートル長くなっています。
「くらま」の飛行甲板の下に黄色い魚型(?)のものがみえます。
これは可変深度ソナー(VDS)というものです。
海流の温度差によりソナーの音波伝播が悪くなったときにこれを沈めて探知を行うソナーシステムです。
現在これを搭載しているのは「くらま」のみです。
次はオーストラリア海軍のフリゲイト「スチュアート」です。
実は何気にこれを書くのが一番大変でした。
とにかく資料がない。
私は陸自装備なら「自衛隊装備年鑑」と「PANZER」と部隊の公式ページを参考に、海自は「世界の艦船」とその増刊と「自衛隊装備年鑑」「Jships」「イカロスMOOK」を、空自は「自衛隊装備年鑑」「航空ファン」「イカロスmook」を参考にして書いている(何気にwikiは使ってないんだよ~)のですが、オーストラリア海軍の本なんて持ってないですから。
ようやく探して見つかったのが世界の艦船増刊の「世界の大型水上戦闘艦」のみ。
自衛艦とくらべると今回かなり手抜きなのは・・・許してね。

観艦式にはゲストとして外国海軍の艦艇も数隻が参加します。
この日オーストラリア海軍のフリゲイトも横須賀に停泊していました。
153「スチュアート」(満載排水量3700トン)です。
「スチュアート」は「アンザック」級フリゲイトの4番艦として2002年に竣工しました。
「アンザック」級はニュージーランド海軍も採用していて「テ・カハ」「テ・マナ」の2隻を保有しています。
「テ・マナ」は以前名古屋港に寄港・一般公開もされました(恐ろしいことにCICまで・・・)。

艦首から。
桟橋の長さの関係で全体を写せなかったのが残念。
艦橋の手前に艦対艦ミサイル(SSM)発射筒が装備されてるんですね。
このSSM発射筒は4連装が左右1基づつ合計8本搭載されています。
装填するSSMはハープーンで海上自衛隊でも使用されているSSMです。
「アンザック」級はもともとSSMの搭載はしていませんでしたが、2002年から搭載することになったようですね。

艦首には5インチ砲を搭載しています。
ニュージーランド海軍の「テ・マナ」はMk45 5インチ単装砲を搭載していましたが「アンザック」級も同じMk45かな?
砲身が非常に長く感じます。
満載排水量がやや大きい「はつゆき」型が76ミリ速射砲を搭載していますが、この規模で5インチ(127ミリ)砲はかなり大型に見えますね。


艦構造物中央付近です。
艦橋構造物後方にラティスマスト、その後方には対空レーダがあります。
海上自衛隊の護衛艦ではマストよりも前方に対空レーダを搭載しますが、海外ではこういう配置もあるのかと興味深いです。

同じく艦構造物中央付近。
艦橋構造物と煙突の間になりますが、ここには複合艇と搭載艇揚収用のクレーンがみえます。

やはりありました、3連装単魚雷発射管です。
米海軍が開発したMk32でしょうか?
口径324ミリの水上発射管で海上自衛隊のHOS-302と非常に良く似ています。

煙突です。
「アンザック」級の煙突は2基あるのですが、海上自衛隊の護衛艦のようにタンデムに2基あるのではなく、V字型に2基配置しているのが興味深いです。
煙突にはオーストラリアらしくカンガルのマークが描かれていました。
「アンザック」級の主機はガスタービンエンジン1基とディーゼルエンジン1基によるCODOG方式をとっています。
高速航行時には大出力のガスタービンエンジンを使い、低速時にはディーゼルエンジンを使って燃費と速度性能を両立させるシステムです。
「アンザック」級はESSM(発展型シースパロー)短距離艦対空ミサイルをMk41VLSに搭載しますが、これは煙突の後部のヘリコプター格納庫上部に設置しています。
VLSは8セルで、ESSM短SAM専用のようでVLアスロックの装備はないようです。

「スチュアート」を真後ろから。
ニュージーランド海軍の「テ・カハ」級はSH-2対潜ヘリコプターを搭載しますが、オーストラリア海軍の「アンザック」級はS-70B哨戒ヘリコプターを1機搭載します。
「アンザック」級は満載3700トン、全長118メートル、幅14.8メートル、満載排水量では似た規模の海上自衛隊の「はつゆき」型護衛艦は満載4000トン、全長130メートル、幅13.6メートルですから、ずんぐりした印象を受けます。
ヘリコプター格納庫は右舷側にドアがありますが、左側はヘリコプター用弾庫でしょうか?
そういえば高性能20ミリ機関砲がみあたりません。
ニュージーランド海軍の「テ・カハ」級は搭載していますが「アンザック」級には搭載していません。
それぞれの海軍がどういう使われ方をするかなのでしょうが興味深いですね。
以上豪州フリゲイト「スチュアート」でした。
ここからは陸上自衛隊の装備品展示です。

横須賀基地に陸上自衛隊の車両が数台装備品展示として参加していました。
こちらは1/2トントラック。
第31普通科連隊の車両ですね。
いわゆる自衛隊ジープで現在のものは三菱パジェロをベースにしているそうです。

こちらは高機動車。
こちらも第31普通科連隊の車両ですね。
普通科部隊の足として配備された車両で高い路上・路外機動性能をもちます。
10名の乗員を載せることができ、発煙機や近SAM発射機、新短SAM発射機、対戦車ミサイル搭載型などさまざまな派生型もありますね。

こちらは3 1/2トントラック。
いわゆる大型トラックで人員や物資輸送などに使われる自衛隊で最も目にすることが多い車両です。
こちらも第31普通科連隊の車両で人員なら22名を載せることができます。

こちらは軽装甲機動車。
普通科部隊などに装備され戦場機動などに使用される装甲車です。
固有の武器はありませんが小銃や機関銃を車載射撃したり、軽対戦車誘導弾を車上射撃することが出来ます。
こちらも第31普通科連隊の車両ですね。

こちらは82式指揮通信車。
戦後国産初の装輪式の装甲車両で、特科部隊や普通科部隊に配備され部隊間の指揮通信に用いられます。
こちらも第31普通科連隊の車両です。

自衛隊は高い練度と士気、優れた装備をもっていますが食事がなければ動けません。
こちらは野外炊具1号です。
200人分の主食や副食を概ね45分以内に同時に調理できる炊具で、炊飯、汁、焼、煮、揚、炒といった調理が可能な万能調理用装備です。
おまけ。

横須賀基地の駐車場にいたグランドエスクード。
護衛艦隊の業務車ですね。
護衛艦隊は横須賀に司令部をおく組織で、自衛艦隊の隷下になります。
人員1万人以上、48隻の護衛艦と16隻の艦艇からなる海上自衛隊の中核をなす組織で、4個の護衛隊群、第1海上補給隊、第1輸送隊、海上訓練指導隊群などによって編成されています。
以上、FREET WEEK!平成27年度自衛隊観艦式艦艇一般公開の模様でした。
平成27年度自衛隊観艦式一般公開
その1/その2/その3/その4/その5/その6
 豊川駐屯地創立65周年記念行事(2015年11月21日)その2
豊川駐屯地創立65周年記念行事(2015年11月21日)その2 





























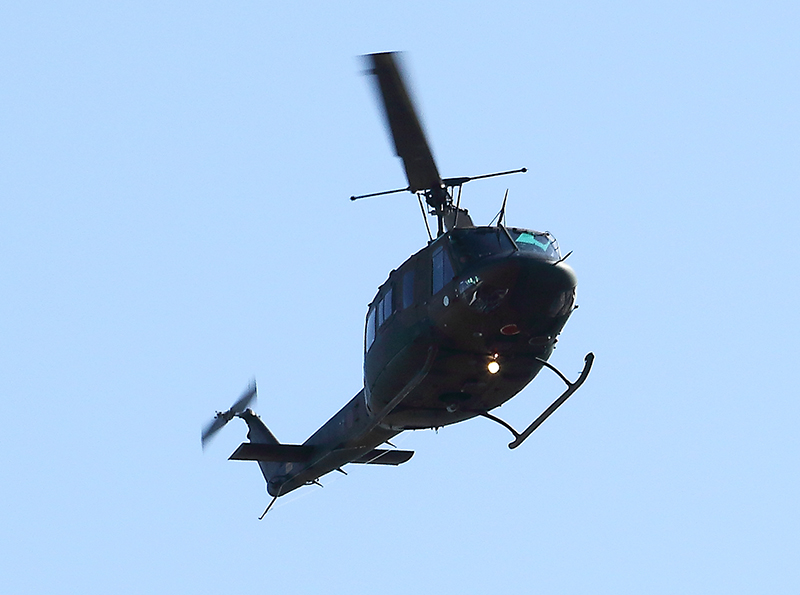
 豊川駐屯地創立65周年記念行事(2015年11月21日)その1
豊川駐屯地創立65周年記念行事(2015年11月21日)その1 


















































 浜松広報館車両・地上支援器材展示イベント(3月26日)
浜松広報館車両・地上支援器材展示イベント(3月26日) 












 FREET WEEK!平成27年度自衛隊観艦式艦艇一般公開(10月10日)その6 護衛艦「くらま」、豪艦「スチュアート」編
FREET WEEK!平成27年度自衛隊観艦式艦艇一般公開(10月10日)その6 護衛艦「くらま」、豪艦「スチュアート」編 





























 FREET WEEK!平成27年度自衛隊観艦式艦艇一般公開(10月10日)その5 護衛艦「あたご」編
FREET WEEK!平成27年度自衛隊観艦式艦艇一般公開(10月10日)その5 護衛艦「あたご」編 





























