ちょっと前のことになりますが、昨年平成27年11月21日土曜に愛知県豊川市にある陸上自衛隊豊川駐屯地にて創立65周年記念行事が行われました。
観閲式、訓練展示、装備品展示、アトラクションと盛りだくさんのないようでした。
その模様をちょこっと紹介します。


記念式典が始まりました。
観閲式式典会場は豊川駐屯地に隣接する演習場(グランド)です。
既に参加部隊が整列をしています。

「部隊整列」
受閲部隊が一同に整列しました。
豊川駐屯地は特科部隊、普通科部隊、施設科部隊他支援部隊が駐屯している大きな駐屯地なので観閲式の規模も旅団規模にちかいものがあります。

「観閲官登壇」
観閲官となる第10特科連隊長兼豊川駐屯地司令が観閲台に登壇し各部隊に対して敬礼をします。
豊川駐屯地には第10特科連隊、第10高射特科大隊、第49普通科連隊、第6施設群、それらを支援する直接支援中隊および支援隊、豊川駐屯地業務隊、第308会計隊、第306基地通信隊、第130地区警務隊といった数多くの部隊が駐屯しています。

「国旗入場」
国旗が入場してきました。
この後全員起立して国旗に対して注目します。
音楽隊の国歌演奏とともに国旗が掲揚されます。
普段気にすることのない国旗という存在ですが、日本国という国家を象徴する非常に重要な旗です。
自国の国旗に敬意をもち尊重できる人は外国の国旗にも敬意を持ち尊重できる人です。
薄い白い布地に描かれた赤い日の丸ですがそこには1000年2000年とつづく文化や伝統、価値感が今に引き継がれているわけです。

「観閲官巡閲」
音楽隊の”巡閲”の演奏とともに観閲官の豊川駐屯地司令が部隊を巡閲します。
赤色の旗がみえますが、これは第49普通科連隊の旗です。
陸上自衛隊は普通科部隊、特科部隊などさまざまな役割(これを職種といいます)を受け持つ部隊がありますが、職種ごとに色が決まっています。
赤は普通科部隊、濃黄は特科部隊、えび茶は施設科部隊、紫は武器科を示します。

「観閲官訓辞」
駐屯地司令による豊川駐屯地開設65周年記念式典の式辞です。
豊川駐屯地は愛知県豊川市に置かれている駐屯地で、陸上自衛隊創立前の昭和25年12月に警察予備隊豊川駐屯地として設立されました。
この地は終戦まで豊川海軍工廠があり、戦後は跡地に豊川市役所、日本車両、そして豊川駐屯地などが設置されています。

「来賓祝辞」
”ひげの隊長”こと佐藤参議院議員ほか来賓が祝辞を述べます。
祝辞は来賓の国会議員、市議会議員、県議会議員などが行いますが「国防は最大の福祉」とはいわれるものの、残念ながら防衛をどんなにまじめに考えても票には結びつきません。
それだけに祝辞の内容も来賓によって非常に中身が濃いものから中身のない挨拶までいろいろです。
災害派遣だけでなく防衛を行ううえで必要な予算や法体系についてこうしていきたいと語る人、災害派遣だけしか語らない人、その災害派遣すら中身がない人、さまざまです。
来賓の多くは周辺自治体の市議会議員、県議会議員が多いのでどのようなことを言っているのか、その中身はどうなのか、しっかり聞いていて損はないと思いますよ。


「観閲行進準備」
観閲官訓辞、来賓祝辞が終わると観閲行進が行われます。
観閲行進のため隊員が車両にかけより一斉にエンジンをかけます。
豊川駐屯地には普通科、特科、高射特科、施設科など多くの部隊が置かれていますので非常に多数の車両が観閲行進を行います。

観閲行進に先立って「大空」の演奏とともに第10音楽隊が入場してきました。
第10音楽隊は名古屋市の守山駐屯地に駐屯する第10師団隷下の音楽隊で、音楽演奏を行うことで隊員の士気高揚を行う部隊です。
記念式典での音楽演奏や学校などへの技術支援、各種イベントでの演奏を行います。

音楽隊の演奏が「大空」から「祝典ギャロップ」にかわると車両による観閲行進開始です。
先頭は観閲部隊指揮官の乗る82式指揮通信車です。

続いて第49普通科連隊です。
第49普通科連隊は平成16年3月に編成された新しい部隊です。
元々は第10師団隷下の普通科部隊でしたが平成26年3月に第10師団を離れ中部方面混成団隷下になりました。


同じく本部管理中隊です。
赤い旗は普通科部隊を示します。
普通科とは諸外国の兵科でいう「歩兵」にあたるもので陸上自衛隊の中心となる職種になります。
第49普通科連隊は自衛官と即応予備自衛官によって編成される部隊です。

続いて同じく第1中隊です。
装備は高機動車。
第49普通科連隊を編成している即応予備自衛官は元自衛官で退職後民間企業などでさまざまな職業についていますが年間30日間の訓練に参加し、有事や大規模災害など必要に応じて召集を受けると身分は即応予備自衛官から自衛官になり任務に当たることになります。

同じく第2中隊です。
装備は高機動車。
第49普通科連隊は災害派遣でもさまざまな民生支援、給水支援をおこなっています。
編成された年の平成16年は新潟中越地震、平成19年の広島県トンネル崩落事故、そして平成23年の東日本大震災では即時救援活動と民生支援を行っています。

同じく第3中隊です。
第49普通科連隊が配置されている中部方面混成団は平成20年に陸上自衛官の教育を行う第2教育団を廃止して新たに中部方面混成団として編成されました。
常備自衛官と即応予備自衛官による普通科連隊2個と教育を行う部隊3個により編成されています。


同じく第4中隊です。
装備は軽装甲機動車。
軽装甲機動車は平成14年度から全国の普通科部隊に配備されている軽装甲車両で乗員4名を載せることができます。
固有の火器はありませんが小銃、機関銃を取り付けることで車載射撃が可能なほか、軽対戦車誘導弾を車上射撃することができます。

同じく第5中隊です。
装備は高機動車。
第49普通科連隊は連隊本部、本部管理中隊、重迫撃砲中隊、5個普通科中隊により編成されています。
第5中隊は平成26年に対戦車中隊を廃止して新たに編成された普通科中隊です。


同じく重迫撃砲中隊です。
重迫撃砲中隊はその名の通り重迫撃砲を用いる部隊で装備は120ミリ迫撃砲RTです。
この迫撃砲は普通科部隊最大の火砲で107ミリ迫撃砲の後継として平成4年度から調達が開始されました。
かって特科部隊が装備していた105ミリ軽砲以上の砲径をもち大火力で、通常弾なら8100メートル、噴進弾なら13000メートルという長大な射程をもっています。
重量は600kgと重いですがタイヤをつかって牽引できるので迅速に展開することが可能です。

続いて中部方面後方支援隊第306普通科直接支援中隊です。
この部隊は第49普通科連隊を後方支援する部隊で第49普通科連隊が装備する火砲や車両等の装備の整備補給をおこないます。


装備は3 1/2トン有蓋車と重レッカ。
第306普通科直接支援中隊はもともと第10師団隷下の第10後方支援連隊第2整備大隊第4普通科直接支援中隊として第49普通科連隊を後方支援していましたが、第49普通科連隊の編成替えに合わせてが平成26年3月に中部方面混成団隷下となっています。


続いて第10特科連隊です。
第10特科連隊は第10師団の野戦特科(砲兵)を担当する部隊で、中部方面隊では唯一の特科連隊(第3師団、第13旅団、第14旅団では規模の小さい特科隊)です。

同じく本部中隊です。
第10特科連隊は昭和32年に姫路駐屯地にて第3管区総監直轄部隊として創隊され昭和35年に豊川駐屯地に移動、以後愛知県三河地方18市町村を警備・防災担当としています。

同じく情報中隊です。
情報中隊は第10特科連隊の目と耳になり射撃の情報を各部隊に提供する部隊です。

装備は対砲レーダ装置JTPS-P16。
敵が射撃する火砲の砲弾を遠距離で捕らえて射撃地点を標定する装備です。
後方の車両は野戦特科情報処理システム。
射撃指揮関する目標情報を処理伝達する装備です。

同じく第1大隊です。
第10特科連隊第1大隊は105ミリ軽砲を装備する大隊として昭和37年に改編されました。

同じく第1大隊本部管理中隊です。
本部管理中隊は通信補給情報など第1大隊の支援を行う部隊です。
第1大隊は本部管理中隊、第1中隊、第2中隊により編成されています。


同じく第1中隊です。
装備は155ミリりゅう弾砲FH70です。
第10特科連隊の主要装備のFH70は陸上自衛隊の主力になる火砲で欧州で開発された火砲です。
我が国では昭和58年度からライセンス生産が開始され昭和60年度から部隊配備が始まっています。


同じく第2中隊です。
装備は155ミリりゅう弾砲FH70。
第10特科連隊では昭和63年に第5大隊にFH70が配備、改編されていますから比較的早い時期に配備されたことになります。

同じく第2大隊です。
第10特科連隊第2大隊は105ミリ軽砲を装備する大隊として昭和37年に改編されました。

同じく第2大隊本部管理中隊です。
第2大隊は本部管理中隊、第3中隊、第4中隊により編成されていて本部管理中隊は第2大隊の支援を行う部隊です。


同じく第3中隊です。
装備は155ミリりゅう弾砲FH70。
第10特科連隊がFH70を受領・改編するまでは105ミリりゅう弾砲M2A1と155ミリりゅう弾砲M1が各大隊に配備されていました。


同じく第4中隊です。
装備は155ミリりゅう弾砲FH70。
FH70は自走砲ではなく写真のようにトラックにより牽引される牽引砲です。
自走砲は自走能力をもち展開先での移動が容易ですが高価で重く、駐屯地から展開先まではトレーラなどにより輸送する必要があります。
一方牽引砲は自走能力がないもののトラックで牽引されるため駐屯地から展開先までの移動が早く、また安価な特徴があります。

同じく第3大隊です。
第10特科連隊第3大隊は105ミリ軽砲を装備する大隊として昭和37年に改編されました。
尚、第10特科連隊には第4大隊、第5大隊もあり計60門ものFH70を保有する大部隊でしたが平成26年3月の部隊改編で第4大隊、第5大隊は廃止されFH70も30門に縮小されています。

同じく第3大隊本部管理中隊です。
第3大隊は本部管理中隊、第5中隊、第6中隊により編成されていて本部管理中隊は第3大隊の支援を行う部隊です。


同じく第5中隊です。
装備は155ミリりゅう弾砲FH70。
FH70は牽引砲ですが補助動力エンジンを備えているので限定的な自走能力をもちます。
そのため陣地の移動、砲列布陣、撤収が迅速に行うことが出来ます。
操作要員はそれまでの105ミリ軽砲が10名、155ミリ中砲が12名なのに対してFH70は給弾が自動化されてるなど9名と省力化されています。


同じく第6中隊です。
装備は155ミリりゅう弾砲FH70。
FH70の射程は通常弾で24km、噴進弾で30kmと非常に長大です。
これはそれまで陸上自衛隊最大射程をもつ火砲だった155ミリ加農砲M2を上回る射程になります。

続いて第10後方支援連隊第2整備大隊特科直接支援中隊です。
第10特科連隊の火砲、車両、通信器材等の整備及び回収を行う部隊で第2整備大隊本部は愛知県春日井市の春日井駐屯地においています。

装備は3 1/2トン有蓋車と重レッカ。
重レッカは大型のレッカ車で大型の車両や火砲の回収や整備には欠かせない車両です。
最大吊り上げ能力は実に10トンとされてます。
観閲行進まだまだ続くよ!
_________________________
豊川駐屯地創立65周年記念行事 その1/その2/その3/その4 豊川駐屯地創立65周年記念行事(2015年11月21日)その4
豊川駐屯地創立65周年記念行事(2015年11月21日)その4 













 豊川駐屯地創立65周年記念行事(2015年11月21日)その3
豊川駐屯地創立65周年記念行事(2015年11月21日)その3 


















































 豊川駐屯地創立65周年記念行事(2015年11月21日)その2
豊川駐屯地創立65周年記念行事(2015年11月21日)その2 





























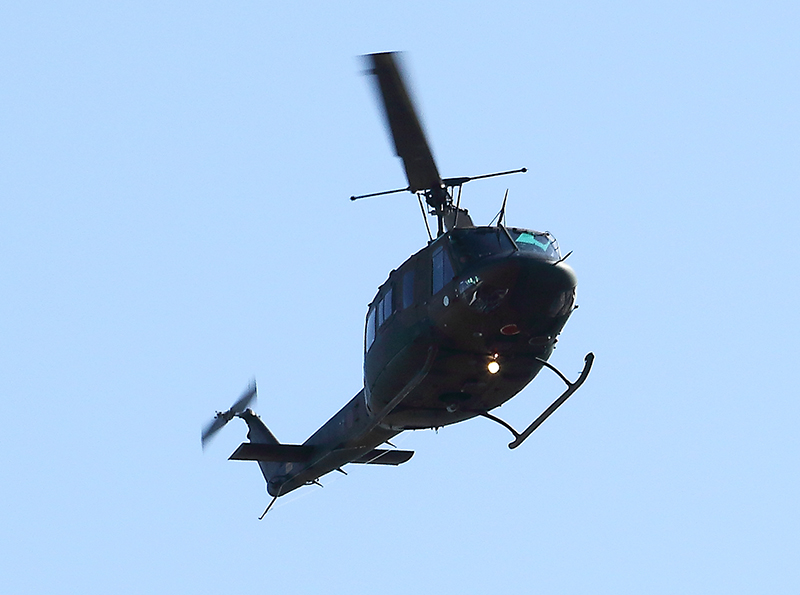
 豊川駐屯地創立65周年記念行事(2015年11月21日)その1
豊川駐屯地創立65周年記念行事(2015年11月21日)その1 






















































