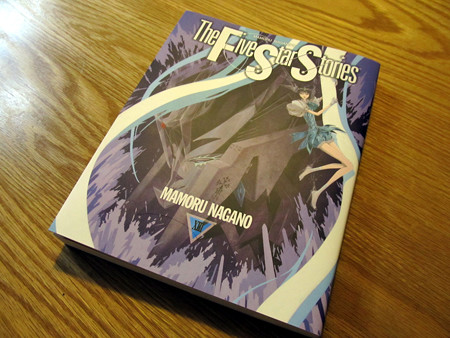IMG_6783
IMG_6783 posted by
(C)shibi-shibi
明日はお休み。
再度カワセミの撮影を試みる予定です。天気が持てば。。。
兄に相談すると、暗いけど600mmあるぞと言われ是非!と借りてきました。
三脚も。。。
で、よくわかりませんが面白い写真撮れると思うから持って行けと、変わった形のレンズも借りました。
600mm。。。追いかけれるのだろうか。。。(゚ε゜;)
--------------------------------
**2017年10月6日更新**
秘密の扉にようこそ(^-^)
よくわかりませんが(^^ゞ、PVレポートを見ていると僕のパッシブネットワークのパーツレビューをご覧くださる方がやけに多かったので、少し追記の意味を込めて作ってみました。
どのような方がご覧下さっているのかわかりませんが、基礎的なことを書いてみました。
僕がわかるのは正直基礎的なことまでです(^^ゞ
そして最後にパッシブネットワークのパーツレビューをあげてからこの2年間で学んだことも少し書いてみようと思います。。。
ごくごく簡単な自作ネットワークを作製するにあたって知っておくと便利な部分を中心に書いておきます。
まず素子たちです。


こちらはコンデンサです。
正確に言うとフィルムコンデンサになります。
カーオーディオアクセサリーでキャパシターという言葉を聞いたことがあると思いますが、要はコンデンサのことで同じものです。
電気を蓄えることができますが、電気信号の特定の周波数以上を通す(=ハイパスする)特徴があります。
特定の周波数というのが接続されるスピーカーの交流抵抗(インピーダンス)と目標とするクロス値から計算式で導かれるキャパシタンス(=静電容量)になります。
パッシブネットワーク好きな方たちがあーでもないこーでもないと色々交換する素子の代表です。
接続する方向は関係ありません。
単位はF(ファラッド)で、ネットワークで使われる場合はほぼμF(マイクロファラッド)で表現されます。


そしてこちらは同じコンデンサの部類ですが電解コンデンサと言います。
アンプやデッキの機材の中によーく入っているものたちです。
電解コンデンサは一般的には極性があり、プラスとマイナスの接続する向きがあります。
ちなみに写真の右上の緑色の電解コンデンサ。


写真にBPと書かれていますが、バイポーラ(=両極性)の意味でこれは電解コンデンサでも向きがないタイプになります。ノンポーラ(=無極性)も同じ意味になります。
フィルムコンデンサと電解コンデンサは価格帯が1ケタ以上違ったりするのでMIDのハイパスなど数値の大きな場合は電解コンデンサが使われることが多いようです。
ちなみに一般的には電解コンデンサよりもフィルムコンデンサのほうが音質がいいと言われます。


次にコイルです。
これはコンデンサと逆の特徴で、ある特定の電気信号の周波数以下を通す(=ローパス)特徴があります。
ここにもスピーカーのインピーダンスと目標とするクロス値から必要とするインダクタンス(mH、ミリヘンリー)が導かれます。
コイルも接続する方向は関係ありません。


さらにこれもよく使う抵抗です。
僕の知らない使い方もあるとは思いますが、一般的にはゲインや出力を下げる素子として使われます。
TWのアッテネーターとして使うとかです。
抵抗もまた接続する方向は関係ありません。
次に具体的な使い方です。
まず一次の場合。
これはクロス値の傾き(=スロープ)を差す言葉で一次が-6dB/octで、二次が-12dB/octです。
さらに急峻な三次(-18dB/oct)、四次(-24dB/oct)もありますが、今回は触れません。
まず、一次のハイパスです。
一般的にはTWに使う回路ですが、MIDの低域周波数のハイパスも原理はまったく同じです。


これは簡単でTWまでのプラスのスピーカーケーブルの間にコンデンサを挟むだけです。
とても簡単ですが、これでもう音声信号がハイパスされます。完成です。
最終的にはリード線(コンデンサから生えている線)を絶縁したり先端を端末処理する作業はありますが、これだけです。
次に一次のローパスです。
一般的にはMIDのローパスですね。
ちなみに3wayなどのスコーカーになるとローパスもハイパスも両方必要になるのでどちらの回路も組み合わせることになります。
その分回路がかなり複雑にはなります。


こちらはコイルを直列に入れるだけです。これで一次のローパスです。
理論的には単純なのですが、ただしMIDを目標とするクロス値でローパスをするにはそう単純な話ではなくかなり難解な知識が必要にはなります。
通常スピーカーのインピーダンスというのはカタログで4Ωや6Ωと書いていてもすべての周波数で同じ数値ではありません。
実際は周波数が上がっていくにつれてインピーダンスも上昇するという現象=自己インピーダンスの上昇というものが現れます。
そのため計算式で得られたインダクタンスで設計してみても実はまったくクロスが切れていないという現象が起きてしまいます。
なので理論上のクロス値よりもかなり高いインダクタンスにしないといけなくなるのですが、設計上の目安になるものとしてもしそのMIDの周波数特性を示すグラフがあれば使えます(^。^)
そのグラフ内でクロス値となるところのインピーダンスで計算してみることです。
またそれとは別に見かけ上MIDのインピーダンスを周波数が変わっても一定として扱ってくれるインピーダンス補正回路というものもあります。
このあたりはネットでググって勉強なさってみてください。
実際にこの回路も使っていましたが、僕には詳しく説明できるほどの知識はございません<(_ _)>
次にコンデンサやコイルのつなぎ方ですが、


目標とするキャパシタンスがお店で売っている規格値では存在しない場合に2つ以上のコンデンサをつなげて作る場合があります。
その場合は写真のように並列につないであげれば単純に各コンデンサの数値の合計で計算すればよくなります。
2つ以上になった場合のほうがコンデンサ自身の持つ合成抵抗が小さくなり音質的に有利になる場合もあります。


コイルの場合はその特性上並列ではなく直列にすると同じ考え方ができます。
手持ちのコイルを2つ連結して目標値にすることはできるわけですが、音質的には劣化しやすいため実験で使うことはあっても本番ではコイル1個にします。
で、よく聞く二次の場合です。
二次になると回路は少し複雑になります。
先に二次のハイパスです。


この場合は、コンデンサの位置は一次と同じですが、コンデンサとスピーカーまでの間に並列にコイルが入る回路になります。
次に二次のローパスです。
こちらは一次同様にハイパスの反対です。


コイルが直列に入り、コンデンサが並列にコイルとスピーカーまでの間に入る回路となります。
このTWとMID両方のクロスを含む回路が2wayのセパレートスピーカーを購入したときに付属しているパッシブネットワークです。
たぶん、、、メーカー製だとあまりないと思いますが、一次だとすると、、、


こんな感じになり、一般的にはこっちが多いと思いますが二次なら、、、


といった感じになります。

これらのパッシブネットワークの設計に使う計算式ですが、手持ちにあるテクニカルデータの写真ですが、

この計算式で求めます。
例えばインピーダンスが6Ωのスピーカーでクロスの見方は、
コンデンサーの数値 = 159,000 / スピーカーのインピーダンス(今回は6)・クロスオーバー値
クロス値, 必要なコンデンサの静電容量
200Hz, 132.5μF
250, 106.0
315, 84.127
400, 66.25
500, 53.00
630, 42.06
800, 33.13
となります。


ちなみにですが、二次の場合は計算式も変わりますので、



このようになります。


で、数値=キャパシタンスが決まったらお店で近似値のコンデンサを購入します。
その際に
「左右できるだけ差の小さいものを使いたいので3~4個購入」しまして、


このようなLCメーターで実測値を計測してペアを作ります。
それらを使ってパッシブネットワークを作製すればOKとなります。
この2年間ずっとパッシブを勉強し続けてきたわけではありませんが、コレは!と思ったことを少し。。。
まず、LCメーターはパッシブネットワークをかじろうとされる方は必須だと思います。
僕は秋月電子で\2,450というやっすいメーターを購入しました。これでも十分役に立ちます。
通常、コンデンサやコイルの値は各素子に印字されておりプラスマイナス○%と記載されています。
この公差を、、、もっと言えばそもそもこの数値をあなたは信じますか??
過信は禁物ということです。
実際に思った以上にこの数値はあてになりません。。。(T.T)
記載された公差すら外れているものにたまに、、、出会います(>_<)
少し数値がずれるだけでクロス値は左右で大きく変わる危険性がありますので、お金がもったいないですが上記のように3~4個購入された上でマッチングすることはとても大切なことだと思います。
また素子たちも上を見ればキリがありませんが、天井を見ないと楽しめないというものでも全然ないと思います。
やっすい素子でも優秀なものはありますし、音質も十分満足できるものはあります。
2017年10月現在オーリスに使っているパッシブネットワークの素子は1つ1000円行かないものばかりです。
この素子たちの音色や音質に対する不満は僕にはまったくありません。
僕よりも断然耳のよい奥さんも不満はありません。。。
また、素子を同じ数値のもので変更して音色の変化を楽しむときに実は
「単に音色が変わっている以外のある変化」もあることを注意しないといけません。
それも合わさっての変化なのでおやっ?とびっくりする変化がたまにあったりするわけです。
そして、パーツレビューではエモーションさんの手ほどきに準じて記載しましたが、現在の設計の仕方はかなり変わりました。
設計時は助手席のみで行っておりません。
必ず左右ともに音出ししています。
オーリスのフロントのTWはAピラーにないことも関係していますが、TWとMIDの音場がエアコン口付近で合成されるかどうかではなくクロスを決めたMIDに対してTWを1000Hz程度動かしていきながら高域がうるさくなくてできるだけ低い数値を選択するようにしています。
その際はTWの最低共振周波数(=F0)には注意します。
どんなスロープであってもクロス値はF0の2倍以上は死守します。
そして
「位相管理」です。
ことカーオーディオに関してはホームオーディオのような教科書的な考え方は不要だと思います。
二次であってもTW正相、、、多いにアリだと思います!
オーリスもそうです。
一次だってTWが逆相、、、あるかもしれません!
絶対はないです。
どちらも試した上でMIDと合成された出音がどのように聞こえているか?どちらが聴きやすいか?で決めていいと思います。
取り付けの位置関係、TWとMIDの距離なんかはホームとはかけ離れた不確定要素です。
教科書的ではなく理論上でもなく実際にご自分のお車に取り付けたときの聞こえ方=現車合わせが正解なはずです。
逆にMIDは正相であるべきだと思います。
正相と逆相の聞こえ方。
正相ははっきり明瞭に、逆相はちょっとぼやけ気味に曖昧になります。
基音が豊富に含まれるMIDは曖昧に聞こえてしまっては困ります。
TWにはそのどちらが合うかは後部座席の中央で少し前に乗りだし気味の姿勢で聴いてご判断ください。
音量の大きいTWのアッテネート。
抵抗を入れるアッテネート回路が一般的ですが、TWのクロス値を上げていくことで音量が小さく聞こえる原理を使うのも手です。
抵抗を直列に入れることで大事な音楽成分が失われてしまう場合もあります。
そんなときに良きアプローチでした。
最後に
「スロープ」。
なんてことはないクロスの肩特性の傾き、、、ではありません。
なんとなく一次にしてみた、、、なんとなく二次にしてみた、、、なんてものでは全くありません。
このスロープをどちらにするかはこのスピーカーシステム、さらに言えばカーオーディオのシステム全体をどう音作りするかにまで波及します。
エネルギーに満ちて歌い手の感情がストレートに感じられるスロープにするか、、、音として奥行きや雰囲気、空間表現に長けたオーディオとしての醍醐味に満ちた音にするか、、、岐路に立つ選択をするというレベルです。
こんなことを学んだ2年間でした。。。<(_ _)>
--------------------------------
**2020年7月31日更新**
前回このエントリーに秘密の部屋を作ってから早3年が経過しました。
PVレポートを見ても、整備手帳のパッシブネットワークには訪問されても、こちらまで足を運ばれる方は、滅多にいないようです。
先日、久しぶりにご訪問があったようです。
ありがとうございました。
なので、こんなサイトにわざわざ足を運ばれた方、特にパッシブネットワークを勉強されたくてこのエントリーを見つけられた方に有益なもの?をとさらに追記することにしました。
とは言いながら、実は2018年以降パッシブネットワークの自作はしておりません(汗)
自作することを辞めました。
いきなり、これで終わってしまっては元も子もありませんのでw、辞めた理由をつらつらと。
一番の理由は、パッシブを素人なりに数年勉強して組み上げても、結局プロであるエンジニアが作られたスピーカーに付属する純正パッシブの設計の足元にも及ばないことを自覚したためです。
純正のパッシブは、ケースを空けて中を覗いてみると、確かに黒や灰色、茶色のやっすそうなフィルムに巻かれたフィルムコンデンサ、、、ではなく、電解コンデンサ。
コイルも空芯コイルではなく、音質は悪いと一般的に言われる鉄芯入りのコアコイル。
アッテネーターに使われる抵抗は、白い長方形のセメント抵抗。
ショボショボです・・・。
ですが、これはパッシブに持たせている役割がエンジニアとDIYするエンドユーザーでは異なるためだと思っています。
エンジニアの考え方は、パッシブはスピーカーのキャラやポテンシャルの「邪魔をせず」、「音を極力変えないで本来の仕事である帯域をカットする」ことを目的に黒子となるように設計しています。
なので、色付けをなるべくしない素子を使う。
歩留まりが悪くなっては困るので、コストも安く、安定供給され、品質も一定な素子を選択しています。
プロとして腕を発揮するのは、高い素子を選ぶことではなく、良質な設計で良い製品を作ることだと思うんです。
パッシブに限りませんが、カーオーディオを6年間DIYしてきて思うのは、機材やケーブルの高い安いではありません。
どう取り付けるか、どう調整するかだと思います。
もちろん、全然使えない機材、癖があり過ぎる機材ではダメですけど・・・。
料理人と一緒だと思います。
料理人が使うのとまったく同じ食材や調味料を渡されても、素人が料理人と同じような美味しいメニューは作れません。
そして、DIYユーザーがパッシブでやっているのは、スピーカーというよりもパッシブの素子のキャラを使って、積極的に「音を変化させる」遊び方になるという点です。
カーオーディオは、趣味ですから、もちろんその遊び方も正解です。
ですが、「音を良くする」ことと「音を変化させる」ことは必ずしもイコールではありません。
パッシブの素子は値段が高いものの方が、音に癖を持つものが増える傾向にあります。
その魅力に惹かれて、とっかえひっかえすることになるのですが、素子1つの音ではなく、パッシブに使うすべての素子の合計で音が作られますので、組み合わせも影響しますので、どれだけ試してもゴールが見えなくなり、パッシブネットワーク沼に入ってしまいます。
この沼の中で、キラッと光る原石を探す旅に出るのもよいですが、僕はそこにはまらず、機材、システム全体を料理ととらえ、バランスよく美味しい料理になるよう努力しています。
このエントリーで以前書いたことを少し補足しますが、コンデンサを同じ定数のまま違う銘柄に交換したとき。
音色が変わりますね。
それは、単純にコンデンサが持つ音色の特徴だけの変化では、ありません。
「位相」も動いています。
どの程度動くかは、銘柄にも寄るようなので詳しくは僕もわかりません。
位相が動くということは、セパレート2wayで作っていればTWとMIDの位相ずれが出てきます。
コンデンサを変えたら、音がクリアではっきりした、それは位相が正相に寄っていることも関係していると思います。
音がぼやけた、それは逆相に寄っていることもあり得ます。
こんなことを計算に入れて作るのは、相当難易度が高い話だと思います。
僕には、到底できません。
そして、僕も実際に経験したから、自作パッシブの道に片足突っ込んだ幻想。
車に社外スピーカーを取り付けたら、音が悪い。
ショボい純正パッシブが原因に違いない。
今のスピーカーの取り付けに合うようにオーダーメイドにパッシブを自作した方が絶対音がいいに決まっている、という幻想。
セミプロレベルで、パッシブが自作できる方は、それは正解だと思います。
ですがエントリーユーザー、パッシブを少しかじった程度では、残念ながら不正解です。
どのスピーカーもすべてそうとは限りませんが、スピーカー設計時、エンジニアはある程度予想される取り付け位置を考慮してパッシブを設計しています。
どいうことか?
ネットなり、雑誌を参考にスピーカーを取り付けて、純正パッシブを使って音が変だったとき。
それは、純正パッシブが悪いのではなく、取り付けに問題があることが多いです。
これは、実際に作業している時点は、なかなか気づけません。
よかれと思ってやってますから。
セパレート2wayの場合、TWはMID近くのほうが音はまとまります。
ですが、ネットや雑誌の情報から取り付けたドアでこれをやると、音場はダッシュの上まで上がってきてくれません。
なぜか?
ドアのMIDがちゃんと仕事をしていないためです。
音が飛んでないからです。
ドアMIDの音をしっかり飛ばして、TWを合成させないといけません。
でもTWは、MIDの近くにいれば、寄り添う準備は出来ています。
MIDが鳴りさえすれば、音が音楽になります。
そんな取り付けと調整に明け暮れたため、パッシブは純正となりました。
そして現在、自車はセパレート2wayではなくコアキシャルです。
前後とも。
SWは鳴らしていますけど。
コアキシャルは、値段こそセパレート2wayの前座みたいな立ち位置ですが、突き詰めた音は前座ではなくラスボスになれます(笑)
コアキシャルのスピーカーフレームについているのは、ちっさな黒い電解コンデンサ1つだけです。
1つの例。
https://www.youtube.com/watch?v=EkwC1lB91GE
これは、youtubeにアップされたONE OK ROCKのTAKAが、AdeleのHelloをカバーしたものです。
それを音声だけにしたmp3音源をUSBメモリに入れ、デッキから再生しました。
撮影機材は、スマホ。
標準カメラアプリの動画撮影モードです。
音源は、圧縮音源なのでショボショボです。16kHz以上はカットされています。
ですが、鳴っている音は音楽になっていると思います。