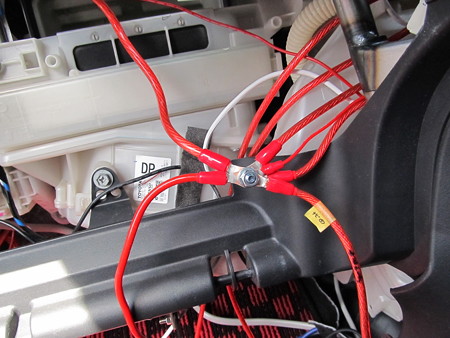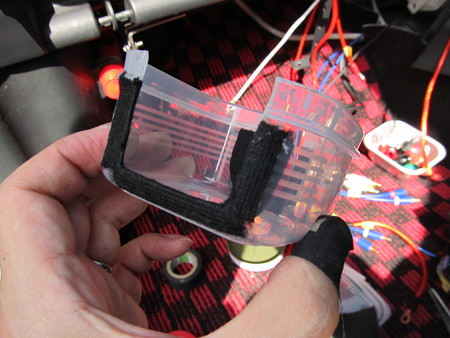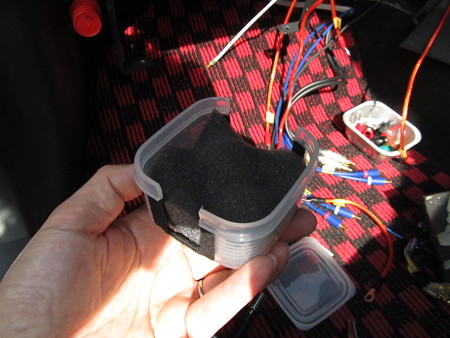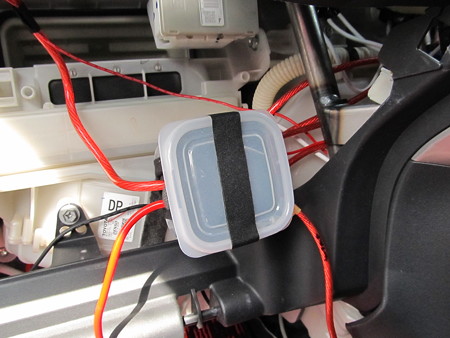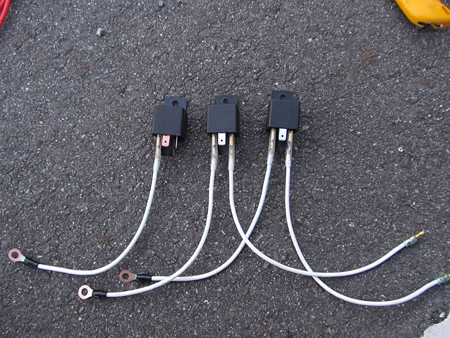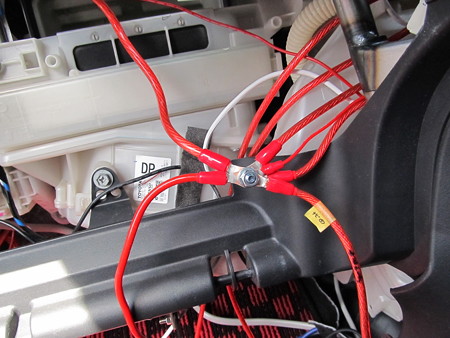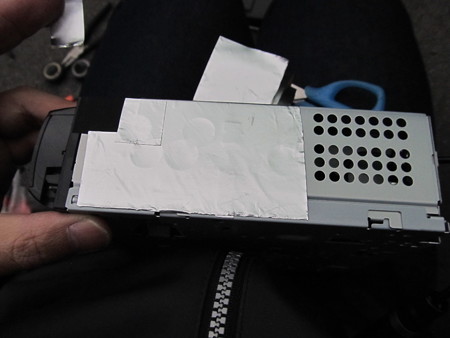前回のブログの流れで作業が始まりました。
今回はたまたま上の子がこの時期インフルエンザに罹ってしまい、家族でどこにも外出できない週末となったので余計に時間をもらえたお陰で2月25日、26日で合計14時間にわたる作業になりました。
ただ、作業内容的にはアンプの電源見直しに合わせてデッキの電源も見直しております。
 IMG_1630
IMG_1630 posted by
(C)shibi-shibi
2月25日は快晴で風も弱くとても作業日よりでした。
 IMG_1611
IMG_1611 posted by
(C)shibi-shibi
シャークワイヤーの4Gです。僕はこのケーブルの太さを処理できる工具を一切持ち合わせておりません。
事前にみん友さんに泣き付いておりまして、、、
 IMG_1647
IMG_1647 posted by
(C)shibi-shibi
とくとくさんから2つの素晴らしい工具をお借りしました。
これがあったからこそのオーリスの今の出音が可能になりました。
御礼申し上げます<(_ _)>
 IMG_1637
IMG_1637 posted by
(C)shibi-shibi
まず大きな作業としては10Gのパワーケーブルから4Gのパワーケーブルに変更しますのでファイヤーウォールに4Gを導通させないと行けません。。。
こんな太いケーブル、shibi-shibiは通したことがありません。。。
なので、今あるものは最大限利用です。。。
 IMG_1640
IMG_1640 posted by
(C)shibi-shibi
10Gの先端と4Gの先端を合わせてテープでぐるっと巻きました。
ここがブツッと切れたら作業効率がガタ落ちになるのでブレーキクリーナーで脱脂してからテープを巻いております。。。
 IMG_1643
IMG_1643 posted by
(C)shibi-shibi
逆にテープを巻いたところ以外はツルツルッと滑ってもらわないといけませんので、シリコンスプレーを雑巾に吹いてからケーブルを拭きます。
 IMG_1644
IMG_1644 posted by
(C)shibi-shibi
案外するっと簡単に導通できて拍子抜けしました。。。(笑)
今回のアンプの電源見直しはデッキにも波及しているわけですが、大きな変更点として電源の集約化があります。
今までデッキの970にはバッテリーから単独で10Gのプラス線をバッ直しており(途中で12Gに分岐しています)、アンプもまたデッキとは別に単独で10Gのプラス線をバッテリーから引き入れておりました。
マイナス線はともに機材から車体になるべく最短でボディーアースしています。
これを変更してプラス線は4Gでアンプのある助手席下まで1本のみ導線。
ここに分岐点を作りまして、そこからアンプのプラス端子へ。
さらにデッキにもこの分岐点からプラス線を延ばすようにしました。
 IMG_1652
IMG_1652 posted by
(C)shibi-shibi
なので、ヒューズボックスがこの1個だけになりました。丸型端子は22-S5です。
丸型端子は先端部のスズメッキを剥がしています。
50Aで事足りると思うのですが、ちょうどよいヒューズがなかったので60Aです。
ヒューズボックスはマインズカンパニーさんのULTIMATE MIDI FUSE SYSTEM 8G用を改造です。
 IMG_1651
IMG_1651 posted by
(C)shibi-shibi
改造と言ってもやったのはこのカバー部分が4Gのパワーケーブルだと当たってしまうのでちょうどよいサイズになるようにカッターで拡大しただけです。
 IMG_1655
IMG_1655 posted by
(C)shibi-shibi
サランラップで簡易防水。
 IMG_1657
IMG_1657 posted by
(C)shibi-shibi
tesaテープで巻いて補強して完成です。
 IMG_1659
IMG_1659 posted by
(C)shibi-shibi
バッテリーターミナルにもPVC製のターミナルカバーも使って取り付け。
 IMG_1661
IMG_1661 posted by
(C)shibi-shibi
ファイヤーウォール貫通部分手前は少しケーブルを垂らして取り付け。
ケーブルに雨水などが付いた場合にケーブルをつたって車内に少しでも入らないように貫通部分よりケーブルを下にたわまして逃げを作りました。
次に車内です。
 IMG_1665
IMG_1665 posted by
(C)shibi-shibi
この段階ではどの程度の長さで切るか決めてなかったので5mをそのまんま使っていたので取り回しの面倒なことといったら。。。(苦笑)
 IMG_1667
IMG_1667 posted by
(C)shibi-shibi
車内側にもケーブルにはたわみを作っています。安全対策です。
 IMG_1671
IMG_1671 posted by
(C)shibi-shibi
こそっとフロアマット下に隠しました。
 IMG_1678
IMG_1678 posted by
(C)shibi-shibi
そして、見た目キレイ推奨派なshibi-shibiはこのようなワイヤリングで助手席下まで4Gを一旦は引きました。
実際の作業の流れだと一旦はこれで音出しまでこぎ着けたわけなのですが、今度は電源に詳しい知り合いの方から打診。
「shibi-shibiさん、それアカンわ。」
何がアカンのかわからないshibi-shibiに簡潔明瞭なお言葉、、、
「ノイズ乗るからそこダメですわ。」
でした。。。(T.T)
純正の配線の束には近寄っちゃいかんということを初めて学びました。。。
回避術を学んだので即実行。
 IMG_1856
IMG_1856 posted by
(C)shibi-shibi
フロアカーペットをめくるのは正直初めてです。。。
RCAとパワーケーブルの直交ワイヤリングです。
まずRCAケーブルをこのようにしてみました。
 IMG_1858
IMG_1858 posted by
(C)shibi-shibi
なぜだかこんなところにトンネルがあったのでその付近に変な配線の束がないことを確認した上で貫通。
 IMG_1862
IMG_1862 posted by
(C)shibi-shibi
今度はパワーケーブル。ぐるっとS字のような引き回しをしてアンプの電源部に向けました。
ちょうどケーブル下には分厚いクッションがあってくれるのでケーブルを足で踏む形になりますが応力は分散してくれそうです(^。^)
 IMG_1864
IMG_1864 posted by
(C)shibi-shibi
カーペットを戻せばあらキレイ(^o^)
次にプラス線の分岐点作りです。
ここは本来ならディストリビューションブロックを使って分岐するのが王道だと思うんですが、お金ないですから。。。
でも安全には配慮したい。。。
ということでいつもの100均です(苦笑)
 IMG_1722
IMG_1722 posted by
(C)shibi-shibi
食品タッパーを使いました。
 IMG_1733
IMG_1733 posted by
(C)shibi-shibi
こんな風にカッターで加工。
 IMG_1736
IMG_1736 posted by
(C)shibi-shibi
分岐部はなんちゃって銅音式ですw
バッテリーからの4G、アンプへの4G、デッキへの10Gの連結になるので本物の銅音ジョイントでは端子の厚さがかなりあるのでボルト長が足りません。。。
なのでホームセンターで売っている鉄製ボルト・ナット・ワッシャー・バネ座金を使って固定。
いずれ黄銅製のボルト一式に変更できるといいですが。。。
で、この連結をビニールテープでこれでもかとぐるぐる巻きです。
この写真ではRCAケーブルが右横から出ていますが、その後の前述の取り回しの変更で現在はここから引き回していません。
 IMG_1738
IMG_1738 posted by
(C)shibi-shibi
これを先ほどのタッパーに入れます。ちょうどウレタン吸音スポンジがあったのでそれも使ってみました。
 IMG_1740
IMG_1740 posted by
(C)shibi-shibi
これで分岐点は完成です。
この段階ではまだ分岐点からアンプまでは10Gですね。
 IMG_1636
IMG_1636 posted by
(C)shibi-shibi
アンプ側への接続端子ですが、GENESISの端子台はかなり幅が狭いです。
4Gを飲み込める丸型端子は到底取り付けれないのですが、マジックアイテムなんですかね?シャークワイヤーから4Gでもほっそりした端子が発売されておりまして、それならこんな具合にまったく大丈夫でした。
分岐点からアンプへの接続はケーブルの太さで音の変化を味わいたかったので当初はここだけ10Gのままにして2日間音出し確認後に4Gに変更しました。
4Gケーブルは、
 IMG_1810
IMG_1810 posted by
(C)shibi-shibi
こうして、
 IMG_1812
IMG_1812 posted by
(C)shibi-shibi
こうして、
 IMG_1815
IMG_1815 posted by
(C)shibi-shibi
こうなって、
 IMG_1825
IMG_1825 posted by
(C)shibi-shibi
こんな感じで作製しました。丸型端子はR22-6です。
写真が膨大になってしまったのでこれまた続きます。。。
Posted at 2017/03/08 16:48:51 | |
トラックバック(0) |
オーリス | 日記