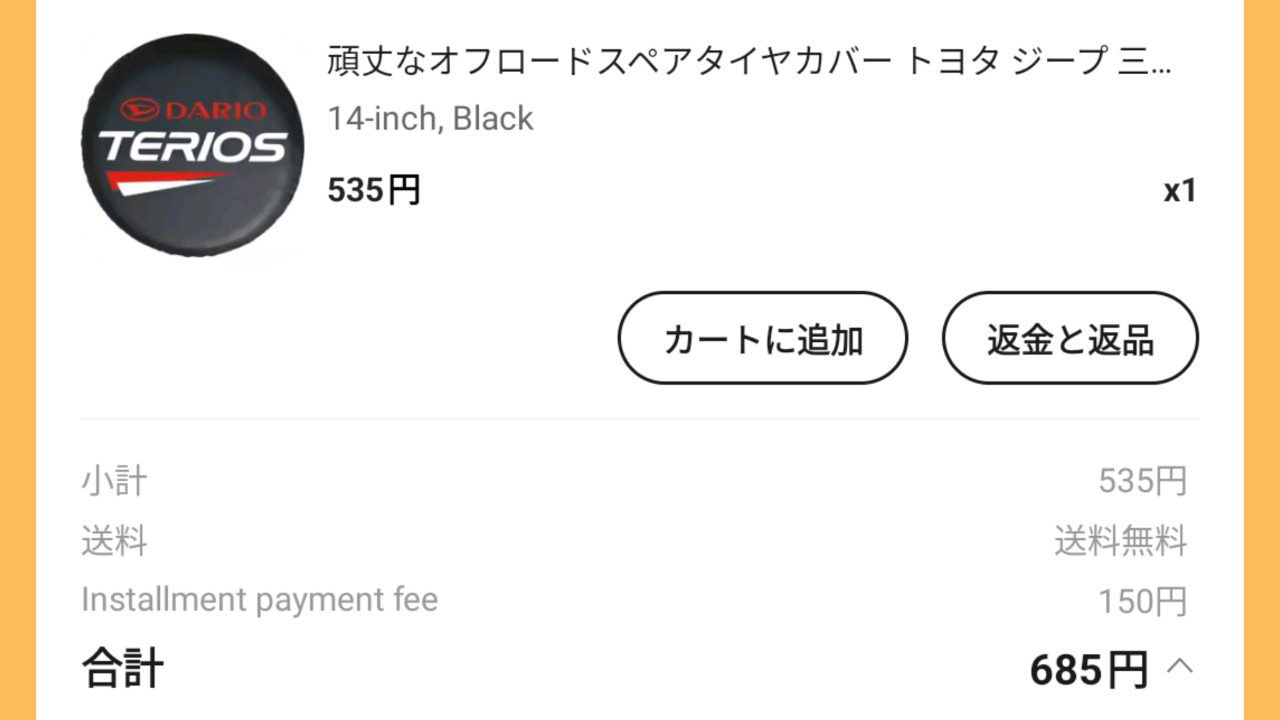時はまさに世紀末。
西暦2000年前後、時代の騒燥に紛れ、ハチマル車はまだ“ヒーロー”などではなく、誰にも惜しまれることもなく、静かに役目を終えていく存在だった。
ならば滅びゆく者のために、せめて記録だけでも残そうと思った。
レンズの先にあったのは、抗う術もなく消えていく存在への、せめてもの葬送だ。
四半世紀を経たいま、手元に残るスナップは、すでに路上から抹消された彼らの、最後の残光である。
だから最初に残しておきたいのは、この街角のシャレードだ。
時間の向こうへ消えていった無数の光のなかで、いちばん最初に私の記憶を照らした一台なのだから。
【初代シャレード】
この頃、初代シャレードはすでに絶滅していた。
昭和50年代の小型車の耐用年数はせいぜい五、六年。バブル期の熱狂のなかで、その多くが潰し尽くされた。
平成11年のモーターショーでメーカーがレストア車を展示しようとした際、前期の現存車は100台にも満たなかったという。(その個体が現在ヒューモビリティワールドに展示されている前期型である)
■後期型XGC 5MT
そんな状況のなか、地元の中古車情報誌に掲載され、見に行ったのがこの個体だった。

昭和55年のマイナーチェンジで追加されたハイグレード“XGC”。
電動リモコンミラー、フルモケットシートを備える上級仕様。
翌56年の改良でメッキのハーフホイールキャップが与えられるが、この車両はそれ以前のモデル。
リアワイパーはXGCとXTEのみ標準装備。
“5SPEED”エンブレムが示す通り、5MT車だった。

某買取店の買取車で、走行約5万キロのワンオーナー。
状態からして車庫保管。価格は確か40万円前後。
当時学生だった自分には手が届かなかったが、希少性と状態を思えば安かったと思う。
数か月後には店頭から消えた。売れたのか、業者オークションに流れたのか。その後イベント等で見かけることはなく、値が付かず解体されていなければいいのだが。
余談ながら、同時期に販売されていた中期型の個体。
旧車雑誌で広告を出していた埼玉の朝日自動車の車両だ。

免許取得時、本気で購入を検討し、資料も取り寄せた。
走行約6万キロ、確かに綺麗な一台だった。
ただ、なぜかダイハツ・ミラ L70用のステアリングを装着していた。
――見覚えがある。
それは、ダイハツが所蔵する中期型そのものだ。

数年売れ残ったのち、前期型が使えない事情があったのか、あるいは別の理由かは定かではないが、ヒューモビリティワールド開設時にレストアされたようだ。
現在は前期型が常設展示されているが、時折ピンチヒッターのように姿を現す。奇な縁を辿り、結果として生き残った、幸運な一台である。
■前期型クーペXTE
もう一台、忘れてはいけない個体がある。石川県の日本自動車博物館に収蔵されていた車両だ。

現在展示されているシルバーの個体(『ノスタルジックヒーロー』60号掲載車)の前には、この黄色の別個体が展示されていた。
2005年頃には入れ替わっていたと記憶している。
あの黄色いマリンウィンドを覚えている人はいるだろうか。
いまもバックヤードのどこかに残っているのだろうか。
そしてもうひとつ。
2010年前後、ダイハツ京都工場の構内で、後期型の姿を目にしたことがある。
あれは保存車だったのか、それとも別の理由があったのか。
いまもどこかで残っているのかは分からない。
【2代目シャレード】
二代目もまた、初代と同じ道を辿った。
私が意識した頃には、すでに街から姿を消しつつあった。
平成8年頃を境に、急激に見なくなったと記憶している。
経済車として親しまれたディーゼルも、ガスケット抜けという持病を抱え、長命とは言い難かった。
■前期型CXドルフィントップ
まるでカタログから抜け出してきたような、当時でもほとんど見かけない仕様の個体で、視界に入った瞬間に思わず息を呑んだ。

場所は兵庫県春日。
現在も開催されている中兵庫クラッシックカーミーティングの会場横駐車場だった。

ただし、いわゆるマニア筋の参加車両ではない。
同時開催されていた地域おこしの祭り目当てで来られていた、地元の“天然”オーナーだったのだと思う。

会場へ入ってくる姿を見つけた瞬間、反射的に駐車場までダッシュしたのを覚えている。
いま思えば、あれは完全に不審者の動きだった。
■後期 デトマソ ターボ ビアンカ
標準車ですら希少な二代目シャレードにあって、さらにその上をいく600台限定の特別仕様車。まさに“レアの中のレア”だった。

街で何度か目撃していた個体だけに、ある日突然、廃車置き場に置かれている姿を見たときはさすがに堪えた。

けれども後年、この個体のホイールやシートが九州のシャレードディーゼル乗りの方のもとへ渡っていたと知る。
一台としては消えても、部品は生き延びる。
世の中は広いようで狭い。――とくにシャレード界隈は。
■後期ガソリンCXターボ
本来は黒バンパーの、いわば“羊の皮を被った狼”的モデルだが、この個体は違った。


前後バンパーとマフラー、ホイールはデトマソターボ用に換装。佇まいは、まるで“5ドアのデトマソ”。

ちなみに、みんカラ内にこの個体と思われるオーナー様の登録があった記憶がある。
ひょっとしたら現在も現役かもしれない。もしそうなら、時をくぐり抜け、なお息づく奇跡のようだ。
【3代目シャレード】
三代目に至っては、少し事情が違う。
前期型はさすがに姿を消しつつあったが、後期型ならまだ車齢十年に満たない個体も多く、街で普通に見かける存在だった。
だからこそ、いつでも撮れる。まだ大丈夫だと、どこかで思っていたかった。好きだからこそ、滅びゆく者としてレンズを向けることを、どこかで拒んでいたのだろう。
だが時間は、等しく進む。三代目は、そんな後悔と共に残っている。
■前期型GT-tiスポーツパック
三代目のコンセプト、ツーサムを象徴するともいえるGT-ti。
平成9年頃から、国道沿いの解体ヤードに、ずっと積まれていた。

新車販売台数はGT-ti単独で約5000台程度。
当時ですら滅多に見かけず、中古車が市場に出るのも年に一度あるかないかという世界だった。
よく見ると、隣にもG100シャレードが積まれている。流石は竜王――ダイハツ工業のお膝元にあったヤードだけのことはある。
さらに視線を落とせば、GT-tiの下敷きになっているのは150系のトヨタ カリーナ後期型、しかも1600ST-EFIというレアグレード。
まさに宝の山――いや、宝の墓標か。撮影から数年後、自動車リサイクル法施行時にヤードは整理され、すべて姿を消した。
■中期型 ディーゼルターボ CX
改良を受け、二代目とは別物と言っていいほど洗練されたディーゼルターボ。性能も信頼性も確実に進化していた。
だが時代はすでに豊かになっていた。
経済性よりも静粛性や滑らかさが求められ、ディーゼル特有の音や振動は敬遠されがちだった。販売は伸び悩み、その流れのまま四代目でディーゼルは切り捨てられることになる。

下級グレードならまだしも、上級グレードのCXターボは当時でも珍しい存在だった。
グリルに掲げられた赤文字の“TURBO”エンブレム。
自身の原点ともいえるTRターボと共通の意匠が格好よく見えた。
確か3AT車だったと記憶しているが、この撮影の直後、オーナーは初代 ノアへと代替。時代は、ミニバンへと舵を切っていた。
■中期型1000ウィル
当時、最もよく見かけた三代目がこの中期型ウィルだった。
元々は限定車として登場しながら好評を受け、そのままカタログモデルへ昇格した、エアコン標準装備の“お買い得仕様”。

このガンメタリックも、当時はどこか冴えない色に思えて、正直あまり好きではなかった。
けれど今見ると、その無機質な色味とシンプルさは、どこか80年代のフランス車のような空気をまとっていて、むしろ味わい深い。
そして皮肉なことに、いちばん見かけたのに、いちばん見なくなったのも、このウィルだった。
■中期型 1000CX
1300が登場した後の1000cc上級グレードは、当時でもすでに珍しい存在。価格差がほとんどなかったこともあり、多くの人は1300のお買い得仕様「KISSA」を選んでいた。

国道沿いのダイハツ販売店に、しばらくのあいだ置かれていた個体。
走行3万キロ程度の5MT車という、条件だけ見れば理想的な一台だった。
当時としても程度は極上。内外装ともに、時間が止まったような保存状態だった。
だが問題は置き場だった。
決断できずにしばらく悩み、いよいよ譲渡を申し出ようと思った頃には、もう姿はなかった。
聞けば、解体されたらしい。いまでも惜しいと思う。
思えば、G100シャレードには当時からあまり縁がなかった。
後年、複数台所有したときでさえ、結局ナンバーを付けるには至らなかった。
あれは単なる偶然だったのか。それとも、何かのジンクスだったのか。
■後期 GT-XX
現在でも営業されている山中のショップで見かけた一台。
いても立ってもいられず、声を掛けて見せていただいた。


GT-tiはデビュー1年後のマイナーチェンジでGT-XXに仕様変更を受けるが、XXは約5年で3000台程度しか販売されていない。なので直接触れるのは、その時が初めてだった。

一見ノーマル然としているが、中身は化け物。
タービンはTD-06に換装、触媒レス仕様。とんでもないチューニングカーだった。

3万円でいい、という話まで進んだ。
だが当時は下宿を引き払い、実家へ戻らなければならない状況。置き場がなく、泣く泣く断念した。
その半年後、もう一度あの店を訪ねた。だが、GT-XXはもうなかった。
売れたのか、解体されたのか、それともどこかでいまも走っているのか。
どうなったのだろう。
けれど、もしあの時、どこかでボタンをひとつ掛け違えていたら――
あのCXを手にしていたら。
あのGT-XXを連れ帰っていたら。
私のシャレードとの距離は、いまとは少し違っていたのだろうか。
記録とは、残せた者の物語であると同時に、手を伸ばさなかった者の記憶でもある。