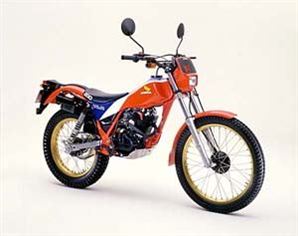このエントリーは
FLAT6さんの投稿に触発されてのMT考 2です。
前回、私のMT嗜好は、
左足を基軸とした四肢と知覚による対話=運転
ということがそもそも刷り込まれている、
ことによるというながーい自分語りをアップしました。
それを踏まえて今回は生理学的に
ATにおける、
右足のみのペダル操作+上肢でのステアリング操作
MTにおける、
左右下肢でのペダル操作+上肢でのステアリング操作+右or左上肢でのシフト操作
両者において脳の活動に差異を生じるのかを考えてみます。
○MT脳とAT脳

まず物凄くざっくりと脳の解剖と神経の道筋を言うと、
脳は左右の半球に分かれており、太い回線の束で連結しています。この回線によって常に左右の連絡を行なって活動しているのです。

横から見ると大脳は前から前頭葉、頭頂葉、後頭葉に分かれています。前頭葉は情感や理性といった分野を中心とした機能を司り、側頭葉は聴覚情報系、後頭葉は視覚情報に関する部位です。
今回は話を絞るため、前頭葉の運動野と頭頂葉の体性感覚野を中心に話を進めていきます。
体性感覚野は温冷触圧覚や関節の角度、運動の方向を知覚し、情報を受け取る場所です。右半身の感覚は左脳の感覚野へ、左半身は右脳の感覚野へ伝達されます。
運動野は身体の運動を制御している場所ですね。しかし運動野そのものは純粋に運動のみを司っている場所で、いわばエンジン単体のようなものです。隣接する運動前野が視覚情報を基にした運動の制御を、補足運動野が「こう動こう」という情動と実際の運動の連結を担当しています。
さて、ATの車を運転する場合、左足はお留守になります。ということは左の大脳ばかりが活性化し、右の大脳はお留守になるのでしょうか?
答えはそうでもあり、そうではありません。

確かに右足の感覚情報の受容や運動の発動は左の大脳を中心とした活動です。
しかし、実験によって頭頂葉の左右同じ特定の部位を刺激した際、右半球では左の上下肢の運動を賦活し、左半球では唇の動きなど言語系の賦活がみられたという報告があります。

これは言語野という言葉の理解から発語のコントロールをしている部分がほとんどの人で左半球にあることに起因します。
また、運動前野や補足運動野の脳梗塞は対側麻痺を起こしたり同側麻痺を起こしたりと様々で、このことから運動前野や補足運動野は運動野を介さず左右とも両側の運動と関わっていると言われています。右半球の障害は左麻痺、左半球は右麻痺と一概には言えないのです。
しちめんどくさい詳述は避けますが、要するに右半身と左半身の運動では、脳の活動はそもそも対称性に活性化することはなく、大きく異なっているということです。
このため、上肢でステアリング操作をし、右下肢で加減速を行うATと、両下肢プラス片側上肢にシフト操作を担わせるMTでは、車の運転という運動課題で賦活され、可塑性によりシナプス結合が強化されている領域がそもそも違います。さらに言えば、RHD/LHDのMTでも異なる訳です。
脳の活動はイメージによっても喚起されます。ざっくり言うと、右手が動いてる映像を見たり、右手を動かすことを自分で思い描いたりすると、実際に右手を動かす時に活動する脳の部位が賦活されて活動するのです。
恐らく運転席から撮ったドライビングの映像を見た時に活性化する脳の部位はMT乗りとAT乗りの人間では大きく異なっているでしょう。
「さあ、運転するぞ」と車に乗り込んだ時、暖機運転のように活性化する私の脳の部位はMTに乗る時に使用する部位の筈です。ところがその車がATだった場合、実際には活性化した部位と違う場所を使って運転することになります。これは違和感やわずかな齟齬を生む要因となるかもしれません。
また、とある研究では、寝た状態で左右のつま先で爪先立ちするように下に板を押す運動を反復したところ、右半球では運動野、運動前野が賦活し、左半球では感覚野が賦活したという報告があります。
同時に行った運動なので一概には言えませんが、利き足である右足は機能脚であり、より繊細な運動を行うために感覚情報を処理する必要から感覚野優位の活動となり、支持脚である左足は支えるという筋活動のために運動野系が優位に活動したと思われます。
このことから、右足でのアクセル、ブレーキペダル操作は運動野よりも感覚野による情報処理作業を主体とするインプット系の活動で、左足のクラシック操作は運動というアウトプット系の操作と言えそうです。かなーり乱暴な飛躍で、言うのは少し勇気がいりますが、運転という動作においては、右足は常に受け身な運動を強いられており、左足は主体的、能動的な運動を行なっている......かも?
もう少しお付き合いください。
脳には「半球間抑制」という働きがあります。
片方の半球が活動すると、反対の半球の活動が抑制されるという働きです。この機能の存在自体は随分前から知られていたのですが、最近はそのメカニズムの解明が進んでいます。とはいえ必要なのは要点だけです。
ラットを使った実験では
左足を刺激→ 右感覚野が活動(100%)
右足を刺激→ 次に左足を刺激 → 右感覚野が活動(25%減)
という結果が得られました。
左右を頻繁に使用しているシチュエーションでは気にすることではないですが、右足ばかりのペダル操作では右半球に絶えず抑制がかかっていると言えるかもしれません。
ちなみに右半球の主な働きは、
視覚情報の解析
空間内の操作能力
というわかりづらい表現しかしようがないものです。右脳が欠落すると言葉の抑揚が失われるなんていうのも有名ですね。巷間で言われる右脳は芸術系ってのは、全否定はしませんが眉に唾して聞いていた方がいいレベルではあります。
結局のところ脳は左右が補完しつつ活動しているので、右脳が抑制されるからこういう機能が抑制される。というよりは、総合的な活動効率が低下すると解釈した方がいいと思います。
さらに言うと、そもそも入力される情報の量がMT/ATでは違います。ドライブトレーンの存在と、自動的に変速してくれるATと違い、MTは機構的にそれを外すことができます。
つまり外さないようにエンジン音やGのかかり方等の情報を脳に送り続けて対応の準備を強いられています。これも脳の活性化のレベルを高めているのではないでしょうか。
以上のように、原体験と習慣によってシナプス結合が強化された私の脳は、MT=運転。というふうに仕上がっており、逆にATを運転する際に使用する部位は開拓されていないと言えるかもしれません。
第2回は本当に読みにくくてすみませんでした。
ここまで読んでくださったあなたは御釈迦様のように慈愛に満ちておられます。正直抱かれてもいいd......いや、ともかく、ありがとうございました。
次回は上記の「ドライブトレーンを外せる」ということと運動学習についてです。
書き溜めがなくなってしまったので、少しかかると思います。
....と言うかコレ読んで面白いかな?
自分でもよくわからなくなってきました(汗
続く。
Posted at 2017/10/31 19:40:27 | |
トラックバック(0) |
車徒然 | 日記



 にわか車好きなりに少しでも経験を積もうと、節操なく試乗を繰り返しております。販促目的で試乗の機会を設けている各ディーラーの方々にはなんとも迷惑な輩ですね。
にわか車好きなりに少しでも経験を積もうと、節操なく試乗を繰り返しております。販促目的で試乗の機会を設けている各ディーラーの方々にはなんとも迷惑な輩ですね。
 最近つらつらとドライビングプレジャーについて考えていました。
最近つらつらとドライビングプレジャーについて考えていました。