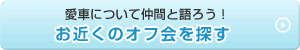- 車・自動車SNSみんカラ
- 車種別
- 日産
- エクストレイル
- クルマレビュー
- クルマレビュー詳細
2022年式 エクストレイルG感想文 - エクストレイル
-
ノイマイヤー
-
日産 / エクストレイル
G e-4ORCE_5人乗り_4WD(1.5) (2022年) -
- レビュー日:2022年10月8日
- 乗車人数:2人
- 使用目的:その他
おすすめ度: 4
- 満足している点
-
1.ミニバンに学んだ快適装備
2.欠点を克服しつつあるe-POWER
3.セダン的な静粛性
4.ほぼ直角に開くRrドア
5.耐傷付き性の高いラゲージ - 不満な点
-
1.あのエクストレイルの精神は何処へ
2.肩から浮く後席シートベルト
3.慣れないe-Pedal
4.Xを買わせないための仕様設定
5.本革シートですらシートベンチレーションが無い - 総評
-
●要旨
4代目エクストレイルはタフギア成分より「上質」寄りになった。最大の目玉は日産独自の可変圧縮比(VC)ターボエンジンを発電用にしたe-POWERである。HEVとしては燃費性能として不利になっている分、あたかもBEVに乗っているかのような「電動感」を追求しているのがポリシー。BEVの様にパワフルかつ期待を上回る静粛性は抜群に優秀。日本国内の脱エンジン勢力による最新製品の魅力がエンジンというのがなんとも皮肉な話だが。内外装も高級セダンユーザーも納得できる内装のクオリティ、後席のアメニティ装備の充実度もミニバンユーザーが不便を感じないレベルを確保。グッと商品力がアップしたが価格にも反映されており先代からは明らかに価格が上がっている。競合(特にトヨタ)よりもお買い得な価格設定だが、散見されるミス(始動後のパワーシートの動き、シートベンチレーション未設定、Rrシートベルトのアンカー)は支払総額500万円を超える車としては鈍臭い。また現状は魅力的な装備が最上級グレードに集中し、中間グレードの仕様的柔軟性に欠けている点が残念。今は最上級グレードだけを買わせる作戦のようだが、いずれ中間グレードの仕様最適化が進むことを期待したい。
●下山し、高層マンションに登った4世代目
日産の4代目エクストレイルが満を持して2022年7月に発売された。エクストレイルの簡単な歴史は先代の感想文をご参照頂くとして、初代から2代目まではオフロード指向の遊べるSUVだったエクストレイルは2013年デビューの先代からグローバルマーケットでの動向に合わせてカーライクSUVに舵を切った。日本仕様だけは、日本の顧客のイメージに合わせてビニール内装を準備してに車体を赤く塗って対応した。エクストレイルというブランドは等身大で使い倒しても壊れない道具―ギア―としてのイメージがあったので、先代モデルの路線変更は残念だったが、モデルライフ途中でHEV追加やプロパイロット装備など改良を重ねながら売り続けられた。
2020年6月、既に北米では新型エクストレイルに相当する新型ローグが発売されていた。昨年頃から雑誌やインターネット上で新型の写真が紙面を賑わして「日本発売か?」と報道されていたが、なかなかデビューせず「出す出す詐欺なのではないか?」とさえ感じられた。ようやく2022年7月に発売された新型は本格タフギアを継承しながら上質さという新しい価値を付け加えた点が特徴だ。
タフギアというDNAに関する最大のトピックは、ガソリン車を廃止して全車e-POWERとしたことである。更に発電用E/Gには日産が独自に開発した可変圧縮比技術を積んだ1.5L直列三気筒直噴ターボE/Gを採用。日本向けではこれが初出し採用である。これによりSUVに求められるパワフルな走りが継続的に得られるようになった。
また、e-4ORCEと名付けられた新四駆統合制御が盛り込まれ、前後揺れ抑制、旋回時の内輪ブレーキ制御、低μ路での高い発進性など安心感確保に繋げている。SUVとして大切な最低地上高も4WDは200mmと高めでタフギア的な意地を見せている。
一方、上質を感じさせるのは主に内装の質感向上と快適装備の採用である。ステッチを強調するソフトパッドは既にこのクラスとしては当たり前になってきた(凄い!)が、更にエクストレイルは木目調オーナメントやフル液晶メーターや大型ディスプレイなど一昔前の高級車レベルの質感を得たのは大きな進化である。更に、後席ロールシェードやRr独立式オートA/Cを上位グレードに採用するなど、ミニバン的な快適性をSUVで実現している点も特徴になっている。
実際に運転してみると、e-POWERの電動車的な感覚、いわばBEV感に一層磨きがかかっている。ノートで強く感じたE/G起動時の強烈なこもり音も無く、黒子に徹して淡々と発電し続けるE/Gはパワーに余裕があり高回転まで回す必要が無い。かつての私は「シリーズハイブリッドは発電にしか使わないのだから小排気量E/Gで十分!」「スズキのスイフトをベースにしたショーモデルは660ccで税金安かったのに!」などと考えていたが誤りであった。シリーズハイブリッドは、駆動モーターの出力・トルク、搭載予定のバッテリーに見合ったE/Gを選択してやる必要があった。仮にモーター仕様と二次電池容量を固定して考えれば、小さいE/Gを搭載すると消費電力の大きい高出力モーターを駆動するためにバッテリーの電気を消費し、バッテリーのSOC(充電量)が不足するため、E/Gが常に回り続ける。一般的なE/Gは最高出力や最大トルクはガソリン車の常用域より高い回転域にあるため、常にE/Gが中回転以上で回り続けて騒音も大きく燃費も悪い。しかも、走りを優先させてバッテリーの電力を使いすぎると、充電量が追いつかずモーターを駆動する電気が不足して性能が低下してしまうと言う問題もある。(実際にセレナe-POWERで峠越えすると速度が全然出なくなったとか、先代ノートe-POWERを雑誌の企画でサーキットを走らせると 後に急減速したといった類いの話がある)
e-POWERを「電気自動車の新しいカタチ」としてBEV感向上を推進したい日産はバッテリー容量を拡大し、電池の使い方を工夫することに加え、遂にE/G本体にもメスを入れた。パワーのあるE/Gによって低回転でも十分な発電量が維持できるため、車両側で発電を我慢できる領域が広がった。
BEV感に必要な静かさも感じられてラギッドなRAV4やフォレスターのライバルと言うよりは、高級感を訴えるハリアーやCX-5のライバルといった方が相応しい内容である。日産は燃費効率に劣るe-POWERゆえに走りの質感で勝負する方針らしく、最近試乗したモデルはどれも静粛性や動力性能に余裕を感じ、商品としては好感が持てる。
全グレードがシリーズハイブリッドであるため、価格帯は税込320万円~450万円という範囲に上級移行した。(先代のハイブリッドから20万円程度の販価アップだ)
新型エクストレイルは、後発モデルらしく競合車をよく調査した上で自社の強みをうまく活かしてキックスとアリアの間をカバーしている。個人的に驚いたのは、このクラスで売り上げナンバーワンのRAV4に対して、価格競争力が高く明確な上質感がある。格上扱いのハリアーとも競合できそうだ。
もはや猫も杓子もSUVという現代では、高級セダン・ミニバン群の移行先としてのSUVも必要だ。スカイラインやエルグランドという、もやは放置プレー気味のセダン・ミニバンの既存ユーザー達も買い換える車を待ち続けているからだ。
それでは、エクストレイルが本来持っていたアウトドアで気兼ねなく使えるタフギアを求める層は何処へ行けば良いのだろうか。本来はSグレードに防水シートをOPT設定しうる選択肢があっても良かったのでは無いか。ちょっとチープだけど、楽しく使えるのがエクストレイルでは無かったか。残念ながら新型からは初代が持つ精神は感じられない。実際に世界戦略車SUVの日本仕向けにエクストレイルと名付けただけに過ぎないのではないか。若い頃からエクストレイルを見てきた私には一抹の寂しさを感じた。
パワーシートの制御とか後席シートベルトのアンカー位置など本当につまらない部分(でも大事な部分だ)で点数を落としているが、最近の日産車(というよりe-POWER)はどんどん改良の成果が一般のドライバー達に分かるレベルに達している。口先だけの宣伝のうまさだけでは無く商品の実力も上がってきたことは日産にとっては非常に良いことだし、商品の力で市場を更に活性化させる事は私達ユーザーにとってもメリットがある。
群雄割拠のSUVの中でエクストレイルを買うべき人はどんな人か。既に上げた通りミニバンを卒業してSUVに降りてくる人、或いはファミリー層で広い車が欲しいがミニバンは過剰だと感じる人、昔だったらV6ターボが選べるからキャラバンを選ぶような人にはエクストレイルを選ぶと満足できるはずだ。
現状の仕様設定でミニバン的な使い方をするなら後席機能が充実したGを、独身・カップルの若者が背伸びして買うなら前席優先のXを薦める。(外装のグレードダウンはそれほど気にならない。)
エクストレイルはファミリー層にこそ魅力的に映る装備を持っているが、残念なことにG専用装備である。Gは高すぎるので本当は後席優先機能をXに単独OPT設定すべきだと思う。(特に3列シート仕様)
今は半導体不足やコロナ禍によって自動車生産がままならない状況なので限られた生産枠で利益を最大化する為に粗利の高いモデルを生産するしか無い。お買い得(=粗利が小さい)モデルは極力作らないに越したことは無いのだ。そういう意図でe-4orceを先にラインオフさせ、Sは売る気の無い最廉価とし、注目装備をGだけに搭載して選ばれ易くした。ついでにXもモリモリのセットオプションで高収益化を図る。日産にとっての最適解が経営的に正しいのは分かる。しかし長年エクストレイルを待ち望んでいた日産ファンの視点はあるのだろうか。
確かに今は緊急事態だ。だが、エクストレイルも購入後半年以上待たねばならないクルマであるし、かつての高級車を超えるような価格帯の車だ。もう少し顧客の要望に柔軟に応えるべきではないか。そこさえ改善されればこのクラスで、ライバルを凌駕することになるだろう。
- デザイン
- 3
-

新型エクストレイルの外装デザインは先代を継承したテイストだが、フロントマスクは北米トラック系車種や傘下の三菱車を思わせる義眼ヘッドライトが目を引く。メインのヘッドライトはマルチリフレクター式LEDで義眼はクリアランスランプやDRL、シーケンシャルウインカーを配置。グリルはVモーショングリル、ほうれい線はFrフェンダー無いに気流を流す役割を持っている。周囲にエクストレイルのカタログを見せてみると、この顔が嫌だという声が聞かれたが個人的には特別スタイリッシュでは無いが目を背けたくなるような意匠では無いし、個人的には力強さが感じられて好意的に見ている。北米仕様と全く同じと思いきや実はグリルのVモーション部のメッキが大味な太い物からピアノブラックと細いメッキに変更されている。メッキはベタッと平面的に存在するより繊細な表現で使う方が上品さを表現することが出来、日本での新型エクストレイルにはこちらの方が似合う。

サイドビューはSUVらしくロッカー部を覆う下見切りドア(横見切りの先代から復活!)やホイールアーチモールの採用があるものの、ベルトラインは前下がりのウエッジ角度を減らして水平基調気味とし、前後ドアで三角窓を廃止したスッキリしした印象である。デザイン的に退屈にならないようにRrドアのブリスター的なホイールハウスの張り出しやドア下モールの錯視効果を使って躍動感を見せている。また、SUS製の光りモールをコンベンショナルなドアベルトラインでは無く、ドアフレーム側に通してクオーターウィンドウを突き抜けてツートンカラーの塗り分け部の目隠しに使うだけでは無く、ルーフラインを低く見せて居る処理は競合のRAV4と同じである。初代・2代目はスクエアなスタイルを取って機能最優先ではあった。新型もラゲージをクオーターピラーの傾斜でエレガントに見せながらも、バックドアのサイドスポイラーをうまく使って機能と意匠を両立させようとしている。この辺りのテクニックは既に最近の常套手段ではあるがエクストレイルもうまく使っている。

Rrビューは先代に引き続き樹脂バックドアを採用。一部の軽自動車や小型車では樹脂バックドアの意匠面がヒケまくってエクボだらけになっているが、先代エクストレイルではそんな車は見かけなかったので恐らく信用して良いだろう。樹脂ならではの難成型に挑んでいるわけでは無いが、継ぎ目がなく、面が大らかなのは良い。
インテリアも先代の方向性を更に前進させて上質感を感じさせる方向に進んだ。ソフトパッドやステッチ、ヘアライン柄樹脂パーツなどを総動員し、土臭さは完全に姿を消した。雰囲気的にはちょっと昔のローレルやグロリアのような高級セダンを思わせる領域に近づいた。

コックピットは乗降性に配慮したDシェイプステアリングの奥にオーラでも採用されていた12.3インチフル液晶メーターが配置されている。速度計やタコメーターはボタン操作で端へ追いやられて、走行状態表示や燃費情報などが大きく表示される。この辺りは必要性云々と言うより流行への対応という側面を強く感じてしまう。(原価的には今後機械式よりも下がるポテンシャルはある)
インパネからは飛び出した日産コネクト12.3インチナビはディスプレイオーディオ機能が備わるが、CDが聞けないのが個人的には残念である。
センターコンソールはSUVらしさを演出する意味も含んでおり、幅と高さをしっかり使った電制シフトやEPB、各種ドライブモード選択ダイヤルやカップホルダーが配置されている。アームレストと繋がるようなイメージで腕を置いたそのままの手で操作できるように高さが揃えられているのだろう。電制シフトはワークスペースが小さくスペース上有利だが、その分アメリカサイズの大型カップホルダーが用意されているのは大変実用的だ。カップホルダーの位置は重要で、シフト操作した肘が来るエリアにカップホルダーを配置してしまうとシフト操作のたびに飲み物が邪魔になるため、車幅に余裕があるなら左右方向で逃げて共存するのがベストだ。
上質感あふれるインパネはツートンカラーのソフトパッド、助手席前にもステッチを活かしたソフト触感のオーナメントを配し、その下には木目調パネルがあしらわれている。(Gのみ)そしてドアトリムも同様にソフトな触感が続く点も魅力的だ。特にドア開閉時に手で持つハンドル部分はPLが目立つことも無く、グリップが前にありすぎて重くて開閉しづらいなどのクセの無い極めて一般的な構造なのだが、奇を衒いがちな昨今、こう言う手堅い設計は有り難く思う。
シートはTailorFitという合皮製のパワーシートである。カラーが黒しか無くちょっと暗い印象である。メーカーオプションでタンカラーのナッパレザーシートの用意があるが、カタログ写真で見る限りはなかなか洒落ている。北米のウェブサイトを確認すると本革シートでも黒の設定があったり、ライトグレーの明るい内装色が選べる。ネイビーなんてお洒落で良いなと思うのだが。もはや高級車なのだからもう少し内装色の選択肢くらいは無くては困る。色の暗さもさておき、この手のレザー系材を表皮にしたシートは冬場は寒く、夏は蒸れて暑いのでシートベンチレーションが欲しいところだが、ナッパレザーでも設定が無いのは残念だ。400万円を超えるエクストレイルのGグレードともなれば装備が当たり前のはず。ハリアーでも本革シート仕様にはベンチレーションが備わっているので年次改良に期待。
G以外のグレードではサイドが黒でセンター部がグレーのファブリックシートになるのだが、これがカタログ写真の段階で生地が引っ張られてヨレているような残念な見た目であり、スタート価格319万円の車格に全く見合わない。
エクストレイルのDNAとも言えた汚れに強い防水シートはXグレードにのみメーカーオプション設定で残される。現代では防水シートを望む顧客がかなり減っているようだ。コロナ禍もあって仲間と長時間車内で時間を共有しながらレジャーに行くような事は減っているかも知れない。最近ではすっかり定着したかに思えるグランピングに代表されるように少し値は張るがその分快適に手軽にアウトドアレジャーを楽しむ機会が増えており、夜通し雪の中高速を走ってスキー場の駐車場で仮眠を取ってオープンを待つ、或いは濡れたサーフボードを室内に積む、なんて人も遊ぶときはシートカバーを被せて普段はクロスシートの快適性を楽しんでいるのかも知れないが。
この様子だといよいよ次期エクストレイルが有るとすれば防水シートが無くなってしまうかも知れない。
以上、新型エクストレイルのデザインをまとめると、北米市場を強く意識したバタ臭い顔つきは共通するものの、サイドやリアはスッキリと力強さのバランスが良い。内装もタフギアと言うよりもセダンライクSUV志向が強い。シートと内装色にあと一息という惜しい部分がある上質感を訴求しているハリアーやCX-5と比較するとSUVらしい頼りがいが感じられ、熾烈なミドルクラスSUVの市場で良いポジションにあると感じた。 - 走行性能
- 5
-
●試乗その1
日本では初めてとなるVC(可変圧縮比)E/Gを積んだ車ということで期待を膨らませてエクストレイルに乗り込む。
カタログの圧縮比の項目は「8.0~14.0」と記載されている。この様な表記を見たのは初めてだ。ご存じの方も多いが、圧縮比はE/Gの効率を左右する諸元である。ガソリンE/Gは空気と燃料が程よく混ざった混合気をより圧縮し、着火する。この圧縮度合いが圧縮比である。圧縮比を上げると熱効率が向上する。すなわちパワーが出る、或いは燃費がよくなる事を意味する。ただし、闇雲に圧縮比を上げるとノッキングの問題があるので圧縮比向上には限度があった。限られた条件下では高圧縮比で運転出来たとしても、実際はあらゆる状況で破綻しない圧縮比に留めておくほかなかった。VCターボE/Gは低負荷で低燃費運転が可能な状況で圧縮比を最大14まで高め、レギュラーガソリン仕様として従来到達し得なかった圧縮比を得た。(マツダのスカイアクティブXは圧縮比15と驚異的だがハイオク仕様である)
断面図を見れば、一般的なエンジンがコンロッドとクランクシャフトで構成されるのに対して、VCエンジンはクランクシャフトから先にリンク機構を持ち、その先にアクチュエータが配置される。

アクチュエータが状況に合わせて作動し、ピストンとクランクシャフト間の距離をリンク機構によって変化させることでピストンの上死点・下死点を連続的に変化させて圧縮比が変わる仕組みである。(変化量はストロークで6mm程度とのこと)
百聞は一見にしかずなので日産公式サイトへのリンクを貼っておくので是非一度見て欲しい。
思えば2代目セフィーロで実用化され、90年代の日産車に広く用いられたマルチリンクビーム式サスペンションもスコットラッセル機構を応用したものであり、日産内には機構学マニアのDNAが脈々と受け継がれているのかも知れない。
可変圧縮比のためのリンク機構ではあるが、繰り返される大きな圧力変動に晒される(クランクピンに従来比1.9倍の応力がかかる)ために強度は非常に気になる部分だが、引っ張り強度「16T」という高強度ボルトを開発して小さく作って慣性力を下げた。さらにそのボルトはコンロッドに互い違いに組む(=現場での組み付け作業性に悪影響)など技術的にも新しい技術を盛り込んだ。
そして可変機構の要であるアクチュエーターは弾性を利用しながらバックラッシュのない「ハーモニックドライブ」を採用している。可変圧縮機構にガタがない確実性が必要で、かつ高強度に耐えられて小型軽量であるためVC機構のアクチュエーターにぴったりである。
こうして高出力のターボながら低負荷時は圧縮比14の運転が出来るなど過給によるデメリットをカバーできるE/Gが完成した。開発者へのインタビュー記事では「もし圧縮比を14にすれば燃費は25~30%改善するが、出力は50%ダウンする。一方、圧縮比が8なら燃費は望めないが出力は10%アップする。両方組み合わせたVCターボでは、3.5lのV6に比べて燃費を27%向上した上で出力は10%高めた。V6と比べてE/G重量が軽く、これは走りの面でもメリットとなる」と語っている。
このE/Gにネガがあるとすれば構成品追加によってベースのKRより10kg~15kg程重くなること、複雑な機構を持つことに拠るコストの高さ、摩擦要素が増えることでフリクション増加も考えられる。素人目には更に絶えず作動し続けるアクチュエータの寿命も未知数だ。また、一般的なエンジンのクランクシャフトがある部分の下に更にリンク機構が有るのでエンジンの高さも上がって実際にエクストレイルの決して狭くは無いはずのエンジンコンパートメントも直列3気筒1.5Lの割には窮屈そうに感じられる。
それでも誰も見たことの無い新機構ゆえ、E/G愛好家にはワクワクが止らないのがVCターボE/Gである。
ドラポジを合わせて左手でスタートボタンを押すとシステムが起動する。ルームミラーは昨今採用事例が多い電子式になっているが、最近はすっかり実用レベルに達した。競合が採用しているような録画機能は無し。
既にシステムが起動しているが、「BEV感の追求」を信条とするe-POWERはE/Gを起動させずに無音を貫いている。電制シフトを手前にスライドさせるとDレンジに入り、あとはアクセルを踏めばEPBが作動して勝手に走り出してくれる。店舗を徐行で出発するとほんの数メートルでエクストレイルの特徴がスムースな走りであることに気づいた。SOCが半分くらいの状態でアクセルを軽く踏むと軽やかに1880kgの車体を引っ張ってくれる。
駆動用モーターはFrが150kW(209ps)/330Nm、Rrが100kW(136ps)/195Nmである。システム出力はFF/4WD問わず150kW(209ps)であるという。競合するRAV4は4WDで160kW(218ps)。スペック的にはエクストレイルの方が控えめなのだが、100%モーター駆動のエクストレイルはレスポンスが非常に良く、微小なアクセル操作にもグッとトルク上昇という反応を返してくるのは気持ちが良い。
それこそが電動走行のメリットであり、あくまでE/Gの補助に徹するマイルドハイブリッドでは味わえない魅力である。ハイブリッドのパイオニアであるTHSも発進は全てモーター駆動であるのでアクセルレスポンス自体は良いはずなのである。ところが、私が乗ってきたTHS車は40km/h手前でブルンとE/Gがかかるのでそのレスポンスが長続きしないのだ。
一方でエクストレイルのe-POWERは歴代e-POWER車の中で最強レベルのBEV感を誇る。アクセル操作に対して良好なレスポンスと静粛性の高い力強い加速性能が味わえるからだ。モーターにもキーンという高周波ノイズが含まれることもあるが、エクストレイルは実際の走行では気にならない。当然、SOC(充電量)が減少するとE/Gが起動するのだが、意地悪目にオーディオを消してエアコンの風量を落としても、ほぼ気づけないようなレベルの音・振動しか出さない点も歴代e-POWER最良である。

e-POWERの頭出しのノートは1.5kWh(現行も同値)だが、エクストレイルは1.8kWhである。対してRAV4 HEVはネット情報では容量:6.5Ah、電圧:244.8Vの為、[Wh]=[Ah]×電圧[V]の公式から、6.5Ah×244.8V=1.59kWhとなり、エクストレイルは大きめのバッテリーを積む。
バッテリーの余裕によってモーターによる走りを味わう時間が長くなるだけでなく、駆動用電池の使い方も進化している。従来は半分くらい減るとE/Gがかかっていたが、エクストレイルではメーター読みでも1/3くらいまではEV走行が可能になった。しばらく走行するとE/Gを起動して充電を開始するが、かかっている事が気にならなず、メーター内の表示を見て初めて気づくレベルだ。市街地走行では起動させないように我慢し、起動した場合は音をロードノイズで隠しつつ、目立たせないようにE/G回転数も落とす(80km/hまでは2000rpm以下に固定)など高出力の新開発E/Gの恩恵は大きい。黒子に徹したE/Gは、その凄みに気づけないほど「BEV感」のために存在が消されている。
試乗コースには数キロ続く上り坂があった。10%程度の坂を特に飛ばすわけでも無く制限速度50km/h程度で登っていくのだが、余裕のあるモーター駆動によって淡々と坂道を登っていく。途中でE/Gがかかっても音も振動も感じないのでハイブリッドカーで良くあるE/G始動でガッカリする感じが無い。アクセルを全開にするとE/G音が聞こえるが、乱暴な加速さえさせなければe-POWERらしい質感の高い走りが楽しめた。

VCターボのための機構の副産物でピストンスピードの変動を無くし、スラスト力を減らすなどの対策によってV6に近い振動特性を持っている。確かにハイテクの塊であるはずのVCターボは振動による存在感を見せない。一回だけ全開加速をさせてもらった。おそらく圧縮比は8になり、モーター由来の強烈な加速が楽しめる。さすがにキャビンにもE/Gの音が聞こえてくるがその後は相変わらず静粛である。絶対的な加速性能は競合並であるが、常用域では優れているので体感としてエクストレイルはパワフルに感じる。豊かなトルクがレスポンスよくリニアに続くからだ。
<後編へ続く> - 乗り心地
- 5
-
●試乗その2
田圃を抜ける軽いワインディングを走ったが、スポーティなキビキビ感よりもどっしりした安定感の高さや19インチ(HK製)を履きながら、突き上げ感が目立たない乗り心地が印象に残る。
試乗車は前後モーターを協調制御することで高い操縦安定性を実現するe-4orceが搭載されている。
前後でトルク配分に差をつけるだけで無くコーナリング時の内外輪でトルクを分けることでスリーダイヤ的に曲がる4WDを実現している。
今回の試乗では限界域の走りを試すわけにはいかなかったが、極めて普通に走る。新型エクストレイルは安定感があり過ぎて、平凡な技量を持った私がディーラーの近所の乾燥路を試乗したくらいでは何も起こらない。真冬の高速道路でのレーンチェンジ、スキー場へ向かう積雪した山道の運転では安定感ある走りを実現するはずである。むしろ、我々一般ドライバーは性能を過信し、速度を出しすぎてタイヤの限界を超えるような事にならないように注意すべきだろう。ステアリング操作に対しては切っただけ反応する。その反応が適切なものであるからS字カーブも気持ちが良い。
ディーラーへの帰り道、交通量の多い市街地を走ったが、こういう場所でも新型エクストレイルはまるで上級セダンかミニバンに乗っているような快適性を維持している。大柄なSUVだが、ドアミラーで確認できるエリアも大きく、像にはRrフェンダーが映るので見切りは確認しやすく、三角窓がないスッキリしたドアのおかげで右折時の抜け感も問題ない。最小回転半径が5.4mと小さいので意外と狭い路地もカメラを使えば入り込める。この様に高速以外のシチュエーションはほぼ試したが、このクラスとしては走りの質感が高く内外装の感覚ともマッチしていた。
競合車と比べると、ちょっと大人っぽいキャラクターを訴求しつつも特に静粛性へのこだわりは群を抜いている。目についた物を列記するだけでも、かなりのコストが割かれており、競合車の中でもこれら全てを装備する競合車は無いのでは無いか。
・アクティブノイズコントロール
・Frドアガラスに遮音層を挟んだアコースティックガラス
・サスタワーの吸音インシュレータ
・ホイールハウスの吸音インシュレータ
・Rrパン下タライの吸音材
・Rrデッキサイドトリムが吸音基材
・ホイールハウスの吸音ライナー
・E/Gアンダーカバーが吸音基材
・バックドアを開けた車体側遮音シール材(マツダ2風)
・ウェザーストリップ類の合わせをラップさせてシール性向上
などなど・・・。高級ブランド車も驚くようなアイテムも見られる。
こんな風に褒めてしまうと提灯記事のように思われてしまうので、試乗で感じた弱点を下記にまとめておく。
まず、走り出しのこもり音だ。現行のノートもE/Gが起動した際のこもり音はかなり酷いのだが、エクストレイルではE/G由来のこもり音が発生しない代わりに荒れたアスファルトを通過したときに、路面がタイヤを揺らし、車体を振動させ、キャビンが増幅されてこもり音になる。(エクストレイルは全車にアクティブノイズコントロールが装備される。古くはU13ブルーバードで搭載されたことのある装備だが、Rrパンのウーハーからこもり音の逆位相の音を出してこもり音の発生を防いでいる。この装備は予めエンジンが発生するデータを適合によってプログラミングしておく事が必要なため、エンジン由来では無い路面入力のようなランダムなこもり音には対応しきれない)
また、e-4orceの特徴として減速時の「ガクッ」とくるショックが少ない事をアピールしており、「ラーメン配膳ラジコン」動画を作成して制御の優秀性を訴えている。ところが実際に運転してみるとガクッとする場面は少なくなく、効能が分かりにくかった。作動はしているんだろうが、ガクッとならない訳では無くて期待外れ。(普通はガクッとならないように運転するものだし・・・。)
加えてe-ペダルも相変わらず私の感覚に合わない。アクセルオフで0.2Gで減速してくれるのは実感できるが、常にアクセルペダルを踏み続ける行為がこんなに疲れるのか、といつも思い知らされる。信号停止でもアクセルオフで減速し、制動が効き過ぎてしまいアクセルを踏み足して減速度を調整し、停止線手前でブレーキに踏み換えて停止させる。この慌ただしさがストレスに感じた。個人差というか相性があると思われるが作動可否はボタンで選べるので個人的には使用しない。
また、右左折など大きくステアリングを切る際に円周下端が凹んだDシェイプステアリングが不快である。手を持ち帰るときに「あれ?」となる事が多くあった。マツダを見習え!とまでは言いにくいが乗降性のためにステアリング下端を切るほどステアリングホイールは大径ではないのだから、丸くしてほしい。いずれステアバイヤー技術が発達して手を持ち帰る必要が無くなればDシェイプでも良いのかも知れないが現状は感心しない。
ついでに言えば、このパワーシートも乗車時に位置を調整しても起動ボタンを押すと、前に運転した人のメモリ位置に動いてしまう。ディーラー試乗車のように毎回ドラポジが変わる事は無くとも、夫婦で運転手を交代する事はあるだろう。この機能は、起動前にシートを調整した場合はその位置を維持させるようなロジックを追加しておくべきではないか。
e-POWERはパワフルに走れ、日常試乗では絶対的なパワーもあり十分満足感があるので★4つ。乗り心地としては乗り心地は★4つ、NV性能は十分感動できたので★5つをつけたい。 - 積載性
- 3
-
居住性を確認した。運転席に座るとはインパネの圧迫感も無く、開放的。ホンダのようなすっきり感は無く、運転席からフードの両端が角のように見えているため、ドットパターンの黒セラミックで誤魔化している。(競合のRAV4も同じ処理をしている)

シートのサイズや堅さは適切な範囲内でステアリング軸のオフセットも気にならないレベルに抑えられている。(競合のRAV4や同P/Fのハリアーはオフセットが気になるレベル)
チルト+テレスコピック機構も標準装備だが、価格帯を考えると電動化して欲しかった。
運転席に座っていると、パーソナル感を損なうほど広すぎず、目に映る大抵の部分はソフトな触感かつ木目調やピアノブラックで高級セダンと見間違えてしまいそうなムードは良く出来ている。その割に室内灯が豆電球というのは精彩を欠く。商品としてはLEDでは?
それはさておき、後席はエクストレイルの一つの魅せ場になっている。なんと言っても後席ドアを開けただけで良さが分かる。このクラスでは珍しい準90度開きを実現しているのでチャイルドシートへの子供の乗せ降ろしや3列シート仕様での乗降もストレスなく行いやすい。ヒンジ単体も廉価なプレスヒンジでは無く型鋼ヒンジが使われている点は実用性と意匠性を両立するためにコストがかけられている。そんなにドアを大きく開ける場面なんて有るのか?と疑問を持つ人も居るかも知れないが、スペースがある駐車場では少しでも大きく開いた方が子供の乗せ降ろしがし易い。抱っこしてCRSに乗せる際は、お着替え入りのリュックを背負っていることもありスペースがある方が有りがたいので有る。(基本的に我が家はドアパンチを防ぐため今は子供にドアの開閉をさせていない)
乗り込むとシート形状自体は可も無く不可も無い一般的なサイズ・ホールド感であるが、クラスでは珍しいシートスライド機構とリクライニング機構を持つ本格的なリアシートが着いている。シートスライドは最後端に引くとフロアのキックアップした縦壁のせいで足引き性は良くない。それどころか、シートベルトのアンカーがCピラーにあるため、シートスライド位置が後ろにあると私の場合肩ベルトが浮いてしまう。安全を考えるとシートスライド位置はRrモーストよりちょっと前、シートベルトを着用してちゃんと肩がベルトに接するような位置が好ましい。同じような設定のRrシートベルトは先代ハリアーでも見られるが、エクストレイルはスライド機構によって成立解があるので我慢は出来るレベルにある。
Rrシートの調整幅が広いことは後席乗員の快適性やラゲージの自由度が格段にアップするが、競合は簡易リクライニング機構しか備えなかったり、エクストレイルの優位性が格段に光る。(数年前まではエクリプスクロスのにシートスライド機構とリクライニング機構があったがPHEV追加時に廃止されてしまった)
また、最上級のGグレードにはサイドドアへのロールシェードが標準装備されている。高級セダンやミニバンの専売特許かと思っていたが、SUVに備わるケースは珍しい。さらに、後席だけ独立して各種調整が可能な後席独立式オートA/Cも備わる。
まさにミニバン顔負けの高級装備が楽しめるのがエクストレイルなのだ。

後席を軽視することを競ってきた国産車の中でエクストレイルは中国車ばりに後席の快適性を重視しており、そこがエクストレイルの見せ場なのだが、魅力を楽しめるのが最上級Gグレードに限られる点が惜しい。

ラゲージはクラストップの575L(VDA法)である。競合のRAV4同様にデッキ面が傾斜していることが気になるが、このクラスのSUVなので、荷物が載らないとか人が窮屈だという事は流石に無い。
特徴としてはデッキ両サイドのトリムも植毛仕上げで荷物を傷つけない優しい素材が使われている事以外は特に特徴は無い。例えばフォレスターは広大な開口幅を持つし、ハリアーはデッキ下に引き出し式シークレットボックスを持っている。ちなみにRAV4はバンパーレベルの荷室と、高さを稼いだ拡張モードがあり、後者は580Lとなりエクストレイルを凌駕している。エクストレイルの場合、デッキ下にちょっとした収納スペースを持っているが、大きなウーハーと補記バッテリーが鎮座しており、そもそもスペースが取れないため、デッキ下スペースを含めない荷室寸法でクラストップと言っている。ちょっと紛らわしいが、自動車のエンジニア達は何らかの数値で自製品がトップになることに拘っている。(はずなんだが)
実用上は十分なラゲージスペースがあるのでアウトドア派も納得できるレベルではないだろうか。
居住性は不満は無いが特に秀でている印象は無い。ラゲージもまた同じ。シートスライドなど便利な機構もありながら、アンカー位置など精彩を欠いていたので★3つ。 - 燃費
- 3
-
e-POWERは一般的にはシリーズハイブリッドでありBEVとICE(内燃機関)車の間を取り持つための存在であるため、決して燃費を追求するためのシステムではない。
とは言え、ハイブリッドを名乗る以上はICE以上の燃費が求められる事も事実である。
試乗したG e-4orceの燃費はWLTCモードで18.4km/L(FFは19.7km/L)。競合関係にあるフォレスターは14.0km/L、RAV4が20.6km/L(FFは21.4km/L)、CR-Vは20.2km/L(FFは21.2km/L)であるからエクストレイルは数値上、トップ群から1割程度負けている。(ちなみにRAV4を借りて乗ったことがあるが燃費計ベースで20km/L程度は走った)
私が試乗した試乗車は乗車時に8km/L(悪い!)それを リセットして13km/L程度だった。短時間の走行故、カタログ値の70%程度しか走れないが、マイカーとして丁寧に乗っていればもう2-3km/Lは伸びるはずである。
実際に2024年に1時間ほど運転した時は難なく15.2km/Lを出したが、パフォーマンスを考えればリーズナブルな数値だ。
さらに燃費の良い車は他にあるかも知れないが、大排気量マルチシリンダーE/G車のような走りが楽しめて、この燃費性能でレギュラーガソリン仕様なら私は十分満足できる。
しかも1.5Lなので自動車税金も安い。例えば競合のCR-V(2L)やRAV4(2.5L)との比較を行った。保有期間5年間として燃費(160円/Lと仮定)のビハインドと自動車税のアドバンテージで相殺するにはCR-Vの場合、年間4827km、RAV4の場合、年間9519kmで損益分岐点を迎えることが分かった。
日本自動車工業会がまとめた平均の走行距離が4440kmであるので、平均的なユーザーなら競合車より燃費の悪いエクストレイルを購入しても自動車税のメリットが燃費デメリットを上回るため計算上は維持費的に遜色は無いということになる。
ノートの場合、直列3気筒1.2LがE/Gの最適解だと言うが、市街地メインの車両ゆえの最適解だろう。明らかにセレナでは力不足だったし、エクストレイルの場合は、高速道路の長距離走行も加味した燃費最適解なのだろう。(ちなみにセレナにはVCターボは載らず1.4L自然吸気E/Gが搭載されるという) - 価格
- 3
-
新型エクストレイルの価格は下記の通りである。

グレードはベーシックなS、中間のXと最上級のGがある。全車にFFと4WDがあるが、2022年9月現在、購入できるのは4WDのみである。エクストレイルの場合28万円の価格差がある。ICE車であれば価格差が25万円程度であるのでとりわけe-4orceが高いわけでは無いので必要に応じて選んで差し支えないだろう。また、中間グレードXに限り3列シート車が13.1万円高で選べる。
最廉価のSは
オーディオレス+4SP
7インチディスプレイつきアナログメータ
ファブリックシート
電動ランバーサポート
後席スライド・リクライニング機構
18吋アルミホイール
カーテンエアバッグ
寒冷地仕様
が備わっている。
いわゆる自動ブレーキなどは備わるものの、本体価格300万円を超えるクラスとしては当たり前装備の一つであるレーダークルコンが備わらずコンベンショナルなクルコンしか着いていないものの、MOPでAC電源(1500W 100V)が5.2万円選択できるのはトヨタをよく研究している。
ボディカラーが3色しか選べない事からも分かるように、日産としてはSをなるべく買わせたくないようだ。
中間のXで追加される装備は下記の通りだが、価格差を考えるとお買い得感は無いがボッタくられている感覚は無い。(液晶メーターは他車実績ベースで推定したが、案外機械式メーターと原価は変わらないんじゃ無いかと予想している)ただしXはボディカラーの選択肢が広がることとMOP選択権が付与される点が大きい。
選べるMOPは
後席ヒーター+ステアリングヒータ(FFのみ):3.85万円
Rrフォグ(4WDのみ):2.75万円
パワーバックドア:6.6万円★
ルーフレール:2.75万円
日産コネクトナビ+ETC2.0+SOSコール
+アラウンドビューモニター+電子インナーミラー+AC電源:41.6万円★
防水シート+助手席パワーシート:3.74万円
最上級のGとの価格差はe-4orceで約70万円違うが、★が着いた装備はGには標準装備されているので、実質的価格差は21.8万円となる。
Gはフラッグシップとして下記の装備が追加される。
シーケンシャルターンシグナル
ヘッドアップディスプレイ
ワイヤレス充電器
後席独立式オートA/C
アラウンドビューモニター+電子インナーミラー
Nissanコネクトナビ+ETC2.0+SOSコール
USB電源ソケット2個+A/C電源
内装加飾(木目調など)+イルミネーション
合皮シート+助手席パワーシート+ポジションメモリ
ロールシェード
パワーバックドア
19インチホイール
前後バンパー+サイドモール加飾
他車のOPT価格から相場観を推定した見積もりで77万円相当のアクセサリーが追加される。価格差約70万円から考えれば多少はお得感が感じられるような設定だ。
Gを買うと更にG専用MOPが待ち構えている。
例えば、
アダプティブハイビーム:1.1万円(安い!)
電動パノラマルーフ:13.75万円
BOSEサウンドシステム:13.2万円
ナッパレザーシート:8.8万円
上記で言えば、アダプティブハイビームが他社と比べて割安な価格設定だ。ナッパレザーシートが8.8万円も割安なのだが、内装色が「タン」固定になることと、夏場の蒸れを緩和するシートベンチレーションが備わらないのが要注意だ。この500万円を超えるクラスともなればあって当たり前の装備が備わらないのはいかがなものか。
ちなみにエクストレイルと言えばもっとオフロードイメージが無いと物足りないという私のような趣味の人向けにXベースで専用の内外装を装着し、オフローダーイメージを高めたエクストリーマーX(412.9万円~)の準備がある。RAV4アドベンチャーやフォレスターX-BREAKを意識した様な仕様設定だ。
ベースのXに対して33万円高なのだが、追加される装備が24万円程度なので専用装備されるアルミや前後バンパーの加飾に惹かれなければ素のXにMOPを奢った方が買い得感がある。
試乗させて下さった営業マンが、お薦め仕様で見積もりを作ってくれたので一例を示す。
G e-4orce(449.9万円)
メーカーオプションはアダプティブハイビームとルーフレール(3.85万円)ボディカラーはカタログカラーかつ、オプション価格的にお買い得感のあるシェルブロンドツートン(5.5万円)を選択。個人的にも既に装備水準の高いG故にこれくらい有れば十分かなと言うレベル。
ディーラーオプションはDSRCセットアップ(0.33万円)、カーアラーム(5.98万円)、ウインドゥ撥水(1.2万円)、5年保証コーティング(16万円)、ベーシックパックプラス(17.4万円)。ベーシックパックプラスはカーペット(ラバーマットとカーペット二枚重ね)、バイザー、ナンバーフレーム、ロックボルト、ホイールロック、前後ドラレコである。合計41万円!(ドドーン!)
メンテパック54ヶ月(12.9万円)やJAF(0.6万円)を含んだ販売諸費用が15.8万円。
納車費用、希望ナンバー、他税金類含んだ最終的な支払総額は約527.5万円となった。
若かりし事に初代エクストレイルを見てきた私の考える相場価格帯より200万円は高く感じてしまった。確かに車としてはいいレベルにあるものの、527万円って中古マンションでも買えそうな高級な価格帯だ。最も日産としてはこの価格帯の商品を全く更新してこなかったのでようやくお薦めできる新商品が出たという感覚かも知れない。
今の自動車販売は、売り手にメリットが大きいザンカザンカの大合唱。それ故、見積書には残価設定型クレジットの案内もある。60回払いで初回を除く毎月23600円。残価は225万円(459.25万円の49%が残る!)、分割払手数料64.6万円(実質年率4.9%)である。
ちなみに、普通のマイカーローンだと実質年率2.1%。ローンミュレータで同じく300万円を60回払いで借りる試算を行った。月々の返済額は52715円。しかし、分割手数料は16.3万円(実質年率2.1%)である。中古車相場の高騰を背景にめっちゃ高いクルマを短期間に乗り換えまくるのも楽しいカーライフの一つのカタチだ。一方で、値上がり傾向が強い新車を購入してそれをじっくり長期保有する(その分最上級グレードを選ぶのもあり)考え方なら、現金、もしくは頭金を確保した上で給与振込先など付き合いのある金融機関でローンを組むことを薦めたい。
話をエクストレイルに戻そう。
G e-4orce(449.9万円)は確かに新型エクストレイルの世界観を忠実に表したグレードであったとしても、お世辞にもお買い得感のある価格設定では無いので、購入を考えるならもう少し視野を広めたい。
まず、セダンやミニバンの乗り換え層で、降雪地帯に住んでいる、スキーが趣味、運動性能にこだわるなど4WDが必要では無いならFFで考えても特に問題は無い。「分厚いワゴン」として有効に機能する。
Xグレードでもプロパイロットが備わるのはノートなどと比べると良心的だが競合車はどれも全車速クルコンや車線維持アシストを持っているのだから、むしろあって当たり前である。Xのメリットはオーディオレスなので用品ナビを選ぶことが出来る。残念ながら用品カタログを見ると純正用品のナビはメモリーナビですら21.8万円という価格である。MOPナビには備わるETC2.0(4.7万円)とアラウンドビューモニターでは無いにせよ、バックモニター(3.7万円)を追加して30.2万というのは余りにも高い。
いっそ、9インチのディスプレイオーディオ(9.9万円)という手もあるが、オーディオレスを活かして社外品のナビを入れても良さそうだ。
Xを選ぶ上で残念なのはMOPの設定がセットだらけで100V A/C電源が単独でMOP設定されていない点である。災害時の緊急使用でトヨタ車のA/C電源が活躍したというニュースから、日産車でも設定が望まれてきていた。ようやく装備されたと思ったら、41万円以上する高価なセットオプションしか選べない。なんと言うことだろう。
このセットオプションに含まれるアラウンドビューモニターもMOPナビとしか連携しておらず、同じ日産の用品ナビと連携していないのも考え方がおかしい。ナビも人気だが、他の単独でも選ばれそうな品目をセットにして価格を吊り上げて客単価を上げようとする下心が明らかである。
そして客単価をどうせ吊上げるなら、エクストレイルの後席快適性を向上させるせっかくのロールシェードや後席独立式A/CをGだけに標準装備せず、XにもMOPで設定してほしい。
営業サイドの巧みな手腕で新型エクストレイルは何も考えないとG e-4orceが選ばれやすいが、本当はXで必要なオプションをきめ細かく選べるようにして欲しい。 - 故障経験
-
試乗しただけの新型エクストレイルで故障は経験してないが、初モノのVCターボは可動部分が多いため経年による故障などの信頼性に関わる部分は未知数である。勿論耐久性が評価されて世に出ているのだが、市場に出れば何が起こるか分からない。その意味で人柱的な部分は避けられない。レパードのNEO Di直噴リーンバーンエンジンやスカイラインのエクストロイドCVTなど限られたグレードに限って新技術を織り込んで徐々に実績を積むやり方も有ったはずだ。私はこの手のエンジンに真っ先に飛びつくことはしないが延長保証・しっかりしたメンテに心がけた方が良い。
そう言えば直接エクストレイルでは関係ないが見積もり待ちの店内で「デフオイル交換」を薦めるポスターを見かけた。BEVだとE/Gオイル交換が不要なために収益確保をにらんで捻り出したカーケアアイテムなのだろう。初回2万km、次は4万kmで交換が推奨され、費用は7500円也。うーん、ちゃっかりしている。
20221108追記:会社の人がエクストレイルを購入したので運転させて貰った。E/Gがかかったかどうか分からないほど綿密に制御されているのは感想文通りだが、全開加速時に車体全体がブルブルと振動するような再現性のある現象があった。「明らかにコレおかしいよ」とアドバイスしておいた。どこかデフなのかユニットなのかが共振しているのかも知れない。この個体だけなら良い(良くない)のだが。
-
1.5 G e-4ORCE 4WD登録済未使用車 禁煙車 ...
449.9万円
-
1.5 G e-4ORCE 4WD純正12.3型ナビ 全周 ...
460.1万円
-
1.5 G e-4ORCE 4WD純正12.3型ナビ 全周 ...
449.9万円
-
1.5 X e-4ORCE 4WDプロパイロット 全周囲カ ...
399.9万円

マイページでカーライフを便利に楽しく!!
最近見た車
あなたにオススメの中古車
-
日産 エクストレイル 純正12.3型ナビ 全周囲カメラ BSM ETC2.0(奈良県)
459.9万円(税込)
-
ホンダ フリード 登録済未使用車(岡山県)
253.8万円(税込)
-
日産 ノート アラウンドビューモニタ(兵庫県)
230.9万円(税込)
-
トヨタ アクア 現行型 寒冷地仕様 全周囲カメラ(北海道)
292.6万円(税込)
注目タグ
ニュース
Q&A
あなたの愛車、今いくら?
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!