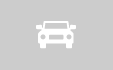- 車・自動車SNSみんカラ
- まとめ
- その他
- RX-7 の秘密を探れ!
まとめ記事

RX-7 の秘密を探れ!

徳小寺 無恒さん
2020/12/19
1,972

あの公害対策の先が見えないクルマに対する絶望感の中、新しい国産車の方向性をスポーツカーという姿で指示したのがRX-7だったのかもしれない。クルマはこんなにも楽しい、単純な乗り物では無いと、公害対策でガスペダルを踏んでも踏んでも走らない青色吐息の国産車の中で希望の光を照らしてくれた。事実、RX-7以降の国産車は、それまでのうっ憤を晴らすが如く続々とワパーを取り戻し、公害対策のデヴァイスがあってもクルマは楽しい時代がやって来た。そしてRX-7も、新しいスポーツカーとしてブラッシュアップしていった。そんな時代の流れを一番表していた初代と2代目迄の「7」の姿を徳小寺的にまとめてみた。
-
久々にロータリーネタをひとつ。 昭和53年3月30日、そのクルマは遂にベールを脱いだ。初代RX-7、SA22の登場だ。 それまで輸出仕様にのみ許されていた「RX」のコードネームが遂に国内にも登場した訳だったが、如何にマツダがこのクルマに期待を寄せていたか、また実際に実力の高い物だったか、その意気込みと熱意が「RX」という二文字に凝縮されていた。 当時の国産車と言えば、公害対策に追われ、どのクルマも青色吐息の状態。踏めども踏めども前には進まず、中古車の世界では「規制(公害)前」というタグが付いたクルマが飛ぶように売れていた。 マツダも「ロータリゼーション」という、全てのクルマを「ローターリー」にするという「妄想」を捨て、 驚異 RE13Bローターリー搭載のバスを君は知っているか!? https://minkara.carview.co.jp/userid/124785/blog/152561/ 軽量でコンパクトでハイパワー、そして、ちょっぴり(かなり)燃費悪し・・・というREを生かすのは、ラグジュアリーカーかスポーツカーだと開眼した最初のスポーツカーが、このRX-7で ...出典:徳小寺 無恒さん
-
公害対策で、もう速いクルマには乗れないんだ。。。と暗雲立ち込めていた国産車の世界に彗星の如く現れた初代RX-7。 シンプルでありながら、ウエッヂの効いたスタイリングは見るからにスポーツカーだったし、実際にも速くて、ソリッドな操縦性はリアルスポーツと言っても間違いの無い存在だった。 しかし、いくらスポーツカーとは言え、劣悪な燃費に、質感の低い内外装や、性能的には問題ないとは言え、商品性的には問題ありのリヤ「アルフィンドラム・ブレーキ」に批判の声が高まった。 昭和53年に登場して以来、初代SA型RX-7は改良の道を邁進する事となった。 まずは劣悪な燃費の改善に翌54年10月29日、それまでの後燃焼方式、つまりサーマルリアクターによる公害対策をようやく捨て、触媒と希薄燃焼による公害対策が為され、それまでの10モード「7.0Km/L」から「8.4Km/L」へと向上した。 昭和55年11月4日には、 ・ボディの大幅な軽量化と意匠の変更、ボディ一体化の樹脂大型フロントバンパーによる空力改善で CD0.36 から 0.34 への向上。 ・ロータリーの肝である「アスペック・シール」の ...出典:徳小寺 無恒さん
-
昭和60年9月20日金曜日。 開発コードネーム 「P747」 こと、よいよ新しいRX-7が七年ぶりに刷新され登場した。 芝にある「東京プリンスホテル」での発表会で、当時のマツダ社長というより「ロータリーの生みの親」として有名な 「山本 健一 氏」は、新しいRX-7を指してこう言った。 「スポーツカーとしてのテクノロジーの追求と、ピュアなスポーツカー市場の拡大への挑戦を目指す」 そして、新しいRX-7は 「自動車文化への貢献を目指したものと思う」 とも自信をのぞかせた。 確かに、ボディメイキングは先代よりさらにスープアップされ、5ナンバーサイズには納まっているものの、よりグラマラスに、そして空力も大幅に改善され、より高級な市場へも十二分に切り込める雰囲気を纏っていた。 先代で提唱した「フロント・ミッド・シップ」レイアウトは継続され、さらにボディの軽量化とバネ下重量の削減の為に、大幅なアルミ部材の使用が為された。 例えばリヤのデフケースも 全てアルミを奢られ、さらに軽量化のみに止まらず快適性の向上を目指して、通常ではサブフレームにもマウントされる構造を、 ...出典:徳小寺 無恒さん
-
この二代目RX-7が登場した際に、盛んに言われたのは、 ポルシェ944に似ている。 という言葉だ。 それを確かめる為に、幾つかの自動車雑誌では、ポルシェとRX-7を並べた画像が氾濫していた。 しかし当時、僕的には、どこをどうやったら・・・と思ったものだ。 確かに、真後ろから見た感じは微妙にテールランプの雰囲気が・・・ とも言えなくは無いが、逆に前から見るとどちらかと言えば、二代目三代目プレリュードの方が、バンパーとヘッドライトのディテールが似ていると思ったもんだ。 RX-7のディテールの醍醐味は、5ナンバーサイズを逆手に取った、全体で「塊感」を具現化している事。 ひとつの塊から余計な部分を削ぎ落とした雰囲気を持っているとは感じないだろうか? だからブリスターフェンダーも全体の中での機能としての必要最小限でしか表現されていないではないか。 対する944は、まずはナローボディがあって、そこにレースカーばりのフェンダーを付足し、それをベースに特に幅方向のボリュームを表現している。言い換えるなら、あたかもブリスターフェンダーが「主」で、ボディそのものが「従」で有るかの ...出典:徳小寺 無恒さん
-
クルマの開発において、特に重要なのは「デザイン」だ。 今でこそ、デザインが販売の良否を決める・・と重要視されているが、昭和の30年代半ばまでは、端的なハナシ「タイヤが四つあって、前にはヘッドライト、後ろには・・・」あればいい、もっと乱暴なハナシになると、まぁ取りあえず「アメ車」か「欧州車」で人気の高いクルマのマネを・・・なんていうレヴェルだったモンだ。 今のクルマのデザインの進め方としては、まぁ多少の差異はあるが、 スケッチを競作して、そこから数案決め、それを実車のスケールダウンしたクレイモデルを造り、さらに案件を絞り、絞った案件のみを実車と同じサイズのクレイモデルを造って比較・・・となるのだが、当時のマツダでは、面白い試みをやっていた。 それがTOP画像のクレイだ。 「?」 と思われたかもしれないが、二案を真ん中でくっ付けたモノだ。 これを社内でプレゼン等をする時には、中心線上に、ボディラインに沿った鏡を置いて、あたかも一台のクルマに見せる・・・という算段だ。 これなら複数案あっても、その案件の半分の数のクレイモデルを造るだけで済むというメリットがあるのだ。 ...出典:徳小寺 無恒さん
イイね!0件
オススメ関連まとめ
-
2016/06/30
-
2016/07/04
-
2026/01/15
タグ
関連コンテンツ( RE の関連コンテンツ )