2008年02月12日

 伯耆安綱の碑を探している時に通りかかった道でちょっと変わった建て方のヤシロを見掛けたので立ち寄ってみました
伯耆安綱の碑を探している時に通りかかった道でちょっと変わった建て方のヤシロを見掛けたので立ち寄ってみました
植松神社
立派な境界の石垣根が有る神社ではないけれど本殿前には今迄見た事も無いような素晴しい竜の彫刻が飾られています
調べれば作者は多分判ると思いますが保存状態があまり良くはないですね
こんなに素晴しい竜の彫刻は後世に残す為にも今の内にコーティングしてあげられたらと思いました
建立当初はコーティングといえば漆の極彩色が主流だったのでしょうがそれを嫌ったのか予算がなかったのかは判りませんが無垢材では痛みやすいのに現在までこの姿を留めているのは大事にされてきた証なんでしょうけど今だったらウレタンコーティングなどで木肌を活かして保護できるのにナァ~
こんな素晴しい彫り物が他の神社や寺にも有るだろうから今後はチョコチョコ立ち寄ってみようかなぁ
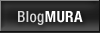
気軽にポチッと押して下さいね
Posted at 2008/02/12 21:29:01 |
トラックバック(0) |
通常日記 | 日記
2008年02月12日

 宗形神社から国道181号を岡山方面に進み伯耆町から大山方面へ向って八郷米の産地である大原千町にこの碑が立てられています
宗形神社から国道181号を岡山方面に進み伯耆町から大山方面へ向って八郷米の産地である大原千町にこの碑が立てられています
ココがホントに伯耆安綱の鍛冶場跡なのかはっきりとした証拠らしい物は出てきてはいないらしいのですが鍛冶場を作る条件は整っています
・鍛冶仕事はかなりの肉体労働なので休憩時に涼める風通しの良い場所が望ましいのですがココは緩やかな丘の上に辺り年中気持ちの良い風が通る場所
・刀の精錬には水が必要ですが地蔵滝の泉を水源とする用水が当時から有った
・当時はまだ当地の権力争いが盛んで、直状の剣より強力な刀が望まれて馬上での戦いに有効でより切れる形状の弓形に反った日本刀を考え出したのでは?
なんて事をこの碑の前に広がる大原千町を見て思いました
住むだけの家を建てるならココに建てたいナァ~と思わせるすばらしい景観です!!
*因みに伯耆、因幡地方は縄文、弥生時代の遺跡数から見ても大陸との交流拠点であったようで青谷上寺地遺跡の出土品からは大陸製鋳造鉄を真似て作った鉄製農工具が発見されています
徐々に鋳造製法から鍛造製法へと進化してゆき、
鍛冶の技術がこの地方に古くから伝承されていたようです
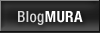
気軽にポチッと押して下さいね
Posted at 2008/02/12 19:39:35 |
トラックバック(0) |
通常日記 | 日記
2008年02月12日

 チョット前に近場に気になる場所がある事を知り天気が良かったのでブラッとお散歩に行ってきました
チョット前に近場に気になる場所がある事を知り天気が良かったのでブラッとお散歩に行ってきました
最初は宗形神社
由緒書きにはこう書かれていますが
コチラの方の説明ではこちらの宗形さんが大本ではないかと推察されています
「米子の宗形神社は古い神社」
「疑い晴らしたスサノオ—2 」
実際に立ち寄ってみると雰囲気のあるいい社です
延喜式神名帳が記された以前より有る1150年以上の歴史有る古社になります
商売繁盛の神様ではないので昨今はあまり寄進がなされていないようですが元々は戦捷祈願、武運長久を願って武家が詣でていたようです
今回は足場が悪く山の上までは上がれませんでしたが時間のある時に山の上に上がって辺りを見渡してみようと思います
どんな景色が見えるかナァ~
元々は北に3町ほどのところにあった社らしいので約300m位北側の現在米子バイパス手前の対面の山の上に社が有ったのでしょうね
そっちの山の上にも上がってみたいけどルートがないんだよね~
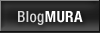
気軽にポチッと押して下さいね
Posted at 2008/02/12 14:54:01 |
トラックバック(0) |
通常日記 | 日記
2008年02月12日

 今朝Dらーへ部品を取りに行ったら見た事ある車がリフトに上がってました
今朝Dらーへ部品を取りに行ったら見た事ある車がリフトに上がってました
そういえば何日か前に交換するってブログに書いてたっけ
クラッチ交換してますます元気になってくださいネェ~
内緒だけどぉ~
I'sスポルトにリアスタビが付いてる拘りなんですよ!
せっかくの青棒、たまには掃除しましょうネェ~(笑)

気軽にポチッと押して下さいね
Posted at 2008/02/12 13:45:32 |
トラックバック(0) |
GC8 | 日記
 近場の気になったトコ巡り 植松神社
近場の気になったトコ巡り 植松神社  伯耆安綱の碑を探している時に通りかかった道でちょっと変わった建て方のヤシロを見掛けたので立ち寄ってみました
伯耆安綱の碑を探している時に通りかかった道でちょっと変わった建て方のヤシロを見掛けたので立ち寄ってみました 近場の気になったトコ巡り 伯耆安綱
近場の気になったトコ巡り 伯耆安綱  宗形神社から国道181号を岡山方面に進み伯耆町から大山方面へ向って八郷米の産地である大原千町にこの碑が立てられています
宗形神社から国道181号を岡山方面に進み伯耆町から大山方面へ向って八郷米の産地である大原千町にこの碑が立てられています 近場の気になったトコ巡り 宗形神社
近場の気になったトコ巡り 宗形神社  チョット前に近場に気になる場所がある事を知り天気が良かったのでブラッとお散歩に行ってきました
チョット前に近場に気になる場所がある事を知り天気が良かったのでブラッとお散歩に行ってきました クラッチ交換ですかぁ~?
クラッチ交換ですかぁ~?  今朝Dらーへ部品を取りに行ったら見た事ある車がリフトに上がってました
今朝Dらーへ部品を取りに行ったら見た事ある車がリフトに上がってました


