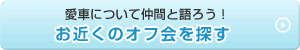- 車・自動車SNSみんカラ
- 車種別
- ホンダ
- ステップワゴンスパーダ
- クルマレビュー
- クルマレビュー詳細
2022年式ステップワゴンe:HEVスパーダプレミアムライン感想文 - ステップワゴンスパーダ
-
ノイマイヤー
-
ホンダ / ステップワゴンスパーダ
e:HEV スパーダ プレミアムライン_7人乗り (CVT_2.0) (2022年) -
- レビュー日:2022年7月9日
- 乗車人数:3人
- 使用目的:通勤通学
おすすめ度: 3
- 満足している点
-
1.オラオラから脱却できたAIRのエクステリア
2.スッキリ整理されたインテリア
3.シームレスで迷いの無いe:HEVの走り
4.運転席から見たスッキリした視界
5.意外に座れる3列目席 - 不満な点
-
1.仕様設定がSPADAありき
2.こもり音の悪さが気になるシーンあり
3.3列目格納時に残るスキマ
4.ドアミラーの二重映り
5.競合より価格競争力が無い - 総評
-
●土俵際で情に訴えかけてみた
あれは1996年だった。たんたらたんたらたんたんたんたん~♪の軽快なメロディとクレヨン画のようなStepWGNのレタリング。写真をコラージュした子供達の映像と共にSTEPWGNの文字だけのアニメーションが走り回るTVCM。最後の小さく実車の写真が映ってナレーション「ステップワゴ~ン、ホンダァ~」で締めくくる。

当時のセミキャブミニバンの常識を覆すパッケージングを纏って初代ステップワゴンは登場した。
確かに宣伝も良かったが、ステップワゴン自体も良かった。当時のホンダが出来ること出来ないことをしっかり把握した上で、当時のホンダが出来る範囲でスライドドア付きの本格的なミニバンを作った点が革新的だった。

私は幸運にもちょい乗り含めて初代から旧型まで運転した経験があり、今回は最新型のステップワゴンにも試乗することが出来た。(3代目は私のチョイスで実家のファミリーカーにもなった)
新型ノアの感想文でも触れたとおり、このクラスの覇者はトヨタだが更にモデル末期の日産にも負けているのがホンダのステップワゴンである。
先代ステップワゴンの苦戦の原因は初期のダウンサイジング過給E/Gが理解されず、初期スパーダのデザインが優しすぎ、わくわくゲートに原価・質量をかけた割に見た目で損をした、といったところだろう。
そこでマイナーチェンジでフロントマスクを変更してまでモーター主体のハイブリッドi-MMD(現在のe:HEV)を追加して巻き返しを図ろうとしたが、結果は上記の通りである。
新型ステップワゴンは「#素敵な暮らし」をグランドコンセプトにした開発思想は「安心×自由」。
ミニバンの基本価値である「空間の広さ」「利便性の追求」に加えて「安心と自由を感じるデザイン」でまとめ上げた。
具体的に見ていくと、歴代モデルの中で最も大きい全長4800mm級のボディサイズを得て室内長2845mmを確保。さらに車幅も初めて小型車枠を超えて1750mmとなった。室内長だけを比較すれば実は先代の方が広い(ただし、メーターバイザーを前方に置いただけ)が、室内幅や高さを考慮すればHonda史上最も室内が広いのだそうだ。

後発ながらミニバンの代名詞として小説にもなったオデッセイ、上級ミニバンとしてエリシオン、ストリームやクロスロード、ジェイド、エディックスなど数々の多人数乗車モデルを生み出してきたが、結局最後に残ったのはステップワゴンとフリードであった。
フリードがミニバンエントリーモデルであるなら、オデッセイは上級モデルの代替需要にも応えねばならず、上級化シフトは仕方がない面もある。4830mm(スパーダ)という全長はデリカD:5や最終型のエスティマとサイズが近い。競合するノア・ヴォクシーは全幅は1700mmを超えたが全長は5ナンバーサイズに留めている。ステップワゴンはe:HEV搭載の為のスペース捻出も兼ねて大胆に大型化している。

エクステリアデザインは標準仕様のAIRとワル系のSPADAの2系統がある。総じて誰かを驚かせたり威圧する為のデザインからは一線を画してスッキリした。特にAIRは優しいデザインが私の好みだ。

実車に乗り込んでみれば、配置関係に先代の影を感じるものの最近のホンダの設計思想であるスッキリしたノイズレスな視界が実現。乗って気づけた人には絶対に気に入ってもらえる魅力だと思う。問題は指摘されないと一般的な人には分かりにくいマニアックな工夫である点であることでセールスマンのアピールが必要。

2列目にオットマンやロールシェードを設けてLクラスミニバン的な世界を垣間見させるが、特にシートが大きめでヘッドレストが頭を包み込む様な形状になっているのは魅力的。そして2列目シート位置を快適な位置に合わせても3列目スペースが残された点も評価できる。また、ヒップポジションの段差を先代よりも大きくしてパッケージング的にアップライトに座らせただけでなく3列目の視界確保にもメリットがある。
初代が持つ道具感は感じられないが、AIRは趣味の良さが光る。そのセンスは初代に近い。
パワーソースは先代のキャリーオーバーなので大きな印象の違いは無く、1.5L直噴ターボとアトキンソンサイクルの2.0L+モーターによるe:HEVの二本立て。ガソリン車のみ4WDが選べる。営業マン曰く、ガソリン車を買うお客さんは大抵後でガソリン代を気にしてハイブリッドを選んでおけば良かったと言う事例が多いそうで、積極的にe:HEVを薦めるようにしているとのことだ。e:HEVに試乗したが、プラットフォーム継承版ゆえに競合車が成し遂げたほど世界が変わるほどの劇的な進化は感じられなかった。しかし、まだe:HEVが持つ魅力は色褪せておらず競合性はあったe:HEVが持つモーター主体の走りは特に発進後、E/Gが掛かり始めるまでの時間が長く、電動感が強い(E/G始動がバレにくい)のが特徴。動力性能的に十分以上の実力を持ち、操縦性もミニバンとしてリーズナブルな範囲内。

静粛性は3列目を中心に手当をしたとのことだが、走り始めて割合に速い段階でタイヤの音が目立つのは近年乗ったホンダ車に共通する特徴。ステップワゴンはソフトながら道路の凹凸を拾ったり、E/G回転が低い場面でこもり音が目立つと感じるシーンが多かった。ノア・ヴォクシーに対してこの点で負けていると感じた。
発売後、大本営発表であるが一ヶ月間の受注実績のプレスリリースが存在する。既に2万7000台の受注があったという。競合するノア・ヴォクシーは3万5000台(正確には2ヶ月で7万台)受注があったとされるので決してランキングで勝利したわけではないが、これは健闘したと言える。
記録が残されている過去のモデルが一ヶ月間に受注した実績を列記したい。
2005年3代目:2.0万台
2009年4代目:1.8万台
2015年5代目:1.5万台
2022年6代目:2.7万台
こうして比較すると、ステップワゴンとしては良い滑り出しのように見えるが、新型は1月から異例とも言える長期のティーザーキャンペーンを展開し、予約受付台数が過去のモデルよりも長い点は有利に働いている事は心に留めておきたい。ただ、値引きも期待できない初期の段階で注文するユーザーはそれだけ新型のスタイルに惚れ込んていると言うことは想像できる。
プラットフォーム流用のため革新より熟成に重きを置くしか無かった新型ステップワゴンだが確かに力作である。オラオラ系とかエモーショナルに飽き始めた私の目線では先行したノア・ヴォクシーには無いものを持っている。しかし、せっかくスッキリしたAIRの存在感をアピールしていながら、実際はSPADA頼りの仕様設定は商品としての選択肢の幅が足りていない。
先程挙げたプレスリリースに拠れば新型のタイプ別構成比は
AIR(ガソリン7% e:HEV8%)
SPADA(ガソリン20% e:HEV35%)
SPADAプレミアムライン(ガソリン6% e:HEV24%)
とAIR構成比は15%しか無く、台数にして4050台だ。例えば4代目の場合45%(8100台)、5代目の場合31%(4650台)が非エアロ系であった。力を入れたと豪語するAIRとしては、寂しい台数では無いか。その原因は、AIRの仕様設定にあると私は指摘したい。「脱・オラオラ」に惹かれた潜在的オーナー候補を取りこぼして居ないだろうか。とにかく早急なAIRのプレゼンス向上策が必要だ。
- デザイン
- 4
-
●エクステリアデザイン
新型ステップワゴンのエクステリアデザイン、初代・2代目のような使い勝手を潔く表現した箱スタイルを改めて取り戻した。3ナンバーによって余裕が出た寸法を使ってモールやプレスラインで流れを表現せずに面の張りで温かみや品質感を感じさせる方向性である。

FFだった初代のように鼻を強調しているが実は初代はヘッドライトが大きかったり、E/Gフードがスラントしている。初代をオマージュしながら実はフロントマスクの本当のモチーフは2代目後期だと思われる。タイトル画像と比較してみてほしい。

AIRは親しみやすいアクリル製のUPRグリルとMID・LWRグリルの3段構成であるがツルンとしたバンパーの面を見せておりギラギラした威圧感とは縁遠い。SPADAはUPR・MIDグリルが統合されて堂々と見せているメッシュ形状のLWRグリルとは分割させて「顔中がグリル」というグロテスクさからは一線を引いている。

LEDライトはデイライトつきのLEDが標準となっており、シビックやヴェゼル同様にLOビーム時はライト中央が黒く見える「黒目」ライトになっておりホンダのテイストを残している。失礼を承知で書けばVWのようなスッキリしたイイモノ感が漂っているというと褒めすぎだろうか。
サイドビューはロングルーフかつ水平基調でステップワゴンらしさを十分表現できた。ただし歴代のサイドビューと比較するとFrオーバーハングが長く、不格好だ。歴代ステップワゴンのオーバーハングも特別短いわけでは無かったが、ヘッドライトやツートンカラーの見切りを使うなどしてノーズを軽く見せていた。寸法的にオーバーハングが長いわけでは無いが、例えば「ほうれい線」を入れる様な錯視効果でオーバーハングを短く見せず、敢えてのシンプル化が仇でとなってオーバーハングが強調された。e:HEV搭載スペースを死守しつつテーマ的にシンプルを重視した結果だと考えられる。
水平基調のベルトラインは歴代よりも高い位置に引かれて守られる安心感を確保。グリルや車体下部のメッキモールで引き締めた。シンプルな面に3代目オマージュ?のスカシカシパン風アルミホイールが懐かしい。縦型Rrコンビランプも初代・2代目ステップワゴンらしさをしめすアイコニックな部分だ。

この様に新型ステップワゴンのエクステリアデザインは初代と2代目を意識しながらも決して懐古趣味ではない。例えばヘッドランプ上やバックドアガラス下端のメッキモール、SPADA専用のバンパー下端とサイドシル部をぐるりと囲ったメッキモールは、やり過ぎない範囲で高級感がある。華やかさを追い求めるあまり面積の大きなメッキ部品を奢ると、メッキ費用がかかる割に逆に安っぽく見えてしまう。最小限にさりげなくメッキを使うからこそ光り物の有り難みが強調されるのだ。

個人的にステップワゴンのエクステリアデザインには好感を持っている。しかしながら、オーバーハングの長さ以上に許せない部分も存在する。実はSPADAはRrバンパーを大きく見せるためにリフレクターをコンビランプに内蔵してバンパーの分厚さを強調している。しかし、実際の寸法自体もバックドア下端のG/Nの張り出し量を増やして大きいのである。

この変更は安全性の観点で大きな差となって現われる。それは隣車線の車両を検知して車線変更時に死角に存在する車両をミリ波レーダーで検知するブラインドスポットインフォメーションが装着できるか出来ないかを左右しているようなのだ。高速道路のみならず活躍する場面が多いブラインドスポットインフォメーションはあって当たり前の装備だ。警報音を鳴らさなくても光るだけで他車の存在を認識できるし、逆に追い越す側の他車のドライバーも「自車が見られている」と認識できて安心感が桁違いだ。例えば軽自動車やコンパクトカーから買い換えた運転に不慣れなドライバーが新型ステップワゴンを運転する際にはあった方が断然良い類の安全装備だと私は思う。しかしながら、AIRにブラインドスポットインフォメーションを装着できない意匠で開発が進められたことは残念である。
せめてメーカーオプションで設定しておくべき装備だとは思う。最初からスペースを見越して意匠開発を進めていなければならない。残念だが、AIRの安全性を軽視してレーダー搭載の検討を見落とした。最初から意匠に制約をかけていればスタイリスト達もその範囲内でAIRの意匠を完成させたに違いない。(それが普通)
AIRを廉価版に見せない為にフォグを採用した、なんてネット記事を目にしたがそれこそが顧客を甘く見ているし、トヨタが先代ノア・ヴォクシーで読みを誤って失敗した事を忘れているのだろうか。そもそも安全装備でグレード差をつけるべきでは無い。これは完全に判断ミスである。
●インテリアデザイン
新型ステップワゴンはデザインに力が入っているが、インテリアもまた同様である。

インパネは先代の配置関係をベースにミニバンらしく縦方向の寸法を使ったボリューム感のある物となった。競合のノア・ヴォクシーの場合、低めに着座させただけで無く、インパネもボリューム感を落としたことと比べるとしっかり棲み分けが出来ている。ステアリングの正面にはシビック譲りの10.2インチフルTFTメーター。インパネ中央には11.4インチナビが装着できるスペースが確保されている。中央部分はシフトレバー(e:HEVはエレクトリックギアセレクター)、オートエアコンの操作パネルが集中配置されている。そして高さのあるインパネの表皮はシート表皮と同じものが貼られている。インパネ素材自体は硬質樹脂の特にソフト感のある材質では無いが、目に入りやすい位置に表皮が貼ってあるのでアイキャッチ性は抜群だ。
そしてインパネから繋がってドアトリム、スライドドアトリムに至るまで連続的に表皮が貼られているのは初代・2代目のインテリアのオマージュを感じる。初代ステップワゴンで育ったであろうターゲットユーザー達の心にも刺さるはずだ。

ちなみに2代目ステップワゴンだとバックドアトリムも生地が貼ってあったので、LPL(開発責任者)が同じようにバックドアトリムも生地を貼ろうとしたところ怒られてやらせてもらえなかったという。
新型ステップワゴンの空間デザインは見晴らしの良さ、乗り物酔いのし難さに配慮した点がポイントだ。この目的の為に運転席の視界を整理してワイパーをカウル下に押し込んだかと思えばE/Gフードを持ち上げて車両感覚の掴みやすさを向上させた。
ミニバンの定石である階段状のヒップポイント差を更に強調して着座位置を整理し、視界に入る1列目。2列目シートを削って圧迫感を低減している事に加えてドアトリム断面に水平面を設けて水平視界を強調して居心地の良さを磨いている。
個人的にはAIR系の明るいインテリアカラーと優しい手触りのシート生地にグッと惹かれた。新型ステップワゴンと言えども完璧では無いが、最近の新型車の内装やシート生地がどんどん安っぽくなる中で久しぶりに内装が良いなと思えるミニバンが表れてくれて嬉しく思う。
ちなみに面白いのは、車椅子仕様車のRrフロアがフローリングになっている。フローリングフロアと言えば3代目ステップワゴンで採用されたあの名物装備である。参考までに通常仕様にも純正フロアマットの中にフローリングタイプというキャッチーなバリエーションがある。
新型ステップワゴンのインテリアデザインはハイセンスなモノを感じた。やはりスッキリ整っている景色は気持ちがスッと穏やかになる。家族を乗せて移動するファミリーカーだからこそ余計な雑音が目に入らない空間デザインは価値があるだろう。 - 走行性能
- 4
-
●走行性能
今回、ガソリン車の試乗車を探したが存在せず、今回はe:HEVのスパーダプレミアムラインと標準のSPADAにしか試乗できていない。個人的にはAIRに試乗したかったのだが今のところ展示車しか見当たらない。

黒一色の運転席に座る。ドラポジを調整するがチルトステアリングの調整幅から想定している着座姿勢は少々低めで先日乗ったノアよりもわずかにヘッドクリアランスに余裕があり、こぶし4つ分。(ちなみに2列目3.5個、3列目3個である)ノア・ヴォクシーより全高が低いがヘッドクリアランスがあると言うことは、人が座るヒップポイントが低めだと言うことである。着座姿勢が低めだからなのかステアリングのオフセット感は小さく気になる事は無い。それでいてミニバン的も感覚はあるのは良い。
スタートスイッチを押し、シフトレバーの代わりに存在するエレクトリックギアセレクターのDボタンを押せば走り出すことが出来る。EPBはもはや2022年としては当たり前装備であり、HOLD機能のボタンを押しておけば停止のたびに駐車ブレーキをかけてくれる。
走り出して25km/hを超える段階でゴーという音が聞こえはじめて「ああ、最近のホンダだな」と変に納得してしまう。ノイズレスな視界もホンダイズム、走り出してすぐタイヤの音が聞こえてくるのもホンダイズムである。

ステップワゴンではそこに路面入力こもり音が付加される。ノアは意外と(失礼)こもり音が目立たなかったのでこの部分は不利になる。ついでにNV性能で言えば、E/Gがかかっているとき(低開度40km/h)も、こもり音が認められる。オーディオをかけていたり、会話に集中していたら気づかないレベルなので発音部が多いミニバンなら許そうかなと思うレベルにはある。どこかの競合車のように常用域でブルブルステアリングが震えるような失態は無い。
e:HEVはモーター主体のハイブリッドなのでE/Gが起動するタイミングがトヨタ比で速度が高いので他の騒音に紛れてE/Gがかかるため、起動時の音や振動が目立ちにくい。そしてモーター主体である分だけアクセル操作に従順で操作に即座に反応するモーター駆動の良さが分かり易い。このあたり、今HEVの方式としてトヨタのシリーズ・パラレル式、日産のシリーズ式に加えてホンダのシリーズ式(直結モードあり)、スズキが採用するパラレル式(ホンダも旧IMAではパラレル式を選択)があるが、今はハイブリッドで盛んに技術競争が繰り広げられているのでクルマ好きの方でも技術好きな方なら楽しめるのはないか。

アクセルを強めに踏み込むとE/Gが始動し、バッテリーとE/Gによって発電された電力でパワフルに加速する。状況の良い幹線道路の信号ダッシュではE/Gが高回転側に張り付いたままパワフルな加速を見せる。しかし、その挙動は常識的で先代に見られた過剰感が無くなっている。過剰感なのであっても使わないので別にかまわないのだが。強加速時は必ずE/Gが起動する為、EV感は確実に目減りする。音質はTNGAの酷い音と比べるとマシではあるが、もう少しE/Gが遠いところにある感じだとステップワゴンには相応しいと私は思う。特にステップワゴンだけでホンダのLクラスミニバンの買い替え需要をカバーしなければならないからだ。もちろん一般的な市街地走行ではモーターで発進してバッテリーのSOC(充電状態)が不足してくるとE/Gをかけて充電を行うがそんな場面でも際立ってうるさいというわけでは無い。
営業マン抜きで試乗できたので、普段余り試乗では走らない淡々とした対面通行のBPを走らせた。流れに乗って巡航で走らせるとホンダ特有のエンジン直結モードに入る。これはマニュアル車のハイギア相当の固定ギア状態で走るモードでそこから加速したり上り坂に入るとすぐにハイブリッドモードに移行してしまうが、このモードの存在感がe-POWERとの差であり強みである。せっかくE/Gを積んでいるのだから魅せ場を残してくれるのはホンダらしさか?
ホンダセンシングが着いており、ACCやLKASを使うと準自動運転感覚で走ることが出来る。ヴェゼルでも同様にトヨタの類似システムより扱いやすく制御が自然である。例えばフリードからの買換えなら広さだけでは無く走りの良さでも感動できる。高速道路でも失速感やE/Gが高速域に張り付くこと無く走りきれるだろう。

16吋を履く標準車カーブが連続するコースも走ったが、ステアリングの応答が曖昧に躾けてあり、コーナリング中に修正舵を入れるケースが多かった。ミニバンは転覆性能云々もあるが、敢えて緩慢味付けにしておくことが常識である。私もさほど腕に自信があるわけでは無いので、一発で舵角を決められず、じわじわ手応えを見ながら曲がり始めると、操舵が足りず追加操舵が必要になってしまったり、追加操舵が余計ですぐステアリングを戻すような下手くそ運転になってしまった。
この曖昧さは高速道路を長距離クルーズするときにはメリットとして表れると思われる。実家のクルマがこれだと、埼玉への帰省の際、カーブが緩い用賀までは良いが都心環状線に入ったら忙しいかな…と頭をよぎった。ところが今は圏央道でパスするから首都高は使わない。頭が平成で止まっているようだ(せめて中央環状線使えよ)。
市街地の交差点の右左折では特に問題は無いのでご心配なく。
乗り心地は大変ソフトな方向性で家族の為の車という観点で正しいと思う。私の好みだけで言えばももう少し締め上げて良いのでフラットな乗り心地と回答性を上げたシャシーが欲しいが、そういう車は私は3台くらい家にあるので、新型ステップワゴンはこのままで良い。(ホイールサイズの差異は特になし)
新型ステップワゴンを走らせてみた感想は、2Lクラスのミニバンとしては十分余裕がある。静粛性や乗り心地は100点は着かなくても80点は十分つけられる。例えば新東名の120km/h区間を制限速度で走らせてもリラックスして走れるだろうし、名阪国道の天理~福住間を走らせても飛ばしすぎなければ家族と怖い思いをすることは無いだろう。ただ、夜の首都高速の都心環状線をぐるぐる流れに乗って周りのタクシーと同じ勢いで走ると少々ステアリングが忙しいかもな、と言う感触だ。
商品性としてみた時に先代が持っていたe:HEVの活発さはややマイルドになった点は気になる。まだ電動感は残るものの、競合は新P/Fや(うるさいけど)高効率な燃焼技術で飛躍的にホンダを追い上げてきており、ステップワゴンの優位性が脅かされつつある。ジャンプアップが期待できない点がP/F流用のFMCの弱点である為、仕方が無いのも理解は出来る。(だから感性に訴えるというか洗練を指向しているのだ)
ステップワゴンがオデッセイやエリシオンの領域をカバーしようとするなら、絶対的な動力性能はこのままだとしても急加速時のE/Gノイズがもう少し遠くから聞こえるようになると素晴らしい。
私だけかも知れないが、要改善点が2点。まず、ドアミラーの像が二重写りしている。当初は自分の目が悪くなったのかと錯覚したほどだ。

もう一点はスイッチ配置に問題がある。ディーラーに帰着して注射する際にRレンジとEPBのスイッチが隣り合わせに存在し、間違えて操作しそうになった。シフトスイッチ自体はPとRとDを押し間違えるような事が無いように配慮があるが、EPBスイッチが隣接すると、目視作業ならまだして手探りでのスイッチ操作は両者が紛らわしいので注意されたし。マシン・ヒューマン・インターフェースに対して配慮不足だ。

走行性能をまとめると、新型ステップワゴンはミニバンとして十分な走行性能、NV乗り心地性能を持っていた。競合の追い上げもあるがレスポンスの良い電動走行が楽しめ、競争力はある。 - 積載性
- 3
-
●積載性
居住性はミニバンである以上、セダン・ハッチバックより良いことは当然、強力なライバルと比較すると長い全長を活かして3列シートまで使い切れる点がステップワゴンの売りとなる。運転席は当然広々としており、2列目はホイールベースの中央に位置して最も揺れが少ない玉座だ。ちなみにCRSを取付ける機会が多いことを反映してキャプテンシートが標準で8人乗りとなるベンチシートはオプションである。

この2列目シートは大きさも昔の常識では考えられないほどたっぷりしたサイズで大人が着座できる。またヘッドレストには頭を乗せたときにソフトな食感と居眠りしてもヘッドレスト両サイドに2代目アコードの助手席シートのような出っ張りがある。ここが頭をホールドしてくれてより一層リラックスできる。

SPADA以上はオットマン、プレミアムラインにはシートヒーターが備わるが、個人的にはAIRの素のシートでもたっぷりしたサイズの魅力は残るし、フロアにフットレスト的なキック形状が作ってある為、ロングスライドシートレールの弊害である足首の角度が大きくなりすぎる欠点を多少緩和している。ここに脚が来るようにシートの前後位置を調整してやれば気持ちよく座れる。

観光バスのようにシートバックテーブルはあるしUSBケーブルも挿せる。更にロールシェードも着いて至れり尽くせりの2列目である。新型ではロングスライドを稼ぐ為に横スライドを新しく追加し、2列目シートを内側に入れると865mmのロングスライドが出来るそうである。このあたりは各社が下らない数字遊びに夢中であり、トヨタは810mm、日産は690mmで今はホンダがトップである。ただし、この数字が大きいからって偉くも何ともない。
現代の集団よりも個を重んじる時代のミニバンと言うことで一人一人のパーソナルスペースを空間を確保したい。そして2列目と3列目のコミュニケーションを取りやすくする、という触れ込みでロングスライドを活用して互い違いに座るアレンジがカタログ内で紹介されていた。私はこれを見て2004年に発売されたエディックスという懐かしいネーミングを思い出した。3人掛けシートを前後に備えた変則的6人乗りMPVであったエディックスもセンター席を一段下げることで広々感と適度なプライバシーを確保できると謳っており、その思想が隔世遺伝的に新型ステップワゴンでも活かされていた。

ポイントは3列目にある。ステップワゴンの3列目は4代目以降「マジックシート」と呼ばれる格納機構を採用していた。ミニバンの3列目の処遇は大抵畳むことに注力されがちである。子供が3人未満の核家族が多いので3列目の使用頻度が高い我が国ではレジャー用の荷室スペースとして活用したいニーズが古くから存在する。
海外のモデルだと脱着式(外したシートはガレージで保管)という潔い事例もあるが、我が国では住宅事情(車庫事情?)が悪い為、跳ね上げる、座面をチップアップして前にスライドさせる、2列目の座面下に潜り込ませるなど様々なエンジニアの技術力が3列目の収納に費やされてきた。
ホンダの場合は当初は跳ね上げ式を選択していたが、Rrフロアパン深い掘り込み形状にシートを押し込む事でフロアと面一の荷室を確保できた。特に跳ね上げ式よりも荷室幅を取りやすく大きい荷物を積みたい人に向いていた。このRrパン格納式とも呼べる機構は初代オデッセイが先鞭をつけている。3列使用時は深いRrフロアによって日常的なラゲージスペースを確保し、格納時はバンパーレベルでフラットな荷室にスペースアップできる。

新型ステップワゴンはフロアもカーペットで覆われており気軽に荷物を放り込みやすい。ただ、角部にタッカー留めの貧乏くさい点がある点は少々興ざめする。また欠点とまでは言えないが3列目収納時に荷物を搭載する場面で乗員の頭が来る位置を脚で踏みつけるのは少々抵抗がある。そのために折りたたみ式のカバーあるのだが、それもペラペラでサイズもギリギリシートを覆う程度しかないので気になってしまった。純正アクセサリーでソフトトレーの設定もあるが3列使用時と両立できてない。その当たりの使い勝手はもう少し検討した方が良い。

また、Rrパン格納式3rdシートには弱点がある。それはシートの形状が車体形状に左右されて薄く平板で小さなものになりがちな点だ。実はRrパン格納式4代目以降のステップワゴンや最終型エスティマが採用していたが、ミニバンとしては信じられないくらい3列目を軽視したシートだと感じていた。最終型エスティマはスタイル重視の「ミニバン界のカリーナED」だと思ったのでまぁ目をつぶるとしても、正統派ピープルムーバーの装いだった4代目ステップワゴンの3列目として個人的に許せなかったのでスペシウム光線で破壊したいくらいだった。確かに3列目格納時の荷室の広さは魅力的で、中学時代の同級生は4代目ステップワゴンの3列目を維持しつつ2列目を外してバイクを積み込んでオフロードを走らせていた程だが…。
競合車ではノア・ヴォクシーやセレナが今なお左右跳ね上げ式を選択している。彼等はシートの座り心地をよく出来るタイプながら、荷室容量減を嫌ってかなり薄く、平板なシートにしている。あくまで緊急用なのだからと言うエクスキューズが聞こえてくるようだ。ステップワゴンの場合、3列目もキチンと使えるようにシートサイズを拡大し、シートの厚みを増やすという競合とは別の方向に進んだが多人数乗車がウリのミニバンとしてはむしろ正統派とも言える方向性である。
座ってみると進化を感じる座り心地に大変感銘を受けた。ショルダー部が大胆に削られているからホールドが全くないかと思いきや、私の体格だとそれなりに体重を支えてくれる。素晴らしいのはヒールヒップ段差を大きく取ったのでアップライトに座れて姿勢が崩れずにキチンと座れる点である。

この点、尻が前にズレがちなノア・ヴォクシーより真面目に感じる。元々ノア・ヴォクシーは3列目使用時のレッグスペースが不足気味で、ここを満足させようとすると2列目をかなり前に出さないとレッグスペースが取れない。
3列目に座る同乗者に気を遣わせずに見晴らしの良さも提供できる新型ステップワゴンの3列目は、そこに座ってもらうことの罪悪感がかなり小さくなっている。もちろん全長の違いゆえ、元々ステップワゴンが有利であることは事実だが、それを補って余りあるパッケージング面の進化をこの3列目に感じた。
ただ、苦言を呈するなら格納式ヘッドレストのアゴが巨大すぎて私の場合、首元と言うべきなのか背中の上の辺りにヘッドレストが接触して不快である。せっかく接触するなら拡大したとは言え、小振りなシートバックの不足分を補完するような形状にしたら良いのでは無いかと私は思う。 - 燃費
- 3
-
●燃費
今回の感想文を書くにあたり別々のシーンで2台のステップワゴンで車載燃費計の数値を確認した。市街地メインで試乗すると15km/L、郊外の信号の少ない道路をまとまった距離を走らせてもらうと18.4km/Lという結果であった。
実家で2Lミニバンに乗っていた時の感覚では2倍燃費が良くなっており大いに驚くべき数字だ。先日、仕事で2014年式のヴォクシーHVで遠出した際は16.5km/Lが出たので、最近のハイブリッドミニバンの燃費改善効果は高い。

燃費向上に対応して燃料タンクの容量が52Lと初代の65Lと比べて小さくなっている。初代はカタログ燃費が11.2km/Lなので728km位の脚の長さを持つ。新型のe:HEVの場合、18.4km/L×52L=956.8kmという飛躍的な航続距離の長さを誇る。ガソリン車で計算すると、13.9km/L×52L=722.8km/Lと実質的には実用性を損なうほどの容量削減にはなっていない。
今後、e:HEVメインになってくると40Lタンクなどが視野に入ってくるかも知れない。車重を軽くする手段としての燃料タンクの容量削減は常套手段だ。
ガソリン車とe:HEVの損益分岐点がどこなのか、ノアの感想文の時と同じように一般的なユーザーのケーススタディを行う。
1.5Lガソリンターボと2.0L_e:HEVの価格差は38.4万円である。(参考:ノア35万円)
保有年数7.1年でレギュラー160円/Lとし、実燃費はe燃費より旧型車の達成率を調べた。
ガソリン車が83% e:HEV車が87%であったのでこれを踏襲する。AIRのカタログ燃費はガソリン車が13.9km/L、e:HEV車が20.0km/Lであるため、実燃費想定値は11.82km/L、17km/Lとなる。
計算してみると85175km程度走行すれば、価格差をガソリン代で相殺できる。これを年間走行距離で表現すると11574kmとなる。(ちなみに排気量が異なることから自動車税額差も考慮すれば12750kmになる)
ノアの感想文でも示したが日本自動車工業会の調査によると一般的なユーザーの年間走行距離は4440kmであることを考えると、ハイブリッドを全員に薦めるものでもないように私は思う。
ステップワゴンのe:HEVに対して上級エンジン的な魅力を感じるなら積極的に選んで良いが、コスパで決めるならガソリン車も意外と捨てがたい。購入希望者はしっかり考慮して欲しい。
- 価格
- 2
-
新型ステップワゴンの価格は下記のとおりである。


スタート価格が299.8万円と先代の228万円から約72万円もアップしている。これは従来型にあったエントリーグレードBが廃止され、Gに相当するAIRがエントリー価格を受け持つからである。またカーテンエアバッグやホンダセンシング、LEDヘッドライトが標準装備されたAIRは「単なる廉価仕様」「SPADAのベース」ではなく、非エアログレードのプレゼンス向上を図る為に仕様強化が図られている点が従来から異なる点である。
ホンダだけに限らないが、我が国の自動車販売は古くから標準モデルに対してエアロパーツを装着したり、ダークカラーの内装やローダウンサスなどが装着されたワルっぽい差別化仕様が好まれる傾向にあった。それは人とは違う仕様を求めるユーザーニーズと販売価格上昇によって収益向上が両立するWIN-WINの施策としてエアログレードとして継続的にラインナップされて事実、選ばれてきた。
ホンダでも「カスタム」「SPADA」「アブソルート」と言ったエアログレードが設定されて標準モデルとの差別化を推進してきた。ところがいつしか車名を代表するグレードがエアログレードであることが当たり前になった。ステップワゴンの場合、初代ではエアロ付きでもカジュアルな雰囲気を残していたが2代目のマイナーチェンジで「SPADA」が登場。デビッド・ボウイの楽曲は今でも耳に焼き付いている。エアロパーツやダーク系のインテリアはちょっと大人びた感覚で「家族の圧力に負けてミニバンに買換えさせられるも、ちょっとした反骨心を感じさせる」点も魅力的なのかも知れない。
3代目では一転してSPADAは廃止され、エアロパーツはSパッケージというパッケージオプション扱いになった。ところが3代目は商業的な支持を得られず、テコ入れで後期型でSPADA復活となった。もう、こうなったら後はSPADA頼みだ。4代目・5代目とSPADAに注力してエアロが着かない標準グレードは「SPADAのベース」扱いになってしまった。
ホンダ自身もこれではまずい。非エアログレードを単なる廉価仕様にせずしっかりしたキャラクターを与えようとしたのがAIRなのである。ステップワゴン史上、標準グレードにサブネームがついたのは初めてである。

AIRはホンダセンシング(衝突軽減ブレーキ+ACC+LKAS+AHBなど)、フルLEDヘッドライト、EPBなどは当然の事として空気清浄機能付き左右独立式オートA/C、両席パワースライドドア、16インチアルミ、LEDフォグライト、10.2インチフルTFTメーターなどが標準装備されている。競合車の装備表と見比べても「廉価グレードではない」と主張する根拠は良く伝わる。
次に、AIRよりワンランク高いSPADAの装備を見てみよう。

AIRに対してエアロパーツや合皮のシート・トリムに変わるだけでなく、本革巻きステアリング、パドルシフト、Rrオートエアコン、オットマン、パワーテールゲート、アクティブコーナリングライトなど安全にかかわる装備や2022年のミニバンとしては一般ユーザーが欲しがる装備が標準装備されている。最初から標準装備とすることでオプション商法から脱却を図ろうとしたのかもしれない。
そしてSPADAにはさらに上級のプレミアムラインが存在する。オデッセイやエリシオンの穴を埋めるべく設定されたフラッグシップグレードである。

17インチホイールやRrシートヒーター、アダプティブハイビームなどの上級装備が追加される。
個人的には新型ステップワゴンの仕様設定には大いに疑問を感じている。AIRとSPADAは見た目だけの装備差にしてエアロパーツ代を販売価格に上乗せすべきだったと私は思う。事実、トヨタはそうしているではないか。SPADAのオラオラを抑えたエアロも魅力的だ。しかし、Rrオートエアコンだけが欲しい人も現状ではSPADAを選ばざるを得ない状況は健全とはいいがたい。慢性的なホンダの「高価格設定病」よりも社内で既に「これまでの標準モデルにあった『エアロを外した安い方』という見方を直したかった」という想いと仕様設定がリンクしていない整合性の無さに問題があると私は思う。
例えば、AIRとSPADAを本当に見た目装備だけの差にしてお気ながら、後はオプションで欲しいものを選ばせ、AIRにもプレミアムラインを設定すれば良かったのではないか。個人的にはAIRに本革巻きステアリングとパドルシフト(減速セレクター)、ブラインドスポットインフィメーションが欲しい。
触感に関わる装備や安全に繋がる装備でSPADAとの差をつけたことは理解に苦しむが、NBOXも標準車とカスタムで同じようなことを行っており、そろそろ目を覚まして欲しいと願うばかりだ。
むしろ、価格設定上の客寄せパンダが必要ならAIRとは別に廉価グレードを設定すれば良かろう。ガソリン車のみの設定でフォグを外し、鉄ホイールを履かせ、片側スライドドアにして、ヴェゼルの7インチディスプレー付きメーターと廉価表皮にしたような「Bグレード」でも設定して税込289万円とでもやれば良かったのだ。その方がよっぽど話題性もあるのではないか。(本当はノアXと価格を揃えるべきだが)
それをやらないのは客単価を下げたくないだけでなく、作り手の都合(仕様数を減らしたい、SPADAへ上級誘導したい)が見えすぎていないだろうか。この点、トヨタは結局オプション商法で高くなるとは言え、お客さんが納得して自ら価格を上げていくような施策が取れていてホンダは負けている。別に廉価グレードさえ出しておけばAIRをもう少し高価な設定にも出来ただろうに惜しい。同時期にFMCした競合車の方がユーザーのニーズに合致した仕様を作りやすい柔軟性がある。結果的にSPADA一極集中を招いてしまっている。投資の面でもAIRにかけた投資が勿体ないではないか。(例えばバンパー金型費用や、車両工場ででAIR用の部品を置くスペース、型式指定費用などなど)
最後に、見積もりを頂いた。
グレードはAIRのe:HEV、マッドガード、ラゲージマット、フロアマット、ナンバーフレーム、Rrカメラあんしんプラス3(ブラインドスポットフィンフォメーションの代替品)、ETC2.0発話タイプ、9吋ナビ、コーティングとドア保護フィルムを選択した。
本体価格338.3万円+用品61.2万円(!)+諸費用(点検パックと延長保証)17.3万円で合計416.8万円。先日試乗したノアHEV(概算408万円)と比べると少し割高に映り、先代スパーダハイブリッドの見積額とほぼ並んでしまった。
オーディオレスでカーナビを後付けしなければ標準装備されているナビ装着用スペシャルパッケージが生かせないという点も残念な仕様設定だが、スマホ連携よりベーシックなナビ機能が欲しい、CDが聞きたい私にはこれでも問題ない。競合するノアと価格がほぼ同じなら室内が広く、内外装のセンスが良いステップワゴンにも勝機があるかもしれない。

しかし、総合的に価格設定・仕様設定に関しては配慮が足りない。一層の改善を求めたい。
まずは、SPADAに対して装備が劣るAIRに対してフィットに設定のあるステアリングカバー(本革製)や
別置きオットマン(アクセサリー扱い)などを設定するという、AIRに踏み出せない人の為の施策が必要。アクセサリーカタログを見ていても、ド派手な外装ガーニッシュやアルミホイールではなく、
カタログモデルの足りない部分を補う様な機能部品や、例えばクロスタールックに返信させるボディキット(ノートがうまくやってる)など、ホンダアクセスならではの配慮があっていい。
インテリアデザインの項目でも触れたが3代目をオマージュしたかのようなフローリングフロア風マットも面白いが、N ONEで見せてくれた「ステッカー芸」のアンコールとして初代クレヨン画風STEP WGNロゴもヘリテージアイテムで出してくれても良いんじゃ無いかというのは流石に悪乗りが過ぎるか。 - 故障経験
-
故障と言うほどでは無いが、試乗した複数の個体から内装の異音が認められた。
前後からランダムに聞こえてくるので、試乗くらいなら良いが400万円以上のお金を支払って納車された新車がこれだと文句を言いたくなるかなぁと言うレベルであった。
●おまけ

上の画像はみん友さんからのネタだ。なんと小物入れの中敷の裏に歴代ロゴマークがこっそり仕込まれている。こういう遊び心は金型代に何ら影響が無く、良いぞもっとやれ!と言いたくなる。
マイページでカーライフを便利に楽しく!!
最近見た車
あなたにオススメの中古車
-
スズキ ジムニー 660 XL 4WD(静岡県)
215.4万円(税込)
-
マツダ デミオ 1.3 13S ツーリング(岐阜県)
95.6万円(税込)
-
マツダ CX-5 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ(兵庫県)
238.2万円(税込)
-
マツダ ロードスター 1.5 S スペシャルパッケージ(福岡県)
330.8万円(税込)
注目タグ
ニュース
Q&A
あなたの愛車、今いくら?
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!