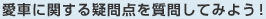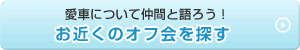この間いつも通りに車を乗っていてフッと思ったのですが、
よくプリはブレーキの感触がどうたらこうたら??と、言われてはいますが、プリちゃんはブレーキを踏まないと充電はされないのですか?それともアクセルを離すと自動で充電するのですか?
その辺の事、未来のプリウス乗りにご教授下さいm(__)m
- 車・自動車SNSみんカラ
- 車種別
- トヨタ
- プリウス
- Q&A・質問
- Q&A・質問詳細
今更ですが…プリウスの充電ってブレーキ踏むんですか? - プリウス
今更ですが…プリウスの充電ってブレーキ踏むんですか?
-
いろいろと勉強になります。
まず、「回生」という言葉の定義。
広義では減速エネルギーの回収という言葉で統一できるが、
それが発電を指すのか充電を指すのかは、バッテリーの有無で曖昧になるようです。
次に「回生効率」とは何を指すのか。
果たして「発電効率」なのか「充電効率」なのか。
決まっているのはハイブリッドカーにおいて重要なのは、より多く充電できること。
「回生効率=発電効率」の定義では、
>Bレンジのエンジンブレーキは、Dレンジのブレーキのみと比較してエンジンを回すために
>余分なエネルギーが消費されるので回生効率は悪くなります。
とエンブレの抵抗による発電効率の低下を説明できるが、
「回生効率=充電効率」の定義では、
>回生電流が大きくなると、回生回路の電力損失=電流の二乗×抵抗なので、損失も大きくなります。
>回生電流が大きくなると電力損失が大きくなり効率が低下します。
と、エンブレによる抵抗が無く、発電効率が良すぎても
かえって充電効率が低くなることが説明できる。
ではもともとの目的に立ち返り、もっとも多く充電できるのは?と考えると、
>弱くもなく強くもないブレーキペダル値17が�Aそのサイトの実験で最も回生効率が良い
と、「回生効率=充電効率」で考えるのが妥当なように思える。
その点をふまえて、改めてBレンジ35km/h超でのエンブレ状態を考えてみると、
エンブレによる抵抗で「発電効率」が低下しても、それが「充電効率低下」とはならないので、
「回生効率が悪くなる」とはならないように思えます。 -
-
-
-
(ここは訂正させてください)
開発者の公式な場での質疑では、「20kW」という表現もありますね。
こちらとしては瞬時値だろうが単位時間あたりの量だろうがどちらでもいいんです。
それらが議論の中で混同されているような気がしたので、確認したかっただけです。
論点は「Bレンジの35km/h以上で回生を放棄する意味の考察」ですから。
>強いブレーキによる大電流・短時間でのエネルギー回収量と
>弱ブレーキによる小電流・長時間でのエネルギー回収量の比較
これは一般的にも広く知られているのではないでしょうか。
充電池の急速充電は内部抵抗が高くなりやすく熱ロスが大きい。
ハイブリッドカーに重要なのは「エネルギー回収量」であること�ヘ、誰にでも明白ですね。
では電車などと違い、一度バッテリーに回収しない限り使用できないハイブリッドカーの場合、
「回生電流の大きさ」や、そもそも「回生限界100A」などという数値は、
燃費を考える場合、あまり気にする必要の無い数値であると理解すべきなのでしょうか? -
Re:63 3児の父さん
>開発者の公式な場での質疑では、「20kWh」という表現もありますね。
その「20kWh」は、どの開発者がどの公式な場で出てきた何のデータですか?
是非、教えてください。わたしは見たことがありません。
バッテリー容量は、約1.3kWhだし、最大でも40~80%の4割しか使わない制御になっているので、最大使用電力量は約0.52kWhです。
20型の瞬間バッテリー出力が25kWで30型が27kWというのは見ました。しかし、それは出力のkWデータであって、電力量のkWhではありません。
>論点は「Bレンジの35km/h以上で回生を放棄する意味の考察」ですから。
えぇっ、そうだったんですか?
わたしは貴方との論点は、貴方がNo.10で書いた以下を議�_していたと理解していました。
>短時間で一気にチャージするのと、ジワジワチャージするのでは、
>効率に違いはあるのでしょうか?
もう貴方とはこのスレッドで議論するのに疲れました。
冒頭の「20kWh」の出典だけ回答してください。 -
Re:61 3児の父さん
>「電力量」という確認をしたうえで統一しましょうという提案だったのですが、
>じゃぁやっぱり「電流値」で考えたほうがわかりやすいのでしょうか?
「電流値」A(アンペア)は、回収されるエネルギーではないのでダメです。
>どちらでもいいので、定量的に比較できる単位に統一しましょう。
どちらでもいい筈はありませんよ。
エネルギーの単位は、J(ジュール)でありWhです。
>フットブレーキ踏み込み時で想定すれば、ブレーキを強く踏むほど、
>エネルギーを回収できる量が多くなっていき、限界を超えると
>油圧が作動する、と一般的に理解されていると思います。
それは貴方の間違った理解です。
油圧ブレーキが動作する(回生限界の100A程度)までは、ブレーキの強さに比例して回生電流が増えます。
それを貴方はエネルギー回収量と間違って理解されています。
エネルギー回収量の単位はWhであり、時間要素を含みます。
強いブレーキによる大電流・短時間でのエネルギー回収量と弱ブレーキによる小電流・長時間でのエネルギー回収量の比較です。
Attilaさんの実験で、ペダル値17の中電流・中時間でのエネルギー回収量が最も大きいことが確�Fされました。
以上です。
なお、40mphは70km/hではなく64km/hです。
また、ペダル値59程度までの通常の減速度では油圧ブレーキが動作しないことは、No.11で説明済です。 -
「電力量」という確認をしたうえで統一しましょうという提案だったのですが、
じゃぁやっぱり「電流値」で考えたほうがわかりやすいのでしょうか?
どちらでもいいので、定量的に比較できる単位に統一しましょう。
フットブレーキ踏み込み時で想定すれば、ブレーキを強く踏むほど、
エネルギーを回収できる量が多くなっていき、限界を超えると
油圧が作動する、と一般的に理解されていると思います。
では、
>ごく普通に多くの車が赤信号を認識して減速する程度
→ペダル値17:70mk/hからの試験では最も「量」が多い
>
→ペダル値59:70km/hからの試験では17より「量」は少ない
>フルブレーキング時
→速度によるがペダル値60~127:回収エ�lルギー最大(100A?)
一度「量」が下がる理由が、
>回生電流が大きくなると、回生回路の電力損失=電流の二乗×抵抗なので、損失も大きくなります。
>ブレーキペダル値が大きくなり回生電流が大きくなると電力損失が大きくなり効率が低下します。
では少し説明が弱く、
記述の通り、あくまで「効率の話」なのか、
または件の試験では、ペダル値18以上で油圧が作動してしまっているのか、
どちらかではないかと推測してしまうのですが、
このあたりを定量的に説明するとなると、どんな表現・数値を使うのが適切なのでしょうか?
勘違いがあれば指摘していただければ幸いです。 -
Re:58 3児の父さん
>>最大回生能力は100A程度
>このときの「電力量」はいくらですか?
電力量の単位はWh、前提の時間が示されていないので愚問ですよ。
>また、この能力を発揮する減速エネルギーとはどんな状況で発生しますか?
たとえば、フルブレーキング時。
>>電流は50A以下でしょう
>このときの「電力量」はいくら~いくらですか?
>ブレーキペダル値18~59までの状況で徐々に低下していくと言われている数字です。
http://vassfamily.net/ToyotaPrius/CAN/BrakeRegenTable.xls
Attilaさんが測定した時間条件を含んだデータ(G列)では…
ブレーキペダル値18:積算値が199.55VA
ブレーキペダル値59:積算値が96.81VA
�香FここでのVAは、Attilaさんが独自に設定したもので、Attila電力量単位と言えるものです。
(国際的な絶対単位ではなくAttilaさん独自の相対単位) -
マイページでカーライフを便利に楽しく!!
最近見た車
あなたにオススメの中古車
-
トヨタ プリウス パノラマルーフ 純正12.3型ナビ 全周囲カメ(奈良県)
413.9万円(税込)
-
ホンダ ステップワゴン 登録済未使用車 両側電動ドア BSM 現行(佐賀県)
404.9万円(税込)
-
スバル レガシィランカスター メモリーナビ フルセグTV リアカメラ(京都府)
97.9万円(税込)
-
日産 エルグランド 純正ナビ/全周囲カメラ/両側パワスラ/ETC(大阪府)
339.9万円(税込)
注目タグ
ニュース
あなたの愛車、今いくら?
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!