2011年01月05日
まずはじめに、2010年度、盗難車ワースト10は以下通りです。。。
1位 車種からお分かりの通り、盗難車の多くはドバイを経由して、アフリカなどに流れてるそうです。暗号の方式ではなく、暗号の「からくり」の方です。 自由に選んだ異なる二つの素数を掛けた数を法とする世界を利用します。 素数というのは、例えば、2, 3, 5, 7, 11, ... のように、その数自身と 1 以外の自然数では割りきることができない 2 以上の整数のことです。 4 は 2 で、 6 は 2 や 3 で割りきることができるから素数ではありません。では、そのような世界の例として、二つの素数に 3 と 11 を選び、これらを掛けた数 33 を法とする世界を考えてみましょう。 33 を法とする世界に存在する数は、0 から 32 までだけです( 33 までいったら 0 に戻るからです)。 (P-1)×(Q-1) という式は必ず( P-1 と Q-1 の最小公倍数)の倍数 になります ので、このべき乗数の一部は簡単に n × (P - 1) × (Q - 1) + 1 11 乗でどの数も必ず自分自身に戻っています! また、n×(P-1)×(Q-1) + 1も、 n=1 で 1×(3-1)×(11-1) + 1 = 2×10 + 1 = 21 となり、上記の表と同じく、 21 乗でも同様のことが起こっているのが分かります。 RSA暗号では、このように適当な素数 P , Q を掛けた数 P×Q を法とする世界を考え、暗号化したい平文の数値 (但し P×Q 未満) を、「適当な数」 分だけべき乗してしまうのです。ここで何乗するかというのが1つ目の鍵(E) となります。 すると、あらゆる数は予想がつかない数に変換されます。これが暗号化でこれにより変換された数値が暗号文 (暗号語) となるのです。そして、この暗号化された数値をもとの数値に戻す復号を行なうには、暗号化の際べき乗した数( E乗 )の部分から、全体として自分自身に戻るようなべき乗数になるようさらにべき乗してやればよいのです。このべき乗数が鍵 (E) に対応するもう一つの鍵 (D) となるのです。 ( E乗 )分を逆算して元の数に戻すことができないのです。これが暗号化に使用した鍵では復号ができない 「からくり」 になっているのです。 (A3)D = A{n × (P - 1) × (Q - 1) + 1} 「奇跡が起きるべき乗数」 に、そして安全性はこの素因数分解の難しさによって保証されているのです。 暗号解読の前に数学って面白いですね^^ その面白いという心を正義の為に使って欲しいのですが、数学者や科学者または物理学者は、発明した後の、使う人間のことまでは考えてくれませんよね。。。
ブログ一覧 |
気になって仕方ないこと | クルマ
Posted at
2011/01/05 06:14:36
 容疑者Aの本能 ≡ 数学者Bの挑戦 (mod盗難車Xのメッセージ) (PC)
容疑者Aの本能 ≡ 数学者Bの挑戦 (mod盗難車Xのメッセージ) (PC)












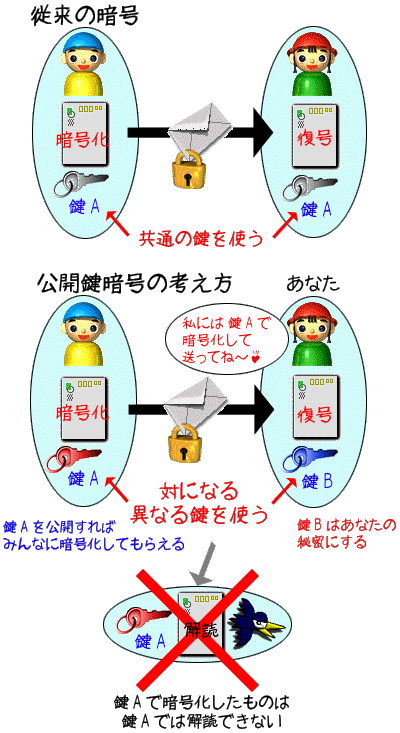

 タグ
タグ 今、あなたにおすすめ
今、あなたにおすすめ






