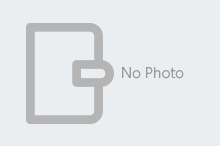- 車・自動車SNSみんカラ
- まとめ
- クルマいじり
- 《編集中》 珍プレー? 好プレー! ~ My オ ...
- フロントルームランプ (パーソナルランプ) にイルミ連動+調光機能を追加 その1 - 回路検討編
まとめ記事(コンテンツ)
SQUAREさん
2019/08/12
フロントルームランプ (パーソナルランプ) にイルミ連動+調光機能を追加 その1 - 回路検討編
カテゴリ : 電装系 > 電装パーツ > 自作・加工
車種:トヨタ オーリス
作業日:2019/07/17
目的:チューニング・カスタム
作業:DIY
難易度:★★
作業時間:12時間以内
1
この整備手帳はフロントルームランプ (パーソナルランプ) にイルミ連動+調光機能を追加してみよう…というちょっと実験的な整備手帳です。
カスタマイズの動機は…
・夜、飲み物を取るとき、置くときボトルホルダー周辺が暗くて使いにくいな~。
・そういえば、前車 WISH などは天井から LED でコンソール周辺をほのかな光で照らしていたな~。
だったら、ルームランプをくら~く点灯させたら、その代わりになるのでは? これだと後付け感もないし (^^)
これが、最初に考えたことでした。いろいろと考えた結果、最終的には機能を追加することはできました。
ただ、私の回路設計の不備だと思いますが、最大点灯時が本来の最大点灯よりすこし暗くなります。
(19/08/14 追記)
実験的ないじりだったので、現在は自作分岐ハーネス以外を取り外しました。(自作分岐ハーネスは別案件で使用中の為、取り外しを行っていません。)
(2021/01/17 12:54追記)
この方法ではなく、別の方法 (別の回路・配線) で調光機能を取り付けました。その整備手帳はこちらからどうぞ。
【関連整備手帳】
・続・フロントルームランプ (パーソナルランプ) にイルミ連動+調光機能を追加
https://minkara.carview.co.jp/userid/381088/car/2292029/6173859/note.aspx
---
このカスタマイズを行うにはルームランプの動作と回路の仕組みを知ることから始まります。
まず図の説明ですが、一番右の2つがサンバイザーのところにあるバニティランプです。
右から3番目が、メーカーオプション (MOP) のパノラマルーフあり車または150X “C パッケージ” に取り付けられているリアのドームランプです。
標準車との違いは…
標準車はリアシートの足元上…天井の真ん中あたりにあり、灯体もパーソナルランプとなっていて左右別々に点灯することができます。
しかし、パノラマルーフあり車の場合は天井がガラスなので、ルームランプを取り付けることができず、ラゲッジの上あたりにあります。そんな場所でパーソナルであってもほとんど意味がないため、パノラマルーフあり車の場合はパーソナルランプになっていません。(ドームランプになってます。)
150X “C パッケージ”は単純にコストカットか、グレードの差別化のためだと思います。
左から二番目が今回いじりのメインターゲット。フロントのルームランプです。
そして一番左が、標準車のリアのルームランプ。
今回のカスタマイズでバニティランプは全然関係ないのですが、一応説明用として追加写真1に追加しておきました。
ここでもバニティランプの説明をしておくと、回路は単純で常時電源をスイッチでマイナスとつなぐことにより電気がプラスからマイナスに流れて灯体が光ります。小学生の理科に出てくるものと同じシンプルな回路です。
バニティランプはライトオートカットの対象になっているため、この常時電源がコンピューター側で制御されて時間が来たら通電しない仕組みになっていると思われます。マイナス側は何もついてなくて、電気的にはボディー→バッテリーのマイナス端子…と言う順番で流れます。
ルームランプに使われてる常時電源はタイマー付き常時電源とでもいいましょうか。
【関連リンク】
・常時電源でもACC/IG電源でもない、新種のタイマー電源に注意! - DIYラボ
https://www.diylabo.jp/column/column-530.html
今回いじりのターゲット。ルームランプも同じで、常時点灯…好きなときにいつでも点灯させる場合、2代目オーリスだと透明のレンズを押したらスイッチがマイナスにつながりルームランプが光ります。こちらもランプオートカットの対象です。
図はフロント、リアともに運転席側を点灯した場合の例です。(リアがドームランプの場合だと、単純に常時点灯させた場合の例です。)
© 2012 - 2018 TOYOTA MOTOR CORPORATION. All Rights Reserved.
カスタマイズの動機は…
・夜、飲み物を取るとき、置くときボトルホルダー周辺が暗くて使いにくいな~。
・そういえば、前車 WISH などは天井から LED でコンソール周辺をほのかな光で照らしていたな~。
だったら、ルームランプをくら~く点灯させたら、その代わりになるのでは? これだと後付け感もないし (^^)
これが、最初に考えたことでした。いろいろと考えた結果、最終的には機能を追加することはできました。
ただ、私の回路設計の不備だと思いますが、最大点灯時が本来の最大点灯よりすこし暗くなります。
(19/08/14 追記)
実験的ないじりだったので、現在は自作分岐ハーネス以外を取り外しました。(自作分岐ハーネスは別案件で使用中の為、取り外しを行っていません。)
(2021/01/17 12:54追記)
この方法ではなく、別の方法 (別の回路・配線) で調光機能を取り付けました。その整備手帳はこちらからどうぞ。
【関連整備手帳】
・続・フロントルームランプ (パーソナルランプ) にイルミ連動+調光機能を追加
https://minkara.carview.co.jp/userid/381088/car/2292029/6173859/note.aspx
---
このカスタマイズを行うにはルームランプの動作と回路の仕組みを知ることから始まります。
まず図の説明ですが、一番右の2つがサンバイザーのところにあるバニティランプです。
右から3番目が、メーカーオプション (MOP) のパノラマルーフあり車または150X “C パッケージ” に取り付けられているリアのドームランプです。
標準車との違いは…
標準車はリアシートの足元上…天井の真ん中あたりにあり、灯体もパーソナルランプとなっていて左右別々に点灯することができます。
しかし、パノラマルーフあり車の場合は天井がガラスなので、ルームランプを取り付けることができず、ラゲッジの上あたりにあります。そんな場所でパーソナルであってもほとんど意味がないため、パノラマルーフあり車の場合はパーソナルランプになっていません。(ドームランプになってます。)
150X “C パッケージ”は単純にコストカットか、グレードの差別化のためだと思います。
左から二番目が今回いじりのメインターゲット。フロントのルームランプです。
そして一番左が、標準車のリアのルームランプ。
今回のカスタマイズでバニティランプは全然関係ないのですが、一応説明用として追加写真1に追加しておきました。
ここでもバニティランプの説明をしておくと、回路は単純で常時電源をスイッチでマイナスとつなぐことにより電気がプラスからマイナスに流れて灯体が光ります。小学生の理科に出てくるものと同じシンプルな回路です。
バニティランプはライトオートカットの対象になっているため、この常時電源がコンピューター側で制御されて時間が来たら通電しない仕組みになっていると思われます。マイナス側は何もついてなくて、電気的にはボディー→バッテリーのマイナス端子…と言う順番で流れます。
ルームランプに使われてる常時電源はタイマー付き常時電源とでもいいましょうか。
【関連リンク】
・常時電源でもACC/IG電源でもない、新種のタイマー電源に注意! - DIYラボ
https://www.diylabo.jp/column/column-530.html
今回いじりのターゲット。ルームランプも同じで、常時点灯…好きなときにいつでも点灯させる場合、2代目オーリスだと透明のレンズを押したらスイッチがマイナスにつながりルームランプが光ります。こちらもランプオートカットの対象です。
図はフロント、リアともに運転席側を点灯した場合の例です。(リアがドームランプの場合だと、単純に常時点灯させた場合の例です。)
© 2012 - 2018 TOYOTA MOTOR CORPORATION. All Rights Reserved.
2
次はドア連動の場合。
ドア連動の場合は、先ほどの常時電源のスイッチがオフであっても電気は流れる仕組みで、流れる先のマイナスが異なる (変更される) のが特徴です。
常時点灯のスイッチは実は回路の切替スイッチってことですね。
そして、ルームランプにあるスライドするスイッチでドア連動かオフにするのかを選べます。ドア連動にしなくても (オフにしても) レンズを押していつでも点灯させることができるのはマイナス側の経路が違うから実現できるんですね。
図でいうと、いつでも点灯する場合は白地に黒線の通常のアース線 (GND、E) に流れて、ドア連動の時は青線の CTY に流れます。
ちなみに、ドアを開けたとき、またはエンジン停止の時にじわっと点灯する機能はこのマイナス側を制御することで実現されてます。
今回、リアのルームランプはいじらないので関係ないのですが、せっかくなので説明しておくと…
この回路図だと標準車はリアとフロントの 青線 (CTY) が、フロントのルームランプとつながっています。(電気の流れは破線の矢印で示しています。)
そのため、標準車はフロントのスライドスイッチが “ドア” になっていないとリアをドア連動で点灯させることができません。
しかし、リアがドームランプ車の場合は、フロントのルームランプを経由していないため個別にオン / オフができます。(フロントがドア連動になっていなくても (オフでも)、リアだけドア連動にすることができます。)
---
動作の仕組みがわかったところで、次は希望の動作を検討。
・常時側は極力手をふれず、そのままの機能を維持したい。
・点灯はイルミ (スモールランプなど) と連動にしたい。
・調光機能はドア連動の時だけ調光したい。(ドア連動オフの時は点灯しない。)
・じわっと点灯 / 消灯機能は使いたい。
なんだか回路が複雑になりそうな予感。
© 2012 - 2018 TOYOTA MOTOR CORPORATION. All Rights Reserved.
ドア連動の場合は、先ほどの常時電源のスイッチがオフであっても電気は流れる仕組みで、流れる先のマイナスが異なる (変更される) のが特徴です。
常時点灯のスイッチは実は回路の切替スイッチってことですね。
そして、ルームランプにあるスライドするスイッチでドア連動かオフにするのかを選べます。ドア連動にしなくても (オフにしても) レンズを押していつでも点灯させることができるのはマイナス側の経路が違うから実現できるんですね。
図でいうと、いつでも点灯する場合は白地に黒線の通常のアース線 (GND、E) に流れて、ドア連動の時は青線の CTY に流れます。
ちなみに、ドアを開けたとき、またはエンジン停止の時にじわっと点灯する機能はこのマイナス側を制御することで実現されてます。
今回、リアのルームランプはいじらないので関係ないのですが、せっかくなので説明しておくと…
この回路図だと標準車はリアとフロントの 青線 (CTY) が、フロントのルームランプとつながっています。(電気の流れは破線の矢印で示しています。)
そのため、標準車はフロントのスライドスイッチが “ドア” になっていないとリアをドア連動で点灯させることができません。
しかし、リアがドームランプ車の場合は、フロントのルームランプを経由していないため個別にオン / オフができます。(フロントがドア連動になっていなくても (オフでも)、リアだけドア連動にすることができます。)
---
動作の仕組みがわかったところで、次は希望の動作を検討。
・常時側は極力手をふれず、そのままの機能を維持したい。
・点灯はイルミ (スモールランプなど) と連動にしたい。
・調光機能はドア連動の時だけ調光したい。(ドア連動オフの時は点灯しない。)
・じわっと点灯 / 消灯機能は使いたい。
なんだか回路が複雑になりそうな予感。
© 2012 - 2018 TOYOTA MOTOR CORPORATION. All Rights Reserved.
3
まずは調光をどのように実現するか…ですが、ここはエーモン工業の調光ユニットを使用することにしました。
以前別案件で使ったこともありますし、入手性がいいというのもありますね。
しかし、これを使うに当たって最後まで悩まされました。
というのも、この調光ユニットを使用する場合、点灯させたい LED のマイナス側は必ず調光ユニットを通す必要があるようです。
(ユニットを通さず、LED のマイナス線をボディーや、他のマイナス線につなぐなど、異なる配線方法については試していません。)
ちなみに配線は既存の配線を切断するか、自作ハーネスを作って対応するかが必要になります。
普通に考えると、赤線 (常時電源) → LED → 白地に黒のマイナス線 に着けたら…
【①常時電源側をいじる場合】
(電源側)
・車両側の赤線 (常時電源) → 調光ユニットの赤線
・調光ユニットの黒線 → 車両側の白地に黒
(LED側)
・調光ユニットの黄色 → ルームランプ側の赤線
・ルームランプ側の白地に黒線 → 調光ユニットの白線
これで実現できますが、常時電源を使用しているので、手動点灯時いつでも調光状態 (笑) 最大光量で点灯したいときに最大に光らない手動点灯機能なんて…。
それに、これだと常時電源が調光ユニットを経由するため、ドア連動もうまく動作しません。
そのため、常時電源側はいじれません。(いじりません。)
そうなると次は赤線の常時電源と、青線の CTY で考えます。
【②ドア連動で点灯側をいじる場合】
(電源側)
・車両側の赤線 (常時電源) → 調光ユニットの赤線
・調光ユニットの黒線 → 車両側の青線
(LED側)
・調光ユニットの黄色線 → ルームランプ側の赤線
・ルームランプ側の青線 → 調光ユニットの白線
しかしこれもダメなんです。
①の常時電源をいじる…と同じで常時側を使っている時点でアウト。
常時電源側を調光ユニット経由にしていることで、いつも手動で点灯させたいときにマイナスの白地に黒線に電気を流すことができないため種痘点灯ができません。
他にも青線はドアが開いていないと流れない(電気の流れがオフになる) ため、運転時にいつも点灯しておくという当初の目的が達成できません。
そもそも①、②もイルミを電源にしていない時点でライトと連動もできません。
【③イルミ連動を検討する】
そこで図のようにイルミを電源にするのですが…
調光ユニットの黄色はどこにつないだらいい? 逆に白線は?
・黄色線を常時電源の赤線に割り込み
・青線から分岐して白線に。
これだといつも手動で点灯できますし、ルームランプのスイッチがドア連動になっているときに、イルミに連動して点灯します。
でも、これもおかしいですよね?
プラス側は整流ダイオードなどで LED にむけて流れる向きを決めることができますが、マイナスの青線側を分岐すると、ドアが開いていないときはコンピューター側の回路がオフになっているので電気が流れず、調光ユニット側に流れますが、ドアが開いたときや、手動で点灯したときはマイナス側の流れる先が二つあるようになります。
これだとうまく動かないはずです。
これまでの考えをまとめると、問題になるのは…
・ルームランプの常時電源が共通である。
・マイナス線が白地に黒と青と2つある。
・青線の分岐をすると流れる場所が2つになって問題になる。
・標準のじわっと機能がマイナスコントロールなのが使いにくい。
この案件、最初はこの時点で不可能。あきらめようと考えました。
しかし、いろいろ考えたところ、
『ドア連動でじわっと点灯 / 消灯機能を自前で準備したら行けるのでは?』と考えました。
以前別案件で使ったこともありますし、入手性がいいというのもありますね。
しかし、これを使うに当たって最後まで悩まされました。
というのも、この調光ユニットを使用する場合、点灯させたい LED のマイナス側は必ず調光ユニットを通す必要があるようです。
(ユニットを通さず、LED のマイナス線をボディーや、他のマイナス線につなぐなど、異なる配線方法については試していません。)
ちなみに配線は既存の配線を切断するか、自作ハーネスを作って対応するかが必要になります。
普通に考えると、赤線 (常時電源) → LED → 白地に黒のマイナス線 に着けたら…
【①常時電源側をいじる場合】
(電源側)
・車両側の赤線 (常時電源) → 調光ユニットの赤線
・調光ユニットの黒線 → 車両側の白地に黒
(LED側)
・調光ユニットの黄色 → ルームランプ側の赤線
・ルームランプ側の白地に黒線 → 調光ユニットの白線
これで実現できますが、常時電源を使用しているので、手動点灯時いつでも調光状態 (笑) 最大光量で点灯したいときに最大に光らない手動点灯機能なんて…。
それに、これだと常時電源が調光ユニットを経由するため、ドア連動もうまく動作しません。
そのため、常時電源側はいじれません。(いじりません。)
そうなると次は赤線の常時電源と、青線の CTY で考えます。
【②ドア連動で点灯側をいじる場合】
(電源側)
・車両側の赤線 (常時電源) → 調光ユニットの赤線
・調光ユニットの黒線 → 車両側の青線
(LED側)
・調光ユニットの黄色線 → ルームランプ側の赤線
・ルームランプ側の青線 → 調光ユニットの白線
しかしこれもダメなんです。
①の常時電源をいじる…と同じで常時側を使っている時点でアウト。
常時電源側を調光ユニット経由にしていることで、いつも手動で点灯させたいときにマイナスの白地に黒線に電気を流すことができないため種痘点灯ができません。
他にも青線はドアが開いていないと流れない(電気の流れがオフになる) ため、運転時にいつも点灯しておくという当初の目的が達成できません。
そもそも①、②もイルミを電源にしていない時点でライトと連動もできません。
【③イルミ連動を検討する】
そこで図のようにイルミを電源にするのですが…
調光ユニットの黄色はどこにつないだらいい? 逆に白線は?
・黄色線を常時電源の赤線に割り込み
・青線から分岐して白線に。
これだといつも手動で点灯できますし、ルームランプのスイッチがドア連動になっているときに、イルミに連動して点灯します。
でも、これもおかしいですよね?
プラス側は整流ダイオードなどで LED にむけて流れる向きを決めることができますが、マイナスの青線側を分岐すると、ドアが開いていないときはコンピューター側の回路がオフになっているので電気が流れず、調光ユニット側に流れますが、ドアが開いたときや、手動で点灯したときはマイナス側の流れる先が二つあるようになります。
これだとうまく動かないはずです。
これまでの考えをまとめると、問題になるのは…
・ルームランプの常時電源が共通である。
・マイナス線が白地に黒と青と2つある。
・青線の分岐をすると流れる場所が2つになって問題になる。
・標準のじわっと機能がマイナスコントロールなのが使いにくい。
この案件、最初はこの時点で不可能。あきらめようと考えました。
しかし、いろいろ考えたところ、
『ドア連動でじわっと点灯 / 消灯機能を自前で準備したら行けるのでは?』と考えました。
4
それで最初に考えたのが、この回路です。
右側の配線が既存のルームランプの配線に割り込む自作のハーネスを示しています。
実際のルームランプの電球を光らせているのは、手動の場合も、ドア連動の場合も常時電源。図でいう6番 赤線です。
なので、電球を光らせる電源はこれを使うことにしました。というか、それしかないと思われます。
また、ここをいじらなければ手動点灯も問題なしです。同じく7番 白地に黒のマイナス線もいじりません。
今回注目したのは1番の青のマイナス線 (CTY)
ルームランプ側を黒に変更して、車体側 (図でいう上側の点線) は使わないか、黒線と同じ距離だけ配線を延長してノーマル戻しに使います。
(ノーマルに戻すときは、青と黒をつなげば元に戻ります。)
配線色は自作分岐ハーネスなので、好きなように変更でき、わかりやすいですね。
これで取り出したルームランプのドア連動マイナス線を自前でコントロールするのが、①エーモン工業の調光ユニット (図の中央) と、②他の案件 (自作のドアイルミ) で作り出したドア連動のプラス出力 (図の中央の水色線) です。
①はスモールランプが点灯すると動作を開始。
調光ユニットの黄色線からプラス流れ始めます。
この時、調光ユニットは明るさを制御するため高速に LED を点滅させる、 PWM 制御を行ってます。
PWM を LED で使うと、人間がその高速点滅に目がついていかないので結果的に暗く見える…というやつです。
しかし調光ユニットは先に説明したとおり、LED側のマイナスの白線を使う必要があります。
そこで、出番なのがエーモン工業の出力変換ユニットです。(図の左側)
これに LED のマイナス線 (白線) をつなぐことで、マイナス側の配線を切り離して高速点滅効果をプラス出力だけで実現します。
これを今度はエーモン工業のユニット用リレーに接続。
高速にオン / オフを繰り返す先ほどのプラス側をユニット用リレーの青線につなぐことで、ルームランプのマイナス側 (自作分岐ハーネスの1番 黒線) を高速にオン / オフして、ドアが閉まっているときにイルミと連動で薄暗く光らせます。
これで問題無いようですが、このままだとドアを開いたときにじわっと点灯 / 消灯ができません。なぜならば、図でいう自作分岐ハーネスの上側の1番を切り離しているため、ドアが開いても標準機能のじわっと点灯 / 消灯機能が働かないからです。
そこで出番なのが、他の案件から拝借したドア連動のプラス線。
これを図の中央。整流ダイオードで合流させることで、ドアが開いたときなどにじわっと点灯をさせることができます。
最初はこれでうまくいった…と思っていたんです。
ところが、ドアイルミの配線を拝借するとドア側イルミを調光したときになぜかルームランプも調光される。
拝借した側には調光ユニットがついていないにもかかわらず…です。
最初は原因を追及しようと考えましたが、なにしろ自作のユニット類すべての回路を通して原因を探らないと行けないので、回路が複雑で…めんどい。
右側の配線が既存のルームランプの配線に割り込む自作のハーネスを示しています。
実際のルームランプの電球を光らせているのは、手動の場合も、ドア連動の場合も常時電源。図でいう6番 赤線です。
なので、電球を光らせる電源はこれを使うことにしました。というか、それしかないと思われます。
また、ここをいじらなければ手動点灯も問題なしです。同じく7番 白地に黒のマイナス線もいじりません。
今回注目したのは1番の青のマイナス線 (CTY)
ルームランプ側を黒に変更して、車体側 (図でいう上側の点線) は使わないか、黒線と同じ距離だけ配線を延長してノーマル戻しに使います。
(ノーマルに戻すときは、青と黒をつなげば元に戻ります。)
配線色は自作分岐ハーネスなので、好きなように変更でき、わかりやすいですね。
これで取り出したルームランプのドア連動マイナス線を自前でコントロールするのが、①エーモン工業の調光ユニット (図の中央) と、②他の案件 (自作のドアイルミ) で作り出したドア連動のプラス出力 (図の中央の水色線) です。
①はスモールランプが点灯すると動作を開始。
調光ユニットの黄色線からプラス流れ始めます。
この時、調光ユニットは明るさを制御するため高速に LED を点滅させる、 PWM 制御を行ってます。
PWM を LED で使うと、人間がその高速点滅に目がついていかないので結果的に暗く見える…というやつです。
しかし調光ユニットは先に説明したとおり、LED側のマイナスの白線を使う必要があります。
そこで、出番なのがエーモン工業の出力変換ユニットです。(図の左側)
これに LED のマイナス線 (白線) をつなぐことで、マイナス側の配線を切り離して高速点滅効果をプラス出力だけで実現します。
これを今度はエーモン工業のユニット用リレーに接続。
高速にオン / オフを繰り返す先ほどのプラス側をユニット用リレーの青線につなぐことで、ルームランプのマイナス側 (自作分岐ハーネスの1番 黒線) を高速にオン / オフして、ドアが閉まっているときにイルミと連動で薄暗く光らせます。
これで問題無いようですが、このままだとドアを開いたときにじわっと点灯 / 消灯ができません。なぜならば、図でいう自作分岐ハーネスの上側の1番を切り離しているため、ドアが開いても標準機能のじわっと点灯 / 消灯機能が働かないからです。
そこで出番なのが、他の案件から拝借したドア連動のプラス線。
これを図の中央。整流ダイオードで合流させることで、ドアが開いたときなどにじわっと点灯をさせることができます。
最初はこれでうまくいった…と思っていたんです。
ところが、ドアイルミの配線を拝借するとドア側イルミを調光したときになぜかルームランプも調光される。
拝借した側には調光ユニットがついていないにもかかわらず…です。
最初は原因を追及しようと考えましたが、なにしろ自作のユニット類すべての回路を通して原因を探らないと行けないので、回路が複雑で…めんどい。
5
そのため、原因特定をあきらめ、これならうまく動くだろうという回路に変更しました。
具体的にはこの案件用に自前でドア連動のプラスを作り出すことにしました。
具体的にはこの案件用に自前でドア連動のプラスを作り出すことにしました。
6
…。いきなり完成形ですが (^^;)
配線をハンダ着けして、収縮チューブで絶縁。
配線をキレイにまとめてケースに入れたものがこちらです。
配線をハンダ着けして、収縮チューブで絶縁。
配線をキレイにまとめてケースに入れたものがこちらです。
7
ということ、でできあがったのがこちら。
これに各部から分岐してきた配線を接続すればうまくいくはずです。
(その2 につづく)
これに各部から分岐してきた配線を接続すればうまくいくはずです。
(その2 につづく)
イイね!0件
オススメ関連まとめ
-
2024/05/25
-
2022/03/03
-
2020/12/10