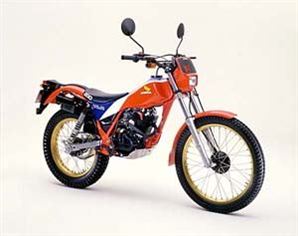FLAT6さんの投稿に触発されてのMT考 ラストです。
運動学習というのをご存知でしょうか。
ブリタニカ百科事典を引いてみますと、
「運動技能の習得を一般にさすこともあるが,通常,特に感覚系と運動系の協応関係を伴う動作の学習をいう。感覚運動学習ないしは知覚運動学習ともいわれる。スポーツ,楽器の演奏,電信作業,あるいはタイプライタの学習などはその例である。」
とあります。
例えば水泳のクロールを想像してみます。

この画像では右手が水中を掻いているでしょう。その時、泳ぎ初心者は
「よし、今から左手を持ち上げよう」
「息継ぎに首を曲げよう」
「おっと、忘れずにバタ足しなきゃ」
と各々の運動を確認してぎこちなく行ってしまいます。
対して熟練した泳ぎ手はそうした運動の分解と意思による発動を簡略化、合理化して「泳ぐ」という一個の運動を無意識に実行できるレベルにまで落とし込んでいます。
この初心者から熟練者に至るプロセスを理論化したものが運動学習です。
運動学習の進行で鍵を握るのが「フィードバック」です。
今のはこうしたから失敗した。
ここの動作があっちと連動していない。
あそこがこうだから上手くいった。
というトライアル&エラーの反復のうちに、脳の大脳基底核や小脳はデータを蓄積し、
む、Aの動きからBの動きに繋ごう
Bの次は...Cか
CからE? いや、やっぱD
DでこっからEだな....。
というプロセスをABCDEというパッケージとしてストックし、自動的に伝達される高速道路として、さっと泳ぐ行為の時に取り出して使うようになっていきます。
この高速道路の構築のためのフィードバックには、外的フィードバック、内的フィードバックの2種類があります。
外的フィードバックは、人から教えられたり、本を読んだり、言語化されて伝えられることの多い外部からの情報です。
対して内的フィードバックは、実際に自分が行なって得た感覚情報を元にした「こんな力加減の時はうまくいくんだ」「この感覚の時にA動作からB動作に移るとスムーズなんだな」という自身のフィーリングを主体にしたものを言います。
どちらが欠けてもいけません。内的フィードバックばかりでは、間違った方向に最適化されていく歯止めが効きづらいですし、外的フィードバックだけではいわば耳学問のように実感が伴わず身につくのが遅くなります。適度に内外のフィードバックを得つつ高速道路は構築されていきます。
この学習プロセスは3段階に分けられています。
◯認知段階
動作を頭で考え、理解するレベル。こうして、次こうして、次こうして....と理論化して動作を行う戦略を練ります。
◯連合段階
実際やってみて失敗しつつ、試行錯誤していくレベル。
いい動作と悪い動作の違いの感覚が掴めてきます。
◯自動化段階
考えなくても実行できるレベル。高速道路が出来上がり、バスケットでドリブルしながらボールを一切見ないなど、意識のリソースを他に割くことができるようになる。
このようにして学習が進んでいくわけですが、当然、より複雑であったり多面的な課題ほど高速道路の構築は難しく、時間を要します。
そして運動と関わりが深い神経伝達物質ドーパミンは、学習、意欲、快感と関わりを持ち、共通して活発な働きを促すため、より複雑な運動課題の達成や運動学習の進捗、自動化は意欲や快感と強くリンクしますし、報酬系と言われる脳の機関による達成感でのドーパミン分泌とオーバーラップしていきます。
より難しい運動学習の過程と達成の方が快感な訳です。
さて、ようやくMTの話です。
上記の運動学習を運転行為に当てはめていくと、複雑な道路状況の中でペース配分や他の車や歩行者等の存在、信号や標識、時事刻々と変わっていくシチュエーションに対応しつつ車を操作します。
教習所を卒業する頃には、「今からアクセルペダルを踏むために右足を曲げよう」なんていう段階の人はいないでしょう.....いない...ですよね?
少なくとも
加速しよう→右足がアクセルペダルを踏む
減速しよう→右足がブレーキペダルを踏む
くらいの自動化はできていると思います。
そうなって初めて周囲の状況やペース配分等々、他の部分に意識を向けるリソースが生まれます。
前回、MTの特徴にパワートレーンをハズせるということを挙げました。ゆったりとした40km/h足らずで流れている道路で5速で巡航は出来なくはないですが、アクセルを踏んでもトルクは乗りません。状況に応じた変速をドライバーが行う必要が常にあるのです。
自分の場合に置き換えてみると、何かあるとクラッチを踏むという動作は自動化されていると思います。エンジンの回転数を聴きながら加速してシフトアップ。これも自動化が進んでいます。
対して減速時のブリッピングは半分は意識してやらないとできません。heel&toeは「さあやるぞ」とやっています。
学習していく過程では、きちんと課題に集中し、結果の分析と実行を繰り返す必要がありますから、最近意識して練習を始めた課題はまだまだ連合段階にあることがわかります。
対してATの車にはドライブトレーンの選択という行為がない、あるいはMT比では極端に少ないということができます。もちろん一つのコーナーでの荷重移動、ブレーキのタイミングやステアリングの舵角等、突き詰めれば失敗はあるでしょう。その辺りを意識しつつ走ると、実家のC-HRもとても良くできた車です。でも常にそのテンションを維持しつつATに乗れるかというと、なんだかんだ漫然と乗ってしまいがちです。
MTはハズせる構造故に、常に回転数を意識してギアを変えざるを得ません。強いられているのです。
四肢を使った非MTと比べて複雑な運動課題を遂行しつつ走るしかないのです。
そしてその運動課題は非MTよりも遥かに明確に失敗という結果をわかりやすくフィードバックしてくれます。
その過程で、シフトショックのない変速とか、ロールを感じながらきちんと姿勢を制御しつつ変速といった動作の学習を繰り返しつつ習熟と達成によるドーパミンの分泌を促しているんだと思います。
いくら速く走れようと、自動ブリッピング機能はMTの運動課題の難しさをスポイルしますし、課題の難度低下は快感の低下に直結します。
加えて、少し脇に逸れますが、内的フィードバックと外的フィードバックの双方が運動学習には必要だと言いました。これは車の電子制御と通ずるものがある気がしています。
先日WRXに試乗させていただいた際、感動するとともに飽きそうだな、とも思いました。

これはトルクベクタリングや電子制御デフの存在がやはりあるんじゃないでしょうか。高度な制御は恐らく私の感覚領域の限界を超えた車の挙動を実現していると思います。
本当に唖然とするくらい地面にビッタリと張り付く車でした。私の試乗程度で電子制御の介入があったのかよくわかりませんが、私がWRXの運転後に得られるフィードバックは、電子制御機構の設計や制御の発動条件の理解等の知識によって、いわば机上で考察して導き出す外的フィードバックが多くを占めてしまうのではないかと思います。対して感覚的には、タイヤが滑るかな、と思うあたりでなんか介入が入ってもう一段高い安定が得られる。というどこか五感で感じたフィーリングに直結しない戸惑いも生まれます。もちろん私のレベルでは、ですが。

MEG3RSを楽しいと感じるのは反対で、得られるのはありありとわかる4輪の接地感とピッチ、ロール、トーの感覚。ステアリングに伝わるトルクステアの予兆など、プリミティブな内的フィードバックです。
それは物凄くわかりやすく、きちんと前輪に荷重をかけて曲がる。前輪が負けそうなら荷重を抜く。というようなシンプルな外的フィードバックと直結しています。
このバランスの良い内外のフィードバックが自身のドライビングの理解と学習の進捗に寄与する最良のものであることは間違いなさそうです。そしてこの素朴な感覚と、車としての素性や限界の高さが相まって MEG3RSを評価の高い車にしているんじゃないでしょうか。
結局ポルシェもシンプルな素のモデルが楽しい。というのもこういう理由なのかな、と想像します。乗ったことないけど。
つまるところ、私は速く走りたいだけではないのですね。タイムを縮める為により合理的に、より先進的にという突き詰めていく達成感を今のところ私は求めていません。
速く走れたら楽しいのではなく、きちんと車をコントロールして、MEG3RSの特性を隅々まで活かしてその中で速く走りたいのです。「MT考 1」 のコメントで、FLAT6さんから、父同様、私はそれぞれの車の個性が訴えるものに惹かれるのではないか、と指摘を頂きました。
なるほど、MTが構造上エンジンとの対話を求める以上、性格や意思を付与された生き物と思うような付き合い方を私はしています。これは車に興味を持つ以前からそうだったと思います。
私はサーキットに近々行ってみたいと思っています。
でも競争がしたいという意識は今のところありません。行こうと思うのは、MEG3RSがそういう場所で思うさま駆けることができる車で、そこに私の知らない個性があるからだと思います。
機械音痴にも関わらず工具を買ってあちこち触ろうとしているのも、構造やボルトの締め付けに至る知識と実感を深めることで、より豊富な内外フィードバックを得ようと望んでのことです。
結局、車=MT= MEG3RS となっている私にとって、よりうまく MEG3RSを操ることが今の楽しみの源泉なのですね。
というわけで、最初に述べたように、MTがどう優れているか、とか新しい観点などの提案はなく、単純に車を擬人化するにはMTである必要があり、より複雑な運動課題であるMTの運転は脳の分泌物から言っても楽しいよね。
という数行で終わるお話でした。
最後まで読んでくださってありがとうございました。








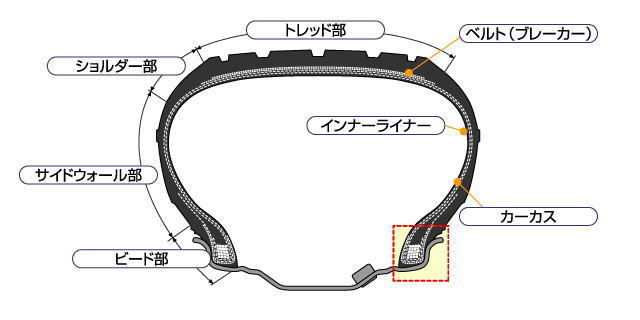




 にわか車好きなりに少しでも経験を積もうと、節操なく試乗を繰り返しております。販促目的で試乗の機会を設けている各ディーラーの方々にはなんとも迷惑な輩ですね。
にわか車好きなりに少しでも経験を積もうと、節操なく試乗を繰り返しております。販促目的で試乗の機会を設けている各ディーラーの方々にはなんとも迷惑な輩ですね。