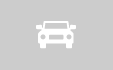- 車・自動車SNSみんカラ
- まとめ
- クルマいじり
- アルミテープチューンの真実
- 静電気とアルミテープチューン(後編) 【改訂版】
まとめ記事(コンテンツ)
2024/05/19
静電気とアルミテープチューン(後編)【改訂版】
(続き)
さて、「タイヤがアースになるから、ボディは帯電しない」と聞いても、恐らく多くの人、特に効果を信じている人は「本当かよ?」と思うでしょう。
あの日本を代表する世界的企業であるトヨタが、そんな嘘などつくはずがないという方は、
「だって、ドアノブを触ったら静電気(の放電)でビリッと来るでしょ」
「実際、ホコリを寄せ付けるじゃない」
と反論されると思いますが・・・
では、まずは静電気とは何ぞや?から
代表的な接触帯電を例にとると、異なる物質(通常は電気的に中性)を接触させると、一方の物質から他方へ電子が移動するので正の電荷を帯び、他方は負の電荷を帯びます(接触した状態で全体を1個の物質として捉えると中性のまま)
この正電荷を帯びた物質と負電荷を帯びた物質を分離すると、それぞれが静電気を帯びた状態になります。
これが帯電が発生する原則的なメカニズムです。
次に、車のボディである鉄(正確には炭素鋼)は、そもそも帯電するのでしょうか?
ネットを見ると、「基礎からわかる物理」とか「高校物理を諦めない」などのテーマで物理を解説している個人の方のHPも多く、中には参考になるものもありますが、「導体は電子が自由に動けるので帯電しない。帯電するのは不導体だけ」と主張される方もいます(※1)
しかし、導体内の電子の移動と電子の増減は別の話で、局所的に見れば不導体の方が静電気が溜まりやすいとは言えるかもしれませんが、導体であっても普通は無限遠というわけではないので、帯電はします(地球は別)
では、導体が帯電するとどうなるのでしょうか?
以下はキーエンスのHPからの引用です。
『導体が帯電しているとします。そのままにしておくと帯電したままです。しかし、導体は「あること」によって、一瞬で静電気がない元の状態に戻ります。「あること」とは「アース」です。
(中略)導体はアースに接続されていれば、静電気が発生してもすぐにアースを伝って逃げるため、帯電したままの状態が続くことはありません。しかし、アースにつながっていない場合は逃げ場がないため、静電気をためたままの状態が続くことになります。』
という訳で、車のボディ(及びボディとGND接続されているパーツ)は、
タイヤというアースがある以上、帯電していないと考えられます(※2)
一方で、樹脂製バンパーなどの不導体は、帯電しても電子が自由に移動出来ないためアースが効きませんから(言い換えれば、部分的に何か対策してもその局所しか除電はされない)、製造現場などではイオナイザー等を使って中和しています。
しかしトヨタは、アルミテープを貼るとバンパーやステアリングコラムカバー等の不導体でも空気の絶縁を破壊して放電する「コロナ放電(空中放電)」が起き、除電されるという謎の主張をしていますが、その後の発表によれば、アルミテープではなく、なんとビニールテープでも可能なんだそうです。
ですが、空気という絶縁体を破壊して放電するには、空気の絶縁耐力である30kv/cm以上の電場が必要で、コロナ放電とは針の先のような局所(電極)に高電圧を掛けた時に相手極(アース)に対して放電する現象の事を言い、車で言えば、スパークプラグの電極間に飛ぶ火花がまさしくそれです(※3)
なので、導体であってもよほどの好条件(真夏の雷雨とか)が揃わない限りは、せいぜいギザギザ加工したぐらいのアルミテープではコロナ放電など起こりませんし、ましてやビニールテープでコロナ放電って、全く意味が解りません。
また、不導体であればそもそも電子が自由に動けませんから、仮に百歩譲ってギザギザのアルミテープでコロナ放電が起きるとしても、局所的な効果しかありません。
いずれにせよ、バンパーなどの樹脂パーツは帯電はするが、
アルミテープを貼ったところで、放電(除電)は不可能でしょう(※4)
ちなみに、冒頭で書いた「触ったら静電気(の放電)が起こる」というのは、実は車が帯電していたのではなく、人間が帯電していて、それがボディに触ることでアースされ、溜まっていた静電気が一気に流れたからであり(※5)、「ホコリを寄せ付ける」も前回指摘したように専ら重力と静電誘導あるいは誘電分極によるものなので、帯電の有無は関係ありません。
という訳で、トヨタの言う「ボディが帯電することによって、車両の安定性が悪くなる(車を揺さぶる力が働く)」というのは前提からして大嘘で、幾人かのテストドライバーが感じたプラシーボに過ぎません(※6)
実際、トヨタがアルミテープ理論を公表してからだいぶ経ちますが、カーメディアという御用媒体やオカルトチューン愛好家、並びに彼らをターゲットにしてオカルトパーツを販売する企業を除けば、その理論に注目する研究機関や企業は未だにありません。
だいいち、帯電物の種類に関係なくアルミテープを数カ所程度貼るだけで簡単に除電ができるなら、イオナイザーなど無用の長物な訳で、不導体の帯電で苦労している生産現場にも疾うの昔に導入されているはずですが、そんな話も一切聞きません。
なぜなら、まともな研究機関や企業であれば「導体はアースをすれば一瞬で静電気がない元の状態に戻るが、不導体にはアースが効かない」という不動の事実認識が共有されているからです。

↑一見すると技術的に深堀りした風な記事を載せているモーターファンですが、内容は出鱈目で、所詮は広告(ヨイショ)記事に過ぎない。それにしても、常日頃「剛性感が~」とか「リニアリティが~」などと仰る自動車評論家が、こんなに簡単にバイアスに掛かるとは・・・いえいえ、大した感性をお持ちのようですネ(画像はモーターファンのHPより引用)
そもそも、昔から電気や静電気に纏わるオカルトが多いのは、その動きが目に見えないから。
その見えない敵と懸命に戦い、相手を制圧した気でいたが、実は最初から敵など誰もいなかった。
あるいは、敵はうまく隠れていて少しも制圧できていなかった・・・
もっとも最近では、産業技術総合研究所が、目に見えない静電気分布を発光させることにより、世界で初めて直接的な可視化に成功した(電荷に反応して発光するセラミックス微粒子を発見し、目に見えない静電気を目視やカメラで可視化する世界初の静電気発光センシング技術を開発)と発表していますので、そういうので実際に検証してみたら面白いかもしれません。

↑世界で初めて直接的な可視化に成功(画像は産業技術総合研究所のHPより引用)
参考)https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2022/pr20220602/pr20220602.html
【結論】
タイヤというアースがあるので、そもそもアルミテープはアースベルトと同様に無意味です。
また、アースの効かない不導体では、イオナイザーでも使わない限り除電できません。
意味があるとすれば、
お守りか御札としての効果(信じる者は救われる)ぐらいです。
注釈
(※1)
プロフを見ると、「国立大理系出身で理科教員を目指している」と書かれていましたが、教わる方の立場で言えば、教員になるのは止めてほしいです。
(※2)
ネット上で電磁気学(回路設計)に詳しい人が、「理論上は理想的な導体を扱うため、ある電荷が存在する導体とGNDを結んだ場合、電荷は一瞬で共有されることになりますが、実際には、配線には抵抗があり、電荷の存在する導体の静電容量と配線の抵抗により決定される時定数での電荷の流れが生じます。電荷が減れば電位も下がり、最終的にはGNDと同一電位となります。」と言っていました。
要するに、回路設計をする上では、僅かな時間差というか(コンデンサなどを含んだ)静電容量を考慮しなければならないケースもある、と言いたいようです。
しかしながら、電気の伝わる速さ=光速であることを考えれば、常識的には「アースによって、一瞬で静電気がない元の状態に戻ります」という認識で間違いありません。
(※3)
30kv/cmとは、金属平板を平行して1cm離し、30kvの電圧をかけたときに金属平板の間に生じる電場のこと。
気温20℃、気圧1,013.25hPaの標準状態において、波高値で約30kV/cm、実効値で21.1kV/cm の電位の傾き(電場)に達すると空気は絶縁力を失い、放電が起きます。
なお、このコロナ臨界電位の傾きは相対空気密度δの2/3乗に比例するため、上空1万メートル(気圧は地上の約1/4)を飛行する航空機の放電索からは更に低い電場でもコロナ放電が起こります。
いずれにしても、地上を走る車とは条件が違い過ぎるので、自説を補強するために放電索を引き合いに出したトヨタの説明は、オカルトパーツ業者と同じで確信犯だと思う。
さらに言えば、放電索はそもそも空力を改善するための物ではなく、通信障害を取り除くための物で目的が全く違うのだから、かなり悪質。
(※4)
静電気の放電現象は、帯電物の種類(導体か不導体か)や形状等により、主に次のような形態に分けられます。
・コロナ放電(針の先のような局所に高電圧をかけた場合に、空気の絶縁が破壊されて起きる放電)
・アーク放電(導体同士の放電で、コロナ放電より大電流のもの)
・ブラシ放電(帯電した不導体と導体との間の放電)
・バルク表面放電(別名コーン放電。絶縁性粉体の表面で起きる放電)
・沿面放電(不導体の表面で起きる放電)
なお、ボディアースする時に塗膜を剥がす必要がある事から、ボディ表面は塗膜に覆われているので不導体じゃないか?と考える人もいるかもしれません。
ですが、導体か不導体かは、相対的に捉える必要があります。
車に使われる塗料の抵抗率は15MΩ・cm程度のようですが、電気抵抗は断面積に反比例し、長さに比例しますので、せいぜい0.1ミリ程度の厚みしかない塗膜の表面抵抗率がどの程度か解りませんが、12Vの電装品を動かすのには支障があっても、絶縁膜ではありません(いわゆる電気絶縁塗料の抵抗率は、100GΩ・cm程度のようです)
(※5)
人間が帯電しているからこそ、GSで「静電気除去パッドに触れてから、給油してください」と書かれている訳で。
もし車側が帯電しているなら「静電気除去スティックを車に触れさせてから、給油してください」となるはず。
にもかかわらずトヨタは、「クルマのボディはドアハンドルに触れると静電気が起きることからわかるように、常に帯電(プラスの電荷)している」とマスコミに説明していたので(=モーターファン記事より引用。原文ママ)、言っていることが素人過ぎて呆れます。
それでも、そのトヨタの主張を無批判に垂れ流すカーメディアの影響もあり、「トヨタが言うのだから事実だろう」という思考停止した人まで含めると、車好きの多くは、やるやらないは別にしても「アルミテープで走りが変わる」と思っているようだから、TVでやってる健康食品(機能性表示食品)のCM影響力の大きさにも、妙に納得した次第。
(※6)
元々は、雨の後にテストコースを走っていて「なんかいつもと走りが違うよね」と感じたのが発端だったそうです。
毎日雨戸を開け閉めする人はわかると思いますが、雨あがりなどは雨戸の滑りがいいですが、これは樋に残った水分が潤滑材の役目を果たすからです(ウェット路であれば、路面とタイヤの間に水の膜ができるので、摩擦係数は下がる)
雨の中、あるいは雨の後に運転すると、確かに普段とは走りが少し異なる印象を受ける事がありますが、このように帯電の有無によるものではありません(つまりは、最初の仮説段階で間違えた)
P.S.
トヨタのアルミテープ理論に便乗したオカルトパーツ(リアクター等)が、各社から発売されていますが、もしこれらに対し措置命令が出たら、当のトヨタはどうするつもりでしょうか?元はといえば、トヨタが言い出した理論な訳で。
ある会社などは、顧問弁護士も雇っていないのか、未だに「トルクが25%以上もアップし、燃費も10~40%以上も向上」などと通販サイト上で堂々と謳っているので、消費者庁はぜひ根拠を示すように命じてほしいですね。
もっとも、過去に措置命令(旧排除命令)を受けたホットイナズマにしてもアドパワーにしても、それ自体を知らなかったり、「広告手法に問題があっただけで、効果が否定されたわけじゃない」という信者も未だにいるようですから、消費者がもっと賢くならないとダメでしょうけど。
「トルクが25%以上、燃費も10~40%以上も向上」って、優良誤認表示の問題以前に、常識で考えてありえないので。
Posted at 2024/05/19 13:36:19
イイね!0件
オススメ関連まとめ
-
2019/04/06
-
2024/10/29
-
2026/02/11