ハチマルミーティング2024 に参加した際に歴史的に重要な5ナンバーセダン3台に乗せていただいたので、ごくごく簡単ながらメモを残す。
1988年式ブルーバードH/T SSS ATTESA ~作った人たちもブルーバードが好きだ~
ブルーバードの話題に触れる前にとにかくCMを見て欲しい。開発責任者が語る形式と手ぶれを許しながらライブ感ある映像が見る人のハートを鷲づかみにする。
VIDEO
いまだったらこんなCM絶対に作らせて貰えないだろう。日産の施設で何度もリハーサルを繰り返して作ったのだろう。いまならYoutubeで専用動画なんかはあるかも知れないが・・・。ほとんどCGで誤魔化されてしまうんじゃないだろうか。
今回の主役のブルーバードが売られていた1988年当時、バブル期と言うこともあって人々の購買力も上がり消費マインドも高く、そこに排ガス規制を乗り越えて技術力を蓄えた各メーカーが意欲的な新機構を次々に送り出した。普及型DOHCやパッシブ制御のサス、そして今回の主役フルタイム4WDシステムなどである。
現代の目線で見ると面白いのはこうした技術が積極的にセダンに織り込まれていたと言うことである。当時の自動車市場の中心はセダンであり、その中でもブルーバードはそれまで20年以上コロナとの販売競争を続けてきた日産の支柱とも言える小型車だった。
試乗したのは1988年式の前期型ハードトップSSS ATTESAである。もうハードトップというのも今や聞きなれない専門用語になりつつある。オープンカーが当たり前だった戦前の世界、雨を凌ぐための幌(ソフトトップ)に対して鋼板性や樹脂製のしっかりした屋根を取り付けた車をハードトップ(H/T)と呼んだ。対候性が良く、時としてオープンエアも楽しめるのだが、いつしか固定式の屋根であっても、セダンには備わるピラーを取り去って窓を下げたときの解放感を残したピラーレスH/Tが産まれた。(その場合ロッカーやクオーターとルーフを強化する)
ドアサッシュを廃止して窓ガラスを支える機構をドア内部に持たせることで見た目にも開放感があるだけでなく、車高を低くしても乗降性を悪化させないメリットがありスタイルを追求するためにサッシュレスドアを採用したクーペやセダンもH/Tと呼ばれ始めた。性能のためにピラーを残した「ピラードH/T」なんて今では当たり前ながら当時はきっと理解しづらかっただろう。
かくしてブルーバードにはスタイル派の為のH/Tセダンの設定がありイメージリーダーでもあった。従来は2ドアだったが、セドグロやローレルがピラーレスH/Tを採用する中で1982年には910系ブルーバードで4ドアH/Tセダンを発売し、高級車のみに許されていた世界観を下方展開させて人気があった。競合車のH/Tは2ドアばかりでセダンがなく、今よりもっと熾烈だった販売競争では4ドアH/Tの存在はライバルにはないブルーバードの強みだった。
当時幼稚園児だった私もブルーバードはカッコイイ車として認識していたし、街でよく見かけた910系と並んでカッコイイブルーバードだと私は思う。同じマンションに後期のセダンがいた関係もあり個人的にも馴染み深いブルーバードだ。
H/Tを今の目で見ると低い全高と傾いたA・Cピラー、水平基調で長さを強調したプロポーションは80年代ならではの美意識で逆に新鮮だ。長めのオーバーハングも重さよりエレガントさを感じさせ、加飾によるエモーショナルの表現よりクリーンで控えめな表現でありながら黒く縁取りされたラジエーターグリルやRrコンビランプは個性的で遠くから見てもブルだと分かる。
一点だけ、エンジンフードとAピラーのつなぎとトランクリッドとCピラーのつなぎの線の段差感が残ってつながりが悪いと思ってしまうがそんなことは些細な問題でありハードトップの魅力を分かり易く表現したグッドデザインだと思う。スタイリングでも高い評価を得ていたが、競合するトヨタはカリーナEDによってブルーバード4ドアH/Tもそのデザインでスマッシュヒットを飛ばしていたので日産としてはブルーバードのデザインを磨くだけで無く、基礎体力とも言える動的性能「走る」「曲がる」「止まる」を鍛えた。
この観点で目玉となったのがATTESA(アテーサ)だ。ATTESAとはフルタイム4WD技術の名称で「Advanced Total Traction Engineering System for All」の頭文字である。
前後回転差を吸収するセンターデフを持つフルタイム4WDにビスカスカップリングを組み合わせており、基本的には前後50:50でトルク配分するが、前後輪がスリップしたときはビスカスカップリングがトルクを適切に配分するのでとにかく安定した走りが可能となる。ビスカップリングがない場合は、センターでフロックを使って機械的に直結させる必要があったが、ATTESAは更なるイージードライブを実現している。
1980年にアウディがラリーに勝つためのメカニズム「クアトロ」として発表したフルタイム式4WDからたった7年で一般の人の手に届くATTESAに進化したのは当時の勢いを感じてしまう。
試乗車はこのATTESAとCA18DE型1.8LツインカムE/G(135ps)と4速ATの組み合わせであり、まさにブルーバードが実現しようとしていた高性能とイージードライブを兼ね備えたスタイリッシュな4ドアを体現している。
是非、というオーナーの勧めに従って鍵を受け取って乗り込んだ。
運転席は特別何か特徴的な装備が有るというわけでは無いが、ラウンドしたメーターバイザーが助手席まで滑らかに滑り落ちていくような大らかな意匠で、メーターは中央に速度計、右に回転計、左に燃料系と水温計、シフトポジションインジケータが配置された。虚仮威し的な意匠性よりも質実剛健とした視認性を与えながらも旧来的な絶壁インパネから脱している。
後期型では意匠が替わってしまう四角いATセレクターレバーをDレンジに入れる。
スポーティな性格を持ったブルーバードだが発売当時(1987年)に既にAT比率が5割を超えていたのでMT同様にATにも力が入れられていたし、前述の「新型ブルーバードSSS ATTESA 技術開発NOTE」を知っていれば寧ろATに乗ってみたいという気持ちになってしまう。
運転姿勢は自然でATゆえ左足のスペースも充分ある。FF一世代目までは足元が広いことをアピールする意味もあってフラットなフロアを目指し、センタートンネルも小さく作っていたが、FFベースとは言え後輪も駆動する4WDではそれなりのセンタートンネルが求められる。特に4WDは凹凸が車内に張り出すような場合もあるがブルーバードは問題ない。
後席はH/Tとしては標準的で現代のエモーショナルセダン(笑)並にヘッドクリアランスが小さい。特に頭上がバックドアガラスに来てしまうので直射日光で暑いという弊害がありそう。後席には小柄な人か子供であれば問題はなさそうだが、標準身長の大人4人乗車は厳しそうだ。
確かにブルーバードの走り出しはイージーだ。デフロック操作不要のフルタイム4WDなのにタイトコーナーブレーキング現象は無く滑らかに曲がれるのは技術の賜物だ。ただし135ps/6400rpmを誇るCA18DEを以てしても1300kgを越える車重はさほど軽快感は無い。パワーウェイトレシオは9.7kg/psとなり、最後のブルーバードシルフィ(9.47kg/ps)に少し負ける程度だ。当時の水準でもカムリやマークIIを少し凌ぐパワーウェイトレシオであり、アクセルを踏み込めばしっかり車速は上がるのだが。
当時としては画期的な4駆とATの組み合わせとは言え、コンベンショナルな油圧式ATのため車速とアクセル開度だけでギア段が決まってしまうので、登坂時にロックアップが作動したり、意図せずシフトアップしてしまうことから駆動力不足が生じて実力よりも遅いと感じてしまう感はあった。一歩先ゆく運転感覚を身に着けるためには電子制御化されたE-ATの搭載が待たれていた。積極的に走るときは7000rpmまで回せる恩恵にあずかってO/D OFFと2レンジを使った方がいいだろう。
加速時に少し駆動系と思われる比較的低めで唸るようなノイズが気になった。これはコンポーネントが増え、複雑な4輪駆動ゆえに多数の共振点と伝達経路を持ってしまうため仕方ない事だ。
車速が上がってきて誰でも感じられるブルーバードの良さはタイヤの接地感である。ATTESAなんだから当たり前、と怒られそうだがフルタイム4WDの良さはまさに4輪で路面を掴む感覚で私が初めて4WD車を所有したときに感じた感動が得られる。車体が低いので多少大きくロールしても恐怖感がなく、べったりとタイヤが路面をとらえている。そしてこの高いシャシ性能を発揮させている縁の下の力持ちがボディのしっかり感だ。ピラーレスH/Tでありながらサイドドアガラスからパキパキ音も出さずに剛性感が感じられたのには驚いた。過去に試乗した他社のピラーレスH/Tと比べると日産の経験が生かされているのだろう。あくまでもニュートラルな旋回性能や安定感ある加速などボディがしっかりしているからこその実力だ。
エンジンよりシャシーが速い状態こそが安全な実用車だとするならばSSS ATTESAはまさにそれである。これよりモアパワーを求めるとCA18-DET型ターボE/Gを積んだLimitedが用意されているし、NAでもう少しスリルが欲しいなら、ビスカスLSDが備わるFFを選ぶ選択肢もある。この時代はH/Tとセダンが同列に位置付けられていて販売上の序列付けを行っていない点も選ぶ人に優しい。
今回試乗したブルーバードH/T ツインカム1.8SSS ATTESAは新車価格248.6万円。
当時新車で売られていた私のカローラ1.6GT(MT)は153.2万円、ビスタH/T2.0VRフルタイム4WD193.6万円、コロナ2.0GT-Rは212.4万円、レオーネ1.8GT/IIが225万円なのだから、ブルーバードのプライスは決して安くない。それだけこのハイテク技術に自信を持っていた現れなのだろう。
それでもこのブルーバードはヒットしよく見かけた。それは日本人をターゲットに企画され、当時の技術アピールがうまく当時の顧客にマッチした結果と言える。
当時のCMを見ても読ませるカタログ本文を見ても意気込みとブルーバード愛を感じた。このクルマに携わった人はみんなブルーバードが好きだったんだろうなと伝わってくる。それだけに次世代で北米のニーズやバブルに目が眩んだ商品企画のゆがみが残念でならない。
ブルーバードのような技術アピールは現代では流行らない。流行らないだけで自動車メーカーの中の人は今も変らずに開発に勤しんでいると思うのだがもう少し技術をただしアピールする努力をした方が良いのでは?と感じた。世の中の全員がクルマに興味を無くしたわけでも無いのだし、技術のアピールは古くさいと脊椎反射的に言われがちだが最近こういう取り組みを続けているのはスバルくらいかなと思う。走行製造のCGの駆動輪を青く塗って「チュイーン」というモーター音のSEを追加して一丁上がりでは物足りない。
日産が本当に技術でガチンコ勝負をしていた時代の作品に触れられてオーナーに感謝申し上げる。
1991年式ギャラン 1.8ヴィエント ~ハイテク満載の背高セダン~
ブルーバードに乗った後で、当時のライバルだったギャランを運転する機会を得た。試乗車は後期型のお買い得仕様1.8DOHCを積んだヴィエント。N兄氏のご実家で愛用されてきた家族間ワンオーナー車でE35Aを名乗る。
1987年にデビューしたギャランは、「インディビジュアル4ドア」というキャッチフレーズがつけられていたが、これは80年代後半からの個人主義の進展をクルマで表現したもので、既にモノ揃え消費も一段落しつつあり、質の高さや自分らしさを表現するツールとして三菱が産みだした運転する喜びを生みアクティブな生活をもたらす新技術を散りばめ、従来の価値観と一線を画す存在感のあるスタイルで包んだ新型車である。
ここで「フルラインハイテク」の三菱らしい最先端メカニズムを軽く紹介したい。イメージリーダーだったVR-4は2.0L直4ターボE/G(205ps/30.0kgm)を搭載。元々三菱が得意としていたターボ技術とサイレントシャフトに加え、DOHC16バルブとしては世界初のローラーロッカーアームによって摩擦ロスを低減し、高回転まで気持ちよく回るスポーツエンジンを搭載。
更にシャシ性能も飛躍的にアップしており、「ACTIVE FOUR」と名付けられたギャランのシャシーはビスカスカップリングを使ったフルタイム4WD、当時流行していた4WS、Rrサスにダブルウィッシュボーン式を採用した4輪独立懸架、4輪ABSから構成されている。
4輪駆動を主役に安全で速い技術をセダンに包み込む思想は当時のスバルや日産でも行われていたが、三菱の場合FF用にもハイテク技術を開発してギャランに実装している。例えばアクティブECS(Electronic Control suspension)は車両姿勢を走行状態に合わせて空気バネを使って制御することで操縦性と乗り心地を両立しようと試みた。オリフィスを切り替えて減衰力を切り替えられるダンパーによってシャシの性格を変える試みは既に行われていたが、エアサスに手を出すとは当時の三菱らしい。
ステアリングセンサやアクセル・ブレーキセンサの感知でロール制御(外輪に給気し、内輪側を排気)、アンチスクワット、アンチダイブ制御を行う動作モードは他社でも実績があるが、アクティブECSはショックアブソーバーだけでなく空気バネの内圧を調整する点で効果を出しやすい。
更にエアサスならではの車高調整機能も備わり、高速域では車高を下げて安定性や燃費に配慮するだけでなく悪路を検知すると自動的に車高アップを図るだけでなく、整備用に車高を上げるとオイル交換が簡単にできたと言う。
アクティブECSはAUTOにしておけばクルマ任せで最適な状態に調整してくれるが、違いを分かり易くしたかったのか性格を割切りすぎたのか各モードの制御が極端だったと言おう当時のオーナーの声もあり、このあたりは現代のドライブモードが持つ悩みと変らないのだなと親近感が湧く。
ギャランは更に当時としては最先端のEPSをも一部グレードで実用化している。燃費性能のためのEPSではなく、SPORTモードを選べば操舵力をノーマルと中高速域で手応えの向上をスイッチ操作で切り替えられる特性のための採用をしている。現代のドライブモードでも行われるEPSチューニングを1987年の段階で実用化しているというのは先進性に恐れ入ってしまう。
更にギャランは単にハイテクを駆使しただけのオタクっぽいクルマでも無かった。
一目見てギャランだ!と識別できる全高1430mmというセダンの相場を無視したかのような背の高いフォルムはそれまでの背高セダンの先駆けだった1982年の初代カムリの1395mmをも越えていた。これまでの背が低く繊細で流麗なフォルムを是としてきた日本のセダンのトレンドに反し、マッシブで背が高いギャランならではの世界観を持っていた。
ビッグキャビンを実現するなら全高を上げるしかない。しかし、全長4.5mクラスのセダンで全高を上げてしまうと、ずんぐりむっくりのちんちくりん(悪口)になってしまう。同レベルの全高のままバランスが取れている車種は、例えば初代センチュリーが挙げられ、全長5mクラスで全高1450mmをマークしているが伝統的なセダンプロポーションを維持している。このことからギャランがいかに「異様な」プロポーションだったかが分かるだろう。
そのパッケージングを魅力的に見せる秘策はウエッジシェイプと逆スラントノーズ、サッコプレートとS字曲面である。
昔から背が高くキャビンが大きく見えすぎるクルマはその違和感を消すためにウエッジシェイプ(前下がり・後上がり)を多用する事例が多い。ギャランの場合、フェンダー先端からドアまでで傾斜させ、ウエッジシェイプ的だが、ベルトラインを極力水平に引きながらトランクリッドもその勢いで繋いでいるのでRrタイヤが小さく見えすぎる弊害を最小化している。プロポーションをよく見せる為にフロントエンドは逆スラントである。これによりE/Gフードを長く引っ張ってプロポーションを調整している。
そして前後バンパーの上下見切りを維持する形でサイドプロテクションモールとサイドマッドガードが融合した「サッコプレート」でボディを薄く見せている。ツートーン塗装やサイドプロテクションモールだけでも近しい視覚効果は得られるが、樹脂部品による成型自由度の高さを活かして平行線をたくさん入れている。ドアハンドル直下のキャラクターライン上は太陽光を受けて明るく見えハイライトにしている。ライン下は凹面で暗く見せることで実際のドアよりも薄く見せている。当時としては大胆な凹面を使ったくびれが類い希で有機的で力強い個性を持っていた。
「うねりのフォルム」と三菱自身が呼んだギャランのエクステリアデザインは競合関係にあったブルーバードやコロナ、カペラなどがまだスマートで流麗なプロポーションの美を追究していた時代にギャランだけが逆張りとも取れる背高フォルムを採用しながらも、数々の処理によって有機的でマッシブな力強さに変換して新時代のスポーツ4ドアに見せた。本来はスポーティから後退するパッケージングを見事に個性に置き換えた偉業は快挙だったと言っても過言では無いだろう。
2000年前後にセダンでも背の高いフォルムを提案する動きがあったが、ギャランほどの鬼気迫る絶妙なバランスを実現したクルマは無かった。彼らも追究すればギャランになってしまうし、当時はツートーンカラーやサッコプレートはオールドファッションであるとして使いづらかった面もあるがいずれにせよ一種の奇跡がギャランに起こったと言えよう。
今回試乗した1.8DOHC仕様はギャラン発売後に追加されており、それまで2.0のみだったDOHCのボアを縮小してを最量販帯域に展開した実質的主力エンジンである。2.0DOHC(140ps/17.5kgm)からは少々スペックダウン(135ps/16.2kgm)していたがサイレントシャフトやローラーロッカーアームなど先進的な機構を引き継いでいてお買い得感が高い。
1989年のマイナーチェンジでは2.0DOHCは145ps/17.8kgmに性能アップを果たし、のちに160psを発揮するプレミアム仕様になったため、1.8DOHCこそがレギュラーガソリン派に向けた実質的上級E/Gである。
試乗車はVientoというお買い得グレードである。2.0譲りの1.8DOHCの新E/Gを積み、過剰なハイテク装備をそぎ落としつつ、上位グレード相当の内外装のエッセンスを移植されている。14インチアルミホイールやマッシブなエアロバンパーや4シーター風スポーツシート、そしてA/Cとカセットデッキが装備されて175万円という価格は全く以てバーゲンプライスと言うほかない。
およそ実用面で引け目を感じさせず、ギャランの特徴を厳選して織り込んだお買い得量販グレードの鏡のようなサービス精神は三菱以外の各社が持ち合わせており、令和の自動車マーケッター達に爪の垢でも煎じて飲ませてやりたいくらいだ。
鍵を借りて当時珍しかったバータイプのアウトサイドドアハンドルを強めに引いて乗り込むとクラスを越えた快適なキャビンの居心地の良さが感じられた。セダンなのにタイトさが一切無く、開放感があり明らかに快適だ。
正面には大型のメーターが目に映る。このあたりは初代FFカムリの影響(特にタコ無しの大型速度計)も受けているのでは無いかと個人的には推測するが位置を追究してドライバーに見えやすく・近づけられた操作系は私個人は三菱重工が昔作っていた自動車教習所用のシミュレータでお世話になった事がつい昨日のことのようだ(20年以上前だが・・・)。
インパネは低めで包まれ感より開放感を重視している。オーディオ用2DINスペースが一番下にあり、冗談にヒーターコントロールがあり、一等地は空調ダクトが占めている。当時らしく全吹出し口にシャットダイヤルがつけられている。
当時のカタログを見てびっくりしたのは本目パネルがディーラーオプションとして設定されているのだが、これってまさにDreizack-Stern?
E/Gを指導してスタイリッシュなガングリップタイプのATを操作すると選択したシフト位置がメーター中央のシフトポジションインジケーターが動く。当時、AT普及期に誤操作によって暴走事故が増えていた時代だったのでシフト位置がどこにあるかをメーター中央にシフト順に直感的に表示したギャランは親切である。
近年稀なオフセット配置されながら手元に近いPKBレバーを下ろし、静々と走り出したギャランは極めて真面目だった。中は広くて快適で走りは真っ当。欲しい加速ができてブレーキも現代の車と較べて少しも不満が無い。
7000rpm以降がレッドゾーンとなる4G67はとにかく軽快な印象で加速が軽い。直前に試乗していた4WDのブルーバードとの対比で特にそう感じたのかも知れないがE/G音も比較的済んでいて小気味よい。具体的なフリクションの値は分からないが本来サイレントシャフトの影響でフリクションロスが増えるはずだが、ローラーロッカーアームによって幾分か取り戻したのだろう。
大型エアロバンパーに組み合わせてあるデュアルロードランプは、フォグランプなのに4灯式でLOビームだとフォグランプが点灯し、HIビームだとドライビングランプに切り替わるという贅沢な補助ランプである。ガラスレンズのハロゲンヘッドライトでも充分明るいはずだが、LEDはおろかディスチャージも無かった時代なので灯火類を積み増すことで光量を確保し安全性に寄与しているのだが、なんとも贅沢さを感じた。
試乗はアップダウンのあるコースで行われたが、ATは電子制御AT(2モード4速ELC)は良い働きをした。2つのシフトスケジュールを持つことが出来るので普段の燃費を意識した早めのシフトアップ(ECONOMY)と引っ張り気味の(POWER)を任意で選択できる。
シフトスケジュールだけでなくロックアップ作動も制御するので上り坂での走りっぷりは大きく変わる。スイッチで選択するタイプは見た目にも「有り難み」がある一方でイージードライブ派(ほったらかし)の人たちは存在に気づかないまま生涯を終える可能性もある。そこで90年代中盤以降でスイッチ操作を行わなくても車両側が登降坂や曲がり角やコーナーを検知して自動的にシフトダウンを行えるように進化をしていった。ギャランのELCは存在を知っている人だけが積極的に操作することで意のままの走りを手に入れることができる。オーナーも上り坂では積極的に操作しているそうだ。
ギャランのサスペンションはFrマクファーソンストラット/Rr3リンク式トーションアクスルという形式でいわゆるトーションビーム式を採用している。これは駆動輪から切り離された後輪を活かしてワイドトレッドやキャンバー変化の小ささに目をつけた為である。
前後方向入力はトレーリングアーム、横力はラテラルロッドが受け持ち、左右逆相の場合は左右を繋ぐアクスルが捻れることで、半独立懸架的な立ち位置の車軸式懸架である。単純なリンク機構のためラゲージスペースが広くなるメリットもありギャランのFF系は3リンクトーションアクスルを選んだ。この方式に弱点が無いわけでは無く、ラテラルロッドが水平配置と言えどもストロークするとロッドが円運動するためにスカッフ変化があり車体とタイヤの位置関係がズレてしまう問題がある。
余談ながらこの問題をスグリを入れたブッシュで解決しようと試みたのが日産が1994年に市販化したマルチリンクビームサスペンションである。
一方、ハイパワーを受け止める4WD系はマルチリンク式と差異があるがFFも決して悪くない。不快な突き上げ感なども無く充分レベルの高い走りを実現していた。
ギャランは、先代までのマークII的なハイソ感覚から脱却して生命的な力強さを表現したボールドなセダンという新しい立ち位置で勝負をした。そこに三菱らしいハイテクが散りばめられておりカーオブザイヤーを受賞するのも納得の力作だった。
試乗車は複雑な機構は控えめで信頼性が高く、基本がよくできた真面目なセダンだった。
このギャランが以降のギャランの方向性を決定づけ、2005年に国内販売が終了するまでのイメージ的な原典になったが、特に痛かったのは試乗車の次期モデルに当たる92年発売の7代目が全く不評で評判を落としてしまったことである。バブル景気の最中にイケイケで開発されて大きく上級指向になって女性からの支持を得るためにデザインを変えて、キャビンも小さくしてしまった。同じようにカペラもアコードも3ナンバー化で失速し、ブルーバードもコロナもバブルで踊らされてしまった。(オースター後継という控えめなキャラゆえに地に足の着いたプリメーラはモデルライフ的にもバブルに踊らされずに済んで被害が少なかった)
このクラスのセダンがマーケットのボリュームゾーンで良い技術が集まってきた、という素晴らしい時代の頂点にあった一台がギャランであり、先に試乗したブルーバードだったんだなとしみじみ思う。三菱の名作に触れることが出来てオーナーに感謝申し上げる。
2001年式プリウスプレミアム21 ~0→1にした革新的なクルマ~
1997年、「21世紀に間に合いました」でデビューしたプリウスは世界初の量産ハイブリッド乗用車である。世界初のシリーズパラレルハイブリッドTHSを搭載して当時のガソリン車の約2倍の燃費を達成した。日本国内で発売し、世界中の注目を集めた。
初期の改良点を織り込んだ上で2000年に初のマイナーチェンジを実施した。このマイナーチェンジ版は燃費を向上させながらバッテリーの小型化でトランクスルー機能の追加やトランクスペースの拡大(362L→392L)、ウォッシャータンクの容量拡大(2.5L→4.1L)など地道な改良が施された。このモデルから欧州や北米に輸出されて自動車先進国はハイブリッド車を知り、恐れをなした。
プリウスの特徴的な心臓部であるTHSはE/Gと駆動用モーター、発電用モーターを持っている。後退と発進はモーターによる駆動のみで行われるが、モーター性能を超える場合にE/Gからの動力を混ぜて足し合わせて走行している。なのでハイブリッド車の最高出力はシステム出力で示されてガソリンE/G+モーターの最大出力を掛け合わせた(≠単純和)値になる。例えば今回試乗した2001年型プリウスは100ps程度とされる。
モーターだけで駆動の全てを賄うシリーズハイブリッドはシンプルだが、これだと最高速度までカバーする大きなモーターが必要になるのと高速域でE/G単独運転ができなくなる。
一般走行時にE/Gがかかっているが、この時の運転状態は効率MAX状態なので穏やかに加速していたとしてもE/G回転数は高め一定で回っている。
E/Gには燃費が最良になる「燃費の目玉」という領域があるがここをめがけて運転している。それが例えばN回転/Pキロワット、などと決まっている。
走行するときに必要な駆動力を算出し、最大効率点のE/Gパワーよりも要求が小さければ、駆動力を全て電気に変換してモーターだけで走らせるか、必要なパワーだけでE/G駆動する。余剰動力は発電モーターを使って電気に変換して貯めておけば無駄にならない。一時的に踏み増したときは駆動力がE/Gの動力を上回る場合、バッテリーからモーターを駆動して補助するが、全開加速時はバッテリーに蓄えられた分の電力も動員してモーターを使う。
プリウスの低燃費の本当の秘訣はアイドリングストップでも発進時のモーター走行によるものでも無く、E/Gを常に燃費最良点に固定して使用している点であることは意外と知られていない。
いままでのICE車とは違い、E/Gが直接動力性能に寄与しなくて良いので極端に低出力低燃費の性格に振り切っていたのが初期モデルだ。現代も残る1NZ型にアトキンソンサイクル(遅閉じミラーサイクル)を組み込んだ1NZ-FXE型E/Gは58psしか発揮しなかったが、モーターが33kW(44.9PS)と組み合わせれば、およそカローラ並の動力性能を持つとされていた。ただ、前期型は動力性能が実用ギリギリで伊勢湾岸道を走らせると亀マーク(出力制限警告灯)が点灯して速度が思うように出なくなった苦い思い出がある。
今回試乗したマイナーチェンジを受けた後期型ではE/Gを73psまでパワーアップさせ、モーターも一時的にアップする制御や回生強化を行った結果バッテリーも小型化しながらもカタログ燃費は28.0km/L→29.0km/Lまで向上させた。
前期型には幸いにも運転経験があるが、後期型は運転したことが無かった。今回は駐車場からの移動時にドライバーを買って出て短時間だけ運転させていただいた。
試乗車はハチマルミーティング2024にエントリーしていたプリウスである。ユーロPKG風だが、Rrブレーキがドラムなので丁寧に仕立てられたユーロPKG風である。車高が少し落とされていたり、ピンストライプが入っていたり、北米仕様の本物部品が着いてたり、オーナーの色にしっかり染まっているものの、初代プリウスの良いところがスポイルされない範囲に留めてあるのはオーナーの見識である。
ちなみに実際のユーロPKGはRrディスクブレーキやRrバンパーR/F(左右を繋ぐブレースとして活用)を装着して欧州で見られる走行条件に適合した成果を日本仕様で味わえるセットOPTである。
久しぶりに運転席に座るとプリウスのパッケージングの気持ちよさは1mmたりとも色褪せていない。着座姿勢そのものがアップライトで気持ちよく、視界も開けている。アップライトでキャブフォワードでセンターメーター、という2000年前後のトヨタが空力性能(前方投影面積が悪くなって不利)をCD値低減で相殺して実用化したインテリジェントパッケージだ。
アメリカはカリフォルニア州に設立されたCALTYでデザインされた初代プリウスは3BOXセダンの形態を取りながら異様とも言えるずんぐりむっくり度合いはお世辞にもカッコイイとは言われなかったが、一目でプリウスだ!と分かる個性を持っていたし私はとても好意的にこのクルマを見ていた。
キーをさして捻るとセルは回らないが「READY」の表示が出る。デスクトップPCの様なスタートスイッチが現われるのは2003年の2代目まで待たねばならない。
左手でDレンジに入れた。ガングリップタイプのコラムシフトは操作しやすく
サイドウォークスルーをも実現していた。後年のミサイルと称された交通事故が増えた時期でも、初代がニュースになる事はよっぽど無かった事実がこのシフト機構の優秀さを端的に物語っている。
2023まで継続採用されていた足踏み式PKBを解除し、ブレーキを離すとEMVはEVであることを淡々と表示していた。この走り出しで一体何人のオーナーがドヤ顔をしてきたのだろう。
初代が売られていた当時、THSの原理などをよく知りもしないまま強めにアクセルを踏んでしまっていた。ジワッと踏んであげればちゃんとEV走行で走り出すことが出来るし、60km/h程度までちゃんとモーター単独で走行が可能だった。ショック無くE/Gが始動すると、EV走行が終わった「がっかり感」はあるものの、NVもよく躾られていた。当時としては珍しい2点+トルクロッド式のE/G懸架方式が採用されて振動伝達には有利な方式が採られていたのである。新しい時代の乗り物を感じさせるNV性能は、現代のTNGA群にも引き継がれて欲しい美点だった。
ルートは上り坂があったりカーブがあったりしたが「ホントにEPSなの?」と思うほどラックEPSのフィーリングは自然だし、登坂時にアクセルを踏み増しても、暴力的な加速はしないまでも、スーッと車速は上がってコーナーも不安感無くクリアした。ここはオーナーの手が入っている部分だとは思うが、初代前期型の低転がり一直線のタイヤはウエットグリップに難があって急制動時にABSが作動しても障害物を避けられるもののその手応えが希薄で冷や汗をかいた思い出もあったくらいだったので、こんなに気持ちよく走ることが意外だった。
我が儘を言って予定よりも長く10分程運転させていただいた。後年のもっと燃費も加速も良くなった世代が持っている不自然さや不快さが顔を出さないことは私にとってはとても意外だった。それだけ初代は在来型E/G車ばかりの市場で全く新しい動力源のクルマの味を作り込んだというエビデンスなんじゃ無いかと思う。初代プリウスがハイブリッド乗用車の世界を「0から1にした」功績は大きい。物体を引きずるときも静摩擦係数>動摩擦係数ゆえ、動き始めるときの方が大きな力を要するものだ。
一旦プリウスが世に出た後は「こうした方が燃費には良いんです」と理屈を並べれば不便で不自然なことでも平気でやってのける。でも最初から違和感の塊のようなクルマを世に出しても受け入れられずに大事な技術が花開かなくなったはずだ。
動力性能不足やカックンブレーキは初代でも指摘をされてきたが、その他のヘンな感覚を「特別なハイブリッドカーだから」と様子見で済ませ続けた結果が空前の大ヒットを記録した後で指摘が増えた3代目プリウスのブレーキ抜け問題だったのかもしれない。
肝心の燃費は21.6km/L。そんなにエコ運転に徹したわけではなかったが、2000年前後のモデルを集めても上り坂もあるコースをたった10分サラッと乗っただけで21.6km/L出せる車種はプリウスくらいだろう。
私は「所有するならMT限定」という宗教的縛りを課しているが、もしもこれに背くなら初代プリウスは所有してみたいクルマの一つだ。今回の試乗で歴代全てのモデルを単独運転した経験を得ることが出来たのだが、初代の力作っぷりは特筆ものである。何回も書くが、欧米先行の自動車技術のなかで日本人の英知を結集させた世界初の量産ハイブリッドカー、という名に恥じぬ実力を今も失っていない。
是非、THS車のオーナーもそうで無い人もオーナーの方が2002年に製作された
プリウスドライビングシミュレータ も面白いので体験してみて欲しい。
ただ、私のようにこのクルマに興味を持ったとしても初代プリウスのチーフエンジニアだった内山田氏が会社から離れたと同時にニッケル水素電池の補給が途絶えたらしいので維持しにくくなっていることは間違いない。初代が27年前と言うことを考えれば立派なクラシックカーゆえ仕方が無いという理解もできる。ただ1970年代までの旧車とは違い、電子部品のちょっとしたNGだけで走れなくなってしまうハイブリッドカーに代表されるエコカーをネオクラシックとかヤングタイマーと呼んで維持する事は今後とても難しくなってきてしまうのではないかとも感じた。
貴重な初代モデルに載せていただきオーナーに感謝申し上げる。























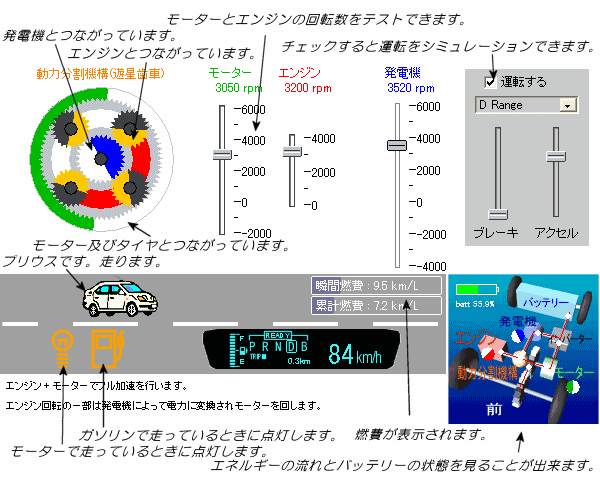
 ふたつの40周年
ふたつの40周年










































 ~超多忙からのハチマルミーティング~
~超多忙からのハチマルミーティング~



























































 ●ホンダの数少ない日本市場特化型モデル
●ホンダの数少ない日本市場特化型モデル



 ●ハイト系×前席優先のパーソナルカー
●ハイト系×前席優先のパーソナルカー








