
アメリカの理想郷。
そう名付けられた映画「アメリカン・ユートピア」。
以前からデイヴィッド・バーンが行なっている
ミュージカルパフォーマンスを
そのままドキュメントとして映像化した作品だ。
撮影監督はスパイク・リー。
彼が撮ったという時点で
ある種のメッセージを持った映画だということがわかる。
そしてデイヴィッド・バーン。
自分たちの世代は、トーキング・ヘッズなしでは語れない。
とは言っても、ずっと好きだったわけでもなく、
パンクであってパンクにあらず、
レゲエ、スカ、アフリカビートなど、
ニューウェーブの変化系という認識でしかなかった。
とはいえ、ルー・リードにも通じる、
クールでありながら熱くエモーションナル。
「STOP MAKING SENSE」で見せた
スタイリッシュなパフォーマンスは、
確かに心を惹かれた。
ただ、音楽的に好きになってきたのは、むしろトーキング・ヘッズ以降。
年齢を重ねた中で、バーンの声を聴くと、
妙な懐かしさの中にもプリミティブなリズムと音が、
自分のフィーリングにすごくマッチするのだ。
「アメリカン・ユートピア」は、
トーキングヘッズとデイヴィッド・バーン、
カヴァー楽曲を織り交ぜながらステージが進んでいく。
プリミティブなリズムの中で、
エレキギター、キーボード等を使うところには、
デジタルと融合していく現代社会の音そのもの。
コリン・キャパニックが映像に映し出されるところから、
よりメッセージが明確になっていく。
曲の最後にはニーダウンして拳を突き上げるポーズ。
スポーツファンなら誰もが知っている話ではあるけれど、
これは、人種差別をあからさまにするアメリカという国に対して、
国歌斉唱の際、歌うことを拒否。その意思表示のポーズでもある。
保守的な愛国者の支持者の多いNFLはこれにいい顔はしなかった。
同調する選手、否定する選手、オーナー側もまちまちの対応。
結果としてアメリカの分断の一端をあからさまに見せた事例だ。

こうした現在のアメリカが包容する歪みと対局にある、
ステージ上にいる多様な人種が織りなす音、動き、言葉の調和性。
そこから伝わってくるのは、人間賛歌だ。
人のつながりによって無限大の表現力と力を持って、
現状に甘んじるおとなく、理想郷実現のためにの未来を変えて行こう!
そんなメッセージにもなっている。
監督のスパイク・リーの映画はずっと好きだ。
「DO THE RIGHT THING」の頃は、
怒りにまかせて映像を作っていた印象だったけれど
怒りだけでは世の中は変わらない!
「GET ON THE BUS」あたりから、
怒りよりも持ち前のユーモア感覚が冴え始め、
大好きなバスケを題材にした「ラストゲーム」では、
映像的にも洗練された世界を見せている。
根底にあるメッセージは変わらなくても、
よりエンターテイメント性を高めて、
ブラックカルチャーを表現し続けている。
「アメリカン・ユートピア」は、大した照明もなく、
今どきのコンサートにありがちな大掛かりな装置は一切ない。
全員がほぼ同じスーツを着て、ただ歌って踊るだけ。
ただ、それが素晴らしい。ステージの動きを計算し尽くして、
どの場面をどう撮ればいいか、徹底的に考えられたカメラワークも見事。
かつてザ・バンドの「ラスト・ワルツ」で
マーティン・スコセッシが見せたものと同等のクオリティを感じさせる。
マーティン・スコセッシ「ラスト・ワルツ」、
ヴィム・ヴェンダースの「ブエナビスタ・ソシアル・クラブ」。
そして、このスパイク・リーの「アメリカン・ユートピア」。
音楽ドキュメント映画の傑作は数あれど、その中でも最上級の映画だ。
Posted at 2021/05/30 10:27:16 | |
トラックバック(0) | 日記
 静岡 vs.岡山 の負けられない戦い
静岡 vs.岡山 の負けられない戦い 





 アメリカン・ユートピア
アメリカン・ユートピア 

 あと60日! 変化する街
あと60日! 変化する街 




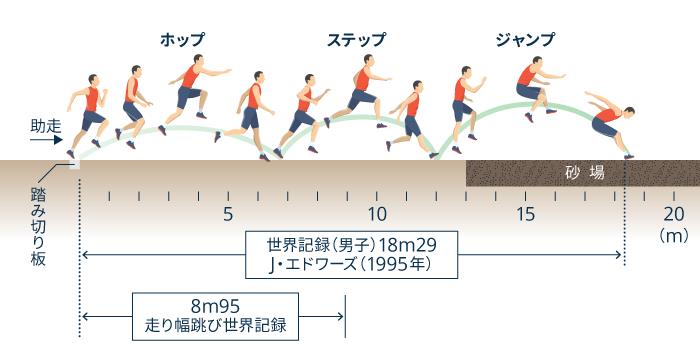






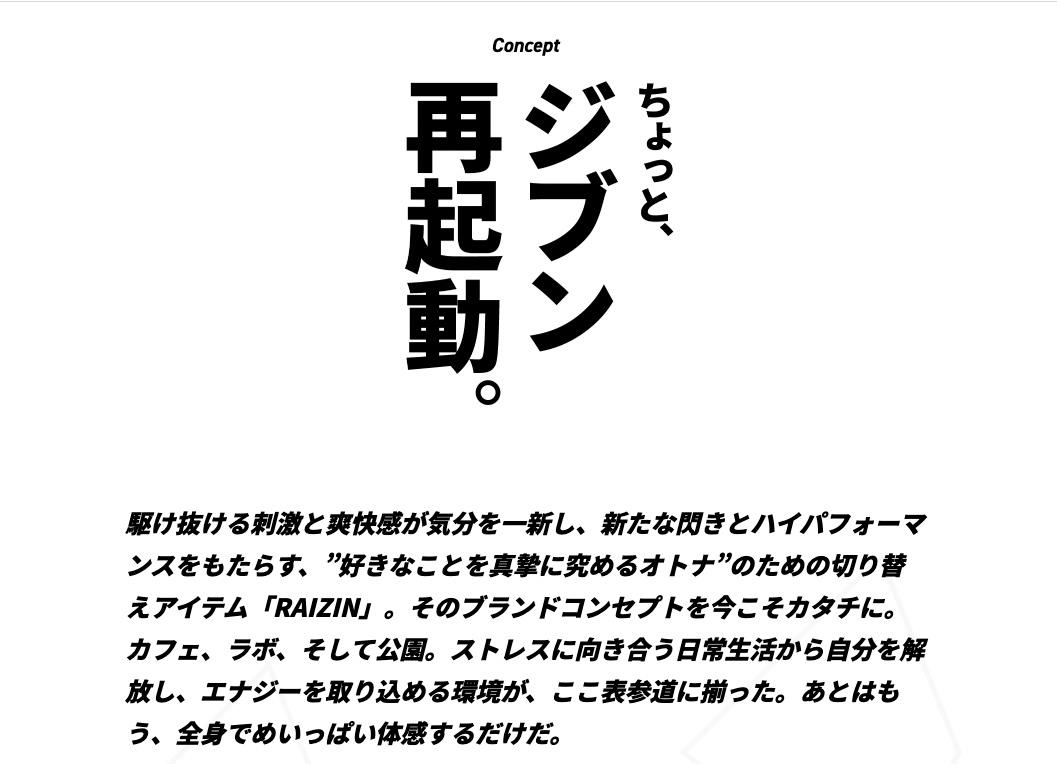


 今年初の富士山
今年初の富士山  このところ週末、ほぼスポーツを見ています。
このところ週末、ほぼスポーツを見ています。










 ガッキーと星野源
ガッキーと星野源 








