
ウチの987ケイマンSは、前後4podのBrenbo製対向ピストン式のブレーキが付いています。
PORSCHEのブレーキ性能要求はかなりのレベルで、エンジン出力の3〜4倍の制動性能を要求しています。

987ケイマンSは295PSなので、885〜1180PSにもなります。
確かにPORSCHEのブレーキの凄さは自分でも実感しており、実際ノーマルのままでもFSW数周なら保ってしまいます。
(ノーマルパッドだと数周でパッドが炭化しますが…)
FSWのストレートでは987ケイマンSだと245km/h位ですが、そこからフルブレーキングすると150m看板だとかなり余ってしまう位効きます。
効きだけで無く、踏んだ時の剛性感やコントロール性の高さも特筆モノです。
ミッドシップレイアウトも有り、つんのめってしまわないので急制動時も安定して減速出来、某自動車評論家が「宇宙一」と評するのも分かる気がします。
先日ウチのBMW X1(F48)のブレーキパッドを交換して印象が激変した事を書きましたが、BMWは昔から一部のハイパフォーマンスモデルを除いてフローティングキャリパーを採用しています。

しかし、だからと言って特に不満は無く、1.7tも有るF48 X1を止めるのに十分な容量を持っており、タッチも987ケイマンSには及ばないものの、それ程悪い訳では有りません。
今回はブレーキについて書いてみようと思います。
①フローティングキャリパー式

いわゆる「片持ち式」ブレーキです。
ピストンはホイール内側だけで、ブレーキを踏むとピストンがディスクの内側からパッドを押して圧着し、その力でキャリパーが内側にスライドして外側のパッドをディスクに押し付けて制動するタイプです。
フローティングキャリパーの作動概要図。
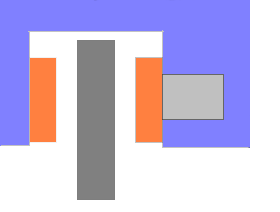
(アドヴィックスセールス株式会社HPより引用)
フローティングキャリパー式ブレーキは対向ピストン式ブレーキに対して、制動力と言う面では、余程重量級のクルマで無い限り、それほど劣っている訳では有りません。

ブレーキパッドが大きくなり過ぎると、平均して押し出す事が難しいので向いていませんが、そこそこの大きさなら全く制動力に問題は有りません。
実際、ブレーキ性能はキャリパーだけで決まるものでは無く、タイヤのグリップ力を超える制動力を持たせる事が出来れば、フローティングキャリパー式ブレーキでも対向ピストン式ブレーキでもあまり変わりません。
フローティングキャリパー式ブレーキのメリットは、
①部品点数が少なく、軽くてコストが低い
②キャリパーがコンパクトな為、ホイールの設計自由度が高い
③鋳鉄製キャリパーなので、熱で開いてしまう様な事が無い
と言う事です。
フローティングキャリパー式ブレーキのデメリットは、
①パッド面積が大きいと、パッドを平均して押し出す事が難しい
②構造上片側から押して反力で反対側を押し付けるので、パッドが偏摩耗しやすい
③上記と同じ理由で、ブレーキタッチは対向ピストン式ブレーキに劣る
辺りでしょうか。
昔はスーパー耐久でも市販車のブレーキ形式を変更出来なかったので、NSXやS2000はフローティングキャリパー式のままレースをしていました。
それでも優秀な成績を収めていたので、フローティングキャリパー式だからダメと言う事では有りません。
実際、自分も前の愛車のALTEZZAの時はパッドやフルード、ブレーキホースは交換したもののブレーキはフローティングキャリパー式のままでしたが、サーキット走行でも特に問題は出ませんでした。
無論、FSWやTwinringもてぎの様な高速サーキットを連続でアタックすると、当然タレて来ますが、少なくとも筑波2000位であれば走行枠20〜30分の走行会の間はちゃんと保ってくれました。
②対向ピストン式

名前の通り、内側と外側の1組以上のピストンが両側からパッドをディスクに圧着させる方式です。
対向ピストン式ブレーキの作動概要図。
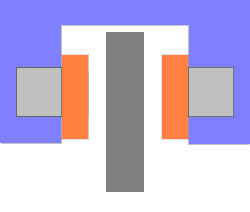
(アドヴィックスセールス株式会社HPより引用)
対向ピストン式ブレーキのメリットは、
①大きな面積のパッドでも平均して押し出す事が出来る
②表と裏から同時にパッドをディスクに押し付けるので、コントロール性に優れている
③上記と同じ理由でパッドの偏摩耗が少ない
と言う点です。
対向ピストン式ブレーキのデメリットは、
①構造が複雑で部品点数が多い為、コストが高く、重量が重くなる
②キャリパーが大きい為、ホイールの設計に制約が有る
③上記①の理由でアルミ製キャリパーを採用しているが、酷使するとキャリパーが開いてしまい制動力が低下する
と言う点です。
実際、ウチの987ケイマンSや911のType997までは、Brenbo製モノブロックキャリパーのパッド取り付け部はボルトだけで大きく開いていて、ボルトを抜けば簡単にパッド交換が出来る構造でした。

とても便利だったのですが、車重があってパワーの有るクルマ(Carrera SやGT3、GT2、ターボなど)の場合、サーキットで酷使すると熱でキャリパーが変形して開いて来てしまう現象が起こりました。
911のType991以降やケイマン/ボクスターの981以降は、キャリパーの開口部にブリッジが付く様になり、キャリパー剛性が大幅に向上しました。

しかし整備性と言う面では少し面倒になりました。
恐らく重量的にもかなり重くなっていると思います。
対向ピストン式ブレーキは見た目もカッコいいので、交換したくなってしまう事も有ると思いますが、元々対向ピストン式ブレーキのクルマは設計がそうなっているので問題が少ないですが、元がフローティングキャリパー式の場合は対向ピストン式ブレーキにする事によってホイールと干渉したり、それを避けるためにオフセットの大きいホイールに変えると、今度はスクラブ半径が大きくなってハンドリングに影響が出たりします。
③曙ブレーキの新構造キャリパー
2年前の東京モーターショーに曙ブレーキが新構造キャリパーを出展していました。

このキャリパー、フローティング式なのですが、フローティング式の弱点を克服するアイディアで作られています。
このキャリパーの特徴は、2つのピストンが背中合わせにつながった形状のピストンを採用している事です。

写真真ん中あたりの丸いのがピストンですが、このピストンが内側と外側両方に押し出されます。
するとホイール外側のピストンはホイール内側のディスク面にパッドを圧着しますが、ホイール内側のピストンが同時にキャリパーをスライドさせてホイール外側のディスク面にパッドを圧着します。
フローティングキャリパー式の弱点を克服してブレーキタッチを向上させ、パッドの偏摩耗も従来の1/5になったそうです。
そしてキャリパーをアルミ製にしたお陰で重量も30%低減しているそうです。
このキャリパーなら、フローティングキャリパー式のメリットである低コストで軽量と言う長所や、ホイール設計の自由度が高いと言う長所を維持(若干コストは上昇するものの対向キャリパー式に比べれば安くて軽い)しながら、タッチやコントロール性を向上させる事が出来ると言うスグレモノです。
ブレーキは自分が知っている限り、何十年もの間基本的な構造は変わらずに進化して来ましたが、曙ブレーキの新構造キャリパーの様な革新的な進歩もしている訳ですね。
④PORSCHEの「PSCB(Porsche Surface Coated Brake)」
2018年にモデルチェンジした現行のカイエンターボでワールドプレミアされた「PSCB(Porsche Surface Coated Brake)」。

ディスクローターがタングステンカーバイドでコーティングされており、通常のブレーキよりも30%の耐久性向上とダストの低減を実現すると同時に、連続使用での耐フェード性も向上しているそうです。
セラミックコンポジットブレーキ「PCCB」に匹敵する制動力と、低コスト・低ダストを実現しているそうです。
これならカーボンブレーキ特有の、サーキット走行すると異常に寿命が短くなると言う弱点や、ディスク交換で200万円と言う超高コストを恐れなくて済むので、サーキット派の人々には朗報かもしれません。
まだカイエンだけの様ですが、その内Type992にも採用されるのでは無いかと思われます。
ちなみにこのブレーキシステムも曙ブレーキ製だそうです。
と言う訳で、ブレーキ関係のテクノロジーでした。
安全装備などでクルマがどんどん重くなり、パワーが向上する中で、それを制御するブレーキシステムもどんどん進化していっているので、そのクルマに合ったブレーキシステムについて知っておくのも良いかもしれません。

























































