
アイドリングの時でも、エンジンは 1分間に600回転以上、1秒間なら10回転以上は回転している。もしも、その回転数のままタイヤに直結すると、1秒でタイヤ10回転分の距離、約21メートル進む。時速にすると約76km/hだ。
けれども、エンジン 1回転の力(2気筒なら 1爆発、4気筒なら2爆発、6気筒なら3爆発)などでは、もちろん、1~2トンもある車体を支えるタイヤを 1回転させることなど、到底できない。だから、ギア(大きい歯車と小さい歯車の組み合わせ)を使って、タイヤの回転数をエンジンの回転数の10分の 1くらいに減らすことで、逆に、タイヤを 1回転させる力を10倍くらいに増やす。この増やし方がギア比だ。
車のギアは2ヶ所にあって、一つはエンジンのすぐ隣で、クラッチを挟んでつながっているギア本体だ。もう一つは駆動輪の近くで、左右のタイヤに回転と力を分ける部分につながっている。こちらは、最後の方のギア、という意味で、ファイナル・ギアと呼ばれている。
たとえば、ギア本体で 1速を選ぶと、エンジンの回転数は4.714分の 1に落とされ=エンジンの力が4.714倍に増やされる。さらに、ファイナル・ギアが、それを 1/2.929回転=2.929倍の力に変換する。4.714×2.929≒13.8だから、もしもエンジンが毎分1,380回転していたら、タイヤは毎分(1380/13.8=)100回転(毎秒約1.7回転、毎時6,000回転=12.7km/h)して、エンジンの力を約13.8倍にして路面を押す。これが車の発進だ。
ひとくちに「車」といっても、エンジンのパワーは色々だし、重い車もあれば、軽い車もある、スポーツ・カーもあれば、4駆のSUVもある。というわけで、仮に同じギア本体を使っていても、エンジンや車種によって、ファイナル・ギアは変えられている。エンジン・パワーが少ない車や、重い車ほど、ファイナル・ギア比を大きくして、回転数を減らす代わりに力を増やせば良い。
このことを、目で見てわかりやすく確認したかった。それで作ってみたのが、次のグラフだ。

「もしも、ファイナル・ギアが、車種を超えて同じだったらどうなるか」…それが左側のグラフだ。右側のグラフは、車種ごとにファイナル・ギアが異なっている、実際の設定だ。縦軸はパワーを、横軸は速度を表している。パワーも速度も、エンジン回転数に対応しているからだ。
簡単に言えば、各曲線の傾きが大きい(立っている)ほど、ある速度の時に使えるパワーが大きい、という意味になる。アクセルベタ踏みの時の加速の良さ、とも言える。
データには、F10の5シリーズを用いた。赤ラインのN52-523iはガソリン6気筒版、緑ラインのN20-523iは、ガソリン4気筒ターボ版、黒ラインのN47-523dは、ディーゼル4気筒ターボ版だ。これらの車は、すべて同じ8速ATを搭載して、ファイナル・ギアだけが異なっている。だから、数値は少しずつ異なるが、この傾向はF30の320d(2.813)と320i(3.154)についても、同じように当てはまる。
比べてみてわかることは、実際のファイナル・ギアの設定によって、赤、緑、黒の各ラインが寄り集まったこと、つまり、各車種間のパワーの差が縮まったことだ。たとえば、N52-523iの最高出力(150kW)時の速度が、左側のグラフでは約58km/hだが、右側のグラフでは約50km/hに早まっている。これは、より手前の速度で、より大きなパワーが使えるようになった、つまり、ベタ踏みの時の加速が良くなったということだ。逆にそれだけに、エンジン回転数の割には、タイヤ回転数が減らされているので、燃費は悪くなる。それに、1速で出せる最高速度も落ちている。
しかしもちろん、車は 1速だけで走っているわけではない。車が速度を上げて、グラフの曲線が頂点を超え、パワーが落ちてきたら、次のギアにバトン・タッチをする。そこで次に、各車種の 1速~3速(523dは4速)までのグラフを見てみる。

このグラフはとても面白くて、私にはいくつか発見があった。
緑ライン、N20-523iを見る。1速では 135kW、40km/hちょっとから50km/hちょっとまでの間に、水平部分、つまりフラット・パワー帯がある。同じような水平部分は、2速、3速にもある。私は
初めてN20B20のエンジン性能曲線を見た時から、フラット・パワーの存在理由がよくわからなかった。パワーがそれ以上伸びないのに回転を上げても、燃料や時間の無駄になるだけだろう、と思っていたのだ。
それが、このグラフでやっとわかった。フラット・パワー帯があるおかげで、次のギアにバトン・タッチするまで、一定のパワーを維持できるのだ。だから、N20-523iのシフト・アップはとても滑らかで、バトン・タッチの間のパワー・ロスがとても少ない。
これに比べると、赤ライン、N52-523iのバトン・タッチはなかなか大胆だ。1速は140kW、55km/hちょっとでレッド・ゾーンに飛び込んでしまい、やむなく2速にバトン・タッチする。ところがその速度では、2速はまだ120kWにも達していないのだ。助走が十分ではないのに、バトンを渡されたのと同じだ。でも文句を言っても仕方がない。2速は頑張ってピークを目指して爆走し、同じように140kW、83km/hほどで息切れして3速を探すと、やはり3速も120kW足らずで待っている…そんな具合に、上がり下がりの激しいリレーだ。
黒ライン、523dも独特だ。何よりも足が速い(曲線が立っている)。ところが、1人で走れる距離が短い(最大回転数が低い)ので、バトンを渡すタイミングが早い。他の2車が3人でリレーしているところを、4人でやっているのだ。それがパワー・ロスになる。と言っても、赤のN52-523iほどの上がり下がりではない。かと言って、緑のN20-523iほどスムーズでもないのだ。
話は少しそれるが、そもそも、この523dのエンジン性能曲線(320dと同じ)では、最大回転数は4,500回転にも満たなかった。ところが、実車のメーターを見ると、レブ・リミットは5,400回転に上げられている。本当にここまで回すとどうなるのか?それは上の最初のグラフに示した通りで、50km/h弱の時点で出力は40kWを切っている。けれども実際は、120kW弱、40km/hちょっと(約4,500回転ほど)で2速にバトン・タッチされるから、5,400回転のレブ・リミットに至ることはない。だから私には、523dや320dのレブ・リミットが高い意味が、いまだにわからない。
さて、最後に、このグラフの高出力部分だけを切り出して見てみる(赤ラインには補助線を引いた)と、上に書いたような、この3車の走りの個性がよくわかる。ただし、何度か書いているが、これはアクセルベタ踏みの全開走行時の個性だ。

スムーズでシームレスなギア・チェンジで、一定の加速度を保つ、緑ラインのN20-523i。
パワフルで瞬発的な加速を、ギアを駆使して何度も繰り返す、黒ラインのN47-523d。
そして、遅れたスタートから、派手な加速をドラマチックに見せる、赤ラインのN52-523iだ。
※この記事は、車の仕組みの一部だけを取り出して、理論上の傾向を書いたものだ。実際の車は、エンジンや補機類によって重量が異なるし、エンジンとギアの間の「フライホイール」や、ギア本体の「トルク・コンバータ」が、車種ごとにパワーを制御している。なお、速度計算にはタイヤ外径を「675mm」とした。またメーター速度は、法規により、実速度よりも高い数値を示すこととされている。
※ 1/19追記 … 赤カブ望さんが、私の記事へのコメント代わりに、なんと
ご自分の記事を構成されたので、そちらへのトラック・バックを追加した。
※ 1/22追記 … ALPINA D3 BiTurboとN52-523iとALPINA D5 Turboのグラフを以下に追加した。

D5 Turboのファイナル・ギア比は「2.471」と、とても低い「ワイド・レシオ」だが、このようにグラフ化して比較すると、それでも十分に、橙ラインの各曲線の傾きが大きい=加速度が大きいことがわかる。1速~8速までのつながりもとてもスムーズ、かつ「クロス(近接)・レシオ」的で、日本では到底望めない最高速までスポーティに伸びていくのが目に見えるようだ。
また、面白かったのは、緑ラインのD3 BiTurbo(6AT)が、紺ラインの523i(8AT)の少し上を、かなり似たステップで、シフト・アップされていく様子だ。つまりD3 BiTurboは、8ATのガソリン・エンジンとよく似たパワーの伸び方を見せる車だ、ということがわかった(なお、このグラフには車重その他の要素は含まれないので、実際のD3 BiTurboはもっと加速が良い)。
それは同時に、523iの7速・8速が、いかにも燃費対策に付け加えられたギアであるように見える。だからたとえば、全力疾走するD5 TurboやD3 BiTurboには、523iは全然追いつけないが、8速や6速で、時々加速をまじえながら走るD5 TurboやD3 BiTurboを追走するには、523iは最低でも5速は維持する必要がある、ということがわかる。
それからこのグラフには、薄緑で着色した帯があるが、これはD3 BiTurboの最大トルク帯(450Nm)である1,750回転~2,500回転に当たる、約81kW~約118kWの出力範囲だ。緑ラインの3速の50km/h~60km/hが一番わかりやすいが、日常使用速度域でのトルクの太さが、曲線の膨らみとなって見え、3速がいかに使いやすいかが良くわかる。けれども、グラフ全体を眺めてみると、この薄緑帯は、D3 BiTurboの性能のごく一部に過ぎない。やはり十分上まで回して楽しめるエンジンとギアの組み合わせだと思う。
※ 1/23追記 … 同じエンジン(2.5L直6NA、N52B25)を載せた、Z4-23i(6AT)と523i(8AT)のグラフを以下に追加した。

同じエンジンと言っても、この対極的なボディの二台については、以前、
比較記事を書いたことがある。その時の表やグラフよりも、こちらの方がわかりやすくなった。
また、このグラフを見ていると、Z4-23iの 1速はレブに当たると2速の約4,000回転まで落ちるが、逆にそこから7,000回転までを一気に駆け上がる音と加速感の楽しさが、十分に想像できる。2速のレブ後は3速の約4,500回転に落ちる。
一方523iの方は、1速→2速、2速→3速のシフト・アップ後は、ともに約5,000回転に落ちるが、もちろん、そこからの加速はこちらも楽しい。3速→4速は段差が少ないが、それでも約5,500回転まで落ちることになる。
そして、前にも書いたことだが、6ATと8ATの違いは、6ATの 1速と3速の間と、6速の後に、それぞれ一段ずつギアが増えていることがわかる。
なお、繰り返しになるが、このグラフは車重その他の要素が入っていない。だから当然、軽量なZ4の方が加速は大きい。たとえば、1速の赤ライン・黒ラインはほぼ重なって見えるけれども、実車では、黒ラインの上を移動する点の方が速いので、レブ・リミットを迎えるまでの時間が短い、というイメージになる。
※ 1/25追記 … やはり同等のエンジン(3L直6ターボ、N55B30)、および同じ8ATを搭載した、X3-35iと535i、そして640i(前2車よりパワーアップされている)のグラフを以下に追加した。

X3-35iと535iのファイナル・ギア比は、それぞれ「3.385」、「3.077」だ。最初は、523i/528iと並んで最も高いファイナル比を持つX3-35iの方が、かなり加速が良いだろうと思ったが、こうしてグラフで見てみると、それほどの差でもなかった(ただ、速度が上がるほど差は増える)。その理由は、X3-35iの標準装着タイヤ(245/45R19)の703mmという外径の大きさだと思う。535i(245/45R18)は677mmだから、26mmも違う(ちなみに、X3-35iのタイヤ径がさらに45mm大きくなると、グラフの黒ラインと青ラインは重なる)。
実車の加速予想については、車重がX3-35iの方が重くて1,900kg、対する535iは1,820kgであること、また、X3-35iは4WDなので、タイヤの大きさと相まって、機構的に少なくないパワーのロスがありそうだから、たぶんこの2車は、同じくらいの加速感ではないかと思う。X3-35iに「3.385」という高いファイナル比を与えたことには、そんな意図が込められていたのだろう。
N55エンジンのハイ・パワー版の640iをこのグラフに描き加えたのは、そのファイナル・ギア比が「3.235」となかなか高いからだ。実際に、低いギアはそのエンジンのパワーを存分に生かし、高いギアでは、7速が535iの6速とほぼ重なるラインとなっている。燃費はあまり良くないが、低くて幅広のボディにふさわしい、スポーティな走りを十分に楽しめそうだ…というよりも、私はこの640iのグラン・クーペに試乗して、そのエンジンとギアの働きにすっかり惹き付けられてしまったことがある。
最後に蛇足ながら、BMWの色々なエンジンとギアのグラフをこうやって眺めていると、かえすがえすも、100km/hという日本の最高速度規制が残念でならない。特にこのN55B30という、素晴らしい直6ターボ・エンジンは、いつでも200km/hまで一気に加速する能力を秘めつつ、そこに控えているのだ。
※ 1/26追記 … 類似のエンジン(直6NAのN52B30とN52B25)を載せた、6ATのE60-530i、そして8ATのF10-528iおよびF10-523iのグラフを以下に追加した。

黒ライン、E60-530iは、パワーもさることながら、6ATのギアのつながり方が、なかなかダイナミックだ。特に1速のレブから2速にシフトアップした後は、一気に4,000回転にまで落ちる(523i/528iは5,000回転前後)。それだけに、2速レブの7,000回転までの3,000回転の間は、さぞかし気持が良いことだろう。
また、黒ライン(E60-530i)と緑ライン(F10-528i)を比較するとわかりやすいが、6ATの1~3速までの間に、もう一段のギアが増えるのが、8ATだ。6ATを基準にたとえて言うと、「1速」→「1.6速」→「2.4速」→「3速」という感じだ。これに、さらに6速の上に一段を加えたのが8ATとなる。
F10同士の間では、523i(赤ライン)と528i(緑ライン)は、同じ8ATでパワーが異なるだけの違いだと思っていたが、こうしてグラフで比較してみると、523iの3速以後が528iの4速以後と重なっているのが面白い。つまり、528iは低速域で1段多く、523iは高速域で1段多いのだ。528iの本気の加速には、523iはとても敵わないけれども、エコ走行なら負けないという具合になる。
そういう目で見てみると、8ATの赤ラインの1~3速は、なんと6ATの黒ライン1~3速の方に似た形をしているのも面白い。こちらはどういうことかというと、150kWしか出さないで走っている530iには、全力で走る523iは、ほぼ同じシフト・パターンで追いついていける、ということだ。

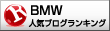
 ガソリン/ディーゼル・エンジンとギアの使われ方
ガソリン/ディーゼル・エンジンとギアの使われ方
 アイドリングの時でも、エンジンは 1分間に600回転以上、1秒間なら10回転以上は回転している。もしも、その回転数のままタイヤに直結すると、1秒でタイヤ10回転分の距離、約21メートル進む。時速にすると約76km/hだ。
アイドリングの時でも、エンジンは 1分間に600回転以上、1秒間なら10回転以上は回転している。もしも、その回転数のままタイヤに直結すると、1秒でタイヤ10回転分の距離、約21メートル進む。時速にすると約76km/hだ。






 タグ
タグ 今、あなたにおすすめ
今、あなたにおすすめ



