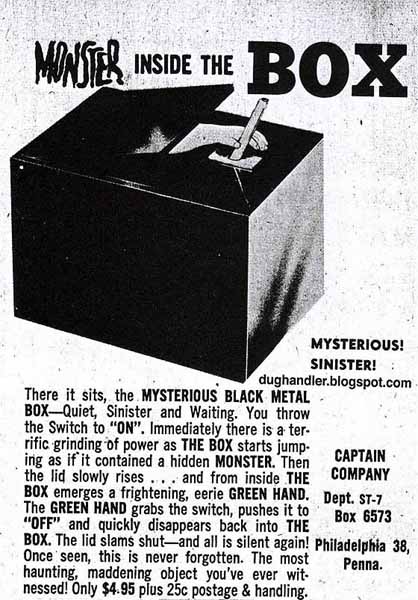彼らは富士山で高所訓練を行い、その上でマッキンリーに
向かったそうだ
旅行会社の公募レベルの隊とは異なる、準備は万全
標高6194mの頂上に対し、5200~300mまで到達していたが
行動予定時間よりの遅れがあるために登頂を断念し
雪崩の危険性に低い夜間に下山していた
彼らは三浦雄一郎氏の言うように「細心の注意を払いながら
慎重な登山をしていたと思う。雪崩の予測は非常に困難で、
不運な事故としか言いようがない」の言葉どおりだと思う
クレバスに押し流される事で助かった方は、一人、仲間を探し続けた、2時間程素手で捜索
疲労のために少し休み再度捜索、さぞ辛かったと思う
米国立公園局は17日捜索打ち切りを発表したが
二重遭難の危険性が非常に高い場所での捜索に頭が下がる
記事によると
日本人登山隊が使っていたものと同じ特徴のロープの切れ端が見つかり、さらに掘り進もうとした
レンジャー隊員。北米最高峰マッキンリーの雪崩の現場で、隊員らは懸命の捜索を行ったが、
行方不明となった日本人4人の捜索は固い氷の層に阻まれた。
記事で、雪崩の圧力で固い氷の層となったとあるが、その硬い氷でザイルが切れたんでしょうね
雪は攪拌されると硬くなるけど、雪でかまくらを作るときもこれがあるんで作れるんですよね
・・・

今回、クレバスに押し流されたことで助かった方がいらしたとの記事を読んで
「運命を分けたザイル」を強く思う、マッキンリーから遠く離れたペルーのシウラ・グランデ峰
この未踏の西壁に挑んだ二人のイギリス人登山家、ジョー・シンプソン、そしてサイモン・イェーツ
(このDVDを見た後にマッキンリーの事故があり、両方が頭の中で交錯した)
登攀は成功、天候が悪化した中の下山、「遭難の80%は下山時に発生する」とナレーション
下降中、ジョーが滑落し足を骨折、6300mの高所、歩けない事は死を意味する
しかしサイモンは果敢にもジョーを残されたザイルに繋ぎ下降を試みる
遅遅として進まぬ下降、ジョーを降ろす自己確保、ザイルの長さ90m毎に急斜面にステップを切る
延々の繰り返し
ジョーを早く降ろさなければとサイモンは衝撃で悲鳴を上げるジョーを非情を装って降ろす
あと少しの所でジョーは宙吊りになってしまう、ジョーからの合図が無いまま待ち続けるサイモン
それが一時間以上も続き、サイモンの支点のステップの崩れが増してくる
ジョーからの合図がない事をサイモンはジョーの死を思い、ザイルを切る
ジョーはクレバスに落下
クレバスに落ちたジョーはクレバスの中のテラスにひっかかっていた
登ろうと試みるも骨折した足ではかなわない
ジョーはクレバスの底に降りることを決意する、「生きて帰りたい」
クレバスの底は氷河の上に続いていた
氷河に出たジョーは後ろ向き座った状態で、両手だけで後ろ向きに進む。延々と
氷河が終わる、ジョーは手持ちの装備で骨折した足にカバーをつける
片足で跳ぶ、骨折した足が地面に当たると、その衝撃で激痛
サイモンはキャンプをたたんでいなかった
夜、ジョーはキャンプのそばまでやっとたどり着き、呼び声を上げる
サイモンがその声に気づく
ジョーを探すサイモン
そして苦難の帰国
『運命を分けたザイル』 予告編
運命を分けたザイル 予告編 -Touching The Void-
・・・
サイモンがザイルを切らなければジョーと共にクレバスの奥深くに閉じ込められてしまっただろう
そして、今回助かった方、ザイルが雪崩の力で千切られなければ
そしてクレバスに流されなければ生還は出来なかったんだろうと思う
ザイルをナイフで切ったサイモンは帰国したら登山界から強い非難を浴びた
そして、ジョーはサイモンを擁護するためにこの映画の原作となった「死のクレバス」を書いた
・・・
今回のマッキンリーに遭難
クレバスへの落下、ザイルの切断、この二つの出来事が「運命を分けたザイル」を想起させた
ジョーとは逆にクレバスの中を20m登り自力脱出、仲間を思うと無念だと思うけど最善の結果と思う
・・・
左は国立公園局のレンジャーが発見したザイル
右は井上靖氏の小説「氷壁」のもとになった岩角で切断したザイル

ザイルの切断というと真っ先に
屏風岩前穂東壁でおきた「ナイロンザイル切断事件」を思い出す
思い出すと言っても、この事件が発生した時点ではまだ物心がやっとついた頃
なんで、知識はその後に聞き及んだ事、昔、日テレでやっていたテレビドラマで見てた
麻のザイルの3倍の強度があるといわれたナイロンザイルがわずか50cm程度のスリップで切断
石岡繁雄氏は実験を繰り返し
ナイロンザイルが鋭角な岩角に弱いことを突き止め、メーカーに突きつける
メーカーと、日本山岳会関西支部長で、かつ工学博士である篠田軍治氏の手で公開実験
しかし、ザイルは切れなかった、岩稜会側には事故をザイルのせいにしたとパッシング
だが、メーカーと篠田氏側はダミーに丸みをつけていた、このことは石岡氏と岩稜会側は知らない
メーカーの若い技術者は「おかしい、我々の実験では切れていた」と、そして内部告発
石岡氏と岩稜会の執念が始まる
切断された岩角を捜索し、ナイロンの糸がわずかに付着していた箇所を捜し当てる
その箇所を石膏でかたどり、再現実験に臨む
ザイルは切れる、いわれの無い非難を浴びた石岡氏側は名誉毀損で訴える
しかし棄却、「特定の条件下で行った実験なので正当であり、名誉毀損には当たらない」と
篠田氏は「あの実験は登山用のザイルの実験ではなく、船舶用ロープの引っ張り試験」と言う
モラル無き企業と御用学者の協奏曲
その間にもザイル切断で何人もの命が失われていた
1975年、やっとザイルの安全基準が制定、日本山岳会と山渓も登山者の安全への軌道修正
日本山岳会はナイロンザイルの弱点(鋭角で切れる、氷塊でも、これは現在も全く同じ)
を世にしらせしる事を阻害した(山渓も同罪)
張本人である篠田氏はその後「日本山岳会名誉会員」
なんだかやりきれない
・・・
氷壁の宿で有名になった「徳沢園」
あの草原(元は牧場)でテントを張ると、それはそれは気持ちいい
つめたい沢の水でさらしたオニオンスライス、うまっ
これをタイピングしてたら指がつった
誤字脱字はあとでそっと修正します
・・・
※以下、2012/9/1:追記
後日の報道で、不可解な行動が伝えられている
時事ドットコム
米大教授「救助要請できたのに」=扇さんらしき男性に遭遇-マッキンリー雪崩
引用ここから
米ノースダコタ州立大のベルリン・ネルソン教授が、雪崩発生現場近くで扇等さんとみられる男性
と言葉を交わし、標高約3000メートル地点でリュックの上に腰掛けている扇さんとみられる
アジア人男性に遭遇した。
男性が雪山に必要なスノーシューズを履いていないことを不審に思い、「大丈夫ですか」と
繰り返し尋ねたが、「片言の英語で『大丈夫』という趣旨のことを言っただけだった」。
スノーシューズについての返答も要領を得ず、雪崩の話などは一切なかったと振り返る。
教授は2900メートル付近まで男性と共に下山したが、気が付くと男性はかなり後方を
歩いており、そのままはぐれてしまったという。
教授は「われわれは衛星電話を持っていたし、C3には少なくとも20人以上がテントを張って
いた。そこで事情を伝えてくれていれば、すぐに捜索を始められた」と話す。
同事務所の広報担当者は「扇さんがなぜ現場に最も近いC3で救助を求めなかったかは聞いて
いない」と説明。ネルソン教授は「仲間を失った精神的ショックに加え、言葉の問題で事情を
伝えられなかったのかもしれない。力になれず、非常に残念だ」と語った。
引用ここまで
そして、記事へのリンクは消失しているが、
読売新聞の記事によると
引用ここから
自力下山した隊長の扇等さん(69)と山中で接触した大阪府の登山隊のリーダー、
林孝治さん(60)が18日、登山口のタルキートナで読売新聞の取材に応じ、当時の様子を語った。
林さんは3人のチームで6月11日からマッキンリーに入った。14日朝、標高約2400メートル
付近で扇さんとあいさつを交わした際に、扇さんから「雪崩に巻き込まれ、4人が行方不明に
なった」などと小声で告げられたという。その段階で林さんが救援を要請した。
扇さんは13日夕方の段階で、すでに大阪隊の近くにいて、林さん以外の大阪隊の2人と
あいさつしていたが、その時には遭難のことは出なかったという。
扇さんがその時点で話していれば、より早い段階で捜索が始まった可能性があるが、林さんは
「扇さんは放心状態だったし、これから登頂を目指すチームに、精神的負担をかけたくないと
考えたのでは」と語った。
引用ここまで
何故!
言葉を失う
 彼らは富士山で高所訓練を行い、その上でマッキンリーに
彼らは富士山で高所訓練を行い、その上でマッキンリーに

 朝7:00からの「宇宙兄弟」を見る
朝7:00からの「宇宙兄弟」を見る ←1961年マン島TTレース 125ccクラス
←1961年マン島TTレース 125ccクラス
 ←ワルシャワ、ワジェンキ公園のショパンの銅像
←ワルシャワ、ワジェンキ公園のショパンの銅像 なにやらYoutubeでいっぱい見かけるようになったので
なにやらYoutubeでいっぱい見かけるようになったので