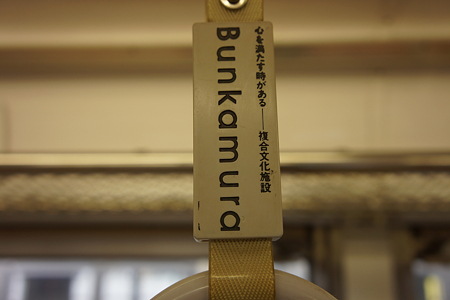この日は電車と徒歩で少しばかり大阪を巡ってみました。
帝塚山古墳は、西南面の前方後円墳で、上町台地南部の西縁に位置しています。
天王寺公園内の茶臼山古墳、勝山通の御勝山古墳と共に大阪市内の古代の三大記念物で、最も保存状態が良いものです。
この古墳の被葬者については、大伴金村とする説があるそうです。
明治31(1898)年には陸軍特別大演習を明治天皇がここからご覧になったそうで、墳丘上には旧住吉村が建立した石碑があるそうです。
古墳は財団法人住吉村常磐会が所有、管理しており、内部へ立ち入ることはできません。
 帝塚山古墳 - 1
帝塚山古墳 - 1 posted by
(C)pismo
 帝塚山古墳 - 2
帝塚山古墳 - 2 posted by
(C)pismo
阿倍野神社は、北畠親房、顕家を祀る神社です。
北畠親房は南北朝時代に後醍醐天皇の親任厚く、吉野朝廷の中心人物として活躍しました。「神皇正統記」を著したことで知られています。
北畠顕家は、親房の長男で元弘3(1333)年、陸奥守に任ぜられました。
延元元(1336)年には上洛し足利尊氏を破り九州へ敗走させました。延元3(1338)年、再度上洛して京都を回復しようとしましたが、足利方に敗れて亡くなりました。
阿倍野神社の地に、明治8(1875)年、地元の有志が顕家を祀る祠を建立しました。
明治15(1882)年1月に改めて阿部野神社として創立しました。明治23(1890)年に社殿が竣工し、鎮座祭が斎行され、別格官幣社に列せられました。
現在の社殿は昭和43(1968)年に再建されたものです。
 阿倍野神社 - 01
阿倍野神社 - 01 posted by
(C)pismo
 阿倍野神社 - 02
阿倍野神社 - 02 posted by
(C)pismo
 阿倍野神社 - 03
阿倍野神社 - 03 posted by
(C)pismo
 阿倍野神社 - 04
阿倍野神社 - 04 posted by
(C)pismo
 阿倍野神社 - 05
阿倍野神社 - 05 posted by
(C)pismo
 阿倍野神社 - 06
阿倍野神社 - 06 posted by
(C)pismo
 阿倍野神社 - 07
阿倍野神社 - 07 posted by
(C)pismo
 阿倍野神社 - 08
阿倍野神社 - 08 posted by
(C)pismo
天神森天満宮は、別名を「天下茶屋天満宮」「子安天満宮」「紹鴎森天満宮」といいます。
菅原道真公が筑紫へ左遷されたおり、住吉明神へ参拝の途中のこの地に休息され、その後祠が建立され、応永年間(1394〜1428)に京都北野天満宮の御分霊を奉斎しました。
当社にまつられている「子安石」は古くより安産の神として、多くの人々に信仰されています。
豊臣秀吉も淀君懐妊のとき参詣し、安産を祈願され、安らかに秀頼公の出産をみられました。
樹齢六百年をこえる楠木の森は「天神の森」とよばれ、茶道中興の祖武野紹鴎(千利休の師)がこの森の一隅に茶室をつくり、風月を友として暮らしたので「紹鴎森」とも呼ばれました。
秀吉公が堺政所の往来の途中、天満宮西側の茶店で休息、この付近を殿下の茶店ということで天下茶屋と称することになり、当社も「天下茶屋天満宮」と呼ばれることになりました。
 天神森天満宮 - 01
天神森天満宮 - 01 posted by
(C)pismo
 天神森天満宮 - 02
天神森天満宮 - 02 posted by
(C)pismo
 天神森天満宮 - 03
天神森天満宮 - 03 posted by
(C)pismo
 天神森天満宮 - 04
天神森天満宮 - 04 posted by
(C)pismo
天下茶屋は、大坂城から住吉大社参拝や堺へ行き来する途中に太閤秀吉が立ち寄って茶の湯を楽しんだ故事で有名な場所です。
昭和20(1945)年、戦災に遭うまで、五千平方メートルに及ぶ広大な屋敷に、太閤秀吉ゆかりの「恵水」と名付けられた井戸や茶室、紀州侯はじめ諸大名も泊まったと伝えられる御殿が残っていたそうです。
現在は広場になっていて土蔵が残っています。
土蔵は屋敷の北西隅に位置し。恵方に向かって建てられ、太閤秀吉を祀った祠で楠とともに往時をしのぶものです。
太閤秀吉が天下茶屋を訪れた天正年間、芽木家の祖、三代目天下茶屋小兵衛昌立が活躍していて、天神の森には茶人、千利休の師武野紹鴎が住んでいました。
この広場の整備にあたり、芽木家から土地と土蔵の寄附を受け、また。地元西成地区土地区画整理審議会から全面的な強力を受けて出来たものです。(説明看板などより)
 天下茶屋跡 - 1
天下茶屋跡 - 1 posted by
(C)pismo
 天下茶屋跡 - 2
天下茶屋跡 - 2 posted by
(C)pismo
天下茶屋公園にある
阿倍寺塔心礎です。
阿倍寺は阿倍氏の氏寺ともいわれる奈良時代の寺院で、現在の阿倍野区松崎町の松長大明神の一帯にあったと伝えられてます。
阿倍寺塔心礎は、阿倍寺の塔の中心となる礎石と考えられ、中央に直径61センチ、深さ13センチの柱穴を掘り、さらにその内部に直径10.1センチ、深さ8.2センチの舎利を埋納するための穴があります。
当初は松崎町にありましたが、現在は天下茶屋公園に移されています。昭和49(1974)年に大阪府指定有形文化財に指定されました。
 天下茶屋公園 - 1
天下茶屋公園 - 1 posted by
(C)pismo
正圓寺は、山号は海照山、東寺真言宗の寺院です。
天慶2(939)年光道和尚により開基により開かれた般若山阿部寺の一坊でしたが、江戸時代の元禄年間に義道見明和尚が寺を移転し、海照山正圓寺と改めました。
享保8(1723)年、常如和尚が来住し、聖天堂や諸堂を再興しました。
「天下茶屋の聖天さん」として信仰を集めています。
奥之院には、鎮守堂(荼枳尼天)、寄松塚(八本松竜王)、石切社分祠、浪切不動明王、弁才天祠などが祭られています。「聖天山正圓寺」とも言われますが、「聖天山」は山号ではなく標高14mの低山の名前で、山頂は正圓寺境内にあります。
 正圓寺 - 01
正圓寺 - 01 posted by
(C)pismo
 正圓寺 - 02
正圓寺 - 02 posted by
(C)pismo
 正圓寺 - 03
正圓寺 - 03 posted by
(C)pismo
 正圓寺 - 04
正圓寺 - 04 posted by
(C)pismo
松虫塚は、この地が松虫(現在の鈴虫)の名所であったことから松虫の音にまつわる伝説がたくさん残されています。
その1
二人の親友が月の光さわやかな夜麓しい松虫の音をめでながら道遥するうち虫の音に聞きほれた一人が草むらに分け入ったまま草のしとねに伏して死んでいたので、残った友が泣く泣くここに埋葬した。
「古今集」松虫の音に友を偲び
秋の野に 人まつ虫の 声すなり われかとゆきて いざとむらわん
その2
後鳥羽上皇に仕えていた松虫と鈴虫の姉妹官女が法然上人の念仏宗に感銘して出家したが松虫の局が老後この他に果て草庵を結んで余生を送ったという。
「芦分舟」
経よみて そのあととふか 松虫の 塚のほとりに ちりりんの声 藤原言因
その3
才句兼備琴の名手といわれた美女がこの地に住んでいたが一夕秘技を尽した琴の音が松虫の自然の音に及ばないのを嘆き、次の詩を吟して琴を捨てたという。
虫声喞々満野荒野閣醸恋情琴瑟抛
(虫声そくそく荒野に満つ、恋情を闇にかもしてて琴瑟を抛つ)
その4
松虫の名所であるこの地に松虫の次郎右衛門という人が住み松虫の音を愛好することすこぶる深く終世虫の音を友とし、
老いてのち
尽きせじな めでたき心 しるならば こけの下にも ともや松虫
の辞世の歌を残して没した。
この地は、かつて松虫通の拡幅工事で取り壊されそうになりましたが、地元住民の要望により残されたそうです。
 松虫塚 - 1
松虫塚 - 1 posted by
(C)pismo
 松虫塚 - 2
松虫塚 - 2 posted by
(C)pismo
 松虫塚 - 3
松虫塚 - 3 posted by
(C)pismo
 松虫塚 - 4
松虫塚 - 4 posted by
(C)pismo
 松虫塚 - 5
松虫塚 - 5 posted by
(C)pismo
安倍晴明神社は、平安時代に活躍した天文博士安倍晴明公を祀る神社です。
社伝によれば、寛弘4(1007)年に創建されました。
安倍晴明公は古代豪族阿倍氏の出身で、伝説では父安倍保名が和泉の信太明神(聖神社)に参詣の際、助けた白狐(葛之葉姫)と結ばれて、天慶7(944)年ここの地阿倍野で生誕されたと伝えられています。
幼名は安倍童子で、資性英明学問を好み、京都に上り陰陽家の賀茂忠行と 子息保憲に師事し、陰陽推算の術を修め、天文博士、大膳大夫、播磨守を歴任し、従四位上に叙されました。
占いは百占奇中神の如しと称され、花山天皇の退位を予知し大江山の鬼退治を指導した事は有名で、又職神(霊)を自在に駆使したと伝えられています。
現在の社伝は大正14(1925)年に再建されたものです。
(説明看板などより)
 安倍晴明神社 - 01
安倍晴明神社 - 01 posted by
(C)pismo
 安倍晴明神社 - 02
安倍晴明神社 - 02 posted by
(C)pismo
 安倍晴明神社 - 03
安倍晴明神社 - 03 posted by
(C)pismo
 安倍晴明神社 - 04
安倍晴明神社 - 04 posted by
(C)pismo
 安倍晴明神社 - 05
安倍晴明神社 - 05 posted by
(C)pismo
阿倍王子神社は、伊弉諾尊、伊弉冉尊、素戔嗚尊、品陀別尊(八幡大神)の四柱を祀り「安倍王子権現縁起」によれば、仁徳天皇のご創建と伝えられ、また一説には往古この地を本拠とした安倍氏の創建ともいわれています。
平安時代より熊野詣が盛行すると、九十九王子の第二王子社として阿倍野王子等と称せられ、法皇上皇、女院等をはじめ、一般参詣客の礼拝、休息などの用に充てられ殷賑を極めました。
大阪府内の九十九王子社で唯一現存している神社です。
(説明看板などより)
 阿部王子神社 - 1
阿部王子神社 - 1 posted by
(C)pismo
 阿部王子神社 - 2
阿部王子神社 - 2 posted by
(C)pismo
伝北畠顕家の墓〔北畠公園〕です。北畠顕家は、南北朝時代に後醍醐天皇に父親房と共に仕えた武将です。、もともとここには「大名塚」と呼ばれていた塚があり、それを江戸時代の国学者 並川誠所が顕家の墓と推定し、その提唱で、享保年間(1716~1736)に北畠顕家の墓として建てられました。
ただし、顕家の戦死の地は太平記には、「5月22日、和泉の境阿倍野にて打死し給ひければ、相従ふ兵悉(ことごと)く腹切り疵を被って一人不残(ひとりのこらず)失せにけり」と記され、顕家公が20余騎の手兵で足利尊氏の大軍を迎え撃ち、弱冠21歳で戦死したところと伝えられていますが、「神皇正統記」などには顕家は延元3(1338)年5月22日朝、1万8千の高師直軍と戦い、摂津国石津(現在の堺市西区浜寺石津町)で戦死したとなっていて、太平記の記述とは異なっています。
 北畠顕家の墓(北畠公園) - 01
北畠顕家の墓(北畠公園) - 01 posted by
(C)pismo
 北畠顕家の墓(北畠公園) - 02
北畠顕家の墓(北畠公園) - 02 posted by
(C)pismo
 北畠顕家の墓(北畠公園) - 03
北畠顕家の墓(北畠公園) - 03 posted by
(C)pismo
 北畠顕家の墓(北畠公園) - 04
北畠顕家の墓(北畠公園) - 04 posted by
(C)pismo
「播磨塚」と「小町塚」はもともと別個のもので、以前は現在地に近い西北の畑の中にありましたが、昭和4(1929)年に道路となったため、現在の場所に移されています。
「播磨塚」は、南北朝の頃、住吉の合戦で楠木正行と戦って敗れた山名、細川両軍が率いる北朝軍の中にいた播磨の太守、赤松円心の子貞範が、戦死した将兵の遺骨を納めて塚を築き、播磨塚と名付け部下の冥福を祈ったと伝えられています。
また、「小町塚」は、古書「芦分船」には、小野小町の塚であると説明しているが、小野小町がこの地で死んだという記録はなく、小野小町の美貌や才能にあやかりたいとの念願から、信仰などの目的のため造られたものと思われます。(説明看板などより)

ここからは少しばかり阪堺電車で移動し、住吉大社を訪れました。
住吉大社は神功皇后が三韓征伐より七道の浜(現在の大阪府堺市堺区七道、南海本線七道駅一帯)に帰還した時、神功皇后への神託により天火明命の流れを汲む一族で摂津国住吉郡の豪族の田裳見宿禰が、住吉三神を祀ったのに始まります。
祭神の住吉大神は、伊弉諾尊が黄泉国の汚れを洗い清めるために禊はらいをされた時、海中より生まれた神様、底筒男命、中筒男命、表筒男命の三神を総称し、住吉三神ともいわれています。
住吉大社は、住吉三神と息長足姫命(神功皇后)を併せ4神が祀られており、第一本宮から第四本宮に祀られています。
現在ある第一本宮から第四本宮にいたる4棟の本殿は全て文化7(1810)年に造られた桧皮葺・切妻造妻入りの住吉造りの建物で、国宝建造物に指定されています
住吉反橋は、通称「太鼓橋」とも呼ばれ、慶長年間に淀殿が造営したといわれています。
 住吉大社 - 01
住吉大社 - 01 posted by
(C)pismo
 住吉大社 - 02
住吉大社 - 02 posted by
(C)pismo
 住吉大社 - 03
住吉大社 - 03 posted by
(C)pismo
 住吉大社 - 04
住吉大社 - 04 posted by
(C)pismo
 住吉大社 - 05
住吉大社 - 05 posted by
(C)pismo
 住吉大社 - 06
住吉大社 - 06 posted by
(C)pismo
 住吉大社 - 07
住吉大社 - 07 posted by
(C)pismo
 住吉大社 - 08
住吉大社 - 08 posted by
(C)pismo
この次は電車で平野へ向かいます。