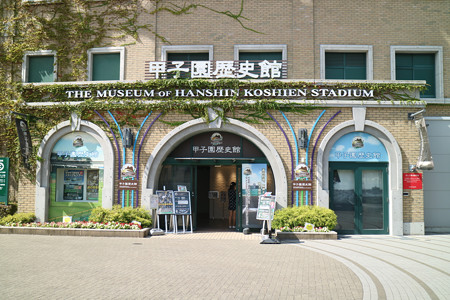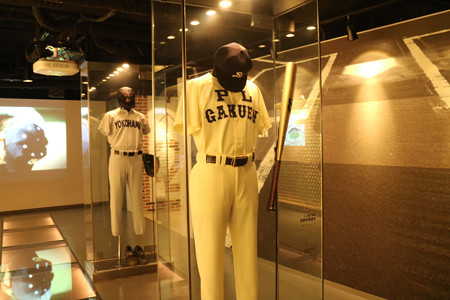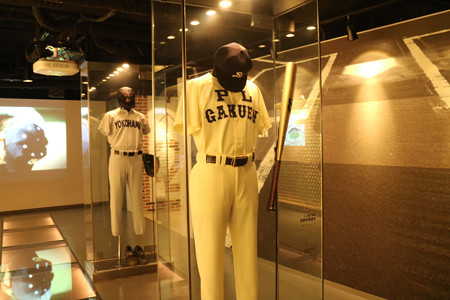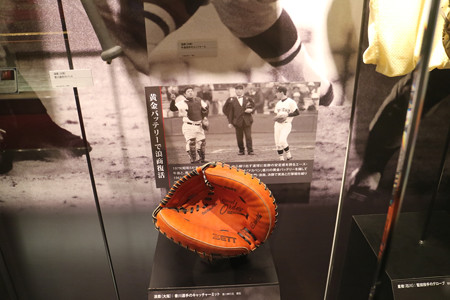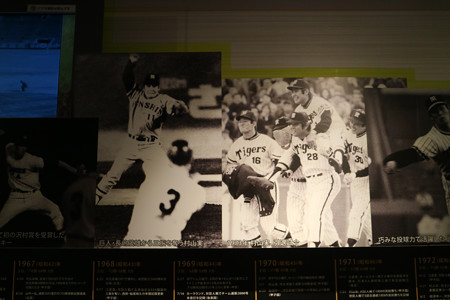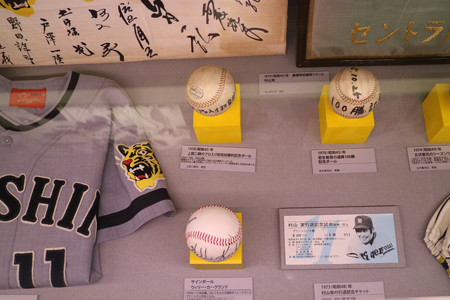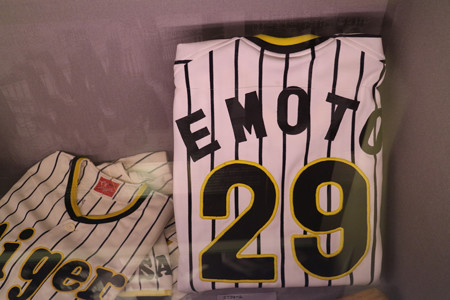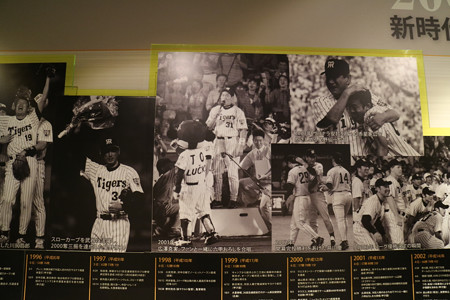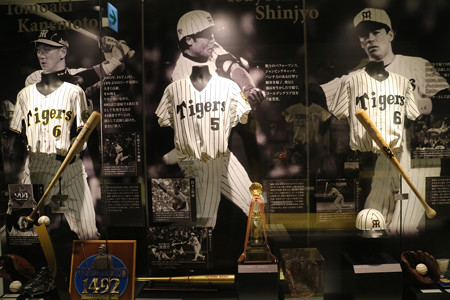昼寝城は、鴨部川上流の南側にある矢筈山の中腹、俗称昼寝山の頂上にあり、寒川氏の城でした。
古代の讃岐公の一族で世々寒川郡司を務めた寒川氏は、室町時代後期には、大内・寒川の二郡のほかに小豆島も兼領し、この昼寝城を本城に池の内の台ガ山城(さぬき市長尾町名)を出城に、大内郡の虎丸城(東かがわ市大内町)、引田城(東かがわ市引田町)を支城にしました。戦国期の終わり頃まではここに城があったと考えられています。
昭和55(1980)年の調査で、白磁はどの陶磁器や、銅環・銅製切羽などの金属製品、多数の銅銭、砥石、玉石などが出土しました。また、最近の調査では、「遺構は尾根筋を堀切で遮断、土塁を囲みを構築した本丸曲輪が見られ、シンプルな縄張りであるが、在地領主の小規模城郭としては、防御構築物に合理性が見られ、良くできた城郭と言える。」と評価されています。〔昭和63(1988)年「中世城郭研究」〕
もともと、大多和神社(延喜式内社)から行基菩薩が布施屋を開いたという伝承のある古大窪に通じる道の途中、今も比丘尼(びくに=女性の宗教者がいたか?)渕と呼ばれる所から右に登る道がありました。
なぜ、こんな奥地にという疑問があるでしょうが、古代の信仰集団の存在や、鉱物資源を求める工人集団の存在を示す遺構があり、今周辺に見られる石垣の見事さから、かなりの人の住居が想像できます。(現津説明板より)
 昼寝城 - 01
昼寝城 - 01 posted by
(C)pismo
 昼寝城 - 02
昼寝城 - 02 posted by
(C)pismo
 昼寝城 - 03
昼寝城 - 03 posted by
(C)pismo
 昼寝城 - 04
昼寝城 - 04 posted by
(C)pismo
 昼寝城 - 05
昼寝城 - 05 posted by
(C)pismo
 昼寝城 - 06
昼寝城 - 06 posted by
(C)pismo
大窪寺は、山号は医王山、正式には医王山遍照光院大窪寺という真言宗大覚寺派の寺院です。
四国八十八箇所の第八十八番札所で、結願所として知られています。
奈良時代の養老年間に行基が開基し、弘仁年間に空海(弘法大師)が奥の院の岩窟で虚空蔵求聞持法を修し、薬師如来を刻んで安置したともされています。
大師が大きな窪の側に堂宇を建立した事から寺号の大窪寺の由来となり、山号を薬師如来を「医王」に見立て名付けました。
境内の「宝杖堂」には、結願した遍路の金剛杖が奉納され、毎年春分の日と8月20日に柴灯護摩供の焚き上げが行われます。また、宝杖堂の手前には、原爆の火が灯されています。
 大窪寺 - 01
大窪寺 - 01 posted by
(C)pismo
 大窪寺 - 02
大窪寺 - 02 posted by
(C)pismo
 大窪寺ー 03
大窪寺ー 03 posted by
(C)pismo
建武3(1336)年足利尊氏に従って京都東寺で戦死した益子下野守顕助の子弥次郎秀助が、阿波屋形細川頼春に従って四国に渡り、父の功績により讃岐国香川郡井原荘を賜り、姓は由佐と改め由佐に屋敷を構えたのが
由佐城の始まりです。
城は東は香東川、南に沼地の多い自然を巧みに利用した要塞で、天正11(1583)年長宗我部元親軍が攻め入ったが容易に落城せず、和議を申し出たほどでした。
由佐家には「由佐家文書」が残されており、当時の由佐城を記す「由佐城絵図」には、「上之城」「下之城」「安部晴明墟」などの記述があります。
昔から由佐家では、水・火・盗難を封じた陰陽師「安部晴明」の練石を神庫に収め、その石を祀って災難を防いだといわれています。
天正13(1585)年、豊臣秀吉の四国平定に伴い讃岐は仙石秀久が統治することとなり、由佐家もその配下に属し九州平定の軍に参陣しました。このときの敗戦の責任を取らされた仙石秀久に代わって讃岐の領主となった尾藤知宣にも従ったとされています。尾藤知宣も程なくして讃岐の領主を免ぜられ、領主の地位は生駒親正に受け継がれます。由佐家は生駒家に属し、文禄・慶長の役と2回朝鮮に出陣しました。その戦功により500石の禄を与えられました。
天下分け目の戦いといわれた関が原の合戦には、東軍として戦った生駒一正に従い戦功を立てました。
その後、生駒氏が讃岐から出羽国矢島(今の秋田県由利本荘市)に移された後は、土地の豪農として、香南地域で大きな勢力を保ち、明治時代を迎えています。
由佐家の居宅とした屋敷内には、内堀、土塁跡を見ることができました。
高松市香南歴史民族郷土館(模擬天守)は、その由佐城跡に建築されたものであり、庭園内には、現在も土塁跡が残されています。
郷土館の風貌は、現存する最古の天守閣を持つ福井県の丸岡城をモデルに建てられており、館内には歴史展示室・民俗展示室・図書室を備え地域の歴史を知ることができ、本格的なお茶室の拵えのある研修室もあります。
(現地説明板などより)
 由佐城 - 01
由佐城 - 01 posted by
(C)pismo
 由佐城 - 02
由佐城 - 02 posted by
(C)pismo
 由佐城 -03
由佐城 -03 posted by
(C)pismo
築城城は、戦国時代の飯田郷3城の一つで下飯田城ともいいました。当時は土塀囲いの屋敷で、小学校の北側に南門、農協支所の北側に北門がありました。
城主は築城氏で、長く勝賀城主香西氏に仕え、3代目城主清左衛門は天正10(1582)年、土佐の長宗我部氏の軍と是竹の伊勢神宮の馬場で戦いました。
その3年後に豊臣秀吉による四国征伐で香西氏は滅亡し、戦国時代も終わりました。
天正15(1587)年、讃岐の大名として赤穂から入部した生駒親正に清左衛門は200石で召し抱えられました。
現在住宅街となり全く城の遺構を残す物は残っていません。
(現地説明板などより)
 築城城
築城城 posted by
(C)pismo
甲山寺は、山号は医王山、真言宗善通寺派の寺院です。四国八十八箇所霊場の第七十四番札所です。
周辺は弘法大師の故郷で、幼少時代によく遊んだといわれる場所で壮年期になった弘法大師は善通寺と曼荼羅寺の間に伽藍を建立する霊地を探し時甲山を歩いていると、麓の岩窟から老人が現れ「私は昔からここに住み、人々に幸福と利益を与え、仏の教えを広めてきた聖者だ。ここに寺を建立すれば私がいつまでも守護しよう。」と言いました。弘法大師は大変喜び、毘沙門天像を刻んで岩窟に安置し、供養しました。
その後、嵯峨天皇の勅命を受けてこの地にある「満濃池」の修築を監督する別当に任命されると、甲山の岩窟で修復工事の完成を祈願し、薬師如来像を刻んで修法しました。すると大師を慕って数万人の人々が集まり、満濃池はわずか三ヶ月で完成しました。朝廷からこの功績を称えられ、金二万銭を与えられた弘法大師は、その一部を寺の建立にあて、先に祈願をこめて刻んだ薬師如来を本尊とし、安置。山の形が毘沙門天の鎧、兜の形に似ていることから「甲山寺」と名づけられました。
 甲山寺 - 01
甲山寺 - 01 posted by
(C)pismo
 甲山寺 - 02
甲山寺 - 02 posted by
(C)pismo
 甲山寺 - 02
甲山寺 - 02 posted by
(C)pismo
 甲山寺 - 04
甲山寺 - 04 posted by
(C)pismo
甲山城(こうやまじょう)は、四国八十八箇所の第七十四番札所の甲山寺の南にある甲山に築かれた城です。
香川氏の居城、天霧城の出城だったと思われます。
築城年代は不明ですが、朝比奈弥太郎によって築かれたといわれています。永禄元(1558)年、三好実休は讃岐に侵攻し、香川氏を攻めました。
このとき、香川氏家中の中でも豪の勇士といわれた朝比奈弥太郎は、甲山城南麓において寄せ手の軍勢およそ190人を討ち取りましたが、最後は力尽き討死したといわれています。城跡は甲山寺より登ることができます。
 甲山城 - 01
甲山城 - 01 posted by
(C)pismo
 甲山城 - 02
甲山城 - 02 posted by
(C)pismo
 甲山城 - 03
甲山城 - 03 posted by
(C)pismo
Posted at 2015/12/26 20:33:05 | |
トラックバック(0) |
ドライブ | 日記