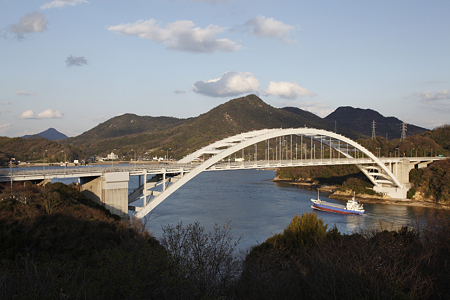次は三津浜に駐車場に車を駐め、すこしばかりサイクリングをしてみました。
この附近も「坂の上の雲」などにゆかりの史跡などがあります。
きせんのりばの碑・子規の句碑です。三津内港は、鎌倉時代から伊予水軍の拠点でしたが三津は寒村でした。
慶長8(1603)年、松山城に移った加藤嘉明が水軍の根拠地とし松前から町民が移り発展が始まりました。
寛永12(1635)年、松平定行が御船手組や町奉行を置き、参勤交代の御用船の根拠地としました。
明治になると、三津浜町は商工業が発展し、大阪商船や宇和島運輸などの汽船が出入りする四国一の商取引所になっていましたが、三津浜港は底が浅いため、大きな汽船は入港することができず、沖合いに停泊したままで、港との間を「はしけ」と呼ばれる小船で結び、物資や人を運んでいました。
明治4(1871)年に「はしけ」で沖の汽船まで運送をはじめた場所に建てられたのが「きせんのりばの碑」です。
元は三津三丁目あたりに建っていました。
夏目漱石や正岡子規もここから出港し、ここに上陸した港です。「きせんのりばの碑」の側には、「十一人一人になりて秋の暮」という子規の句碑が建っています。
明治28(1895)年、日清戦争に従軍後、病に倒れた子規は松山に帰郷していましたが、再度上京することになり、松風会会員により送別会が開かれました。その際に漱石が「御立ちやるか御立ちやれ新酒菊の花」を贈り「十一人一人になりて秋の暮」を作り応えました。
 きせんのりばの碑・子規の句碑 - 1
きせんのりばの碑・子規の句碑 - 1 posted by
(C)pismo
 きせんのりばの碑・子規の句碑 - 2
きせんのりばの碑・子規の句碑 - 2 posted by
(C)pismo
三津の渡しは、三津浜港内で運行されている渡し船です。
三津浜の人々は「洲崎の渡し」「三津の渡し」といい、港山の人々は「古深里の渡し」「港山の渡し」といっています。
文明元(1469)年、伊予守河野通春が港山城主だった時、この渡しを利用したのが始まりといわれています。
慶長8(1603)年、加藤嘉明が水軍を根拠地とした時ここに御船場を置き、寛永12(1635)年、御船手を配置してからは、その統括の元に運行されていました。
寛文4(1635)年、洲崎の魚市売買に御沙汰があったことにより商人で賑わい、小林一茶も寛政7(1795)年、古深里洗心庵の句会の時に渡っています。
大正の初め頃までは小舟を水竿で操り、その後手漕ぎ時代が続きましたが、昭和45(1970)年、エンジン付渡船となりました。
現在正式名称は松山市道高浜二号線の一部(約80M)です。
映画「がんばっていきまっしょい」においては主人公が通学中に利用する場面が登場します。
 三津の渡し - 1
三津の渡し - 1 posted by
(C)pismo
 三津の渡し - 2
三津の渡し - 2 posted by
(C)pismo
 三津の渡し - 3
三津の渡し - 3 posted by
(C)pismo
大原其戎居宅の跡です。大原其戎は、正岡子規の俳諧の師匠です。
明治20(1887)年、正岡子規は勝田主税の紹介で柳原極堂とともに其戎を訪ね、俳諧の手ほどきを受けました。
三津浜の南、大可賀に芭蕉の句碑(あら株塚)を建て、その傍らに草庵を結びました。
屋敷跡には現在も芭蕉翁塚(あら株塚)があります。
「しくるるや 田のあら株のくろむほと」
その他、「大原其戎居宅の跡」の石碑と其戎の句碑「花之本大神 敬へはなほまたたしや花明かり」が建っています。
 大原其戎居宅の跡
大原其戎居宅の跡 posted by
(C)pismo
三津浜の町並みには古い情緒が残っています。下の写真は辻井戸です。
 辻井戸 - 1
辻井戸 - 1 posted by
(C)pismo
 辻井戸 - 2
辻井戸 - 2 posted by
(C)pismo
厳島神社は、崇峻天皇の時代に筑紫国の宗像大社から宗像三女神を迎えたのが始まりだとされています。
神亀元(724)年安芸国の厳島神社の神を迎えて厳島神社となりました。
応仁元(1467)年、河野通春が社殿を造営しましたが、慶長5(1600)年、関ヶ原の戦いの際の苅屋敷の戦において、戦火にかかって消失し、慶長7(1602)年に現在地へ遷座しました。
江戸時代には参勤交代が三津を通ることもあり、松山藩の庇護を受けました。
 厳島神社 - 01
厳島神社 - 01 posted by
(C)pismo
境内には陸軍大将秋山好古揮毫の日露戦役表忠碑があります。
 厳島神社 - 02
厳島神社 - 02 posted by
(C)pismo
 厳島神社 - 03
厳島神社 - 03 posted by
(C)pismo
 厳島神社 - 04
厳島神社 - 04 posted by
(C)pismo
 厳島神社 - 05
厳島神社 - 05 posted by
(C)pismo
大原其戎・大原其沢の墓〔三津公園〕です。
大原其戎は、松山藩士で父大原其沢の跡を継ぎ、御船手大船頭となりました。
京の桜井梅堂の門に入り、二条家より宗匠の免許を受けて帰郷しました。明治13(1880)年、三津に明英社をおこし、日本で三番目に古い月刊俳誌「真砂の志良辺(まさごのしらべ)」を主催刊行しました。
奥平鶯居と共に伊予俳壇の双璧といわれました。
明治20(1887)年夏に帰省した子規は、其戎を訪ね以後文通により指導を受けました。
墓には「明月や 丸うふけ行ものの影」の句が刻まれています。隣には父大原其沢の墓があり「造作なふ 共に消えけり 雪仏」の句が刻まれています。
 大原其戎・大原其沢の墓(三津公園)
大原其戎・大原其沢の墓(三津公園) posted by
(C)pismo
河野通春公のお堂です。河野通春は、室町時代に河野家の分家、河野予州家の武将として活躍しました。
港山城主として伊予水軍を統率し応仁の乱など多くの戦いに出陣し、四海に勇名を轟かせました。
文明14(1482)年、港山城で逝去しました。
港山駅近くの住宅街にお堂があり、地元住民が現在も大事にしています。
 河野通春公のお堂 - 1
河野通春公のお堂 - 1 posted by
(C)pismo
秋山好古の銅像は、昭和11(1936)年、道後公園に建てられました。
昭和18(1943)年に撤去供出されました。
昭和45(1970)年、梅津寺に再建されました。
最初の銅像は、「騎兵の父」らしく騎馬姿でしたが、現在の姿は立ち姿です。
 秋山好古の銅像 - 1
秋山好古の銅像 - 1 posted by
(C)pismo
 秋山好古の銅像 - 2
秋山好古の銅像 - 2 posted by
(C)pismo
秋山真之の銅像は、昭和6(1931)年、日本海海戦25周年を記念して道後公園に建立されました。
台座には東郷平八郎の「知謀如湧」の揮毫があります。昭和18(1938)年に秋山好古の銅像と同じく撤去供出されました。
昭和38(1963)年に石手寺に再建され、昭和43(1968)年9月に梅津寺へ移されました。
 秋山真之の銅像 - 01
秋山真之の銅像 - 01 posted by
(C)pismo
 秋山真之の銅像 - 02
秋山真之の銅像 - 02 posted by
(C)pismo
東京ラブストーリーのロケ地、
梅津寺駅があるので少し休憩がてら立ち寄りました。ここは、
平成18年にも訪れました。梅津寺パークが閉園し、公園になっていたのは驚きました。
 梅津寺駅 - 01
梅津寺駅 - 01 posted by
(C)pismo
 梅津寺駅 - 02
梅津寺駅 - 02 posted by
(C)pismo
 梅津寺駅 - 03
梅津寺駅 - 03 posted by
(C)pismo
 梅津寺駅 - 04
梅津寺駅 - 04 posted by
(C)pismo
 梅津寺駅 - 05
梅津寺駅 - 05 posted by
(C)pismo
湊山城は、建武年間(1334〜1337)に河野通盛が道後湯築城を築いた時に、海の守りとして築城したといわれています。
その後、室町時代に河野通春が湊山に堅固な城を築きました。当時、河野家は湯築城の宗家河野教通(通直)と、港山城に拠る庶子家の通春に分かれて争っていました。
通春は、周防の大内氏と結び制海権を有して教通を凌ぐ一大勢力を持っていました。
応仁の乱後、通春は文明10(1478)、文明13(1481)年の二度の戦いを教通と行い、ついに湊山の北麓で流矢にあたり戦死したともいわれています。
天正13(1585)年、秀吉の四国征伐で滅び、廃城となりました。
現在は石積や、井戸跡、3つの郭などが残っているそうです。登城口付近に説明看板が建っていますが、竹藪がひどく、登城はほとんど不可能です。
 港山城 - 1
港山城 - 1 posted by
(C)pismo
 港山城 - 2
港山城 - 2 posted by
(C)pismo
 港山城 - 3
港山城 - 3 posted by
(C)pismo
洗心庵跡です。
寛政7(1795)年、1月15日、俳諧師小林一茶が松山に来遊し、20日ばかり滞在し2月5日三津浜の方十亭を宿にし、9日小深里(現在の港山町)の洗心庵に俳友を集めて句会を催し下記の4つを詠みました。
「汲みて知るぬるみに昔なつかしや」
「にな蟹と成て女嫌れな」
「山やく山火と成りて日の暮るゝ哉」
「梅の月一枚のこす雨戸哉」
なお、洗心庵は、徳川中期より代々尼僧が住んでいた尼寺でしたが、明治5(1872)年、廃仏毀釈により廃寺になりました。
港山城登城口付近に石碑が建っています。
 洗心庵跡
洗心庵跡 posted by
(C)pismo
この後は再び三津浜の駐車場に戻り、車で高浜方面に移動します。