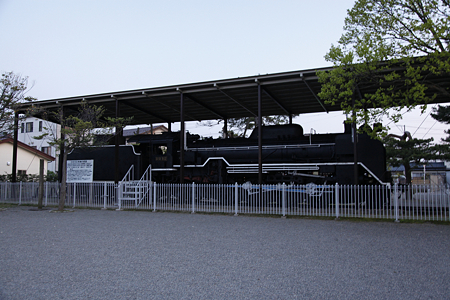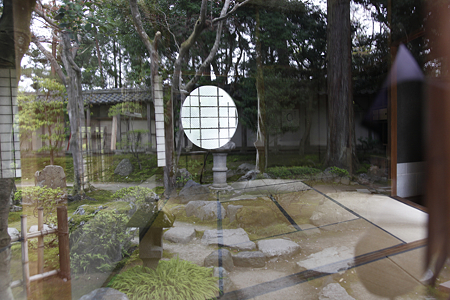天神山城など岩室地域で時間を使ったのもう夕方になってしまいました。
この日の宿泊は新潟市なので、周辺の城を巡ってみます。
木場城は、天正9(1581)年に上杉景勝により築かれた城です。
当時景勝は、当時、景勝は織田信長の結んだ新発田城の新発田重家と争っていて木場城は景勝の前線基地でした。
景勝は、木場城の実城(本丸)に蓼沼友重、二の郭には山吉景長を配属し、新潟に拠点を置く新発田勢と戦いました。
戦いは主に舟を使って火矢を放つ焼き打ち合戦でした。
木場城勢が新潟を攻略したり、新発田勢が木場城を攻略したり戦いは一進一退を繰り返しながら6年余りも続きました。
木場城は、天正15(1587)年 新発田氏が滅亡したあとも存続しましたが
慶長3(1598)年の上杉家の会津移封ににより廃城となりました。木場城は木場集落の西端にあったと推定されていますが、遺構は確認されていなく正確な位置は分かっていないそうです。
主郭部と推定される位置に、木場八幡宮が祀られていて、木場八幡宮を含む跡地全体を「宮のもり・木場城公園」として整備されています。
 木場城 - 01
木場城 - 01 posted by
(C)pismo
 木場城 - 02
木場城 - 02 posted by
(C)pismo
 木場城 - 03
木場城 - 03 posted by
(C)pismo
 木場城 - 04
木場城 - 04 posted by
(C)pismo
水原城は、伊豆の豪族大見家秀が源頼朝の挙兵に功績があり、白川荘地頭に任ぜられ、その子孫が安田氏となりその庶流が水原の地を分与され水原氏を称しました。
戦国時代、水原氏は上杉謙信に仕え、御館の乱では水原満家が上杉景勝に味方しました。
新発田重家の乱では、満家は景勝方として戦いましたが、天正11(1583)年、新発田城の包囲を解いて退却する途中、新発田重家の追撃を受け、殿として戦い戦死しました。
その際、水原城は新発田方に攻め落とされました。
天正12(1584)年には、一度水原城は上杉景勝が奪還しましたが、新発田方はよく戦い、再び水原城は新発田方のものとなりました。
天正13(1585)年、景勝は水原城を再び攻め、内通により火を放たせようやく落城させました。
その後、景勝は水原城に大関弥七親憲を入れ、水原常陸介親憲と名乗らせました。
水原親憲は、関ヶ原の戦いの長谷堂城からの撤退戦や、大坂冬の陣で活躍しました。大坂の陣の際、徳川秀忠から感状を貰いましたが、その際宛名が「杉原常陸介」となっていたので、杉原(読みはすいばら)親憲と改めました。
「子供の石合戦で感状を賜るとは」と言っていたそうです。
水原城は、慶長3(1598)年、水原親憲が上杉景勝の会津移封に従い会津へ移ったため廃城となりました。
水原代官所は、江戸時代の延享3(1746)年、水原城跡地に幕府により設けられた天領の代官所です。支配高は時代により増減がありますが、5万石前後から7万石、多い時は10万石にも及び、専任の代官は22代を数え、慶応4(1868)年に会津藩預かりとなるまで約120年間続きました。
現在の水原代官所は、平成5(1993)年、代官所平面図を基に復元が計画され、平成7(1995)年に完成したものです。
もう夕方と言うことで閉まっていたので、また明日訪れてみることにします。
 水原代官所・水原城 - 1
水原代官所・水原城 - 1 posted by
(C)pismo
 水原代官所・水原城 - 2
水原代官所・水原城 - 2 posted by
(C)pismo
 水原代官所・水原城 - 3
水原代官所・水原城 - 3 posted by
(C)pismo
笹岡城は貞和年間(1345~1350)篠岡中将資尚が築城したといわれています。
また、一説には、和田義盛の子、三郎五郎兵衛義茂の子が中条郷の地頭となり、その居城であったといわれています。
応永の乱の際には、中条房資(奥山荘中条)が一時期ここに派兵して築城しました。
戦国時代には、山浦国清(村上義清の子)の居城でしたが、上杉景勝の時代、今井源右衛門国広が御館の乱の功績で魚沼上郷城から転封され、酒井新左衛門、黒金宮内の二人がこれを守りました。
新発田重家の乱の際には、鉢盛城とともに新発田城攻撃の前線基地として重要な役割を果たしていました。
天正13(1585)年には、新発田重家により落城し、その後城主がなく廃城となりました。
城跡主郭部は公園になっています。鑑洞寺や稲荷神社も城域です。
 笹岡城 - 01
笹岡城 - 01 posted by
(C)pismo
十郎杉は、十郎丸という連絡船を繋いだとか、十郎という人が植えたとか、城楼杉から転じて十郎杉で。笹岡城の望楼の役目を果たしたとか、女郎杉が転じて十郎杉となり笹岡城の奥女中を葬ったとか、宿場町笹岡の遊女を葬ったとかいろいろな説があり、阿賀野市(旧笹神村)の指定文化財になっています。
 笹岡城 - 02
笹岡城 - 02 posted by
(C)pismo
 笹岡城 - 03
笹岡城 - 03 posted by
(C)pismo
 笹岡城 - 04
笹岡城 - 04 posted by
(C)pismo
 笹岡城 - 05
笹岡城 - 05 posted by
(C)pismo
笹岡城から安田城から移動途中、田園風景の夕日をみることができました。
新潟県の田園風景は関西では見ることができない、広大な田園風景です。
 阿賀野市福井付近の夕日
阿賀野市福井付近の夕日 posted by
(C)pismo
安田城は大見氏の子孫安田氏の居城です。
柏崎市にも安田城がありますが、あちらは毛利一族の系統の安田氏の居城です。
中世の安田町周辺は白河庄と呼ばれる荘園で摂関家の領地でした。
鎌倉幕府が創設されると、源頼朝挙兵に参陣して功績のあった関東御家人伊豆の大見氏が地頭職として着任し、のちに安田氏を名乗りました。
安田氏は安田城を拠点地に守護上杉氏や上杉謙信に仕え、数々の戦功をたてました。安田長秀は川中島の戦いの際、同じ揚北衆の色部勝長・中条藤資らと共に「血染めの感状」を貰っています。(感状を貰ったのは長秀ではなく、長秀の子安田有重という説もあります。)
慶長3(1598)年上杉景勝の会津若松城移封で安田氏も同行し、 村上城主村上義明の重臣吉竹右近が在番しました。
元和4(1618)年、村上氏の改易により村上城主となった堀直竒の支配となったが、元和元(1615)年の一国一城令のもとに、 元和8(1622)年安田城は破却されました。
寛永16(1639)年、直竒は63歳で没し、その遺言により次男直時が3万石を分与され、安田に居城を構えて立藩しました。
正保元(1644)年、直時の子直吉が領地替えで村松城へ移り、安田城は廃されました。
現在は教習所風?の公園、公民館、体育館などの敷地になっています。水堀が残っています。
 安田城 - 01
安田城 - 01 posted by
(C)pismo
 安田城 - 02
安田城 - 02 posted by
(C)pismo
 安田城 - 03
安田城 - 03 posted by
(C)pismo
 安田城 - 04
安田城 - 04 posted by
(C)pismo
五泉城は永禄2(1382)年、長尾憲顕により築かれました。
初代城主は五泉数馬です。
天正11(1583)年、上杉景勝の家臣甘糟備後守景継は、護摩堂城(田上町)より2万石を与えられ五泉城に移りました。
甘糟景継は、上田長尾家の家臣、登坂家の出身で、景勝が上杉家の養子に迎えられたときも春日山城へ入城しました。
文禄2(1593)年、五泉城から庄内の酒田城へ移り、上杉家が会津に移封された際には白石城主となりました。
五泉はその後天領となり、五泉城は五泉八幡宮社地として整地し、慶安2(1649)年、社殿を調えて宮腰より遷宮しました。
もうほとんど真っ暗になっていたので「甘糟備後守城」の石碑があると聞いていますが、見つけることが出来ませんでした。
 五泉八幡宮 - 1
五泉八幡宮 - 1 posted by
(C)pismo
この日の行程はここまでで、二日目に続きます。