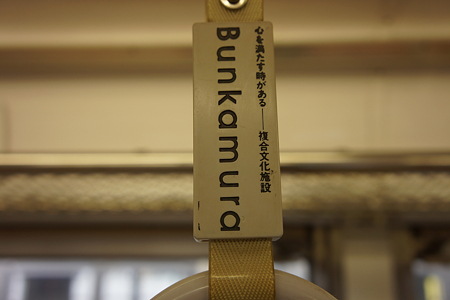南海電車で岸和田駅へ移動しました。
岸和田駅では朝の連続テレビ小説「カーネーション」、主役の小原糸子役の尾野真千子さんが出迎えてくれます。
 岸和田駅
岸和田駅 posted by
(C)pismo
 岸和田駅前商店街 - 1
岸和田駅前商店街 - 1 posted by
(C)pismo
「和撫子〔カーネーション〕」は、岸和田カーネーション推進協議会のオフィシャルショップです。
岸和田の地元ならではのお土産や連続テレビ小説「カーネーション」にちなんだグッズやだんじりグッズなどが揃います。
ショップ名の「和撫子」は、カーネーションの和名「和欄撫子(オランダナデシコ)」からの造語です。
※平成23(2011)年9月1日〜平成24年3月末までの営業。
 和撫子 カーネーション
和撫子 カーネーション posted by
(C)pismo
洋裁コシノは、連続テレビ小説「カーネーション」のヒロイン小原糸子のモデルとなった「小篠綾子」さんのお店で、コシノ三姉妹の生家です。
現在は、ギャラリー、ショップとして改装され、昭和初期を再現した外観になっています。
1階は「コシノ三姉妹」グッズなどを販売しており、2階は小篠綾子さんが実際に使っていた作業場も再現されています。
 洋裁コシノ - 1
洋裁コシノ - 1 posted by
(C)pismo
「NHKギャラリー カーネーション」は、NHK連続テレビ小説「カーネーション」のPRのためNHK大阪放送局とタイアップした観光施設です。
番組紹介パネルやロケ風景パネルの展示やメイキング映像の放映などを行っています。
展示期間 ※平成23年11月3日~平成24年3月31日の期間限定
 NHKギャラリー・カーネーション - 1
NHKギャラリー・カーネーション - 1 posted by
(C)pismo
本徳寺は、山号は鳳凰山、臨済宗妙心寺派の寺院です。
明智光秀の子南国梵桂が建立したと伝えられ、元々は現在の貝塚市鳥羽にあった海雲寺でしたが、岸和田藩主岡部行隆の命で現地に移され、寺号も本徳寺と改められました。
当寺には南国が描かせた明智光秀画像が伝わり、光秀の肖像画としては唯一のものとして有名です。
ただし、観光寺院ではないようで、内部は拝観できていません。
 本徳寺
本徳寺 posted by
(C)pismo
市内は、レトロな建物もよく残っています。
 旧四十三銀行
旧四十三銀行 posted by
(C)pismo
円成寺は、山号は長泉山、真宗大谷派の寺院です。
信濃国の武士、加藤主計大允則政が藤原信継に従い戦場に赴き、数々の武功を残しましたが、信継の没後発心し、本願寺証如上人本願寺證如上人のもと剃髪得度しました。法名を釋専稱と号して諸方に伏匿し、ようやく天文5(1536)年現在の地に坊舎を建立し、同信の人々に布教を始めたのが、円成寺のはじまりです。その後、460年余の長きにわたり専修念仏の道場として現在に至っています。
(説明看板などより)
観光寺院ではないようで、中に入ることはできませんでした。
 円成寺 - 1
円成寺 - 1 posted by
(C)pismo
 円成寺 - 2
円成寺 - 2 posted by
(C)pismo
周辺は紀州街道沿いの本町で、古い町並みがよく保たれています。
 本町のまちなみ - 01
本町のまちなみ - 01 posted by
(C)pismo
 本町のまちなみ - 02
本町のまちなみ - 02 posted by
(C)pismo
紀州街道本町一里塚跡にある
一里塚弁財天です。
一里塚とは、江戸幕府の命により慶長9(1604)年、江戸の日本橋を五街道の起点と定め、36町歩を一里と定め一里ごとに塚を築造し、榎、松などを植えさせたのが始まりだと言われています。
紀州街道は脇街道、紀州往還道であるため、大坂の高麗橋を起点として、和歌山城下まで一里塚が設けられていました。
由緒によれば弁財天は元々は一里塚に植えられていた松の下に小祠があったものを、天保7(1836)年8月頃に弁財天として社殿をつくり現在のところに遷座したものとされていて、現在も街道を往来する人々を見守り続けています。
(現地説明板より)
 紀州街道本町一里塚跡 - 1
紀州街道本町一里塚跡 - 1 posted by
(C)pismo
蛸地蔵天性寺は、山号は護持山、院号は朝光院、浄土宗の寺院で、本草は阿弥陀如来と蛸地蔵尊です。
元亀元(1570)年に建立された地蔵堂としては日本最大級の建物です。
寺に伝わる蛸地蔵縁起では、本尊の地蔵菩薩は古くから岸和田の守本尊とされましたが、戦乱を免れるため当時の領主により堀に入れられていました。後の天正年間、岸和田城が根来・雑賀衆に攻められ落城の危機になった際、数千の蛸と一人の法師が現れ城を救ったといいます。数日後、堀から矢傷や弾傷を負った地蔵菩薩が発見され、法師は地蔵菩薩の化身であったことがわかりました。地蔵菩薩は、城中の別殿に安置されましたが、民衆が参拝できるように天性寺に移されました。その伝承にちなんで蛸絵馬を奉納し、蛸を絶って願をかける人もいるそうです。
平成24年2月現在、本堂が修復工事中です。
 蛸地蔵天性寺 - 1
蛸地蔵天性寺 - 1 posted by
(C)pismo
 蛸地蔵天性寺 - 2
蛸地蔵天性寺 - 2 posted by
(C)pismo
岸和田だんじり会館は、元禄16(1703)年に始まり、およそ300年間の伝統を誇る岸和田だんじり祭の資料を豊富に展示しています。
映像や音響により祭りを再現しており、祭りそのものが体験できる資料館です。
 岸和田だんじり会館 - 01
岸和田だんじり会館 - 01 posted by
(C)pismo
 岸和田だんじり会館 - 02
岸和田だんじり会館 - 02 posted by
(C)pismo
 岸和田だんじり会館 - 03
岸和田だんじり会館 - 03 posted by
(C)pismo
 岸和田だんじり会館 - 04
岸和田だんじり会館 - 04 posted by
(C)pismo
 岸和田だんじり会館 - 05
岸和田だんじり会館 - 05 posted by
(C)pismo
 岸和田だんじり会館 - 06
岸和田だんじり会館 - 06 posted by
(C)pismo
岸和田城は楠木正成の一族和田高家が現在位置からは約700m南東の位置に築いたといわれています。室町時代に現在の位置に移りました。
天正13(1585)年、豊臣秀吉の外戚小出秀政が城主となり、城郭を整備しました。天守閣もこの時に築かれました。
小出氏は秀政・吉政・吉英と3代続き、出石に転封になった後は、松平(松井)氏の松平康重が城主となり、城下町などの整備を行いました。寛永17(1640)年に康重の子康映が播磨山崎へ転封した後は岡部宣勝が入城しました。その時伏見城の櫓と城門が移築されました。以後13代にわたって岡部氏が城主となり明治維新を迎えます。
天守閣は文政10(1827)年に落雷で焼失しました。明治を迎え、本丸・二の丸の石垣と水堀を残して破却されましたが、昭和29年(1954年)に鉄筋で天守閣を復元しました。現在の天守閣は3層3階ですが、本来は5層天守だったそうです。
天守閣の中と、本丸には資料館があり、旧藩主岡部氏の遺品や郷土史料を展示しています。
 岸和田城 - 01
岸和田城 - 01 posted by
(C)pismo
 岸和田城 - 02
岸和田城 - 02 posted by
(C)pismo
 岸和田城 - 03
岸和田城 - 03 posted by
(C)pismo
 岸和田城 - 04
岸和田城 - 04 posted by
(C)pismo
 岸和田城 - 05
岸和田城 - 05 posted by
(C)pismo
岸城神社(きしきじんじゃ)は、南北朝時代、京都の八坂神社を勧請し岸和田村の鎮守にしました。小出秀政が岸和田城を築城したとき、八幡大神を合祀しました。
明治維新後に社名を岸城神社と改めました。だんじり祭では14台がこの神社に宮入りします。
平成23(2011)年に御鎮座650年を迎え社殿などが整備されました。
 岸城神社 - 01
岸城神社 - 01 posted by
(C)pismo
 岸城神社 - 02
岸城神社 - 02 posted by
(C)pismo
 岸城神社 - 03
岸城神社 - 03 posted by
(C)pismo
 岸城神社 - 04
岸城神社 - 04 posted by
(C)pismo
この日の「まちあるき」はここまでです。
Posted at 2012/03/26 21:04:53 | |
トラックバック(0) |
旅行(ドライブ以外) | 日記