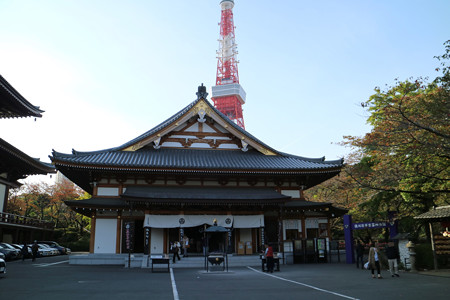迎賓館は、かつて紀州徳川家の江戸中屋敷があった広大な敷地の一部に、明治42(1909)年に東宮御所(後に赤坂離宮となる。)として建造されたものです。構造は鉄骨補強煉瓦造りで、地上2階、地下1階の耐震、耐火構造となっており、明治時代の建築家片山東熊の総指揮の下に、当時の一流建築家や美術工芸家が総力を挙げて建設した、日本における唯一のネオ・バロック様式の西洋風宮殿建築です。
この建物は、昭和天皇や今上天皇が一時期お住まいになった以外、東宮御所としてあまり使用されることがなく、戦後、建物、敷地共に皇室から行政に移管され、国立国会図書館、内閣法制局、東京オリンピック組織委員会などの公的機関に使用されていました。
この間、わが国が国際社会へ復帰し、国際関係が緊密化し、外国の賓客を迎えることが多くなったため、国の迎賓施設をつくる方針がたてられ、これに伴い建設地や施設内容等の検討を行った結果、昭和42(1967)年に「旧赤坂離宮」を改修してこれに充てることとなりました。
改修工事は昭和43(1968)年から5年有余の歳月と総額108億円の経費をかけて行われ、賓客に対し和風の接遇を行なうための別館の新設と合わせて、昭和49(1974)年に現在の迎賓館が完成しました。
開館以来、世界各国の国王、大統領、首相などの国賓、公賓がこの迎賓館に宿泊し、歓迎行事をはじめとし、政財学界要人との会談、レセプションでの懇談など、華々しい外交活動の舞台となっています。また、先進国首脳会議(1979、1986、1993)、日本・東南アジア諸国連合特別首脳会議(2003)などの重要な国際会議の会場としても使用されています。
平成18(2006)年から3年間、大規模な改修工事を行い、平成21(2009)年4月から迎賓施設としての運用を再開しました。同年12月、創設当時の建造物である旧東宮御所(迎賓館赤坂離宮)本館、正門、主庭噴水池等が国宝に指定されました。
平成27(2015)年11月1日から3日までの前庭公開を利用して、訪れました。本館及び主庭が公開されることもあります。
 迎賓館赤坂離宮
迎賓館赤坂離宮 posted by
(C)pismo
 迎賓館赤坂離宮 (1)
迎賓館赤坂離宮 (1) posted by
(C)pismo
 迎賓館赤坂離宮 (2)
迎賓館赤坂離宮 (2) posted by
(C)pismo
 迎賓館赤坂離宮 (3)
迎賓館赤坂離宮 (3) posted by
(C)pismo
 迎賓館赤坂離宮 (4)
迎賓館赤坂離宮 (4) posted by
(C)pismo
 迎賓館赤坂離宮 (5)
迎賓館赤坂離宮 (5) posted by
(C)pismo
 迎賓館赤坂離宮 (6)
迎賓館赤坂離宮 (6) posted by
(C)pismo
 迎賓館赤坂離宮 (7)
迎賓館赤坂離宮 (7) posted by
(C)pismo
 迎賓館赤坂離宮 (8)
迎賓館赤坂離宮 (8) posted by
(C)pismo
喰違見附は、江戸時代初期の慶長17(1612)年に甲州流兵学者の小幡景憲によって縄張りされたと伝わる、江戸城外郭門のひとつです。通常江戸城の城門は枡形門と呼ばれる石垣を巡らしたものとなりますが、ここは土塁を前後に伸ばして直進を阻むという、戦国期以来の古い形態の虎口(城の出入口)構造となります。
この地域は、二つの谷に挟まれた、江戸城外堀の中では最も高い地形に立地するため、寛永13(1636)年築造の江戸城外郭門に先駆けて、江戸城防御の要として構築されたと考えられます。現在は一部土塁が削り取られているものの、その形状は保存されており、往時の様子を留めています。この遺構は江戸城築城史を捉える意味で重要です。
(現地説明板などより)
 喰違見附
喰違見附 posted by
(C)pismo
 喰違見附 (1)
喰違見附 (1) posted by
(C)pismo
この坂を
紀尾井坂といいます。「新撰東京名所図会」には「喰遠より清水谷公園の方へ下る坂を称す」また「喰違内坂を、紀尾井坂といふ、蓋し此坂の両側に、紀州、尾州、井伊三公の邸宅ありしが故に、各頭字を取り名とせるものなりといふ」と記されています。
このあたりが紀尾井町と呼ばれているのもそのためです。また坂下が清水谷なので清水谷坂の別の名もあったといいます。
なお、明治11(1878)年5月に内務卿大久保利通公が殺害された事件は、この坂ではなく、麹町清水谷(清水谷公園付近)で起きています。「紀尾井坂の変」と誤って伝えられているのは、灯火を持ち馬車を先導した人物がこの坂を上っている最中に事件が発生したためです
(現地説明板などより)
 紀尾井坂
紀尾井坂 posted by
(C)pismo
 紀尾井坂 (1)
紀尾井坂 (1) posted by
(C)pismo
明治11(1878)年5月14日朝、麹町清水谷において、赤坂御所へ出仕する途中の参議兼内務卿大久保利通が暗殺されました。現在の内閣総理大臣にも匹敵するような立場にあった大久保の暗殺は、一般に「紀尾井坂の変」と呼ばれ、人びとに衝撃を与えました。
また、大久保の同僚であった明治政府の官僚達(西村捨三・金井之恭・奈良原繁ら)の間からは、彼の遺徳をしのび、業績を称える石碑を建設しようとの動きが生じ、暗殺現場での周辺であるこの地に、明治21(1888)年5月
「贈右大臣大久保公哀悼碑」が完成しました。
「哀悼碑」の高さは、台座の部分も含めると6.27mにもなります。石碑の材質は緑泥片岩。台座の材質は硬砂岩と思われます。
「贈右大臣大久保公哀悼碑」は、大久保利通暗殺事件という衝撃的な日本近代史の一断面を後世に伝えつつ、そしてこの碑に関係した明治の人びとの痕跡を残しつつ、この地にたたずんでいます。
碑がある清水谷公園は、明治23(1890)年から東京市の公園とされています。
井伊家との境目付近が谷だったことと、井伊家との境目付近の紀州徳川家の屋敷から清水が沸き出ていたことから、付近は「清水谷」と呼ばれていました。
石碑は、千代田区の文化財に指定されています。園内には麹町大通り拡幅工事の際に出土した玉川上水の石枡が展示してあります。
(現地説明板などより)
 清水谷公園・大久保公哀悼碑
清水谷公園・大久保公哀悼碑 posted by
(C)pismo
 清水谷公園・大久保公哀悼碑 (1)
清水谷公園・大久保公哀悼碑 (1) posted by
(C)pismo
この一帯には、江戸時代に
紀伊和歌山藩徳川家の麹町邸がありました。
明暦3(1657)年の大火の後、この地を拝領しました。紀伊徳川家は、徳川家康の十男頼宣に始まる家で、尾張家(九男義直)、水戸家(十一男頼房)と共に御三家と称されました。頼宣は慶長8(1603)年常陸水戸藩主、ついで慶長14(1609)年駿河府中藩主を経て、元和5(1619)年に紀伊和歌山藩主となり、紀伊国と伊勢国の一部を領地としました。紀伊徳川家は、以後、14代にわたって明治維新まで続きましたが、その中で、8代将軍吉宗と14代将軍家茂は、藩主から将軍の座についています。石高はほぼ55万5000石でした。明治5年、この地域は紀伊徳川家・尾張徳川家・井伊家の頭文字を合わせて、「紀尾井町」という町名になりました。
(現地説明板などより)
 紀伊和歌山藩徳川家屋敷跡
紀伊和歌山藩徳川家屋敷跡 posted by
(C)pismo
明治から亡くなるまでこの地に住んだ勝海舟の屋敷跡・
勝安房邸跡です。
この地は、幕末から明治にかけて、幕臣として活躍した勝海舟が明治5(1872)年の49歳から満76歳で亡くなるまで住んでいた屋敷の跡地です。その間、参議・海軍卿、枢密顧問官、伯爵として顕官の生活を送り、傍ら有名な「氷川清話」などを遺しました。その時の屋敷跡は東京市に寄付され、平成5(1993)年春まで港区立氷川小学校敷地として使用されていました。その後、氷川小学校が廃校になったため、その建物を生かしつつ改修を行い、平成15(2003)年から区立特別養護老人ホーム及び子ども中高生プラザとして使用して現在に至っています。施設内には、屋敷跡の発掘調査で出土した当時の縁の品などが展示されています。
(現地説明板などより)
 勝安房邸跡
勝安房邸跡 posted by
(C)pismo
 勝安房邸跡 (1)
勝安房邸跡 (1) posted by
(C)pismo
 勝安房邸跡 (2)
勝安房邸跡 (2) posted by
(C)pismo
幕末の動乱期の
勝海舟邸跡です。
港区赤坂6丁目10番39号のソフトタウン赤坂が建つこの地は、幕末から明治にかけて幕臣として活躍した勝海舟が安政6(1859)年から明治元(1868)年まで住んだ旧跡です。
海舟は終生赤坂の地を愛し、3ヶ所に住みましたが、当初居住中の10年間が最も華々しく活躍した時期に当たります。海舟は号で名は義邦。通称麟太郎、安房守であったから安房と称し、後に安芳と改めました。夫人は民子です。
海舟は文政6(1823)年、本所亀沢町の旗本屋敷、現墨田区両国4丁目の両国公園の地で、貧しい御家人の子として出生しました。長じて赤坂溜池の筑前黒田藩邸、のちの福吉町、現赤坂2丁目の赤坂ツインタワービルや衆議院赤坂議員宿舎などの地に通って蘭学を学び、その縁から新婚23歳で赤坂田町中通り、現赤坂3丁目13番2号のみすじ通りの借家で所帯を持ちました。
36歳からは赤坂本氷川坂下、のちの氷川町のこの地に住みました。
明治元(1868)年45歳で、引退の徳川慶喜に従って、ここから静岡市に移りましたが、明治5(1872)年再び上京し、満76歳で亡くなるまで赤坂区氷川町4番地、現赤坂6丁目6番14号に住み、参議・海軍卿、枢密顧問官、伯爵として顕官の生活を送り、傍ら氷川清話などを遺した。この時の屋敷跡は東京市に寄付され、平成5(1993)年春まで区立氷川小学校敷地として使われました。
当初に住み始めた翌年の安政7(1860)年、幕府海軍の軍艦頭取=咸臨丸艦長として上司の軍艦奉行木村摂津守、その従僕福沢諭吉らを乗せ、正使のの外国奉行新見豊前守を乗せた米艦ポーハタン号に先行して渡航、日本の艦船として初めて太平洋横断・往復に成功した。
文久2(1862)年11月、海舟を刺殺しようとして訪れた旧土佐藩士坂本龍馬らに世界情勢を説いて決意を変えさせ、逆に熱心な門下生に育てて、明治維新への流れに重要な転機を与えることになったのもこの場所です。
明治元(1868)年3月には、幕府陸軍総裁として、官軍の江戸城総攻撃を前に征討総督府参謀西郷隆盛と談判を重ね、無血開城を決めて江戸の町を戦火から救いました。
第1回会談は、高輪の薩摩藩邸品川駅前の、のちの高輪南町、現港区高輪3丁目のホテルパシフィックの地で行われました。第2回については芝田町薩摩藩邸、のち三田四国町、現港区芝5丁目芝税務署辺りの地または、三田海岸の薩摩藩蔵屋敷の裏側にある民家、現港区芝5丁目の三菱自動車ビル周辺で行われたとの両説があります。いずれも当所居住中のことです。
明治維新では、明治元(1868)年5月、海舟の留守中に、一部の官軍兵士がここの勝邸に乱入しましたが、海舟の妹で佐久間象山未亡人の瑞恵(旧名・順)が家人を励まして一歩も引かずに応対し、危急を救いました。
海舟は終生赤坂の地を愛しましたが、郊外の風光にも惹かれ、初めは葛飾区東四ツ木1丁目に、次いで洗足池に面して造られ、自ら建てた西郷隆盛を偲ぶ碑と共に大田区文化財に指定されています。
(現地説明板などより)
 勝海舟邸跡
勝海舟邸跡 posted by
(C)pismo
 勝海舟邸跡 (1)
勝海舟邸跡 (1) posted by
(C)pismo