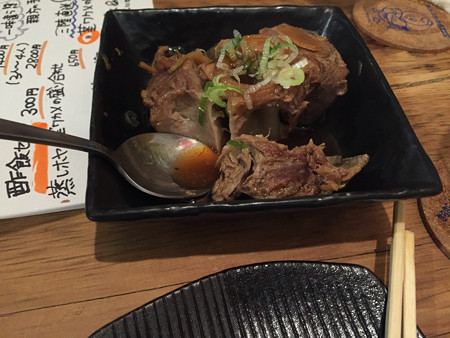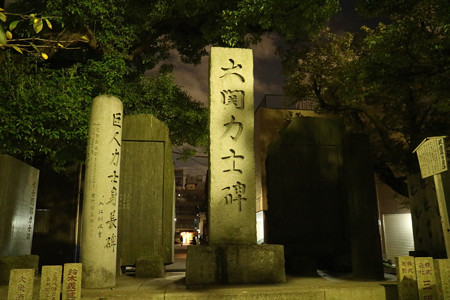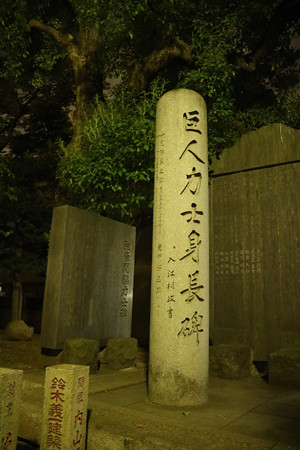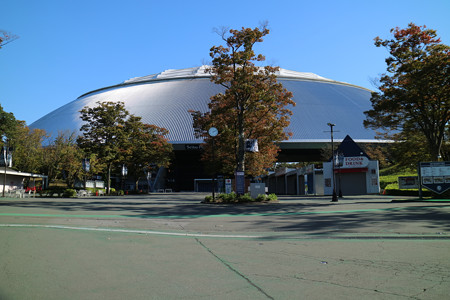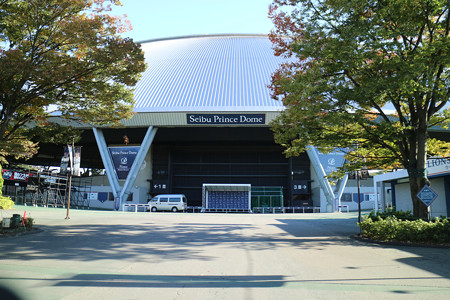新選組副長土方歳三の生家は、資料館になっているこの地の300m東、石田寺の北方にありました。
弘化3(1846)年、歳三が12歳の6月末、長雨による増水で多摩川・浅川の堤防が決壊し、万願寺や石田村などは大洪水に見舞われたが、歳三の生家も土蔵などに被害を受けました。その後、残った母屋や土蔵をこの地に解体移築しました。
歳三は、その家で文久3(1863)年2月、京都に上洛するまでの青春時代を過ごしました。生家は、万願寺地区の区画整理により平成2(1990)年に取壊されました。現在、屋敷内には歳三の植えた矢竹が繁り、新築された家屋には相撲の稽古をした大黒柱や梁を移植して一室を作り、
土方歳三資料館として月に2回、公開しています。
土方歳三の鎖帷子などの武具、写真や手紙などが展示されています。
平成17(2005)年春には3倍の広さになって新装開館し、これまで展示しきれなかった資料も新たに見られるようになりました。
 土方歳三資料館
土方歳三資料館 posted by
(C)pismo
 土方歳三資料館 (1)
土方歳三資料館 (1) posted by
(C)pismo
 土方歳三資料館 (2)
土方歳三資料館 (2) posted by
(C)pismo
 土方歳三資料館 (3)
土方歳三資料館 (3) posted by
(C)pismo
 土方歳三資料館 (4)
土方歳三資料館 (4) posted by
(C)pismo
 土方歳三資料館 (5)
土方歳三資料館 (5) posted by
(C)pismo
 土方歳三資料館 (6)
土方歳三資料館 (6) posted by
(C)pismo
石明神社(せきみょうじんじゃ)は土方家を含めてこの辺り一帯の 産土神(うぶすなのかみ)です。
創建年代は不明ですが、慶長2(1597)年に社殿を改築した棟札が最古のものであり、その後、寛永2(1673)年、元禄12(1699)年、享保2(1717)年にわたって社殿改築の棟札があります。古くは堰大明神、または石明社または石大明神といわれていましたが、近代にいたって石明神社と改称され、戦後も石明神社と呼ぼれています。
現在の社殿は平成14(2002)年にできたものです。
 石明神社
石明神社 posted by
(C)pismo
 石明神社 (1)
石明神社 (1) posted by
(C)pismo
伊十郎屋敷は、土方歳三の生家跡の東隣にあります。
当家は、隣家の先祖源内の分家です。伊三郎、伊十郎、久蔵は幕末三代村役人を勤めました。
伊三郎は弘化3(1846)年、隼人家あわや流亡の折、名主として陣頭指揮し、現在地に移住させました。
この洪水の7年前、14歳の娘なかを本家喜六(隼人)に嫁がせていました。時に歳蔵(歳蔵は宗門人別書上帳に記されている土方歳三の名です。)は5歳でした。
多摩川の本流は更に居村に迫り、安政5(1858)年、伊十郎家も此の地に移りました。
石田村の歳蔵は在郷の若者に武芸を奨励し、特に分家の久蔵(貞作)には、近藤勇からの稽古への誘いの手紙を此の長屋門を通り届けています。
145年の歳月が過ぎ、村の原風物は少なくなった。近藤や歳蔵が見覚えあるものは、とうかんの森や石田寺の榧の木、建物では此の長屋門と母屋ぐらいになってしまいました。
(現地説明板などより)
 伊十郎屋敷
伊十郎屋敷 posted by
(C)pismo
 伊十郎屋敷
伊十郎屋敷 posted by
(C)pismo
とうかん森には土方一族(十家余)の氏神を祀る稲荷社があります。
稲荷社は、古くから地元の土方一族が祀ってきたもので、宝永5年(1708)の記録にもそのことが書かれています。「とうかん」の呼称は、「とうかん森」とは「稲荷森」を音読した「とうかもり」あるいは十家の音読みに由来するとも伝えられています。
森は、稲荷祠とカヤ2本及びフジによって形成されています。
カヤはいずれも大木で、樹齢250年と推定されているものもあり、2本とも雄株です。
かつては20mを超えるムクノキ が、稲荷祠を中心にカヤ・フジを取り囲むようにしてあり、こんもりとした森を形成していました。
土方歳三の生まれた家はとうかん森の北東にありましたが、彼が5歳の時多摩川が洪水により土蔵を壊したため、移転しました。
かつては、うっそうとした森ですが、平成23(2011)年、枝が隣家にかかるようにもなり、大幅に伐採されてしまいました。
 とうかん森
とうかん森 posted by
(C)pismo
 とうかん森 (1)
とうかん森 (1) posted by
(C)pismo
石田寺は、山号は愛宕山、院号は地蔵院、高幡不動尊金剛寺の末寺で真言宗の寺院です。
南北朝時代の康安元(1361)年、吉祥坊慶興という僧が建立したものの、永和3(1377)年頃から衰えて一時は廃寺となった場所に、百数十年を経た天文13(1544)年7月9日、多摩川に大洪水が起こり、一体の観音像が石田に流れ着きました。それを村人が廃寺になった堂跡に観音堂を建てて安置したのがきっかけになり、文録2(1593)年に慶心という僧が一宇を建立、石田寺と号したといいます。
土方家の墓所があり、土方歳三の墓がもあります。
歳三は函館で戦死しているため、この墓には遺骨はないため「引き墓」です。
 石田寺
石田寺 posted by
(C)pismo
 石田寺 (1)
石田寺 (1) posted by
(C)pismo
甲州街道万願寺一里塚です。
江戸幕府は江戸日本橋を起点に街道を整備し、慶長9(1604)年に大久保長安が一里(約4km)ごとに塚を築かせました。
一里塚という名称は、一里ごとに存在したことに由来します。
一里塚は道を挟んで両側に造られ、平面規模は五間四方(約9m)を基準とし、高さは1丈(約3m)と大きなものです。
一里塚は旅人には距離の目安になり、塚の頂上には榎が植えられることが多く、大きく成長すると夏場には木陰を与えるものでした。
今の日野市域には、万願寺と現在の日野台に一里塚が築かれましたが、現存するのは万願寺の一里塚のうち甲州街道(甲州道中)の南側の一基のみです。北側の塚は昭和43(1968)年に取り壊されました。
当初の甲州街道は、青柳(国立市)付近から万願寺渡船場で多摩川を渡り、万願寺一里塚を通り日野宿に入りました。この一里塚は江戸日本橋から9番目にあたり、参勤交代の大名・甲州勤番やお茶壺道中の役人も行き来しました。
その後、貞享元(1684)年に甲州街道は、上流の日野渡船場を通る道筋へと改められました。しかし、万願寺渡船場や日野宿へと至る道は、その後も利用され、多摩川を渡ってこの塚を越えると日野宿に到着することから、このあたりは塚越(つかこし)と呼ばれていました。
平成15(2003)年、現存する甲州街道の南側の塚について範囲や構造を探るために調査を行いました。
塚は直径9m、高さ3mと一里塚の基準通りで、平面形は道に沿って長めでやや楕円形をしています。
塚の構築にあたっては、砂礫層まで掘削し外周を一部掘りくぼめ、砂を多く含む粘土質の土を積み上げました。また、道との境には塚の崩壊を防ぐためか、3段ほどの石積みが見られます。その石積みの上には宝永4(1707)年に噴火した富士山の火山灰が認められたことから、その年代より古いことが確認できています。
この塚の北側に隣接する甲州街道は、3間(5.4m)幅で、道普請の痕跡も見つかっています。
この調査の後、塚の頂上には榎を、塚全体には保護のために芝を、それぞれ植え、甲州街道のイメージも可能なよう復元しました。ただ、甲州街道は本来の3間幅(5.4m)ではなく、幅4mで復元しています。
(現地説明板などより)
 甲州街道万願寺一里塚 (1)
甲州街道万願寺一里塚 (1) posted by
(C)pismo
 甲州街道万願寺一里塚 (2)
甲州街道万願寺一里塚 (2) posted by
(C)pismo
 甲州街道万願寺一里塚
甲州街道万願寺一里塚 posted by
(C)pismo
金剛寺は、山号は高幡山、院号は明王院、正式な寺号は高幡山明王院金剛寺、高幡不動尊の通称で知られる真言宗智山派別格本山の寺院です。
成田山新勝寺、總願寺、雨降山大山寺あるいは高貴山常楽院とともに関東の三大不動尊の一つとされています。
土方歳三の墓のある日野市内の愛宕山石田寺は末寺のひとつです。
創建は、大宝年間(701)以前とも或いは奈良時代行基菩薩の開基とも伝えられていますが、寺伝では今を去る1100年前、平安時代初期に慈覚大師円仁が、清和天皇の勅願によって当地を東関鎮護の霊場と定めて山中に不動堂を建立し、不動明王をご安置したのに始まります。
建武2(1335)年8月4日夜の大風によって山中の堂宇が倒壊し、時の住僧儀海上人が康永元(1342)年麓に移し建てたのが現在の不動堂です。続いて建てられた仁王門ともども重要文化財に指定されています。
室町時代の高幡不動尊は「汗かき不動」と呼ばれて鎌倉公方をはじめとする戦国武将の尊祟をあつめ、江戸時代には関東十一檀林に数えられ、火防の不動尊として広く庶民の信仰をあつめました。
当時門末三十六ケ寺を従え、関東地方屈指の大寺院であったが安永8(1779)年の、大日堂をはじめ大師堂、山門、客殿、僧坊等を一挙に焼失しました。
その後、徐々に復興に向いましたが、昭和50年代以降五重塔・大日堂・宝輪閣・奥殿・大師堂・聖天堂等が再建されていきました。
境内には土方歳三の立像や、近藤勇、土方歳三の顕彰碑「殉節両雄の碑」があります。奥殿には新選組関係の書簡なども展示されています。
 高幡不動尊金剛寺
高幡不動尊金剛寺 posted by
(C)pismo
 高幡不動尊金剛寺 (1)
高幡不動尊金剛寺 (1) posted by
(C)pismo
 高幡不動尊金剛寺 (2)
高幡不動尊金剛寺 (2) posted by
(C)pismo
 高幡不動尊金剛寺 (3)
高幡不動尊金剛寺 (3) posted by
(C)pismo
 高幡不動尊金剛寺 (4)
高幡不動尊金剛寺 (4) posted by
(C)pismo
 高幡不動尊金剛寺 (5)
高幡不動尊金剛寺 (5) posted by
(C)pismo
 高幡不動尊金剛寺 (6)
高幡不動尊金剛寺 (6) posted by
(C)pismo
 高幡不動尊金剛寺 (7)
高幡不動尊金剛寺 (7) posted by
(C)pismo
 高幡不動尊金剛寺 (8)
高幡不動尊金剛寺 (8) posted by
(C)pismo
高幡城は、高幡不動尊の裏山にあった城です。
この城の詳細は不明です。高幡氏や平山氏の城ともいわれています。
享徳4(1455)年1月、関東公方足利成氏と関東管領山内上杉氏、扇谷上杉氏の間で行われた立河原合戦で敗れた上杉憲秋は高幡不動まで逃れて自刃しています。
不動ヶ丘と呼ばれる丘陵にあり、高幡不動尊の山内八十八箇所巡拝コースになっています。
頂上の広場の本丸付近に説明看板が立っています。麓は根小屋、陣川戸等城址ゆかりの地名が残っています。
 高幡城 (1)
高幡城 (1) posted by
(C)pismo
 高幡城 (2)
高幡城 (2) posted by
(C)pismo
 高幡城
高幡城 posted by
(C)pismo
 高幡城 (3)
高幡城 (3) posted by
(C)pismo
平山季重居館は、平安時代末期から鎌倉時代初頭にかけ、源氏に属して各地で活躍した武将、平山季重の居館の跡です。
平山季重は、保元の乱、一の谷の合戦など数々の合戦に参加し、その武勇伝は「平家物語」「吾妻鏡」にも登場するほどです。
遺跡の碑が建てられている周辺は、その後曹洞宗由木永林寺末・大福寺のあり、文化2(1805)年、大福寺を訪れた平山正名(下総国香取郡鏑木村・季重の子孫と称する)は寺内の季重の墓に詣で、その荒廃を嘆いて修復を発願しました。その意思は子の正義に受け継がれ、平山季重遺跡之碑は、嘉永4(1851)年に平山正義により建てられたものであり、碑文には季重の功績をたたえています。碑文の筆者は幕末の剣客として有名な男谷精一郎信友です。大福寺は、明治6(1873)年廃寺となりました。季重居館跡の碑は、大正14(1925)年12月に七生青年団平山支部によって建てられました。
現在この地には、平山季重ふれあい館等が建てられ、居館跡を伝えるものとして、平山季重遺跡之碑と季重居館跡の碑があります。
(現地説明板などより)
 平山季重居館
平山季重居館 posted by
(C)pismo
平山城は、平山城址公園駅の南側にある丘陵にあります。
丘の尾根一帯は都立公園「平山城址公園」として整備されています。
公園の敷地外には、平山季重を祀る「平山季重神社」がありますが、ここが曲輪跡のようです。
歴史的な由緒は不明ですが、平山氏に関わる城と推定されています。
 平山城址公園近く
平山城址公園近く posted by
(C)pismo
 平山城址公園近く (1)
平山城址公園近く (1) posted by
(C)pismo
 平山城
平山城 posted by
(C)pismo
 平山城 (1)
平山城 (1) posted by
(C)pismo
宗印寺は、山号は大澤山、曹洞宗の寺院です。
境内地は、安行寺無量院のあったところといわれています。
慶長4(1599)年、中山照守が一庵を建てました。寛文3(1633)年になり、一東天樹が一寺を開き宝永2(1705)年、三世大本慧立大和尚が痛んだ堂宇を復興させました。このときから開基中山照守の戒名宗印居士をとって、大沢山宗印禅寺と号することになりました。平山季重を供養するために建てられた大平山大福寺が明治6(1873)年、廃寺になったため、平山季重の墓、日奉地蔵堂、大福寺本尊の千手観世音菩薩立像も宗印禅寺に移されました。墓は季重二十五代の孫松本藩の平山季長が追悼のために建立したものです。
(現地説明板などより)
 宗印寺 (1)
宗印寺 (1) posted by
(C)pismo
 宗印寺 (2)
宗印寺 (2) posted by
(C)pismo