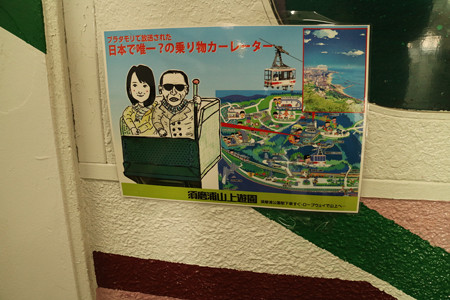この日は、山科の桜を見に訪れました。
平成23年にも訪れています。
→
山科疎水の桜
山科・毘沙門堂の桜
山科疎水
 山科疎水 (1)
山科疎水 (1) posted by
(C)pismo
 山科疎水 (2)
山科疎水 (2) posted by
(C)pismo
 山科疎水
山科疎水 posted by
(C)pismo
 山科疎水 (3)
山科疎水 (3) posted by
(C)pismo
 山科疎水 (4)
山科疎水 (4) posted by
(C)pismo
毘沙門堂
 毘沙門堂
毘沙門堂 posted by
(C)pismo
 毘沙門堂 (1)
毘沙門堂 (1) posted by
(C)pismo
 毘沙門堂 (2)
毘沙門堂 (2) posted by
(C)pismo
 毘沙門堂 (3)
毘沙門堂 (3) posted by
(C)pismo
 毘沙門堂 (4)
毘沙門堂 (4) posted by
(C)pismo
 毘沙門堂 (5)
毘沙門堂 (5) posted by
(C)pismo
 毘沙門堂 (6)
毘沙門堂 (6) posted by
(C)pismo
 毘沙門堂 (7)
毘沙門堂 (7) posted by
(C)pismo
 毘沙門堂 (8)
毘沙門堂 (8) posted by
(C)pismo
 毘沙門堂 (9)
毘沙門堂 (9) posted by
(C)pismo
 毘沙門堂 (10)
毘沙門堂 (10) posted by
(C)pismo
 毘沙門堂 (11)
毘沙門堂 (11) posted by
(C)pismo
蓮如上人は晩年、山科の南殿に隠居されていましたが、自らの臨終を悟られた時、輿に乗られて山科本願寺の正面より親鸞聖人の御真影に参られ、「極楽へ参る御いとまごひにて候、必ず極楽にて御目にかかり申すべく候」と別れを告げられました。御臨終の枕元には、一間の押板に親鸞聖人の御影を掛け、頭北面西してその時を待たれた明応8(1499)年3月25日(新暦5月14日)に蓮如上人示寂、御年85歳でした。翌26日に葬送され、荼毘に付されたと伝えられています。そうして、御遺骨が埋葬された地に御廟が建てられました。
蓮如上人御廟所は、明治維新後に官地となっていましたが、明治15(1882)年3月、蓮如上人に慧燈大師の諡号が贈られたことを機に、両派に下賜されました。御廟所の周囲には山科本願寺の遺構、西本願寺山科別院、東本願寺山科別院、蓮如上人が隠居された南殿跡など、蓮如上人縁の史跡が残されています。現在では、御廟所は東西本願寺が共同で護持しています。(現地説明板などより)
 蓮如上人御廟所 (1)
蓮如上人御廟所 (1) posted by
(C)pismo
 蓮如上人御廟所
蓮如上人御廟所 posted by
(C)pismo
山科本願寺跡は、土塁跡が山科中央公園によく残っています。
文明10(1478)年に浄土真宗中興の祖である蓮如上人により造営が開始された寺内町です。寺域は南北約1km、東西約0.8kmにおよび、周囲には防御施設として土塁や濠が巡っており、寺域内は主要な堂舎がある「御本寺」、家臣や僧侶が生活する「内寺内」、寺に関わる職人・商人などが生活する「外寺内」の3つの郭で構成されていました。
「寺中広大無辺にして、荘厳さながら仏国のごとし」と言われるほど、繁栄していたことが想像できます。しかし天文元(1532)年に細川晴元が率いる法華宗徒と延暦寺、近江守護六角氏の連合軍により、焼き討ちにあいます。
昭和48(1973)年に団地の建設に伴い、山科本願寺の北東部では山科本願寺における最初の本格的な調査が行われました。
「御本寺」と「内寺内」を限る南北方向の土塁と平行する濠や「御本寺」と「内寺内」をつなぐ道路や、石垣、鍛冶場、石組みの井戸が見つかりました。またこれら上面に堆積していた焼土や灰は、山科本願寺が焼き討ちにあったことを裏付ける証拠となりました。
これまでの調査成果で、土塁の造成の様子や中枢部である「御本寺」西側に庭園や石風呂などの施設のほか、全国的にも珍しい工芸品なども出土し、その重要性がより一層明らかになってきました。
また寺域を巡る土塁は一部現存しており、その姿を今も目にすることができます。
中でも山科中央公園に残る土塁は、「内寺内」の北東角にあたり、東西75m、南北60mにわたって残っており、当時の状況をよく留めています。
平成14(2002)年には蓮如の隠居所としてつくられた南殿とともに、国史跡に指定されています。
(現地説明板などより)
 山科本願寺跡 (1)
山科本願寺跡 (1) posted by
(C)pismo
 山科本願寺跡 (2)
山科本願寺跡 (2) posted by
(C)pismo
 山科本願寺跡
山科本願寺跡 posted by
(C)pismo
醍醐寺は、真言宗醍醐派の総本山です。
弘法大師の孫弟子、理源大師・聖宝が貞観16(874)年に創建しました。山岳信仰の霊山であった笠取山(醍醐山)に登った聖宝は、白髪の老翁の姿で現れた地主神・横尾明神より、こんこんと水(醍醐水)が湧き出るこの山を譲り受け、准胝観音と如意輪観音を刻み、山上に祀りました。これが醍醐寺の始まりです。
開創後、醍醐・朱雀・村上の三代にわたる天皇の深い帰依を受けて山上に薬師堂、五代堂、山下に釈迦堂、法華三昧堂、五重塔などが次々に建立され、山下山上にわたる大伽藍が完成しました。通称、山上を上醍醐、山下を下醍醐と呼んでいます。
下醍醐は、文明・応仁の乱で五重塔を残して焼失しましたが、慶長3(1598)年、豊臣秀吉が開いた「醍醐の花見」を契機に秀吉、秀頼により金堂や三宝院などが再建されました。
 醍醐寺 (1)
醍醐寺 (1) posted by
(C)pismo
 醍醐寺 (2)
醍醐寺 (2) posted by
(C)pismo
 醍醐寺
醍醐寺 posted by
(C)pismo
 醍醐寺 (3)
醍醐寺 (3) posted by
(C)pismo
 醍醐寺 (4)
醍醐寺 (4) posted by
(C)pismo
 醍醐寺 (5)
醍醐寺 (5) posted by
(C)pismo
 醍醐寺 (6)
醍醐寺 (6) posted by
(C)pismo
 醍醐寺 (7)
醍醐寺 (7) posted by
(C)pismo
 醍醐寺 (8)
醍醐寺 (8) posted by
(C)pismo
三宝院は永久3(1115)年、醍醐寺第14世座主・勝覚僧正の創建です。醍醐寺の本坊的な存在で、歴代座主が居住する坊です。
現在の三宝院は、建造物の大半が重要文化財に指定されています。中でも庭園を見渡せる表書院は、寝殿造りの様式を伝える桃山時代を代表する建造物で、国宝に指定されています。
国の特別史跡、特別名勝に指定されている庭園は、慶長3(1598)年に豊臣秀吉が「醍醐の花見」に際して自ら基本設計をした庭で、桃山時代の華やかな雰囲気を伝えています
 醍醐寺三宝院 (1)
醍醐寺三宝院 (1) posted by
(C)pismo
 醍醐寺三宝院
醍醐寺三宝院 posted by
(C)pismo
 醍醐寺三宝院 (2)
醍醐寺三宝院 (2) posted by
(C)pismo
 醍醐寺三宝院 (3)
醍醐寺三宝院 (3) posted by
(C)pismo
 醍醐寺三宝院 (4)
醍醐寺三宝院 (4) posted by
(C)pismo
 醍醐寺三宝院 (5)
醍醐寺三宝院 (5) posted by
(C)pismo
 醍醐寺三宝院 (6)
醍醐寺三宝院 (6) posted by
(C)pismo
 醍醐寺三宝院 (7)
醍醐寺三宝院 (7) posted by
(C)pismo
 醍醐寺 (9)
醍醐寺 (9) posted by
(C)pismo
 醍醐寺 (10)
醍醐寺 (10) posted by
(C)pismo
 醍醐寺 (11)
醍醐寺 (11) posted by
(C)pismo
 醍醐寺 (12)
醍醐寺 (12) posted by
(C)pismo
 醍醐寺 (13)
醍醐寺 (13) posted by
(C)pismo
 醍醐寺 (14)
醍醐寺 (14) posted by
(C)pismo
 醍醐寺 (15)
醍醐寺 (15) posted by
(C)pismo
 醍醐寺 (16)
醍醐寺 (16) posted by
(C)pismo
随心院は、真言宗小野流の大本山で、正暦2(991)年弘法大師第8世の法孫仁海僧正が創建しました。
元の名は牛皮山曼荼羅寺といい、その名はある夜、亡き母が牛に生まれ変わっている夢を見た仁海僧正が、その牛を探し求めて世話を尽くしたものの、間もなく死んだため、悲しんでその牛の皮に両界曼荼羅の尊像を招いて本尊としたことに由来します。
当院は真言宗小野流発祥の地であって、第5世増俊が塔頭に随心院を建立し、第7世親巌の時、後堀河天皇より門跡の宣旨をうけ、以来、小野曼荼羅寺御殿随心院門跡と称しました。
その後、応仁の兵火で炎上しましたが、慶長4(1599)年九条家から入った第24世増孝が再興し、今日にいたっています。
本堂は再興当時のもので、本尊如意輪観世音菩薩像のほかに、阿弥陀如来像(重要文化財)及び快慶作の金剛薩埵像等を安置しています。書院は天真院尼の寄進です。
この附近は、小野小町の旧跡と伝え、境内には小町文塚、化粧の井戸があり、小町の艷書をはったという地蔵菩薩も安置されています。
境内には唐棣の梅があり、3月最終日曜に「はねず踊り」と観梅の催しが行われる梅の名所です。
なお、境内地は昭和41(1966)年6月21日文化財保護法による史跡に指定されました。
(現地説明板などより)
 随心院
随心院 posted by
(C)pismo
 随心院 (1)
随心院 (1) posted by
(C)pismo
 随心院 (2)
随心院 (2) posted by
(C)pismo
 随心院 (3)
随心院 (3) posted by
(C)pismo
 随心院 (4)
随心院 (4) posted by
(C)pismo
 随心院 (5)
随心院 (5) posted by
(C)pismo
 随心院 (6)
随心院 (6) posted by
(C)pismo
 随心院 (7)
随心院 (7) posted by
(C)pismo
勧修寺は正式には真言宗山階派大本山亀甲山勧修寺という門跡寺院です。地名は「かんしゅうじ」と読みますが、寺の名前は「かしゅうじ」と読むのが正しいそうです。
昌泰3(900)年醍醐天皇が、生母藤原胤子の追善のため創建されたのが始まりです。寺号は、天皇の祖父に当る藤原高藤の諡号をとって勧修寺と名付けられました。
本堂は、江戸時代に霊元天皇より仮内侍所を、書院と宸殿は、明正天皇より旧殿を賜って造られたといわれ、本堂内に千手観音像を祀ります。
庭園は「勧修寺氷池園」と呼ばれ、「氷室の池」を中心に造園されていて、周囲の山を借景とした池泉庭園です。古く平安時代には、毎年1月2日にこの池に張った氷を宮中に献上し、その氷の厚さによってその年の五穀豊凶を占ったと言われています。
池には季節により睡蓮、杜若、蓮などが咲き誇ります。
 勧修寺 (1)
勧修寺 (1) posted by
(C)pismo
 勧修寺
勧修寺 posted by
(C)pismo
 勧修寺 (2)
勧修寺 (2) posted by
(C)pismo
 勧修寺 (3)
勧修寺 (3) posted by
(C)pismo
 勧修寺 (4)
勧修寺 (4) posted by
(C)pismo
 勧修寺 (5)
勧修寺 (5) posted by
(C)pismo
 勧修寺 (6)
勧修寺 (6) posted by
(C)pismo
 勧修寺 (7)
勧修寺 (7) posted by
(C)pismo
 勧修寺 (8)
勧修寺 (8) posted by
(C)pismo
 勧修寺 (9)
勧修寺 (9) posted by
(C)pismo
 勧修寺 (10)
勧修寺 (10) posted by
(C)pismo
 勧修寺 (11)
勧修寺 (11) posted by
(C)pismo
 勧修寺 (12)
勧修寺 (12) posted by
(C)pismo
 勧修寺 (13)
勧修寺 (13) posted by
(C)pismo
 勧修寺 (14)
勧修寺 (14) posted by
(C)pismo
 勧修寺 (15)
勧修寺 (15) posted by
(C)pismo Posted at 2017/04/26 22:42:09 | |
トラックバック(0) |
ドライブ | 日記