 今年の東京モーターショーのレポートも、これが最後です。今回は、他の皆さんがあまり注目していない、屋外の「架装メーカー」さんの展示です。こちらは各架装メーカーさんがそれぞれ出展しているのではなく、業界団体「日本自動車車体工業会」としての出展で、その会員各社の架装物を展示しているわけです。
今年の東京モーターショーのレポートも、これが最後です。今回は、他の皆さんがあまり注目していない、屋外の「架装メーカー」さんの展示です。こちらは各架装メーカーさんがそれぞれ出展しているのではなく、業界団体「日本自動車車体工業会」としての出展で、その会員各社の架装物を展示しているわけです。
















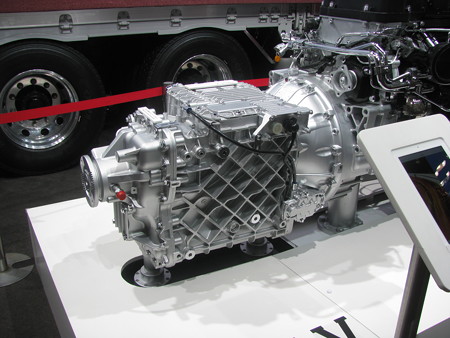


 今回の東京モーターショーでも、見学のメインは商用車。というわけで、その辺をレポートさせていただきます。正直言って、タイトルの「大型車」というより「商用車」という括りの方が相応しいのではありますが…何はともあれ、ご覧下さい。
今回の東京モーターショーでも、見学のメインは商用車。というわけで、その辺をレポートさせていただきます。正直言って、タイトルの「大型車」というより「商用車」という括りの方が相応しいのではありますが…何はともあれ、ご覧下さい。








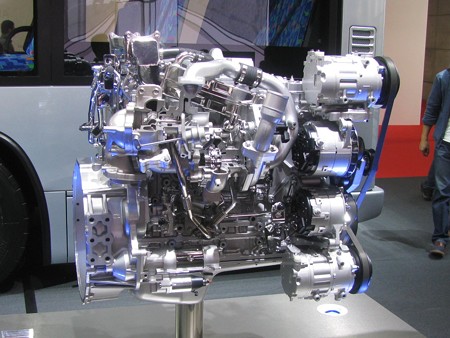
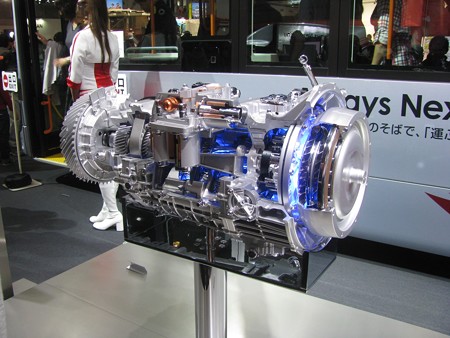










 シルバーウィークの最中に、スカニアに乗る機会を得たので、乗ってみました。その様子をレポートいたします。
シルバーウィークの最中に、スカニアに乗る機会を得たので、乗ってみました。その様子をレポートいたします。
















|
【ハイドラ】 チェックポイント追加のお知らせ カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2022/04/28 18:40:02 |
 |
|
ホンダシティハッチバックRS カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2021/08/09 09:39:45 |
 |
|
春の遠足~工場見学&水族館ツアー カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2019/11/16 14:03:55 |
 |
 |
4代目P嬢 (プジョー 308 (ハッチバック)) とうとう、P嬢も4代目に進化しました。私が選ぶ初のディーゼル車です。今までイメージカラー ... |
 |
三代目P嬢 (プジョー 208) 現在、私が乗っているのは208AllureのMT仕様で、2015年4月上旬に納車されまし ... |
 |
トヨタ スターレット 学生時代に初めて所有したマイカーで、さすがに中古調達でした。3代目スターレットの平成元年 ... |
 |
ホンダ シビック 必死に貯めたお金で買った、初めての新車です。本来は「シビッククーペ」が欲しかったのですが ... |
| 2025年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2024年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2012年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2011年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2010年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |