
海浜幕張駅前に植えられている
ネムノキが咲いていた。
ネムノキと言えば、夜になると就眠運動で葉を閉じる「眠る」木。繊細な花と、緑の木がこの時だけほのかなピンクと甘い香りに包まれるのが好きで、毎年楽しみにしている。
台風で枝が落ち幹が裂けたこともあったけれど、今年も元気に咲いていた。
でもそろそろ今年もおしまいのようだ。
**
今朝のNHK「ニュース深読み」は、放射線のことを取り上げていた。
以下、片手間に見ていたので勘違いもあるかも知れない。
3人の立場のことなる研究者に発言させていたが、おおよそ標準的な考え方を紹介する二人と、自説のアルファ線による内部被曝問題に偏りがちな一人という構図で、番組が現状の食品の安全性についてどう考えるべきかという部分と話がずれがちで軌道修正に入る場面が何度かあったような。
それはともかく、NHKの解説委員とゲストの芸能人は、割と一般的な一の感覚を代弁していた様子。
結局、情報が少なすぎて、どう行動すればわからないので、
・安全と言われても放射性物質が含まれているのなら、リスクがとの程度かわからない。
・1mSvが平常の基準だと聞かされたのだから、それをあげると言われても納得がいかない。
・後からあげると言われると、緊急時のことが準備されていなかったように感じる。
等々。
**
放射線の長期の影響がガン死あるいはガン発生で分析されるため、「それだけが影響なの?」という疑問もあって、それ以外の影響についても知りたいところ。チェルノブイリでは原発の処理に当たった兵士らに脳への影響・精神的な影響があったという話もあったが。ヒマがあったら論文を探してみたいが。
**
しかし、ICRP勧告の年間1mSvは安全の絶対基準ではない。1mSv/年が安全を保証するものではないからそれ未満でも運が悪ければガンになるし、それ以上でもガンにならない人は大勢いることになる。
100mSv/年以上であれば、放射線量とガン死率の関係は間違いないと言えるレベルになる。それとて
リスク率としては野菜不足や受動喫煙、塩分の取りすぎやら何やらと比較できる程度の比較的低いリスク率。
それ故、放射線を扱う職業人はその程度のリスクは我慢しなさいという基準を設定することになる(100mSv。福島第一原発での特例では250mSv)。
しかし、放射線を扱わない一般の人は我慢をする理由はないから、放射線を扱う場合、基本的に周囲に放射線を出してはいけない。影響は充分に小さいと考えられる、自然放射線(世界平均2.4mSv/年)よりも低くきりのいい値(1mSv/年)を基準にしている。
1mSv/年はこれ以上の放射線を人工的に周囲の人に放射してはいけないという基準であって、個人の安全を保証するための基準では全く無い。
もし「人工放射線を○○mSv/年以上あびてはならない」と個人の放射線被曝量の限度を法律的に決めていたらどうだろう。
それを守るためには、全ての人が線量計という放射線をどれだけ浴びたかを記録するものを身につけ、放射線量を管理する必要がある。ブラウン管のテレビを見るのも神経質にならなければならないし、空港でX線チェックを受けるのも、飛行機に乗るのもえらいこと。しかも、自然放射線と人工放射線をどうやって区別するのかという大問題がある。特に自然放射線に埋もれる数mSv/年の極低線量では極めて困難。
(放射線でわかりにくかったら、個人が許される紫外線被曝の基準を考えてみるといい)
1mSv/年と言う基準は、出す側に対する基準(規制)だと言うことを勘違いしてはいけない。このあたりは化学物質の排出規制と同じである。
そのため、その規制が守れなくなった事故時には、事故時の規制(緊急時20~100mSv/年、復旧時1~20mSv/年)をかけ、元の1mSv/年に戻していくことを求めることになる。あくまで出す側に対して。
出す側に課される(厳しめの)1mSv/年規制を、個人があびることをどこまで許容できるかどうかと言うことと同じに扱えない。
個人はどの程度までなら安全かという基準はなく、問題はそれを学問的には示せないことにある。
はっきりしているのは100mSv/年なら有意に影響があること。とりあえず100mSv/年ならガン死率が0.5%増えると見込まれる。
それ以下は、他のリスク要因にうもれて判別が困難。
・放射線量に比例して小さくなるか
・あまり影響がないのか
・100mSv/年からあまり変わらないのか
ヒトについてのデータは少なく、様々な実験データがあり統一した見解はないと言うこと。
はっきりしないことには安全側に考えるというのがあるべき姿で、厳しめである1mSv/年もそうしてきめられている。
管理上は職業人被曝の規制を超えたり一般人の1mSv/年規制を超えればまずいので、判明すれば監督官庁は指導なり処分なりをすることになる。
しかし、出てしまったものについては、健康被害を最少にする必要がある。リスクはあまり高くないと考えられているのにあまりに厳しくすれば飲むもの、食べるものがなくなりかねない。そこで緊急時の規制をすることになる。
飲料水や食品の場合、最悪でも17mSv/年程度を超えないよう暫定規制をかけている。しかし、現実にはヨウ素とセシウムが主なので、それらを取り込んでも最悪で7mSv/年程度という規制になる。
東京近辺であれば通常の食生活をすれば内外被曝併せて8mSv/年を超えることは考えにくく、実際にはそれよりかなり少ないはず。
1mSv/年を絶対基準と考えればその8倍だが、もともとリスクは少ないと考えられている100mSv/年からみるとリスクはさらに0.08倍で充分少ないとも考えられる。
これが多いと思えば、産地を見て食品を選べばさらにかなり減らせる。
水産物についても今のところ福島・茨城産をさければ問題ないレベルになる。
物質が拡散しにくい閉鎖系であり、ミネラル分を吸収しやすい湖や川の魚はやめた方がいい。
今後はセシウムを取り込みやすいキノコ類が気になるところではある。
(産地偽装には注意)
結局、一つ一つの食品について、放射線汚染度合いがわかることが安心につながると言える。
現在の測定方法は専門機材が必要で時間がかかるし手間もかかる。それ故地域ごとのサンプリング調査しかできていない。食品ごとの値を知るためにはその場で測定できる方法がないことにはかなり困難。
現在簡易に測定できる機器類を開発しているとも聞くが、そうしたものが完成し普及しないことにはちょっと難しそうだ。
それまでは産地で考えるしかない。


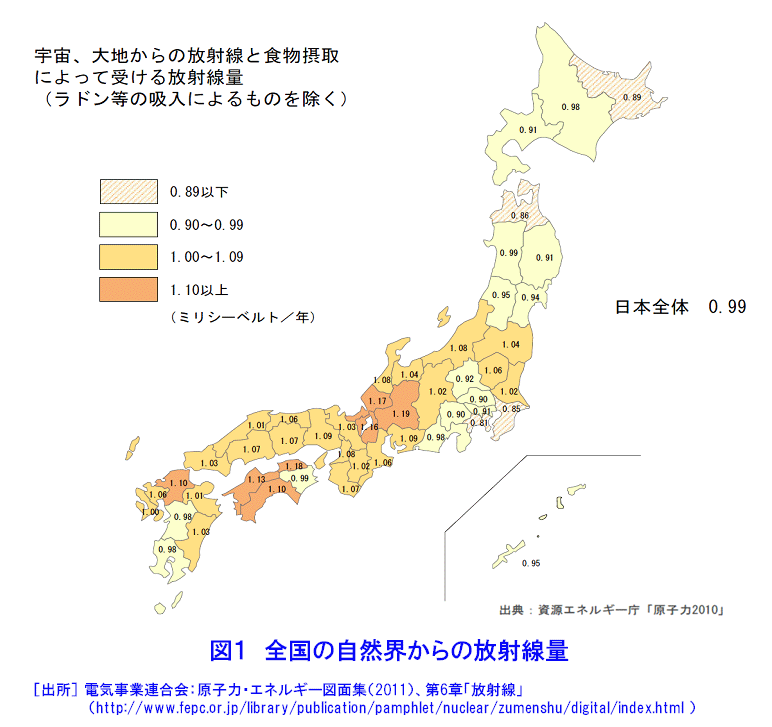
 海浜幕張駅前に植えられているネムノキが咲いていた。
海浜幕張駅前に植えられているネムノキが咲いていた。


