
■雲台さんは
PWRを主に研究していました。
(ここは不思議な所で、
浜岡はBWRなんですよね)
コレは、予想が異なってくる
大きな要因になったのでは?
と外野は思っています。
【追記】単に急いでいたのではないかとの御指摘。
PWRをBWRに間違える。うん確かにカタカナを間違えまくる私にも
ありえますね。【追記終】
■雲台さんは悩んでらっしゃいました。
「
溶融しているのに爆発もしないしモニタリングの数字が低い」
コレは事後に眺めている外野(私)からすると興味深い発言です。
雲台さんはどれかの情報が嘘だと思ったようですが、
どれも正しかったようです。あえて言えば、
嘘は溶融のタイミングの発表でしょうか
■しかしコレを事後でいうのはちょっと「ずるい」と言うか無理があります
なぜならコレは、十分にパラメータが出ていて
結果も分かる現状からの分析だからです。
■ではその理由は何故でしょう?
BWRにも改良型と、初期型があります。
■もちろん改良型のほうが理に適っているのですが、
どうも・・・
初期型だから大惨事が防がれたのではないか?と
私は思っていたりします。
■
どうして??画像は改良型です。
一方、今回のタイプは何度も登場してますがコレ(プロトタイプ)です。
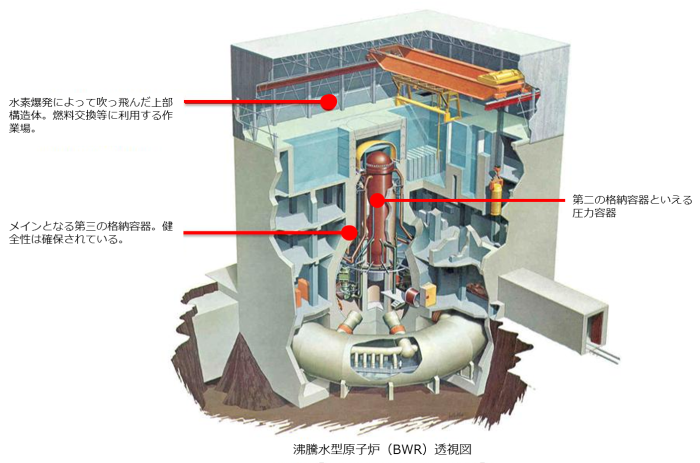
とおなじみの写真

■何が違うの???
実は違うのです。
【追記】違わないみたいです。お騒がせしました。【追記終】
仮に溶融した燃料が落ちても、
1)フラスコ上の格納容器の底に当たる
2)上から水がかかりながら、サプレッションチェンバーに落ちていく
3)サプレッションチェンバーは、格納容器と隔離されている。
【追記】初期型同様改良型も、そのまま圧力抑制室に落ちたりはしないそうです。
よく考えるとBWRは燃料棒のメンテを下からしますから、何もなかったら困ります。
私の不勉強でした。一つ勉強になりました【追記】
■格納容器の底は燃料が落下した場合穴が開きやすく
サプレッションチェンバーとのつなぎパイプは弱点ではあるのですが
こういうちょっとした損傷が、爆発力をそいでいる感触があります。
つまり、
溶融燃料がダイレクトに落下して、格納容器全体が破裂する、
そういうケースが「初期型」では防がれている可能性があります。
砂時計のように、ちょっとずつ燃料が落ちていくわけです。
■階上の使用済プールも弱点であると同時に、
階上なので「水が直接注げる」わけです。
今再び階上のプールのせいで、水漏れの危機があるわけですが、
階下にプールがあれば、空焚き→ポポポポーンを起こすわけで
利点と欠点は背中合わせのようです。
■
実は2号機の予想が、雲台さんの予想に最も近い経緯をたどるのですが
(11日に70時間で安全がわかるという発言は、
RCICの作動時間とほぼ合致しています。)
2号機で起きたのは
サプレッションルーム内での爆発であり、
この爆発にによって、何とガス漏れを起こし、爆発力を失います。
(代わりに14~15日にプルームがばら撒かれます)
メインの格納容器は、「
それなり」の健全性を保つため、
それなりの放射線しか出てこない、わけです。
(→モニタリングの数字が雲台さんの予想より上がらない)
■
2号機マニアとして断言してしまうと、
2号機がもし改良型で、爆発をしていれば、
雲台さんは英雄だったでしょう。
しかし、2号機がBWRプロトタイプで、
中途半端な爆発と放射能漏れを起こした為
■雲台さんの予想はよい方向に崩れ去り、
その迷いは、彼の数字に対する観念の迷いにつながり
17日以降の協力者の間違いデータの公開と
ネット総攻撃の憂き目に遭う事になりました。
と私は思っています。
■探って出てきたのは、
日本と言う国にツキがあった事と
幸運だったが故にボロッカスに集中攻撃を受けた
雲台さんの運命でした。
ブログ一覧 |
雲台さんの再評価【挑戦?】 | 日記
Posted at
2011/05/22 18:37:25
 雲台さんの誤算(爆発が起きない!!)
雲台さんの誤算(爆発が起きない!!)
 ■雲台さんは
■雲台さんは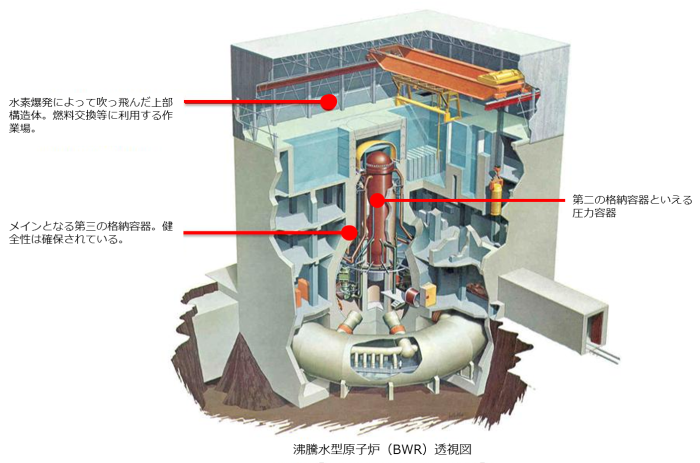

 今、あなたにおすすめ
今、あなたにおすすめ


