今エントリーも先程用いたエントリーから情報を抽出します。
2011年03月27日
再臨界疑い(12日~14日)
■気になる記事を発見。再臨界はあったのかもしれません。
もう何も驚かない!!
でも今はしていないと思います。問題は解けた燃料の再臨界によって放射性物質が大幅に
増えたと言う事が問題です。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110323-OYT1T00534.htm?from=navr
引用
東京電力は23日、東電福島第一原発の原子炉建屋の約1・5キロ・メートル西にある正門付近で、これまでに2回だけ計測されたとしていた中性子線が、12~14日に計13回検出されていた、と発表した。
観測データの計算ミスで見落としていたという。
中性子は検出限界に近い微弱な量だった。東電は、「中性子は、(核燃料の)ウランなど重金属から発生した可能性がある。現在は測定限界以下で、ただちにリスクはない。監視を強化したい」としている。
(2011年3月23日13時10分 読売新聞)
引用終)
***************************
となっています。
これは、12日前後から続いた、1,2,3、号機のメルトダウンの影響でしょう。
圧力容器が密閉ではなく、漏水があったせいでそれらの悪影響は、
今石棺の最深部、サプレッションチェンバーへと場を移しています。
例えば2号機では、サプレッションチェンバー内での放射線量の激しい上下があり
今はこの中でJCO型の再臨界が起きている可能性がある訳です。

面白いのはCAMSデータ(ドライウェルのA)です。
このデータは3月14日以降たまに書いてあります^^;
★1号機は3月14日6:00にはすでに164シーベルトでした。
★一方2号機は
3月14日6:00で0.001シーベルトです。
それが3/14 22時で、15シーベルト
3/15 1時53分 30.4シーベルト
6時で62.7 13時で47.7
3/15 15時25分 122シーベルト
3/20 0時 65.8シーベルト
★3号機も3月14日5:00で158シーベルトでした。
■1、と3号機は炉内の状態は相当悪かったといえます。
同時に早い段階でメルトダウンを起こしたために、水素爆発へと向かったのは
技術的には面白い傾向だと思います。
■また早い段階で爆発したために、
その放射線は、日本を汚す事が余りなかったのも事実です。
責任を追い求めるのもいいですが、中途半端に状態が長持ちした場合
最悪の結果が迫っていたというのは皮肉な事実ではないでしょうか。
■2号機については、放射線の上がり方がとてもよく分かりやすいですね。
同時に、発生時刻を考えると20シーベルト程度のプルームが、
水戸で0.15マイクロシーベルト
埼玉で0.1マイクロシーベルトの汚染を一時的に起こしています。
福島が高い汚染となったのは、燃料の崩壊に伴って
非常に高い汚染が外部流出したからと思われます。
■更に、1,3号機はJCO型再臨界を起こしているわけですから
(ここで大事なのは、ほんの一瞬の再臨界では、
恐らく正門で中性子は検出されないし
サプレッションチェンバーの中は地下なので、
正門では中性子は角度的に出てきにくい)
2号機も放射線量的には再臨界が、起きていたと見るのが自然でしょう。
それらの汚染は、ほぼすべてが福島内陸に向かいました。
■これらの検証は数年をかけて学者達に検証されます。
もし事実でありうるなら
関東に住まい関りを持つ人間はこの事を忘れてはいけないと思います。
例え、少々汚染されていたとしても、
私達が、偶然に救われている存在であるという事をです。
【追記】私が状態の悪い、1,3ではなく2号機を汚染の主原因としているのは
1,3号機は15日段階では格納容器の密閉性がある程度残されているからです。
一方の2号機はサプレッションチェンバーの損傷によって
格納容器の密閉性は早期に失われています。
また圧力容器が最後まで健在だったが故に、
ベント等の回避措置が一番行われたのが2号機でした
汚染の発生時間の推定やその経路については
詳しくはシリーズ3月15日をご覧下さい。【追記終】
Posted at 2011/05/22 02:10:18 | |
トラックバック(0) |
事故発生当初 | 日記
 再臨界を考えて、初期段階での再臨界は?
再臨界を考えて、初期段階での再臨界は? 
 運命の3月11日15:40
運命の3月11日15:40  ■2号機パラメータを見ていますと
■2号機パラメータを見ていますと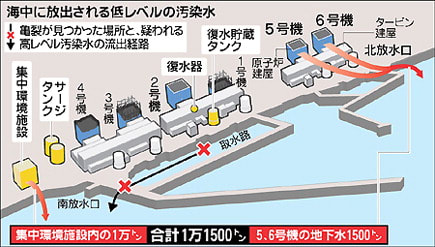
 ドナルドキーンさんの選択と日本人への愛憎
ドナルドキーンさんの選択と日本人への愛憎  【危険厨VS安全厨】やんぢさんのコメントから発想を得た事
【危険厨VS安全厨】やんぢさんのコメントから発想を得た事  【危機回避】お客さん、新鮮?なネタが入りましたよ。【祝!東京電力パラメータ公開】
【危機回避】お客さん、新鮮?なネタが入りましたよ。【祝!東京電力パラメータ公開】  ■本題から入ります。
■本題から入ります。

